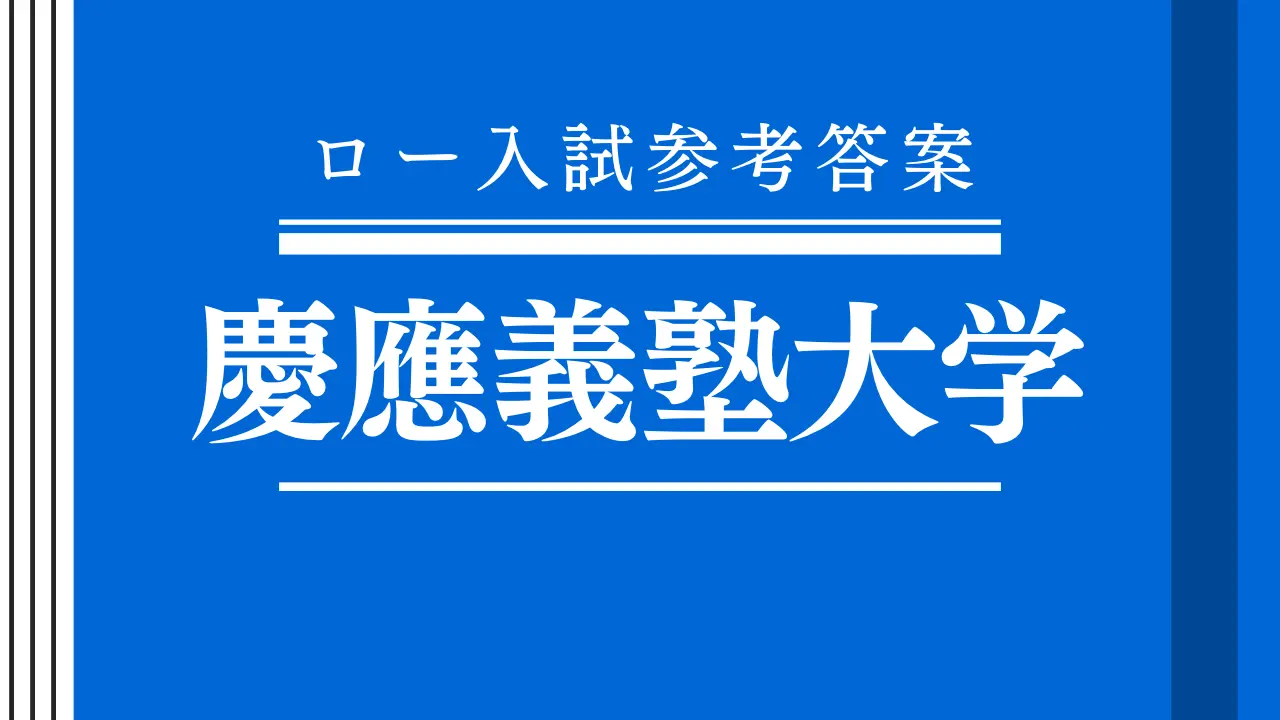
2023年 刑法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2023年 刑法
第1 問題1
1. XがAの頸部をロープで強く締めた行為に殺人罪(刑法(以下、略)199条)が成立しないか。
⑴ 実行行為とは、法益侵害結果発生の現実的危険を有する行為をいうところ、頸部をロープで強く締める行為は、締め付けられた者を窒息させ死亡させる危険を有する行為であるから、上記行為は殺人罪の実行行為に当たる。
⑵ そして、Aには死亡という結果が生じている。もっとも、Aの死亡という結果は、Xが上記行為後にAを林の中に放置したときに水たまりに顔がかぶさってしまいそれによって窒息したことで生じている。そのため、Xの上記行為とAの死亡の間に因果関係が認められるかが問題となる。
因果関係とは、発生した結果につきいかなる範囲で行為者に帰責させられるかという客観的帰属の問題であるところ、因果関係は行為の危険が結果に現実化したときに認められると考える。
これをみるに、本件でAの死亡の直接に原因は上記のとおり水たまりに顔がかぶさったことによる窒息である。しかし、Xは自らの犯行の発覚を防ぐ目的でAを山林に遺棄しており、XによるAの遺棄はXがAの首を絞めつけた行為を原因として行われたものである。また、一般的にも殺人を行った者が犯行の発覚を防ぐために死体を山林等に遺棄する行為に出ることは、容易に想定しうるものでありそれほど特異な事態ではない。加えて、Aは、Xに首を絞められたことにより失神していたために顔が水たまりにかぶさっていたのに動けず窒息してしまったのであり、Xの首を絞める行為の結果への寄与度は大きい。
以上より、Aの死亡はXのAの首を絞める行為の危険が結果に現実化したものといえる。したがって、因果関係が認められる。
⑶ もっとも、Xは、Aの首を絞めたことによってAが死亡したと認識しているところ、実際は、Aは首を絞められた時点ではまだ生きており山林に放置されたことによって窒息死している。そのため、Xは、現実と異なる因果経過を認識しており、Xには殺人罪の故意が認められないとも思える。しかし、故意責任の本質は、犯罪事実を認識し反対動機を形成可能であったのにもかかわらずあえて行為に及んだことに対する道義的非難にある。そして、行為者の認識した因果経過と実際の因果経過が同一の構成要件内で符合する場合には、行為者は同一の犯罪事実を認識したといえ非難できる。そのため、かかる場合には故意が認められるところ、本問では、Xの認識と現実の因果経過は殺人罪という同一の構成要件内で符合しており、Xには同罪の故意が認められる。
⑷ 以上より、Xの上記行為に殺人罪が成立する。
第2 問題2
1. XがYに本件土地を売却した行為に横領罪(252条1項)が成立しないか。
⑴ まず、Xはすでに本件土地をAに売却し、全額の支払いを受けていたから本件土地はAという「他人の物」といえる。
⑵ そして、「占有」とは濫用のおそれのある支配力のある状態をいい、占有には事実上のみならず法律的支配も含まれる。そのため、不動産については、登記名義人が不動産を法的に処分しうる地位にあり登記名義人に法律的支配が認められるところ、本件土地の登記名義人はXであり、Xによる法律的支配が認められるからXによる「占有」が認められる。
したがって、本件土地は、「自己の占有する他人の物」にあたる。
⑶ また、横領罪における占有は占有離脱物横領罪との区別のため、委託信任関係に基づくものである必要があるところ、XはAと売買契約を締結した売主の地位に基づき、所有権移転登記に協力すべき義務があるため、Xの占有は委託信任関係に基づくものといえる。
⑷ 次に、「横領」とは、委託の任務に背いて、権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思たる不法領得の意思を発現させる行為をいう。そして、不動産の場合、その所在が不動であることから、権利関係の変動のみによって横領罪が実現されるところ、横領罪は権利関係の変動が確定的に生じた場合、すなわち登記完了時に既遂に達すると考える。
本件では、Xは、Yに本件土地を売却するという所有者でなければできない処分を行い、Yへの所有権移転登記を完了しており、「横領」したといえる。
⑸ 以上より、Xの上記行為に横領罪が成立し、後述のとおりYと共同正犯(60条)になる。
2. YにXの上記行為について共同正犯(65条1項、60条)が成立しないか。
⑴ 「共同して犯罪を実行した」(60 条)といえるには、犯罪が共謀に基づいて実行されたことを要する。そして共謀とは、①犯罪の実現に関する意思連絡が、②正犯性を備えた者らの間で交わされた状態をいう。
これをみるに、Yは、本件土地の登記名義がX のままであることを奇貨として、Xに本件土地を再度自己に売却することを働きかけ、Xはこれを了承しており、XY間で横領罪の実現に関する意思連絡が行われている(①)。そして、Yは本件土地をYに売却し改めてAに売りつけるという計画の発案者であり、これによって得られた利益もXYで折半する計画となっていた。そのため、Yに正犯意思が認められる(②)。
以上より、共謀が認められるところ、Xは、上記共謀に基づいてYに本件土地を売却し登記を移転している。
したがって、共同正犯の要件を満たす。
⑵ もっとも、民法177条は、不動産の権利取得は登記しなければ「第三者」に対抗できない旨を定め、この「第三者」には単純悪意者を含むと解されている。そうすると、譲受人が単純悪意者である場合には、登記を先に備えることによる権利取得は、民法上適法な行為であるから、刑法の謙抑性に鑑み、犯罪の成立を認めるべきではない。
これを本件についてみると、たしかにAは本件土地購入後も所有権移転登記を備えていなかった。しかし、Yは、そのことを認識しているのみならず、それを奇貨として、Xに自己に本件土地を売却させて再度Aに高値で売りつけようと計画しており、Yは背信的悪意者に当たるから民法177条の第三者に当たらず民法上も保護されないため共犯の成立を否定する必要はない。
⑶ したがって、Yに横領罪の共同正犯が成立する。なお、横領罪は、占有者という身分によって構成すべき犯罪であるから占有者でないYには65条1項が適用されることになる。
第3 問題3
1. まず、Xの罪責の認定のために実行行為者であるBの罪責を確定する必要があるため、以下簡単にAに建造物等以外放火罪(110条1項)が成立しないかを検討する。
⑴ Xは、A 車からガソリンを流出させてサドルシート付近に所携のライターで火を放っており「放火」したといえる。
⑵ また、「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続しうる状態になったことをいうところ、本件では、サドルシート上に1メートルほどの火柱が上がり、A車が「焼損」している。
⑶ そして、上記放火による火柱はA方家屋にも延焼しており「公共の危険を生じさせた」といえる。
⑷ また、Bは、A方への延焼を予期しておらず公共の危険を認識していなかったとも思われるも、建造物等放火罪の成立に公共の危険の認識は不要と考える。なぜなら110条1項は、「よって」との文言を用いており建造物等放火罪は結果的加重犯と解されるところ、公共の危険の発生は同罪の結果に当たるからである。
⑸ 以上より、Aに建造物等放火罪が成立する。
2. では、XにAの上記行為について共同正犯が成立しないか。
⑴ 上述の共同正犯の要件に該当するか否かを検討する。
ア まず、Xは、Bに対し、「Aの単車を潰せ」「燃やせ」などと指示をし、Bはこれを承諾しているから建造物等放火罪の実現に関する意思連絡が認められる(①)。そして、Xは、暴走族のリーダーという支配的地位にあり、配下のBにリーダーとして上記行為を行うことを命じており、BもXからの命令として上記行為を行っている。そのため、Bの行為は、Xのための犯罪として行われたと評価できXに正犯意思が認められる(➁)。
イ そして、Bは、Xの指示に従い、Aバイクを放火する上記行為に及んでいる。したがって、上記共謀に基づく実行行為が認められる。
⑵ 以上より、Xに建造物等放火罪の共同正犯が成立する。なお、Xは、A車がP橋の下の河川敷にあるものと認識しており、P橋は、鉄筋コンクリート製の鉄道橋であり、周辺一帯は砂利敷きで周囲に燃えやすいものはなかった。そのため、XにはA車への放火によって公共の危険が発生するという認識がなかったため、建造物等放火罪が成立しないのではないかが問題となるも、上述のとおり同罪の成立において公共の危険の認識は不要である。したがって、かかる点によってXに同罪が成立することが否定されることはない。
以上





