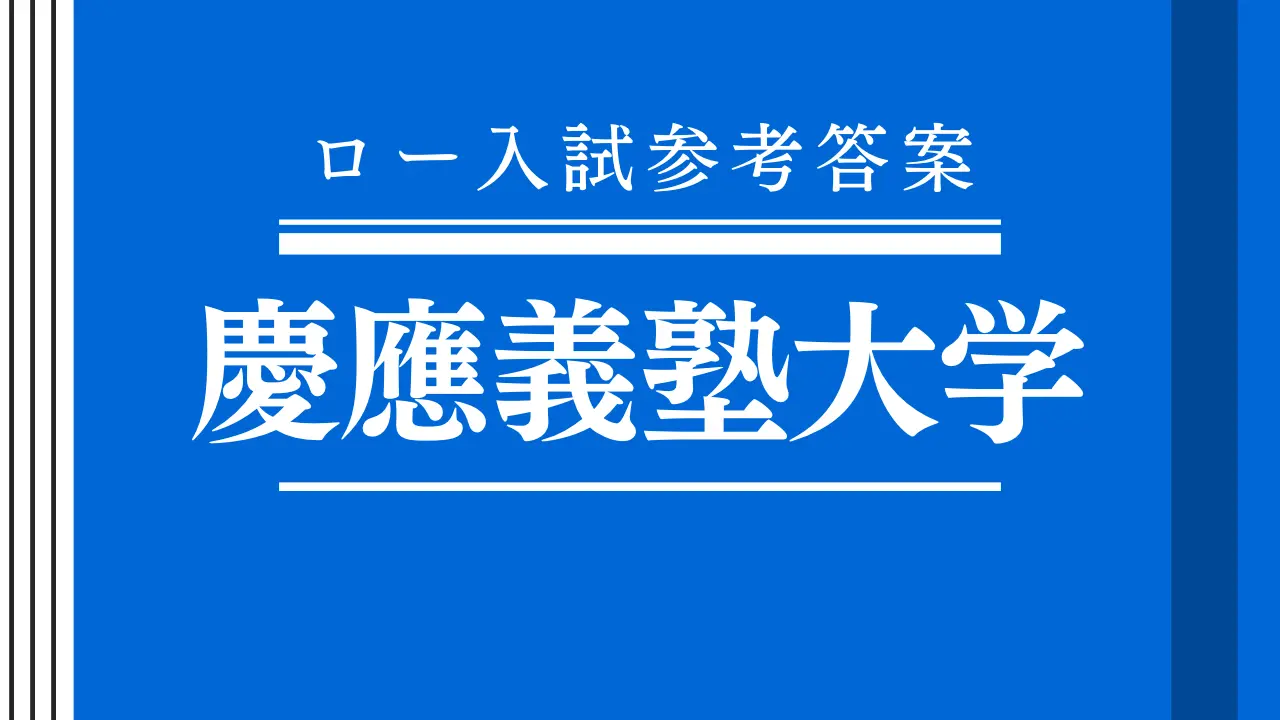
2023年 刑事訴訟法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2023年 刑事訴訟法
第1 設問1
小問1
刑事訴訟法(以下、法令名略)256条3項は、訴因の明示を求めている。これは、刑事訴訟における審判対象が訴因とされ、その訴因を設定・変更する権限が検察官に認められる当事者主義的訴訟構造の下では、裁判所は訴因として検察官が主張する犯罪事実の範囲で審理・判決する権限と義務を有する(378条3号)ことから、訴訟の前提として、裁判所が審理・判決すべき範囲が画定される必要があり、審判対象が画定されれば、被告人はそれを超えて刑事責任を問われることがないため、防御すべき範囲が限定されることとなるからである。
小問2
1. Vに対する強制性交等致死に係る部分は、訴因を明示した記載といえるか。「できる限り…特定し」たといえるかが問題となる。
2. 上述のとおり、訴因の明示の第一次的機能は裁判所に対する審判対象画定機能にあり、その反射的効果として被告人に対する防御権告知機能がある。したがって、①構成要件に該当する具体的事実が記載され、➁他の犯罪事実と識別可能な程度に特定されていれば、「できる限り…特定し」たといえると考える。
3. 本問をみる。本件公訴事実には、Xが胸部や腹部を多数回足蹴にしたり、踏みつけたりする暴行を用いてVと性交しようとした旨の記載があり、加えてVがかかるXの暴行によって死亡したことも記載されている。したがって、強制性交致死罪の構成要件に該当する具体的事実が記載されているといえる(①)。また、本件の公訴事実には、犯行の日時、場所が具体的に記載されているし、Vの死という事実は一回しか起こり得ないものであるから他の犯罪事実と識別可能な程度に特定されているといえる(➁)。
4. 以上より、本件公訴事実におけるVに対する強制性交等致死に係る部分は、「できる限り…特定し」たといえ、訴因を明示した記載といえる。
第2 設問2
小問1
320条1項が伝聞証拠を排斥する理由は、供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述の各過程を経るものであって各過程に誤りが生ずるおそれがあるところ、公判期日外の供述は、公判期日における供述と異なり、宣誓、偽証罪の告知がなされず、不利益を受ける当事者による反対尋問も経ず、裁判所による供述態度の観察も行われないため、公判期日における供述に比して類型的に誤りが入り込むおそれが高く、これを内容とする証拠を事実認定に用いると誤った事実認定のおそれがあるからである。
小問2
検察官Pの考える推論の過程は以下の様なものと考えられる。
すなわち、まず、Vの「いやらしいことばっかりする」という供述からXがVにいやらしいことばかりしていたという事実を認定する。そして、そこから人が他人にいやらしいことばかりするのはその人がその他人に性的関心を持っているからだという経験則を経て、XのVに対する性的関心を推認する。そして、最後に、性的関心は強制性交罪の犯行動機となるという経験則を経て、XにはVに対する強制性交罪を実行する犯行動機があったという事実を推認し、そこから動機がある者は当該犯行に出る可能性が高いという経験則によってXの犯人性を推認するというものである。
小問3
1.Wの証言中の上述のVの証言の部分(「『いやらしいことばっかりする。』と言っておりました。」)は、伝聞証拠に当たらないか。
⑴ 小問1で述べた伝聞法則の趣旨から、320条1項によって証拠能力が排除される伝聞証拠とは、公判期日外における供述を内容とする証拠であって、要証事実との関係で原供述の内容をなす事実の存在を証明するために用いられるものをいうと考える。
⑵ これをみるに、上記証言の部分は、Vの供述という公判期日外における供述を内容とするものであって、上記検察官Pの推論過程から、いやらしいことばっかりするという事実の存在を証明するために用いられるものでると考えられるから、原供述の内容をなす事実の存在を証明するために用いられるものといえる。
したがって、上記証言部分は、伝聞証拠に当たり原則として証拠能力が否定される。
2. もっとも、324条2項の準用する321条1項3号の要件を満たす場合には、例外的に証拠能力が認められる。
⑴ すなわち、上記証言部分は、Wという「被告人以外の者の…公判期日における供述で」Vという「被告人以外の者の供述をその内容とする」(324条2項)ものであるため、321条1項3号の要件を満たせば、証拠能力が認められることとなる。
⑵ したがって、原供述者Vが供述不能であること、Vの当該供述が犯罪の証明のために必要不可欠であること、その供述が「特に信用すべき状況でされたもの」であること、という要件を満たせば証拠能力が認められる。
以上





