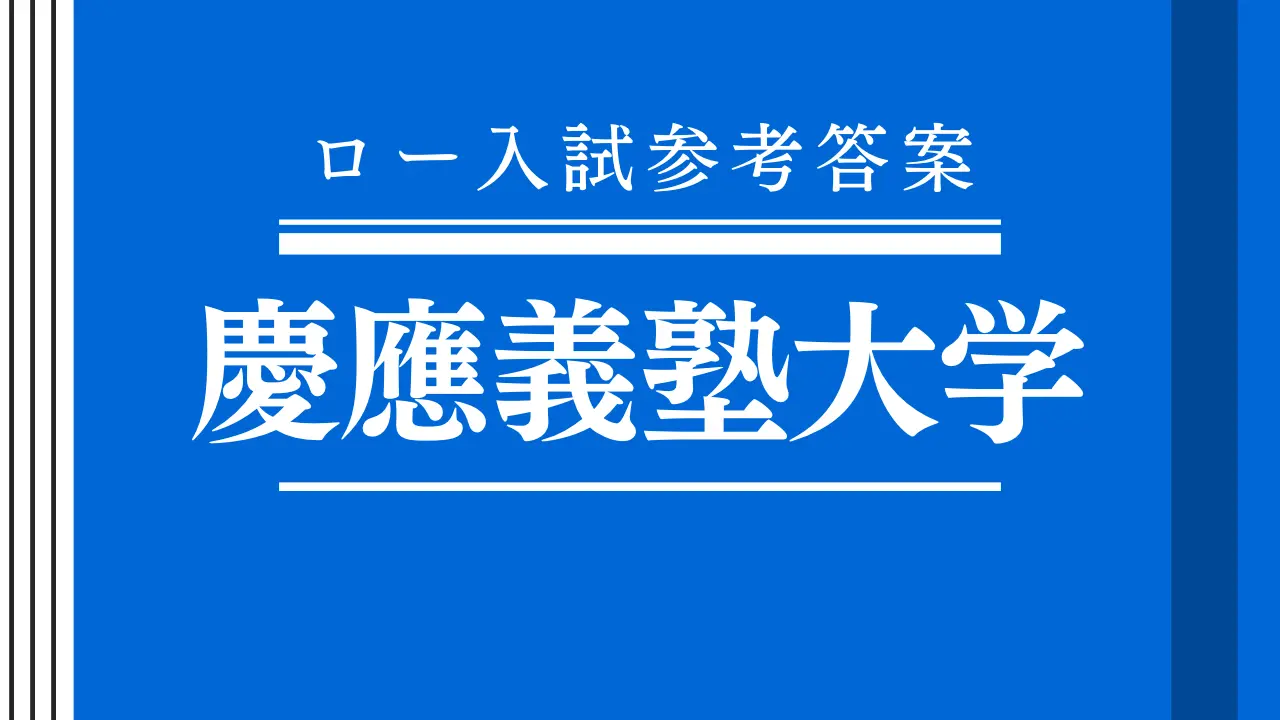
2022年 民法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2022年 民法
設問1
1. EはAから本件賃貸借契約に基づく2021年5月から翌年3月分までの賃料債権を同年4月10日に譲渡されているが、譲渡の時点で同年5月分以降の賃料債権は発生していない。そのため将来債権譲渡になるが、かかる譲渡は有効か。
⑴ 民法(以下略)466条の6第1項により、将来債権の譲渡も認められる。もっとも契約の一般的要件から、目的債権が特定されており、公序良俗違反(90条)といった事情がない必要がある。
本件の債権は本件賃貸借契約から発生するもので、債権の範囲も2021年5月分から2022年3月分までの賃料債権と特定されている。加えて、公序良俗に反するような事情もない。よって上記債権譲渡は有効である。
⑵ 内容証明郵便によるCへの通知(467条1項)も備えている。従って、債務者Cへ債権譲渡を対抗できる。
⑶ よってEはCに対し賃料債権の取得を主張でき、請求は認められるとも思える。
2. Cは、2021年7月分以降の賃料債権は、混同(520条本文)により消滅したと反論できないか。
⑴ Aは2021年6月10日、本件建物をCに4000万円で売却(「譲渡」)したため、賃貸人の地位がAからCに移転する(605条の2第1項)。したがって、賃貸人と賃借人の地位は共にCに帰属するに至っているので、賃料債権は混同により消滅したと思える。したがって、Cの反論は認められるとも思える。
⑵ これに対し、本件債権が「第三者の権利の目的」(520条但書)になっていないか。
ア Eは本件賃貸借契約の当事者または包括承継人でないため、「第三者」にあたる。
イ 本件債権は「権利の目的」になっているといるか。将来債権譲渡契約の効力が新賃貸人の下で発生する賃料債権に及かが問題となる。
混同により賃料債権が消滅すると解した場合、賃貸人が賃貸不動産を譲渡することにより、これに先行する将来債権譲渡契約で債権譲受人が将来賃料債権を取得することを妨げることができてしまう。そうなると、債権譲受人に不測の損害を与えることになり、取引の安全を害しかねない。そこで、将来の賃料債権が譲渡された後に賃借人が不動産を取得したとしても混同により賃料債権は消滅しないと解するべきである。このように解しても不動産の譲受人は、売買の前に賃料債権譲渡の事実を知ることができたはずであるから、譲受人に不測の損害を与えることもない。
よって、「権利の目的」に当たる。
ウ 以上より520条但書が適用される。
3. 以上より、Eの請求は認められる。
設問2
1. Eは、Cを被告として(424条の7第1項1号)、AC間の本件建物の売買を詐害行為として取消請求し、(424条1項本文)、Cに本件建物のAへの返還を請求できないか(424条の6第1項前段)。
⑴ EはAに対して、弁済期が到来した500万円の売掛代金債権を有している。したがって被保全債権が存在し、Eは「債権者」(同条1項本文)である。上記売掛代金債権は2021年4月10日の本件売買より「前の原因」(同条3項)によって生じている。また金銭債権であり、「強制執行により実現」(同条4項)できる。
⑵ 2021年4月10日本件売買時、Aは同月5日に銀行取引停止処分を受け、事実上倒産状態に陥っていた。従ってAは4月10日時点で無資力だった。また、Aは売却代金3500万円のうち3300万円をDに対する債務の弁済に使用し、現在でも資力は回復していない。そのため、A(債務者)は無資力である。
⑶ 本件売買は、時価4000万円である本件建物を3500万円で売却する廉価売却である。このような売買をすれば、債務者Aの責任財産は減少するためし、債権者は害される。しかも、前述の通り無資力に陥っていたため、廉価売買をすれば債務超過になり、Eへの弁済ができなくなることをAの代表取締役Bは認識していたと考えられる。よって、本件売買は「債務者が債権者を害することを知ってした行為」にあたる。
⑷ 本件売買は、「財産権を目的」(同条2項)とする行為である。
2. Cは、Eを「害することを知らなかった」(同条1項但書)を反論として主張することが考えられる。しかし、Cの取締役Bは、Aの代表取締役であるので、法人Cとしても本件売買が詐害行為にあたることを「知らなかった」とは考えられず、この反論は認められない。
3. EはCに対し、本件建物の「返還」(424条の6第1項前段)を求めている。これに対してCは、本件建物の返還は困難であり、Eは「価額の償還」(同項後段)ができるにとどまると反論すると考えられる。この反論は認められるか。1
⑴ 不動産の売却が詐害行為にあたる場合でも、かかる売却代金でもって抵当権の被担保債権に対する弁済がされ、その抵当権の登記が抹消されたような場合は、もはや現状の回復は困難であるといえる。そこでこのような場合は、価額の償還が認められるにとどまる。
⑵ 本件では、Aは本件建物の売却代金でもってDへ弁済し、本件建物を目的とするDの根抵当権設定登記は抹消されている。
⑶ よってCの反論は認められ、Eは価額の償還ができるにとどまる。
⑷ 価額償還は「可分」(424条の8第1項)であるため、Eは「自己の債権の額の限度」である500万円について償還請求できる。
4. 以上より、EはAに対し、500万円の償還を請求できる。
以上





