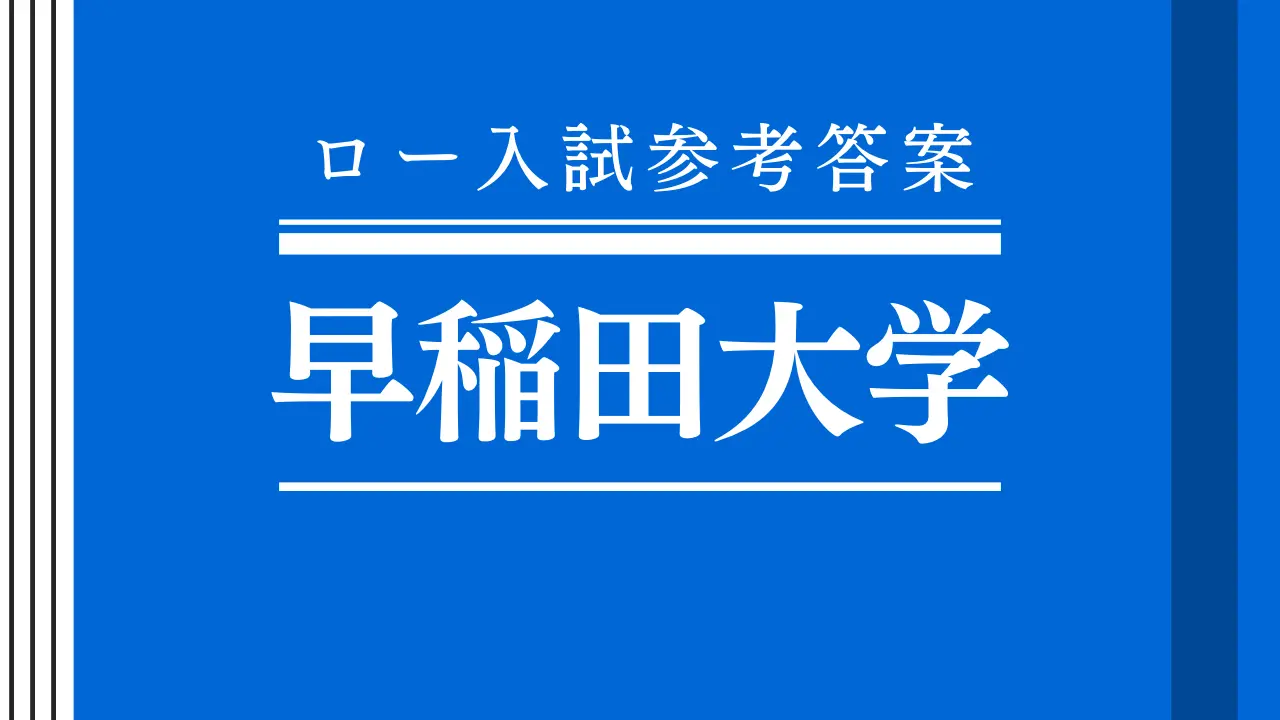
2024年 民法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2024年 民法
問題1
設問1
小問⑴
1. Dは、Aに対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法(以下、略)717条1項)をする。
⑴ 本件店舗は、「土地の工作物」である。また、Aは、本件店舗の占有者である。
「設置又は保存に瑕疵」とは、当該工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
少なくとも外部からの衝撃なくして外壁が剥落しないというのは、店舗用建物が通常有すべき安全性といえる。本件では、本件請負契約どおりに本件店舗の外壁工事がCによってされなかったために、2023 年 3 月に本件店舗の外壁の一部の剥落しているから、本件店舗は通常有すべき安全性を欠いているといえる。そのため、本件店舗の「設置又は保存に瑕疵」がある。
かかる「瑕疵」に「よって」、本件店舗の外壁が剥がれ落ち、本件店舗の近くを通行していたDに重傷を負わせ、治療費その他の「損害」を生じさせている。
⑵ なお、本件店舗の所有権は、A・B間の本件売買契約(555条)によって、Aに移転している(176条)ため、本件店舗の所有者であるAは「損害の発生を防止するのに必要な注意をした」ことをもってその責任を免れることはできない。(717条1項ただし書)。
⑶ よって、Dの上記請求は認められる。
2. Dは、Cに対して、不法行為(709条)に基づく損害賠償請求をする。
⑴ Cは、注文者たるBに対して債務を負うのみで、第三者に対しては何ら債務を負わないのが原則である。
もっとも、契約当事者以外の者の生命、身体、財産を侵害してはならないのは当然であることから、建物に携わる設計者等は、建物に建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負っていると考える。そこで、かかる義務を怠れば、「過失」があるといえると解する。
⑵ たしかに、外壁の剥落の危険があることによって、建物内部にいる者の生命、身体、財産には危険は及ばない。しかし、通行人の生命、身体、財産を侵害する危険が大きいことからすれば、外壁の剥落の危険がないことは、建物としての基本的な安全性に当たる。Cは本件請負契約どおりに本件店舗の外壁工事をしなかったことで、外壁の一部の剥落の危険のある建物を漫然と完成させており、かかる注意義務違反は「過失」に当たる。それにより、通行人であるDに重傷を負わせ、その身体に係る権利を侵害し、治療費その他の「損害」を生じさせている。
⑶ よって、Dの上記請求は認められる。
3. AがDに上記不法行為責任を果たした場合、Aは、Cに対して、717条3項に基づいて、求償請求をする。
⑴ 上記の通り、Dが重傷を負ったのは、Cが本件請負契約どおりに本件店舗の外壁工事を行わなかったことによって生じたものであるから、「損害の原因について他にその責任を負う者があるとき」に当たるからである。
⑵ よって、本件店舗の「所有者」であるAの上記請求は認められる。
小問⑵
本件の不法行為は、Dの身体を害する不法行為であるから、Dは、「損害及び加害者を知った時から」「5年間」以内に上記損害賠償請求権を行使する必要がある(724条の2、724条1号)。
Dは、2023 年 3 月に本件店舗の外壁の一部の剥落によって重傷を負っており、その時に、「損害及び加害者を知った」といえるから、2028年2月までに上記請求権を行使する必要がある。
設問2
小問⑴
1. Aは、Bに対して、契約不適合責任に基づいて、本件店舗の修補請求(562条1項)をする。
⑴ 本件売買契約では、本件店舗の外壁の一部の剥落のきけんがないことが当然の前提となっていたといえる。にもかかわらず、かかる危険があったから「品質」に関して「契約の内容に適合しない」といえる。
⑵ Aの「責めに帰すべき事由」は本件では存在しない(同条2項)。
⑶ よって、Aの上記請求が認められる。
2. Aは、Bに対して、本件売買契約の代金減額請求(563条1項)を取得し得る。
⑴ 上述の通り、「前条第1項本文に規定する場合」に当たる。
⑵ よって、Aは、「相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、上記請求が認められる。
3. Aは、Bに対して、債務不履行に基づく損害賠償請求(564条、415条1項本文)をする。
⑴ 上記の通り、本件売買契約には契約不適合があるから、「債務の本旨に従った履行をしないとき」に当たる。これに「よって」Aは契約に適合した本件店舗を受け取れないという「損害」を被っている。
⑵ 本件の債務不履行は、Bが本件店舗の設計等を任せたCが本件請負契約どおりに本件店舗の外壁工事をしなかったために生じたものであって、店舗の安全性に係るリスクはBによって引き受けられていたといえるから、Bに帰責性がある。
⑶ よって、Aの上記請求は認められる。
小問⑵
Aは、当該不適合を知った時から1年以内にBに対して、契約不適合の内容である本件店舗の外壁の剥落の事実を通知しなければならない(566条本文)。その上で、遅くても本件重傷事故が発生した時から、5年間当該権利を行使しないときには、各権利は、時効によって消滅する(166 条1項1号)からその時から5年以内に各権利を行使しなければならない。
問題2
設問1
1. Aは、Bに対して、離婚を請求することができる。Bは現在、Aでない女性と乙建物に暮らしていて、その女性とは不貞な関係にある。そのため、「配偶者に不貞な行為があったとき」(770条1号)に当たる。
2. 他方、BからAに対して離婚を請求することができるか。
⑴ AとBで共有している乙建物には、かつてAとBが居住していたが、現在BはAでない女性と暮らしていて、Aとは別居状態にある。そのため、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(同条5号)に当たる。よって、Bは上記請求をすることができるとも思える。
⑵ しかし、かかる離婚原因のほとんどを作り出したのはBであるから、Bからの請求は信義則に反して、許されないのではないか。有責配偶者からの離婚請求の可否が問題となる。
ア 有責配偶者からされた離婚請求であっても、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、②その間に未成熟の子が存在しない場合には、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解する。
イ 本件についてみると、乙建物にはかつてAとBが居住していたが、現在はBがAでない女性と暮らしていて、その女性とは不貞な関係にあり、Aは隣の街に居住していることから、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいると考えられる(①)。未成熟の子が存在しているというような事情もない(②)。Aは医師であり、一般的には高所得の職業についているから離婚によって生活に苦労するというようなことも考えにくい。そうすると、上記のような特段の事情も存在しない(③)。
ウ したがって、Bからの上記請求は信義則に反するものではない。
⑶ よって、Bは、Aに対して、離婚を請求することができる。
設問2
1. Bの債権者であるCは、Aに対して、A・Bの財産分与の協議について、424条1項本文に基づいて詐害行為取消権を行使する。
2. Aは、財産分与の協議により、甲土地および乙建物のBの持分の譲渡を受け、その旨の登記を受けている。Cは、Bの上記行為よりも前に(同条3項)、Bに対して貸金債権を有しており、これは強制執行によって実現できるものである(同条4項)。
3. Bが相続により取得した甲土地とA・Bで共有していた乙建物をAに譲渡することにより、Bは無資力になったと考えられ、「保全」の「必要」性がある(同条1項本文)。
4. しかし、財産権を目的としない行為については詐害行為取消請求の対象とはならない(同条2項)ところ、Bの行為は財産権を目的としない行為でないか。
⑴ 責任財産保全の必要性と家族法上の行為における本人意思尊重の要請との調和の観点から、財産分与は、夫婦の共同財産の清算分配という768条3項の趣旨に反し不相当に過大で、財産分与に仮託してされた財産処分と認めるに足りるような特段の事情のない限り、財産権を目的としない行為にあたると考える。
⑵ 離婚に伴う財産分与(768条)には、①婚姻中に形成した夫婦の共通財産の清算(清算的要素)、②離婚後の相手方配偶者の扶養(扶養的要素)の性質であることが一般に認められている。
まず、甲土地をAに譲渡したことについて、甲土地は元々Bが相続により取得した者であり、Bの所有物であった。これは「当事者双方がその協力によって得た財産」とはいえない(①)。また、Aは医師であり一般的に高所得であり、自立することができるということから、上記譲渡は扶養的要素があるともいえない(②)。そのため、上記の甲土地譲渡は、不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分と認めるに足りるような特段の事情がある。
次に、乙建物をAに譲渡したことについて、乙建物はA・Bの婚姻中にA・Bの資金で建築したものであり、A・Bが共有し、その旨の所有権の登記がされていたことから、婚姻中に形成した夫婦の共通財産といえる(①)。そのため、上記の乙建物譲渡は清算的要素があり、不相当に過大で、財産分与に仮託してされた財産処分と認めるに足りるような特段の事情はない。
⑶ よって、甲土地譲渡は、財産権を目的としない行為ではない。
5. また、客観的には詐害性が十分に認められるし、Bは、上記行為時、これによってCを害することを認識していたと考えられるから、詐害意思がある。
6. 以上より、Cは、悪意(424条1項ただし書)のAに対して、甲土地譲渡の財産分与協議については、詐害行為取消しの請求をすることができる(424条の6第1項、424条の9第1項)。
以上





