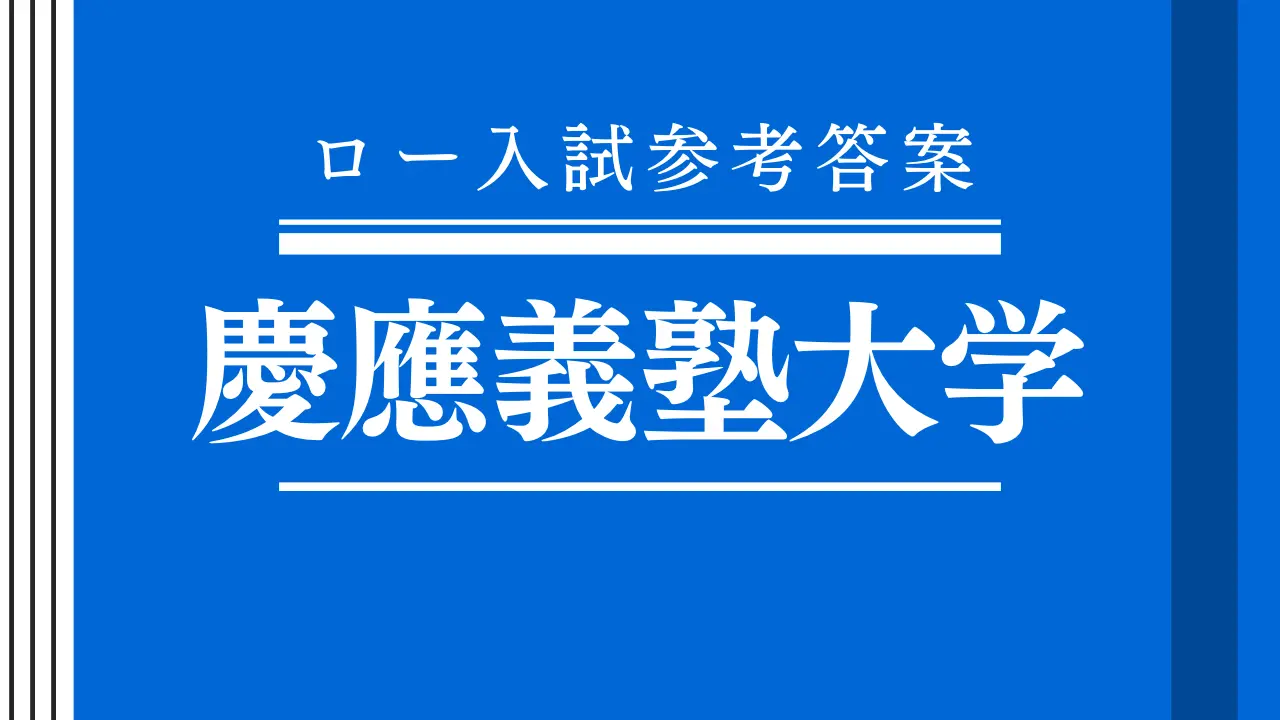
2024年 刑法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
2024年度 慶應ロー 刑法
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2024年 刑法
1. XはAを頭から床に思いっきり投げつけ(以下「本件行為」という)、Aに頭部打撲の傷害を負わせ、Aはその頭部打撲に起因する急性硬膜下血腫によって死亡した。そのため、Xには傷害致死罪(刑法(以下略)205条)が成立しないか。
⑴ Xには少なくとも暴行罪(208条)の構成要件的故意は認められる。傷害罪は暴行罪の結果的加重犯であり、傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯であるため、傷害致死罪の構成要件的故意が認められなくとも、暴行罪の構成要件的故意が認められれば足りる。
⑵ また、Xの実行行為と死亡結果の間には因果関係が認められる。
⑶ そのため、Xは傷害致死罪の構成要件該当性は満たす。
2. もっとも、XはAが強盗に入っていると誤認し、コンビニ店員を助けようとしているBに加勢すべく、Aを投げつけているため、正当防衛(36条1項)が成立し、違法性が阻却されないか。
⑴ 正当防衛が認められる要件は①急迫不正の侵害があること、②防衛の意思、③「やむを得ずにした行為」であることである。「急迫」とは法益侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいう。防衛の意思があるといえるには、侵害の認識と侵害に対応する意思があれば足り、防衛の意思と攻撃の意思とが併存していてもそれだけで防衛の意思を欠くとはいえない。「やむを得ずにした行為」であることとは防衛行為の相当性のことを指し、武器対等の原則を念頭に置きつつ、性別、体格差、年齢等を考慮して社会的に許容される行為であれば相当性を満たすといえる。
⑵ 本件において、Aは強盗ではなく、体に力が入ったにすぎず、Xを攻撃しようとしていない。そのため、急迫不正の侵害は存在していない。よって、①の要件を満たさない。
⑶ よって、正当防衛は成立せず、違法性は阻却されない。
3. Xは急迫不正の侵害があると誤信して本件行為に及んでいるため、責任故意が否定され、責任阻却されるのではないか。
⑴ 故意責任の本質は犯罪事実の認識によって反対動機が形成されるのに、あえて犯行に及んだ点に求められる。したがって、自己の犯罪事実を認識・認容した場合、故意責任を問うことができると解する。ここで、違法性阻却自由がないのにあると認識した場合、違法性の意識を喚起することはできない。よって、違法性阻却事由に錯誤がある場合、犯罪事実を認識・認容しているとはいえず、故意は阻却される。
⑵ では、Xの主観において、正当防衛は成立しているといえるか。
ア Xは「強盗だ」という叫び声を聞いた後にコンビニに入り、ゴルフクラブを手にしていたAを強盗と誤信し、Aの体に力が入ったことから、Aがゴルフクラブで殴りかかってくると勘違いした。そのため、法益侵害が間近に迫っているとして急迫不正の侵害があると誤信している。よって、Xの主観において①の要件は満たしている。
イ また、XはBがコンビニの店員を助けるために本件行為に及んでおり、防衛の意思があったといえるため、②の要件も満たす。
ウ Aはゴルフクラブという武器を有していたのに対してXは素手で対抗しているため、武器対等の原則から相当性を満たしているとも思える。しかし、XとAは身長が15cm差、体重が25kg差と体格差が大きく、かつ年齢もXが大学生であるのに対し、Aは中年で年齢差も大きい。また、Xは大学の柔道部のキャプテンであったのにもかかわらず、柔道の動きでAに対抗している。これらのことを総合的に考慮すると、本件行為は社会的に許容される行為とはいえず、相当性を満たすとはいえない。そして、体格差や年齢差などは客観的に見ればわかり、かつXは自己が柔道部のキャプテンであることからその過剰性については認識していたといえる。よって、Xの主観において③の要件は満たさない。
⑶ したがって、Xの主観において正当防衛は成立せず、責任故意は否定されない。そのため、Xには傷害致死罪が成立する。
4. もっとも、Xの主観としては過剰防衛となっていることから、いわゆる誤想過剰防衛のときにも36条2項を準用することができるかが問題となる。
⑴ 過剰防衛による刑の任意的減免の根拠は不正の侵害に対する反撃は違法性が減少しているのと同時に、たとえ過剰なものであっても行為者を非難し得ないとの責任減少に求めることができる。
⑵ そのため、本件では責任減少が認められる以上、36条2項を準用するべきである。
⑶ もっとも、過剰性に認識がない場合も、過失犯が成立し、刑が科される可能性がある一方で、故意犯が成立するのに刑が免除されるとなると、不均衡である。そのため、誤想過剰防衛の場合は刑の免除はできず、任意的減軽にとどまる。
第2 問題2
1. Aの首を両手で強く絞めた行為
Xは殺意を持ってAの首を両手で締めて窒息死させていることため、殺人罪(199条)が成立する。
2. Aのスマートフォン及びシステム手帳を持ち去った行為
⑴ XがA宅からAのスマートフォン及びシステム手帳を持ち去っている行為には窃盗罪(235条)が成立しないか。
⑵ 実行行為性
ア 窃盗罪の保護法益は占有であり、「他人の財物」を「窃取」することが成立要件である。「窃取」とは、他人が占有する財物を占有者の意思に反して自己の占有に移転させることを指す。
イ Aのスマートフォン及びシステム手帳は「財物」にあたる。もっとも、AはXが持ち去った時にはすでに死亡しており、Aの占有は認められず、「他人の財物」を「窃取」したとはいえないのではないか。
(ア) 死者には占有を認めることはできない。占有を認めるためには占有の事実と占有の意思を要するが、死者には占有の事実も占有の意思も認められないからである。しかし、自ら被害者を殺害した者との関係では、殺害から財物奪取までの一連の行為を全体的に観察し、生前の占有を侵害するものと評価することができる。よって、その者との関係においては、窃盗罪が成立しうる。
(イ) 本件において、XはAを自ら殺害し、A宅でAを殺害した直後にその場にあるAの財物を持ち去っており、時間的場所的近接性もあり、これらの事情からAの生前の占有を侵害する行為であったと評価できる。
(ウ) よって、「他人の財物」を「窃取」したといえる。
⑶ 不法領得の意思
ア もっとも、Xは保身のために窃取行為に及んでおり、窃取後にスマートフォンを破壊すること及びシステム手帳をシュレッダーにかけることを考えてバッグの中に入れている。
そのため不法領得の意思、特に利用処分意思が欠け、窃盗罪の成立が否定され、器物損壊罪(261条)の成立にとどまるのではないか。
(ア)窃盗罪の成立には、主観的構成要件要素として、不法領得の意思が必要となる。具体的には、不可罰的な使用窃盗と窃盗罪との区別、また、窃盗罪と毀棄罪との区別との観点から、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用・処分する意思である。
(イ)犯行隠蔽目的で財物を持ち出す行為は、一般的に財物から生じる何らかの効用を享受する意思、すなわち利用処分意思が欠けているといえ、不法領得の意思を否定するべきである。
(ウ)本件において、XはAとの関係が知られないように本件窃取行為に及んでおり、犯行隠蔽目的である。そのため、利用処分意思が欠けているといえる。
イ そのため、不法領得の意思が否定される。
⑷ したがって、Xには窃盗罪は成立しない。
⑸ もっとも、上記行為は、スマートフォンとシステム手帳を利用者であるAが利用できないようにしている点で物の効用を害する行為といえ、Xに器物損壊罪が成立する。
3. Aのキャッシュカードを取り出して隠匿した行為
⑴ Xは前述の通り、犯行隠蔽目的でシステム手帳を持ち出し、その後X宅でキャッシュカードの存在に気づき、現金を引き出すために同カードを取り出し、自室内の物入れに隠匿しているが、かかる行為につき、窃盗罪が成立しないか。
⑵ この点につき、毀棄・隠匿の意思で財物を奪取した後に、不法領得の意思が生じたとしても、窃盗罪は成立しない。窃盗罪の保護法益は他人の占有であり、不法領得の意思は占有侵害時に必要であるため、占有侵害時に不法領得の意思がなかった場合には、事後的に生じたとしても、窃盗罪を構成しない。
⑶ 本件において、Aの占有を侵害した時点では、不法領得の意思が前述の通り否定されるため、かかる行為について窃盗罪は成立しない。
以上





