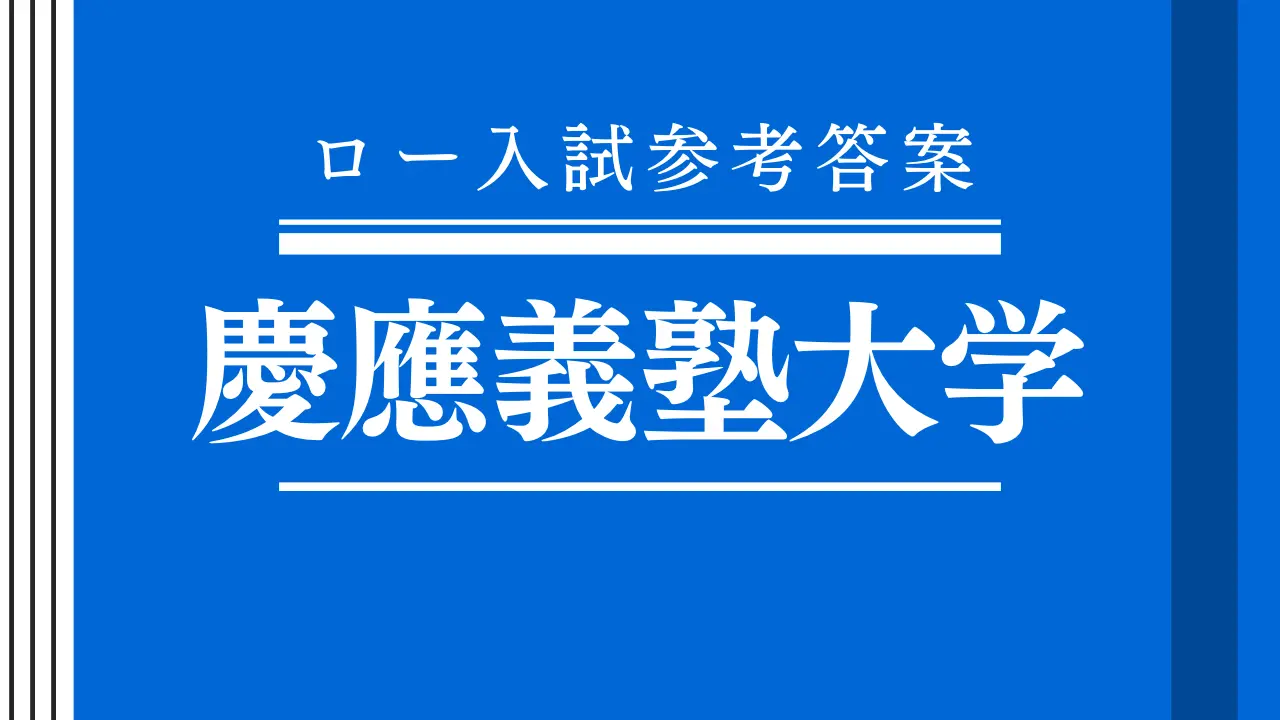
2022年 商法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2022年 商法
設問1
1. 取締役会決議は、「議決に加わることのできる取締役の過半数」の出席且つ、「その過半数」によって決議される(会社法(以下略)369条1項)。後述の通り、本件契約は利益相反取引に当たり、Aはその相手方である。そのため、Aは本来決議に参加できない特別利害関係取締役(369条2項)に該当するのではないかが問題となる。
⑴ 369条2項の趣旨は、取締役の忠実義務(355条)違反を予防し決議の公正を図ることである。そのため、「特別の利害関係」とは、会社に対する忠実義務を誠実に履行することが期待できない個人的利害関係を有する取締役をいう。
⑵ 利益相反取引が取締役会の承認を要する(365条1項、356条1項2号)趣旨は、会社への不利益を防止するためである。とすると、契約金額が安ければ安いほど甲社は経済的損失を被る一方、契約の相手方であるAは個人的利益を得る。そのため、Aは会社に対する忠実義務を誠実に履行することが期待できない個人的利害関係を有する。
⑶ したがって、特別利害関係取締役に該当する。
2. 特別利害関係取締役が決議に参加した取締役会決議は、瑕疵ある取締役会決議に当たるため、法の一般原則に従い原則として無効であるただし、当該取締役を除いてもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情がある場合には、法的安定の要請から、かかる決議も例外的に有効と解するべきである。
⑴ 本問では、Aは議事に参加して本件契約は甲社の通常の販売価格と変わらないことを主張している。たしかに同様の点をBも主張しているものの、Bの主張への支持をより集めやすくしようとしている点で、決議への影響があるといえる。さらに、Aの決議参加がなければ、議決に参加できるB Cの内、半数のBのみの賛成しかなく、賛成の決議とはならなかった点で、決議の結果に影響がある。
⑵ よって、特段の事情も認められない。
3. よって、本件取締役会決議は無効である。
設問2
1. 本件契約は利益相反直接取引に当たるか。
⑴ 取引安全の要請及び間接取引規制からすれば、直接取引における「ために」は、名義、つまり取引の当事者)を意味すると解するべきである(名義説)。
⑵ 本問では、甲社の「取締役」であるAが、A自身(「自己」)を取引の当事者として(「ために」)、甲社(「株式会社」)と本件契約を締結した。
⑶ よって、利益相反直接取引に当たる。
2. よって、前述のとおり、取締役会決議による承認を要するが、本件取締役会は無効である。そこで取締役会決議を欠く利益相反直接取引の効力が問題となる。
⑴ 356条2項が承認を受けた利益相反取引に民法108条の適用を排除していることの反対解釈として、承認を受けていない利益相反取引は民法108条により無権代理行為に当たると解するべきである。そのため、当該取締役との関係では、かかる取引の効果は会社に帰属しない。なぜなら、このように解しても、転得者が存在しない以上、取引の安全を害さないからである。
⑵ 本問では、既述の通り甲社とAの利益相反関係が認められるため、かかる取引の効果は甲社に帰属しない(民法108条2項、113条1項)。
⑶ したがって、甲社はAの請求を拒むことができる。
3. また、本件契約が「重要な財産の処分」(362条4項1号)に該当するかも問題になるが、本件契約の目的物の総資産に占める割合は0.3%であり、一般的に1%未満であれば原則「重要な財産の処分」には当たらないと解されており、これを覆す特別の事情もない。よって、「重要な財産の処分」には当たらない。
以上





