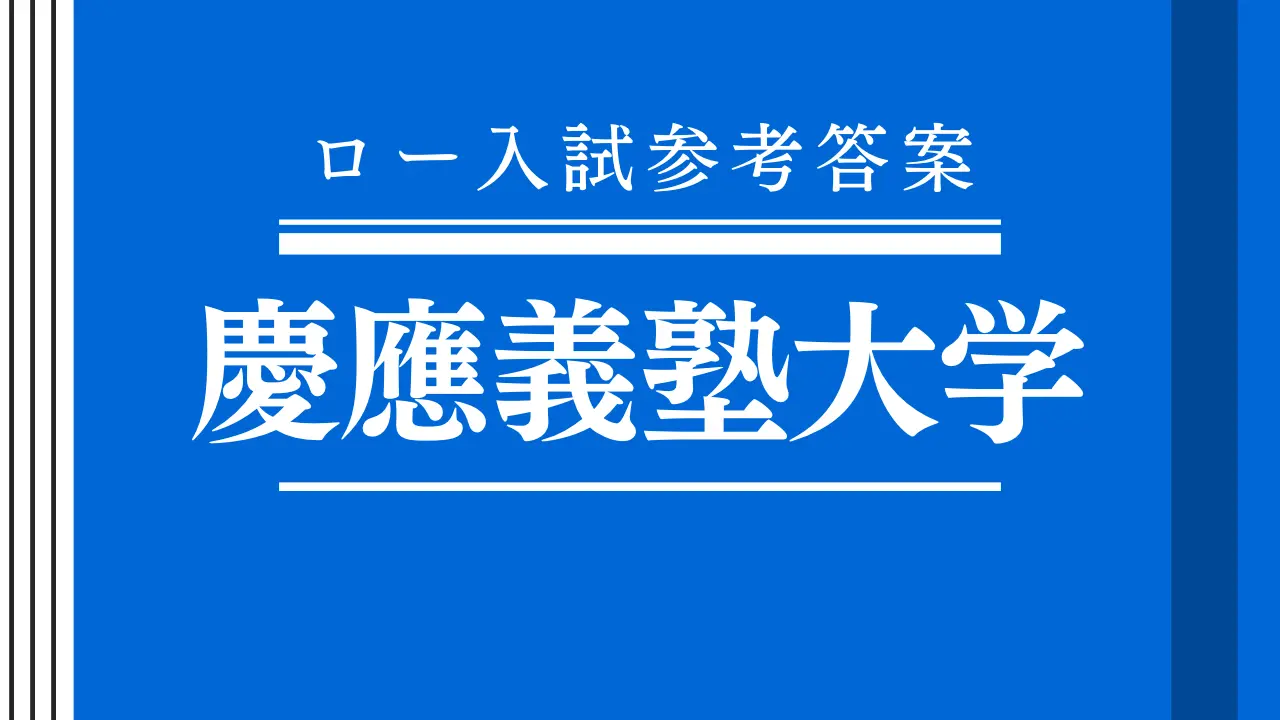
2024年 刑事訴訟法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2024年 刑事訴訟法
第1 設問1 小問(1)
当事者主義的訴訟構造の下、審判対象は検察官の主張する具体的犯罪事実たる訴因である。そのため、検察官の主張する具体的事実に変更が生じた場合には、訴因変更手続(刑事訴訟法(以下、略)312条1項)が必要となるのが原則である。もっとも、多少の事実の食い違いについて、常に訴因変更が必要とするのは訴訟不経済である。そこで、重要な事実に差異が生じた場合に限り訴因変更が必要となると考える。
そして、訴因の第一次的機能は裁判所に対して審判対象を明確にする点(審判対象画定機能)にあり、第二次的な機能は被告に防御の範囲を明確にする点(防御権告知機能)にある。
そこで、訴因変更の要否は、①罪となるべき事実の特定に不可欠な事実に変更が生じ、又は②被告人の防御にとって重要な事実に変更が生じたかを基準に判断する。但し、③ ②の事実に変更が生じた場合であっても、被告人の防御活動等の訴訟の具体的経過に照らして被告人にとって不意打ちとならず、かつ変更前の事実よりも不利益とならないときには、例外的に訴因変更を要しないと解する。
第2 設問1(2)
1. 訴因変更の要否に係る判断は、第1の通り行う。
⑴ 嘱託殺人罪は、「嘱託を受けた」(刑法(以下、「法」という)202条)ことを構成要件として規定していることから、「嘱託」という構成要件に該当する事実は、罪となるべき事実といえる。そして、本件訴因では、「自殺を図ろうとしていた長男V1から嘱託を受け」との事実が記載されている。他方で、裁判所の心証は、“V1からの嘱託を受けずに同人を殺害した“点にあり、「嘱託」に該当する事実に変更が認められる。そこで、罪となるべき事実に変更が生じたといえる(①充足)。
⑵ したがって、裁判所は訴因変更手続を経ることなく、その心証に従い、殺人の事実を認定することはできない。
第3 設問2
1. 訴因変更の要否に係る判断は、第1の通りに行う。
⑴ これをみるに、幇助犯は、「正犯を幇助した」(法62条1項)ことを単独犯を修正する構成要件として規定していることから、「幇助」という構成要件に該当する事実は、罪となるべき事実といえる。そして、本件訴因では、「共謀の上…窓から侵入し、…窃取した」という住居侵入罪及び窃盗罪の共同正犯に係る事実が記載されている。他方で、裁判所の心証は、「普通常用自動車1台を貸与し、よって、…住居侵入及び窃盗を幇助したものである」という点にあり、「幇助」に該当する事実に変更が認められる。そこで、罪となるべき事実に変更が生じたといえるとも思える。
しかし、ここで、縮小して認識される犯罪事実については、当初から検察官により黙示的・予備的に併せ主張されていた犯罪事実と考えることができる。そうだとすれば、縮小認定は、訴因の記載と「異なる」事実認定の問題ではなく、訴因の記載どおりと認定の一態様であることになる。
⑵ これをみるに、「幇助」とは、実行行為以外の行為を以て、正犯者による実行行為を容易にするものをいう。他方で、「共同」(法60条)正犯についても、共謀共同正犯が認められ得ることから、共謀者が実行行為を行なっていない場合にも成立し得る。そこで、幇助犯と共同正犯は、その行為にかかる事実が一般的ないし抽象的に包含関係にあると評価できる。加えて、共同正犯が成立するためには、特定の行為を自己の犯罪を完遂する手段とする意思たる正犯意思を要するところ、正犯意思の有無に係る判断は、「幇助」該当事実足りうる重要な役割を担ったか否かを考慮要素とする。そこで、当該観点からも、両者は一般的ないし抽象的に包含関係にあると評価できる。
したがって、「共謀の上」には「幇助」行為が包含されているといえ、裁判所が上記心証通りに事実認定をすることは、縮小認定にあたる。
⑶ 以上より、本問で訴因変更手続は不要である。
第4 設問3
1. 「公訴事実の同一性」(312条1項)とは、紛争の一回的解決を図りつつ、被告人の防御上の不利益を防ぐという観点から設けられた訴因変更の限界を画する機能的概念である。そこでこのような機能に鑑み、公訴事実の同一性の有無を判断すべきである。
具体的には、両訴因の基本的事実関係の同一性に加え非両立関係の有無を補充的に勘案すべきであると考える。
2. これをみるに、確かに、新旧両訴因で、犯罪当事者たるZ、B及びCの犯罪に関与した立場は異なる。しかし、新旧両訴因に係る犯罪日時及び場所は、令和4年9月5日午後10時頃、H市K町4丁目5番6号所在スナックLと共通しており、また、犯罪行為の当事者がZ、B及びCであるという点及び供与された賄賂が現金30万円であるという点で共通する。そこで、両訴の基本的事実関係は、共通するといえる。
次に、受託収賄罪(法197条1項後段)は、「公務員が、…賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした‥場合において、請託を受けた」(同項)ことを構成要件として定める。他方で、贈賄罪(法198条)は、「贈賄を供与し、又はその申込み若しくは約束をした」(同条)ことを構成要件として定める。賄賂を収受、要求又は約束した者が、同時に贈賄を供与、その申込み又は約束をすることは、事実上両立し得ない。そこで、新旧両訴因は、事実上両立し得ないといえる。
3. したがって、両訴因間に「公訴事実の同一性」は認められる。
以上





