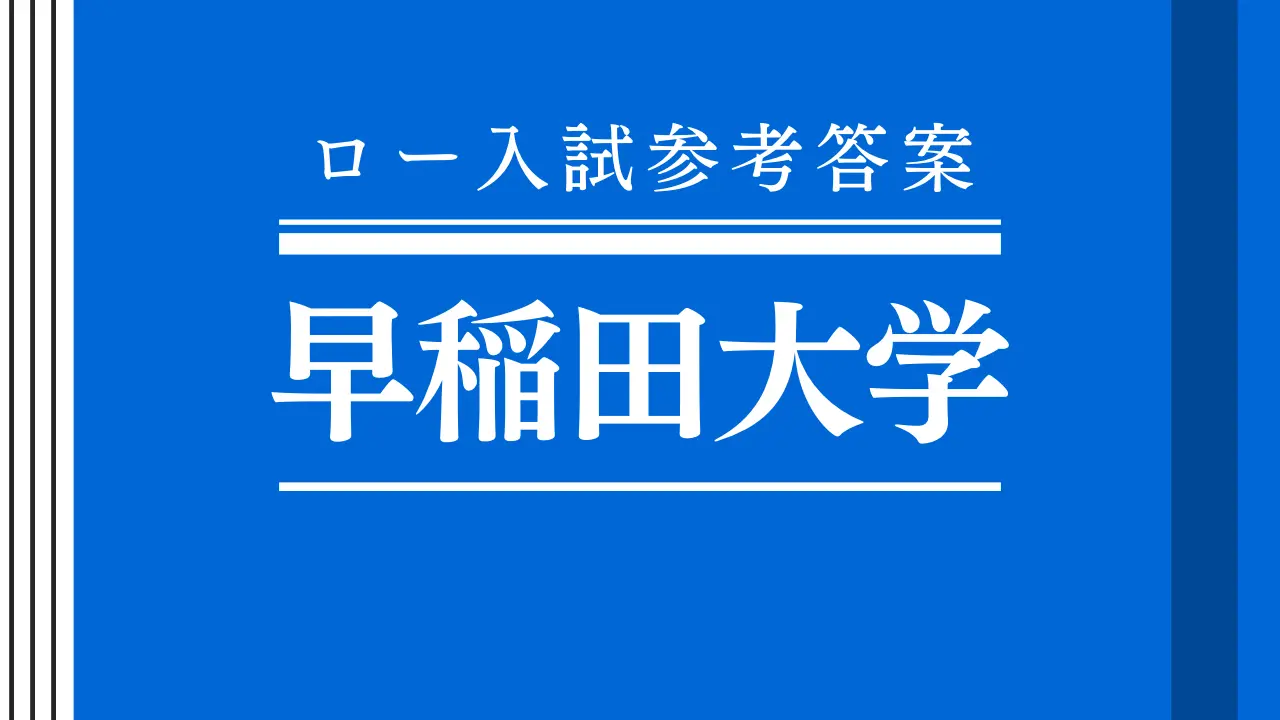
2025年 刑法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2025年 刑法
設問1
1. 甲が、息子を装って高齢者Aに電話をかけ、D名義の口座に500万円を振り込ませようとした行為に、詐欺未遂罪(刑法(以下略)44条・43条本文・250条・246条1項)が成立するか。
⑴詐欺罪(246条1項)は交付罪だから、「欺」く行為とは、「交付」行為に向けられ、財物を「交付」するかの判断の基礎となるような重要な事項を偽る行為をいうと解する。
本件では、甲は、自身がAの息子であり、交通事故を引き起こし、その示談金のためにすぐに500万円の被害者への振込を必要としている旨Aに述べているところ、これらは真実に反する。これらの点を偽った行為は、預金の振込という交付に向けられた行為である。また、甲が真実はAの息子であるか否かはAが振り込みという交付をするかの判断の基礎となる重要な事項である。また、一般人を基準にしてもそういえるから、取引通念上重要な事項を偽ったといえる。
よって、本件行為は「欺」く行為にあたる。
⑵預金は、口座から別口座への振込により、その支配領域の移転が観念できるから、「財物」性が認められる。
⑶Aは、「欺」く行為により、息子が窮状にあるとの錯誤に陥っており、その錯誤に基づき振込行為をしているものの、甲がキャッシュカードを保有しパスワードを知っていることで支配が及んでいるD名義口座への振り込みはなされず、甲は500万円について自己の支配に移転させたとはいえない。
よって、「交付させた」と言えず、結果発生が認められない。
⑷故意(38条1項)及び不法領得意思は認められるから、甲に詐欺未遂罪が成立する(ⓐ)。
2. 乙が、甲の詐欺に加担した行為に、詐欺未遂罪の共同正犯(60条)が成立するか。
⑴60条が「全て正犯とする」として一部実行全部責任を負わせる根拠は、相互利用補充関係にある共犯者が、一体となって結果に対して因果性を及ぼし特定の犯罪を実現する点にある。そこで、①共謀と②共謀に基づく実行行為が認められれば、「共同して犯罪を実行した」として共同正犯が成立すると考える。
⑵ア 本件では、甲から乙に口座からの引出し作業を行うことの「依頼」があった。また、乙はその「受け子」としての役割を「理解」した上これを「引き受け」た。甲から乙に事情が知らされていることや、引き出しをしなければ利用処分ができないことから受け子の役割が非常に重大であることからすれば、特定の犯罪の意思連絡があるといえ、正犯性も認められるから共謀が認められる。
イ 乙が加担した時点では既に甲により実行行為の全てが終了しており、乙が法益侵害危険性惹起に対し因果性を及ぼすことができず②を欠くか。
本件では、Aの振込みによって支配移転へのプロセスは完了し、甲の詐欺未遂罪は終了している。乙の関与は、犯罪終了後の行為であり「交付」結果にすら因果性を持たないから、②は認められない。
⑶以上から、本罪は成立しない。
3. 乙の窃盗未遂罪(243条、235条)
⑴「窃取」とは、相手方の占有する財物を、その意思に反して、自己又は第三者の占有に移転することをいう。
乙の行為は、Aの誤振込のために、事後的・客観的には口座から引き出すことは不能である。それでも「実行」(43条本文)に着手したといえるか。不能犯が問題となる。
未遂犯の処罰根拠は結果発生の現実的危険性の惹起にある。行為時において結果発生の現実的危険性がおよそないのであれば、不能犯として「実行」に着手したとはいえないと解する。構成要件は一般人への行為規範であり、一方で帰責範囲の妥当性も図るべきだから、かかる危険性は、行為時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎に、一般人を基準に判断する。
本件では、乙の行為時点において、Aが誤振込をした事実は、一般人は認識しえず、また行為者乙もこれを認識していなかった。そこで、誤振り込みの事実を除外して判断すると、一般人が財物移転結果の現実的危険を感じるものであったといえ、未遂犯としての処罰は可能であると解する。
また、銀行の占有する現金を引き出そうと、正しいキャッシュカードの使用及びパスワードの正確な入力をすることにより、500万円が自己ないし甲への占有に移転する危険性のある行為をした。銀行は、詐欺などの不法な行為によって振り込まれた金員でないことや、名義人又はその正当な許諾がある者であることを引出しの条件としているといえることから、その条件違反の乙の引出し行為は銀行の意思に反するものといえる。
よって、「窃取」が認められる。
⑵故意及び不法領得の意思も認められる。
⑶よって、乙に本罪が成立し、下記の通り、甲と共同正犯となる。
4. 甲の乙の窃盗についての共同正犯
乙の参加は甲の働きかけに応じたことによるものであり、その計画やキャッシュカードの提供など重要な役割をしている。犯行で得た利益は甲に帰属する予定であったことをも考慮すると、正犯意思が認められ、500万円を引き出すとの範囲で甲との共謀が認められる。乙はこの共謀に基づき引出し行為をした。よって、甲の行為に本罪が成立し、乙と窃盗の限度で共同正犯となる(ⓑ)。
5. 罪数
ⓐ及びⓑは、被害者を異にするから、併合罪(45条前段)となる。
設問2
1. Pにクロロホルムを嗅がせる行為(以下、行為1)に強盗殺人罪が成立するか問題となる。
⑴甲は、詐欺グループのリーダーPに対して多額の借金があり、弁済の目途が立たなくなっていたため、行為1を行っている。そして、これは、以下のように人を死亡させる現実的危険性があるから、「財産上…の利益」の処分に向けられた、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使であり、「暴行」に当たる。
甲には故意が認められるから甲には強盗未遂罪(243条・236条2項)が成立する。
「強盗」には強盗未遂罪に含まれると解されるから、「強盗」(241条1項)に該当する。
⑵また、241条1項に、殺人の故意ある場合も含むか問題となるが、同項は、強盗の機会に致死傷結果が発生することが、刑事学上顕著であるから、これを重く処罰することにあり、故意ある場合を排除する趣旨ではない。したがって、同項には、殺人の故意ある場合も含む。
2. 次に、Pにクロロホルムを嗅がせる行為のみを実行行為とみる限り、行為1は殺人行為といえ客観的構成要件を満たすものの、甲が同行為により人を死亡させる現実的危険を認識していないので、未必的な故意すらなく、強盗殺人罪は成立しない。
⑴では、行為1の時点で、Pを自動車ごと海中に転落させて沈める行為(以下、行為2)を通じた結果発生の現実的危険が生じたとして、行為2の「実行に着手」(43条本文)したといえないか。実行の着手が認められれば、一連の実行行為により殺害する認識により、故意も認められうるから問題となる。
⑵「実行に着手」(43条本文)とは、その文言と実質的処罰根拠より、①構成要件該当行為に密接し、②既遂結果発生の現実的危険性を有する行為をいうと解する。行為者の計画も考慮に入れ、⒜構成要件該当行為を確実かつ容易に行うための準備的行為の必要不可欠性、⒝準備的行為以降の計画遂行上の特段の障害の存否、⒞両行為の時間的場所的近接性などを総合して判断する。
まず、甲は、行為1によりPの意識を失わせた上で近くの港まで運び、失神した同人を車ごと海中から転落させて溺死させる計画を立てている。かかる計画に照らすと、行為1がなければ、行為2を行うことは極めて困難であることから、行為1は、行為2を確実かつ容易に行うために必要不可欠な行為といえる。また、行為1を行えば特段の支障もなく、行為1後すぐに行為2を行うことができる。そうすると、行為1の時点で、一連の行為に着手したといえる。
⑶一連の行為は、Pが死亡する現実的危険を有する行為であり、強盗殺人罪の実行行為に当たる。また、Pは死亡している。では、一連の行為「によって」死亡したと認められるか。行為1の後、行為2は行われず、甲の丙と共にしたPの殴打行為が介在し、Pは丙の殴打行為によって生じた硬膜下血腫が原因で死亡しているから問題となる。
因果関係を肯定できるのは、当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重い刑法的評価を加えるに足る関係が認められるときである。そこで、因果関係は当該行為に内包する危険が結果として現実化したといえるときに認められると解する。
たしかに、行為1自体に直接に、硬膜下血腫によってPを死亡させる危険は内包されていない。もっとも、行為1は、詐欺グループのリーダーPを被害者とするものであり、犯行隠滅行為として対立する詐欺グループとの抗争を装うこともあるといえ、その際になされる殴打行為により硬膜下血腫を生じせしめ、よってPを死亡させる危険を内包するといえる。そうすると、甲と丙がした殴打行為は、行為1に誘発されたものであり、行為1と一連の行為といえる。よって、行為1の危険が結果として現実化したといえる。
⑷もっとも、甲が予測した因果の流れは、行為2を通じたPの死亡であり実際と異なるが、故意は認められるか。
故意責任の本質は、犯罪事実の認識によって、規範の問題に直面し、反対動機が形成できるのに、あえて犯罪に及んだことに対する道義的非難である。犯罪事実は、刑法上構成要件として与えられるところ、行為者が事前に予見した因果経過と実際の因果経過とが、危険の現実化の範囲内で符合しているならば、認識と客観が構成要件的評価として一致しているといえるから、故意責任を問える。
甲が予見したのは、行為2の危険がPの死として現実化する因果経過であり、上記実際の因果経過と、行為の「人を殺」す危険が現実化したという範囲で符合するので故意も認められる。
⑸よって、甲に強盗殺人罪が成立する。
3. 丙が、Pを殴打した行為に、丙に殺人罪が成立する。
丙は、Pの頭部を角材で複数回殴打するという人の死亡する現実的危険性の高い行為を行い、よって、Pは死亡しているし、丙はそのことを認識しており故意も認められるうえ、あくまで自らの犯罪として行っているから正犯性に欠けるところもないからである。
4. 甲が、乙とPを殴打した行為に、殺人罪若しくは強盗殺人罪の共同正犯(60条)が成立することはない。共謀内容は、犯行を隠滅するためにPの死体に対して攻撃を加える死体損壊罪(190条)を行うことを内容とするものであり、殺人罪若しくは強盗殺人罪の共謀はないからである。また、死体損壊罪と殺人罪若しくは強盗殺人罪は保護法益を全く異にするため、死体損壊罪の共同正犯も成立しない。
以上





