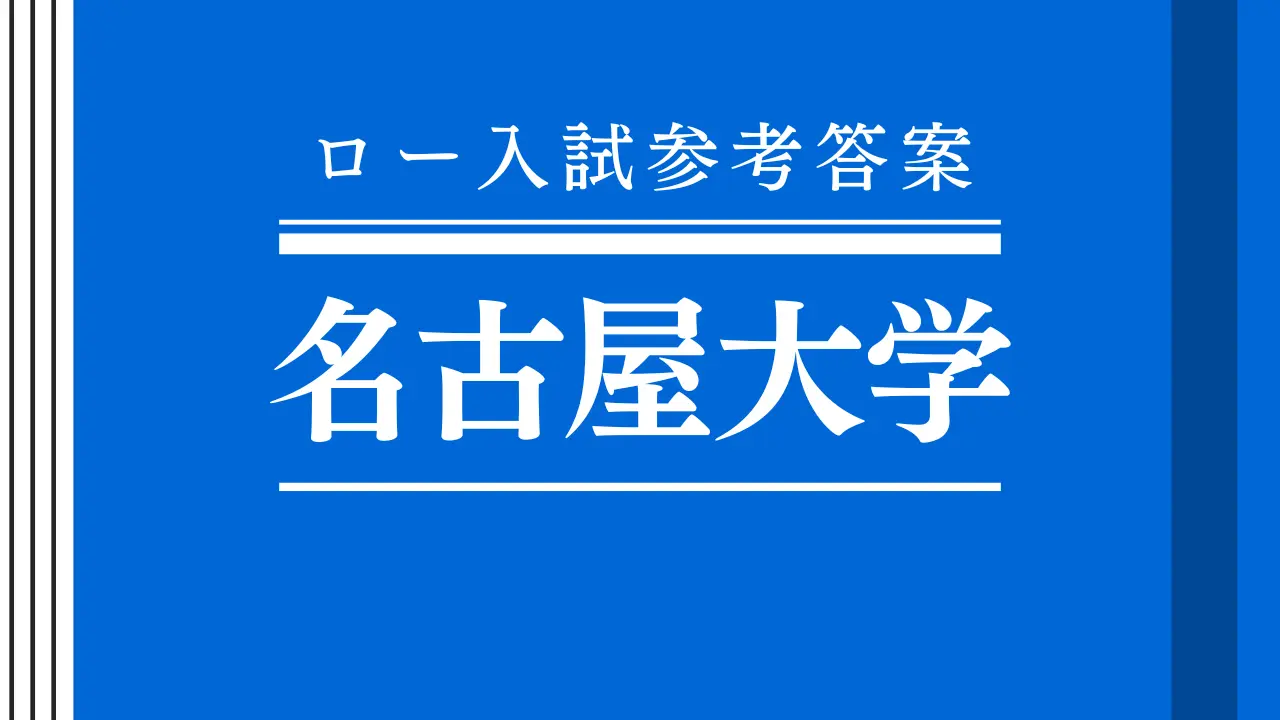
2025年 刑事法系 名古屋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/14/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
名古屋大学法科大学院2025年 刑事法系
設問Ⅰについて
1. 中止行為における任意性は、「自己の意思により」(43条但書)犯罪を中止したといえるかにより判断される。判例においては、やろうと思えばできたものの、あえてやらなかった場合には任意性が肯定されるとの判断枠組みが示されており、外部的事情の有無のみによって結論を出すものではないと解されている。
2. 学説上は、大別して主観説と客観説が主張されている。
⑴主観説は、行為者自身ができると思ったのに止めたのか、それともできないと思って止めたのか、を基準とする見解である。
⑵一方で客観説は、行為者の認識した事情を基礎として、社会通念上犯行の障害となるものであるか否か、を基準とする見解である。
設問Ⅱについて
1. 甲の罪責について
⑴万引きを目的として大型書店に立ち行った行為について、建造物侵入罪(130条)が成立するか。
ア 大型書店は、入口に警備員を配置していたのであるから、「人の看守する…建造物」に当たる。
イ 「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいう。甲は一般の客を装っており、警備員も一見不審者でなければ誰でも立ち入らせていたのであるから、管理権者の意思に反しないとも思える。しかし、甲が万引き目的であることを管理権者が知っていれば、立ち入りを拒否したと解されるため、甲の立ち入りは管理権者の合理的意思に反するものであるといえる。したがって、「侵入」にあたる。
ウ よって、上記行為につき建造物侵入罪が成立する。
⑵新刊書数冊を鞄に入れて持ち去り、追いかけてきたXに暴行を加えて逃走した行為について、事後強盗罪(238条)が成立するか。
ア 甲は新刊書数冊という「他人の財物」を自己の占有下に移転させることで「窃取」している。また、不法領得の意思及び故意に欠けるところはない。したがって、「窃盗」にあたる(235条、238条)。
イ 「暴行」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使をいう。甲はXを手拳で何度も殴打し、それでも手を離さなかったXに対して乙とともに何度も足蹴にしているため、客観的に見て相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使が認められ、「暴行」にあたる。
ウ 甲は追いかけてきたXを振り払おうとしており、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れる」目的であるといえる。
エ 甲につき、不法領得の意思及び故意に欠けるところはない。
オ よって、上記行為につき事後強盗罪が成立し、後述の通り乙との間で共同正犯となる。
⑶以上より、甲には事後強盗罪の共同正犯及び建造物侵入罪が成立する。
2. 乙の罪責について
⑴甲と意思を通じた上でXに暴行を加え、盗んだ本を持ち去った行為について、事後強盗罪の共同正犯(238条、60条)が成立するか。
ア 乙は甲から本を盗んできた状況について説明を受けており、助力することを承諾しているため、犯罪実行についての合意があるといえ、共謀が認められる。また、上記行為はかかる共謀に基づくものである。
イ ここで、上記共謀は甲による窃盗が終了した後に成立しているところ、乙は犯罪全体について責任を負うか。事後強盗罪の法的性質が問題となる。
(ア)事後強盗罪は条文の文言上、「窃盗が」と規定しており、窃盗犯が身分であることを前提としているように読める。そこで、実行行為が暴行又は脅迫であり、「窃盗」は身分であると解する。
(イ)ここで、「窃盗」犯たる身分のない乙について事後強盗罪の共同正犯の成否が問題となる。65条はその文言から、1項が真正身分犯についての成立及び科刑を、2項が不真正身分犯についての成立及び科刑を規定したものと解する。そして、事後強盗罪については保護法益の異なる暴行罪・脅迫罪の加重類型と解するべきではないため、「窃盗」犯であることを成立要件とする真正身分犯であると考える。したがって、乙については65条1項が適用される。
⑵よって、上記行為につき事後強盗罪の共同正犯が成立する。
3. 罪数
甲には事後強盗罪の共同正犯及び建造物侵入罪が成立し、両者は目的と手段の関係であるため、牽連犯(54条1項後段)となる。乙には事後強盗罪の共同正犯が成立する。
以上





