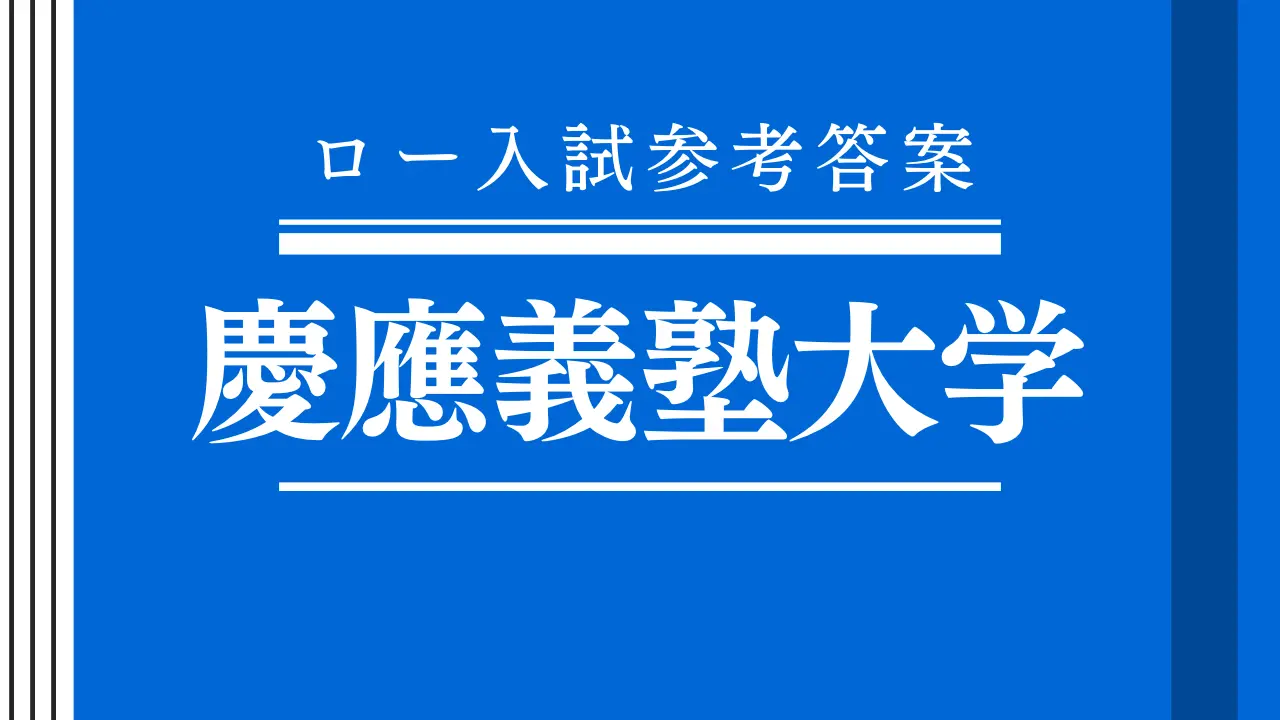
2024年 民法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2024年 民法
第1 設問1
1. 請求の内容
⑴ DのBに対する請求は、賃貸借契約終了に基づく返還請求として、甲の4階、5階部分の明渡請求をすることが考えられる。
⑵ これをみるにAは、2021年5月20日、Bとの間で、甲4階と甲5階を、賃料月額各100万円、期間を同年6月1日から5年間とする約定で、スポーツ・ショップの営業を目的として賃貸する契約を締結した(民法(以下、略)601条)。Bは、同年6月1日、同契約に基づいて、甲4階と甲5階の引渡しを受けている。
⑶ そして、Aは、翌年3月1日、Dに対し、甲を売却した(555条)。Bの賃借権に対抗力が具備されていることから(借地借家法31条)、これによりAの賃貸人たる地位はDに移転する(605条の2第1項)。そして、Dは所有権移転登記を済ませているので、賃貸人たる地位の移転をBに対抗することができる(同条第3項)。
⑷ この点、本問では上記賃貸借期間途中での明渡請求なので、Dとしては、解除による本件賃貸借契約の終了を主張することになる。
ア 無断転貸
Bは、2022年5月15日、Aに無断で、甲5階を、賃料月額100万円、期間を同年6月1日から4年間とする約定で、Cに賃貸する契約を締結しており、これは「賃貸人の承諾」を得ることなく「転貸」したものである(612条1項)。そして、Cは、同契約に基づき、同年6月1日に甲5階の引渡しを受けており、Bは「第三者に賃借物を使用又は収益させた」ものと認められる(同条2項)。
イ 用法遵守義務違反
また、本件賃貸借契約は、スポーツ・ショップの営業を目的としている。にもかかわらず、甲5階はスポーツ・バーとして利用されていることから、用法遵守義務(616条、594条1項)に違反するものと認められる。
ウ 上記アイから、DにはBD間賃貸借契約の解除権(民612条2項、541条本文)が生ずる。そのため、Dは、Bに対し、同解除権を行使する旨の意思表示(540条1項)をすることが考えられる。これに対して、Bは、賃貸借契約は当事者間の信頼関係に基づく直期の契約であるから、賃借人の債務不履行が当事者間の信頼関係を破壊するに至らない場合、賃貸人は当該債務不履行を理由に賃貸借契約を解除することができないところ(541条但書)、本件では背信行為と認めるに足りない特段の事情が存在すると主張することが考えられる。
確かに、スポーツ・バーの営業開始にあたって、甲を改装していることから、使用形態の変化は軽微なものとはいえない。しかしながら、本件では、Bとその妻、その弟Cという「家族ぐるみ」で事業を手伝いまた支援していたことから、利用主体には大きな変化があったとは認められない。また、Dは、2023年2月1日にEの案内で甲を見学し、スポーツ・バーであることを確認のうえ気に入って甲を購入したという事情が存在する。にもかかわらず、同年6月になって、甲4階及び甲5階を月額合計400万円で借りたいという者が現れたとの理由から解除を主張するものであり、上記アイを理由とするものではない。そうすると、背信行為と認めるに足りない特段の事情が認められる。
したがって、DによるBD間賃貸借契約の解除は認められない。
⑸ 以上より、Bに対する請求は、認められない。
2. Cに対する請求の当否
Cに対する請求は、所有権に基づく返還請求としての明渡請求である。これをみるに、Dによる甲の所有及びCによる甲5階の占有は認められる。これに対し、Cは、転借権に基づく占有権原の抗弁を主張すると考えられる。BC間の転貸借契約はBの承諾を得ていないものの、前述のように背信行為と認めるに足りない特段の事情が存在するため、Cは適法に転借権を取得する。したがって、Cの主張は認められる。
よって、Cに対する請求も認められ得ない。
第2 設問2
1. まず、Cは、Bに対し、必要費償還請求(608条1項)として 200万円の支払を請求することが考えられる。同条では、「賃貸人の負担に属する」「必要費」であることが要件とされている。
雨漏りを止めるための補修は物の保存に通常必要な費用であり、「必要費」に該当することは明らかである。賃貸人は賃貸物の使用・収益に必要な修繕をする義務を負っており(606条1項本文)、本問で修繕を要するようになったのは大地震によるのであって賃借人の帰責事由によるものではないため(同項ただし書)、上記必要費は「賃貸人の負担に属する」ものである。
したがって、Cのこの請求は認められる。
2.また、Cは、Dに対し、①債権者代位権(423条1項本文)、又は②転用物訴権(703条)に基づいて、補修費200万円の支払を請求することが考えられる。
⑴ 上記①については、債権保全の必要性としてBの無資力という要件が満たされていることを前提に、被代位権利をBのDに対する必要費償還請求権、被保全債権をCのBに対する必要費償還請求権とすることが考えられる。もっとも、Bは、未だ「費用を支出」(608条1項)しておらず、BのDに対する必要費償還請求権は発生していない。
したがって、被代位権利が存在せず、Cの請求は認められない。
⑵ 上記②について、Cは、甲の修繕費を出捐したこと(Cの損失)、及び甲がDの所有物であること(Dの利得)を主張することが考えられる。
ア これに対し、Dとしては、CはBに対する必要費償還請求権を取得する以上、甲の価値の増加によるDの利得は、Bの財産に由来するものといえ、Cによる甲の修繕との間に直接の因果関係が認められないと主張することが考えられる。
しかし、Bが無資力の場合にはCのBに対する債権の無価値化するため、甲の価値増加はなおCの費用支出に由来したものといえ、直接の因果関係が認められる。
イ また、前述のように、BのDに対する必要費償還請求権は、CのBに対する必要費償還請求権を弁済しない限り発生し得ないため、DB間の関係を全体としてみてDが対価関係なしに右利得を得たといえ、同利得には「法律上の原因」が存在しないと認められる。
3. なお、CのAに対する代位請求(423条1項本文)及び転用物訴権に基づく直接請求(703条)は、Aがこれに先立つ賃貸人の地位の喪失、先立つ所有権の喪失をそれぞれ反論として主張することができるため、認められない。
以上





