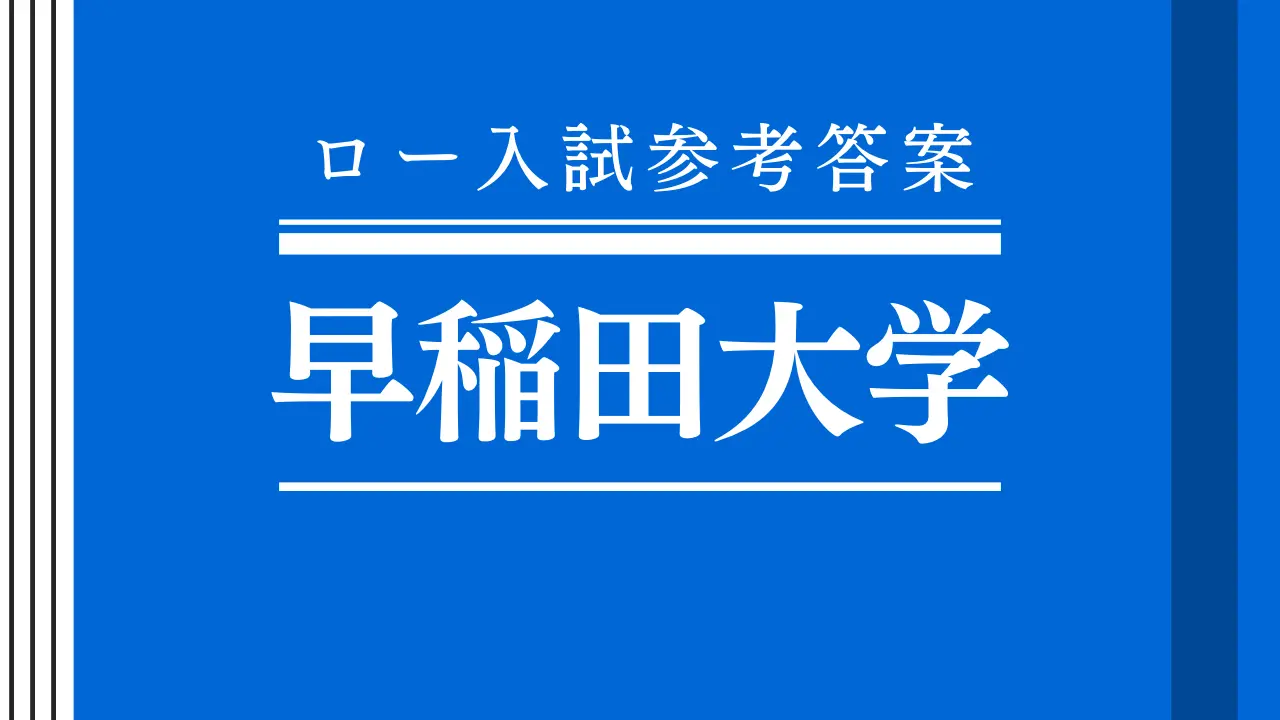
2024年 民事訴訟法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2024年 民事訴訟法
1. まず、本件判決の既判力について論じる。
⑴ 「既判力」(民事訴訟法(以下、略)114条1項)とは確定判決の判断内容についての後訴への拘束力であるところ、「主文に包含するもの」すなわち訴訟物の範囲につき生じる。また、前訴基準時に生じた既判力が後訴に作用する場面は前訴訴訟物と後訴訴訟物が同一・先決・矛盾いずれかの関係にある場合であり、作用する場合、既判力は前訴基準時における訴訟物の存否の判断に矛盾する後訴での当事者の主張を排斥し(消極的作用)、かかる判断と矛盾する裁判所の判断を禁止する(積極的作用)効力を有する。なお、基準時とは前訴最終口頭弁論終結時(民事執行法35条2項)である。当事者はその時点まで裁判資料の提出ができるし、裁判所もそれを元に心証形成するからである。
また、114条2項における既判力の客観的範囲について、同項の趣旨は反対債権の二重行使それによる二重利得を防止することによって紛争の一回的抜本的解決に資する点にある。そこで、「相殺をもって対抗した額について」とは反対債権の不存在についてとの意義であると解する。
⑵ これを本問についてみるに、XはYを被告として、本件請負契約(民法632条)の残報酬1000万円の支払を求める訴えを提起している。したがって、前訴訴訟物はXのYに対する請負契約に基づく報酬支払請求権1000万円である。このXの請求に対し、Yは、口頭弁論期日において、Xに対して有していた1200万円の本件売買代金債権を自動債権として対当額で相殺する旨の相殺の抗弁(民法505条・506条)を主張した。そして、審理の結果、裁判所は本件請負契約に基づく残報酬債権は1000万円であること、本件売買代金に関しては500万円が支払済みであり、残額は700万円であることをそれぞれ認定したうえ、反対債権たる700万円の売買代金債権を自動債権とする相殺を認め、Yに300万円の支払を命じる一部認容判決を下し、本件判決を確定した。したがって、既判力は114条1項によって前訴基準時における本件前訴訴訟物の存在につき、同条2項により前訴基準時における1000万円の売買代金の不存在につき生じる。
2. その後、YはXを被告として後訴を提起しており、この訴訟物はYのXに対する売買契約(民法555条)に基づく代金支払請求権200万円であり、後訴の訴訟物は前訴訴訟物と同一・先決・矛盾関係にないことから原則として前訴基準時に生じた既判力は及ばない。
3. もっとも、信義則(2条)により例外的に後訴の却下が認められないか。
⑴ この点、相殺の抗弁には、抗弁でありながらもそれ自体訴訟物となり得る反対債権を持ち出すという特殊性がある。すなわち、相殺の抗弁は、その債権自体を訴訟物として審理した場合と同じ審理を当事者、裁判所に求めるものである。そうすると、前訴で債権の一部を相殺に供し、これが一部棄却された場合に、後訴で棄却部分を請求することは、数量的一部請求に対する一部棄却がされた場合と同様であると解することができる。
⑵ そして、通常は一部請求であっても、当該債権全体について弁論を尽くし、審理がなされるから前訴の一部請求が棄却された場合には、残部も存在しないとの判断がなされていると考えるのが自然である。とすれば、同一債権について、残部の支払いを求める後訴は、実質的には前訴で認められなかった主張を蒸し返すものであり、前訴確定判決によって当該債権全体について紛争が解決されたとの相手方の合理的期待に反し、被告に二重の応訴を強いるものである。したがって、前訴で相殺の抗弁に供された債権全体について審理がなされなかった等の特段の事情がない限り、後訴の訴えは提起は、信義則に反するといえるため、裁判所は控訴を遮断すべきである。
⑶ 本問では、前訴において相殺の抗弁が一部棄却されているが、前訴において債権全体について審理がなされなかったなどの特段の事情は存在しない。したがって、裁判所は、Yの後訴における訴えを信義則に反するとして棄却すべきである。
以上





