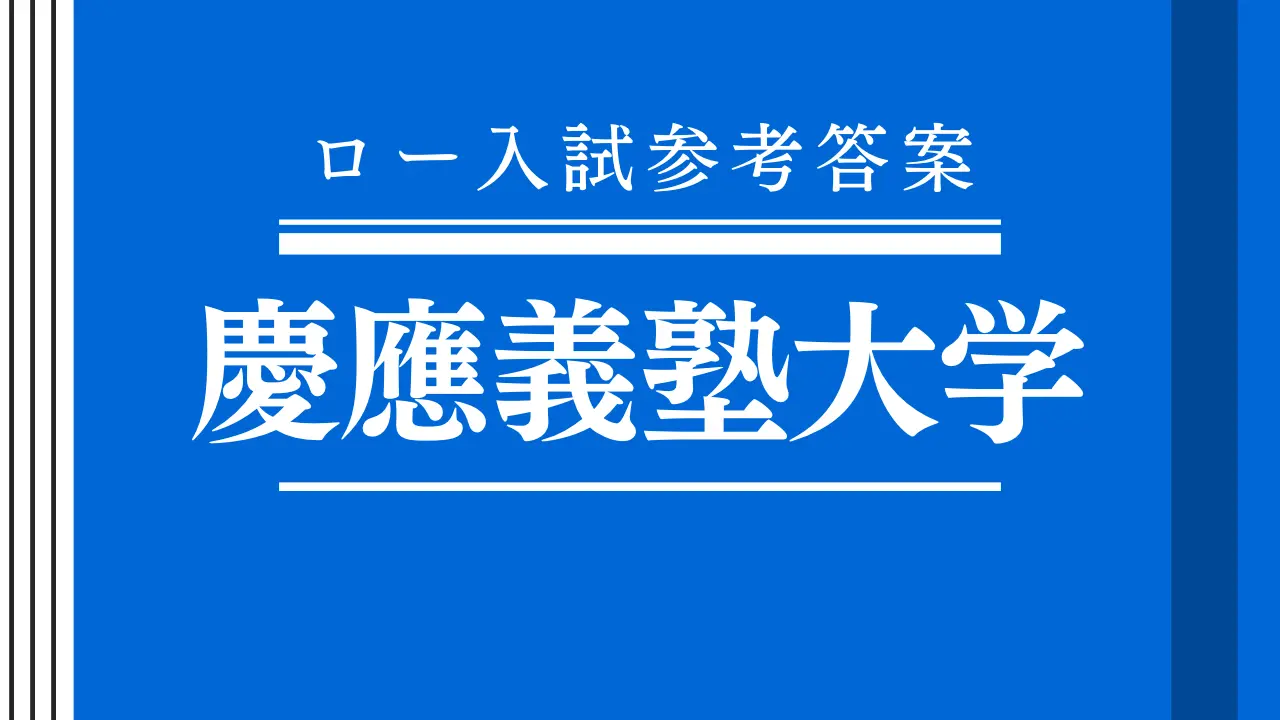
2025年 刑法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2025年 刑法
設問1
1. 甲の罪責
⑴ 甲が A を脅迫及び緊縛するなどして 300 万円を奪った⾏為について、強盗罪の共同正犯(刑法(以下略)60 条、236 条 1 項)が成⽴するか。
⑵まず「暴⾏⼜は脅迫」(同項)とは、客観的に相⼿⽅の反抗を抑圧するに⾜りる程度の不法な物理⼒の⾏使⼜は害悪の告知をいう。 ⼀⼈暮らしで、体調を崩している者の家に成⼈男性が押し⼊り、「死にたくなかったら⾔うことを聞け」との申し向けることは、相 ⼿⽅に傷害や死の危険を抱かせ、⼼理的に抵抗不能な状態を陥らせる害悪の告知といえるうえ、粘着テープで⾝体を緊縛し物理的にも抵抗不能な状態にしている。そのため、客観的に相⼿⽅の反抗を抑圧するに⾜りる程度の不法な物理⼒の⾏使及び害悪の告知があるといえ、「暴⾏⼜は脅迫」が認められる。
Aの現⾦300万円は「他⼈の財物」(同項)に当たる。
「強取」(同項)とは、暴⾏・脅迫により、相⼿⽅の反抗を抑圧することで、その意思によらず財物を⾃⼰⼜は第三者の占有に移すことをいう。本件では、甲の上記⾏為によ って A は抵抗が困難になっており、現⾦ 300 万円を奪っていることから、「強取」が認められる。
⑶「故意」(38 条 1 項本⽂)とは、客観的構成要件該当事実の認識・認容をいう。甲は ⼄と計画して犯⾏に及んでいることから、⾃⾝の⾏為を認識・認容していたといえ、「故意」が認められる。
また、甲は、失業中であり、現⾦ 300 万円は⼭分けし、⾃⾝のものとして使う意思であったことから、不法領得の意思が認められる。
⑷したがって、甲がAを脅迫及び緊縛するなどして300 万円を奪った⾏為について、強盗罪が成⽴し、後述するように、⼄と丙との間で窃盗罪の共同正犯となる。
2. ⼄の罪責
⑴甲がAを脅迫及び緊縛するなどして 300 万円を奪った⾏為が⼄にも帰責し、甲及び丙との間で強盗罪の共同正犯が成⽴するか。
⑵⼄は、甲に犯⾏を提案・計画しただけであり実⾏⾏為を⾏っていないため、甲の強盗⾏為ないし結果が帰責するかが問題となる。
この点について、実⾏⾏為を担当していない者が実⾏に準ずる重要な役割を果たし、実⾏⾏為者とともに構成要件該当事実を共同惹起 したと⾔える場合には、共謀共同正犯が認められると解する(準実⾏⾏為説)。そして、 共犯の処罰根拠は、共犯者を通じて間接的に構成要件的結果発⽣の現実的危険性を発⽣させ、共犯⾏為が結果に対して物理的・⼼理的因果性を及ぼす点にあることから、共謀及び共謀に基づく実⾏⾏為が認められる場合には、共同正犯が成⽴する。
⑶⼄は、甲に A 宅の現⾦を盗み出すことを提案・計画し、甲に窃盗を実⾏するための情報を提供していたことから、犯罪共同の合意が形成されていたといえ、意思連絡が認められる。
同様の事情から、甲に犯⾏の機会を提供したのは⼄と評価でき、⼄は犯⾏のために重要な役割を果たしている。
また、報酬を⼭分けする計画であったことから、正犯性が認められる。
よって、⼄及び甲との間で窃盗罪(235条1項)についての共謀が認められる。
⑷ 甲及び⼄は窃盗についての共謀が認められるが、甲が実⾏したのは強盗である。そこで、甲の⾏為は共謀に基づく実⾏⾏為といえるか否か、いわゆる共謀の射程が問題となる。
共犯の処罰根拠は結果に対して因果性を与えた点にあることから、その判断は、ⅰ当初の共謀と実⾏⾏為の内容との共通性(被害者の同⼀性、⾏為態様の類似性、法益侵害の同⼀性など)、ⅱ当初の共謀による⾏為と過剰結果を惹起した⾏為との関連性(機会の同 ⼀性、時間的場所的近接⽣など)、ⅲ犯意の単⼀性・継続性、ⅳ動機・⽬的の共通性とい った事情を総合的に考慮して決する。
窃盗罪と強盗罪の保護法益は、財物の占有であり、共通であると考えられる上、相⼿⽅の意思に反して財物の占有を移転するという意味で、犯⾏態様の共通性がある。また、甲は当初の共謀で想定されたのと同⼀の被害者から、当初の共謀と同⼀の財物を⽬的にして 犯⾏に及んでいる。これらの事情から、当初の共謀と実⾏⾏為の内容との共通性が認められる(ⅰ)。
また、当初の共謀では A 宅に⼈がいることが想定されていなかった。そのため、甲はより確実に⾦銭を奪うために窃盗から強盗に犯⾏計画を切り替えたとみることができ、犯⾏対象の財物が同⼀であることを考えると、当初の共謀による⾏為と過剰結果を惹起した⾏為との関連性が認められる(ⅱ)。
さらに、甲らは、当初の共謀と同じように、取得した 300 万円を⼄と⼭分けするつもりであって、実際に甲と⼭分けされたことか ら、犯意の継続性及び⽬的の共通性が認められる(ⅲ,ⅳ)。
このような事情から、当初の共謀が強盗に対して因果性を与えたといえ、甲の犯⾏は⼄との共謀に基づく実⾏⾏為である。
⑸共犯者たる甲が客観的には強盗を⾏っているが、⼄がその事実の認識を⽋いているた め、強盗罪の「故意」(38 条 1 項本⽂)を⽋き、強盗罪によって処断することができない (同2項)。
では、⼄が認識していた軽い犯罪である窃盗罪の共犯の「故意」を認めることができないか。
両犯罪の構成要件が同質で重なり合いが認められる場合、すなわち⾏為の共通性と保護法益の共通性が肯定される場合には、「故意」が認められると解する。 上記の通り、窃盗罪と強盗罪は、保護法益は占有と共通であると考えられ、被害者の意思に反して財物を取得するという点で⾏為態様の共通性も認められる。そのため、両罪は同質であり、構成要件の実質的な重なり合いを認めることができる。
よって、⼄には、軽 い窃盗罪の限度で、「故意」を肯定することができる。 ⑹ 共同正犯の関与者間に何罪の共同正犯が成⽴するのか問題となるところ、構成要件の 重なり合う限度で、「犯罪」の「共同」(60条)を認めることができる。本件では、窃盗罪の限度で共同正犯となる.
⑺ 以上より、甲がAを脅迫及び緊縛するなどして 300 万円を奪った⾏為が⼄にも帰責され、甲と丙との間で窃盗罪の共同正犯が成⽴する。
3. 丙の罪責
⑴甲がAを脅迫及び緊縛するなどして 300 万円を奪った⾏為が丙にも帰責し、甲と⼄との間で強盗罪の共同正犯が成⽴するか。
⑵上記より、共謀及び共謀に基づく実⾏⾏為が認められる場合には共同正犯が成⽴する。
本件において、丙は甲から窃盗の計画を共有して、共に実⾏していたことから、犯罪共同の合意が形成されていたといえ、意思連絡が認められる。丙は、窃盗のために運転と⾒張りを担当したことから、犯⾏のために重要な役割を果たしている。また、報酬を⼭分けする計画であったことから、正犯性が認められる。よって、甲との間で窃盗罪(235 条 1 項)についての共謀が認められる。
⑶ 次に、共謀の射程が問題となるところ、⼄と同様の事情で共謀の射程が及ぶ。また、「故意」(38 条 1 項本⽂、2 項)も同様に認められる。さらに、構成要件の重なり合う窃盗罪の限度で共同正犯が成⽴する。
⑷甲が A を脅迫及び緊縛するなどして300万円を奪った⾏為が丙にも帰責し、甲と⼄との間で窃盗罪の共同正犯が成⽴する。
設問2
1. 甲が A 宅から現⾦を盗もうとし、B にナイフを向けた⾏為について、強盗致傷罪(240 条)が成⽴するか。
2. 甲は、現⾦を取得できておらず窃盗罪の既遂に⾄っていないが、「実⾏に着⼿した」(43 条本⽂)といえ、「窃盗」(238 条)に当たるか。なお「窃盗」には、窃盗未遂も含まれる。
43 条の⽂⾔上、実⾏の着⼿は構成要件該当⾏為に密接した⾏為であることが要求される。また、未遂犯の処罰根拠は、構成要件的結果発⽣の現実的危険性を惹起させた点にある。したがって、構成要件該当⾏為に密接し、構成要件的結果発⽣の現実的危険性が認められた時点で、「実⾏に着⼿した」と認められると解する。
窃盗罪では、財物の取得に⾄っていない場合でも⽬的物に⾏きかけた時点で、財物取得⾏為の密接性及び占有移転の危険性が⽣じるため、「実⾏に着⼿した」といえる。
本件において、甲は現⾦が存在すると考えられる箪笥に近寄ろうとしているため、「実⾏に着⼿した」といえる。 よって、甲は窃盗未遂犯であり、「窃盗」に当たる。
3. 事後強盗罪における「暴⾏⼜は脅迫」は上記の強盗罪における「暴⾏⼜は脅迫」と同じ意味であると解されるところ、ナイフを向けて「どかないと刺すぞ!」と⾔うことは、客観的には相⼿⽅の反抗を抑圧するものである。本件において、Bは怯んでいるだけであり反抗抑圧されたとはいえないが、反抗抑圧の程度は客観的に評価するものだから、「脅迫」(238 条)が認められる。
また、これはA 宅に駆けつけた警察官Bに向けて⾏われた⾏為であり、「逮捕を免れ」(238 条)る⽬的である。
4. 明⽂はないが、事後強盗罪において、窃盗後の暴⾏・脅迫は、強盗罪における財物奪取⼿段としての暴⾏・脅迫との均衡を図る必要があることから、窃盗の機会に⾏われることが要請される。そして、窃盗の機会に⾏われたといえるか否かは、窃盗犯⼈に対する追及可能性が継続していたか否かで決すべきである。
甲は、A宅内の屋根裏部屋におり、逃⾛することが困難な状態にあることから、未だ A 及び B による追及可能性が継続している。そのため、窃盗の機会性が肯定される。
5. 甲は現⾦を盗み出す⽬的で、ナイフは万が⼀のために携帯していたことから、⾃⾝の⾏為の意味を認識・認容していたといえ、「故意」(38 条 1 項本⽂)が肯定される。同様に、不法領得の意思も肯定される。
6. 事後強盗罪の未遂既遂の区別は、窃盗の既遂未遂によって区別されると解されるところ、強盗致傷罪の「強盗」は強盗未遂犯も含まれる。したがって、甲は強盗未遂犯であるが、「強盗」(238 条)に当たる。
7. A の傷害結果は甲に帰責されるか否かが問題となる。
240 条の趣旨は、強盗の機会に死傷結果をもたらす残虐⾏為を伴うことが少なくなく、 その害悪性に鑑みて重罰に処する点にある。そのため、致死傷結果の原因⾏為は、強盗の機会に⾏われたことで⾜りると解すべきである。ただし、240 条の趣旨に鑑みて、原因⾏為が強盗⾏為と密接な関連性を有する場合に限られる。
本件において、A は全治約10⽇ 間の傷害を負っているが、これは、BがAにナイフを投げ渡そうとして⽣じた結果であり、甲の⾏為によって直接的に⽣じた結果ではない。しかし、A の傷害結果は、ナイフを持つ甲とそれに対抗するBとの揉み合いの結果に⽣じたものであるため、甲の⾏為とAの傷害結果には密接な関連性が認められる。
したがって、強盗の機会性が肯定され、Aの傷害結果は甲に帰責されうる。
8. Aの傷害結果はBの⾏為が介在しているところ、因果関係が認められるか。
因果関係の存否は、条件関係があることを前提にして、当該⾏為が内包する危険性が結果へと現実化したか否かで決するものと解する。具体的には、⾏為者の⾏為の危険性と、 介在事情の結果への寄与度を中⼼に諸事情を総合的に判断して決すべきである。
本件において、Aの傷害結果は甲の強盗がなければ当然に発⽣しなかったはずであるから、条件関係が肯定される。
そして、ナイフを⼈に向ける⾏為は、ナイフが刺さるなどして傷害結果を発⽣させる危険が⾼いものである。Bとの揉み合いの最中に、Bがナイフを奪い、それを投げるという介在事情によって、A の傷害結果が発⽣しているところ、揉み合いによってナイフが予期せぬ形で⼈に刺さることはあり得るといえため、介在事情の 結果への寄与度は⼩さくないが、異常性は低いと評価できる。
そのため、甲の⾏為が内包する危険性が結果へと現実化したといえ、因果関係が肯定される。
9. よって、甲の上記⾏為について、強盗致傷罪が成⽴する。
以上





