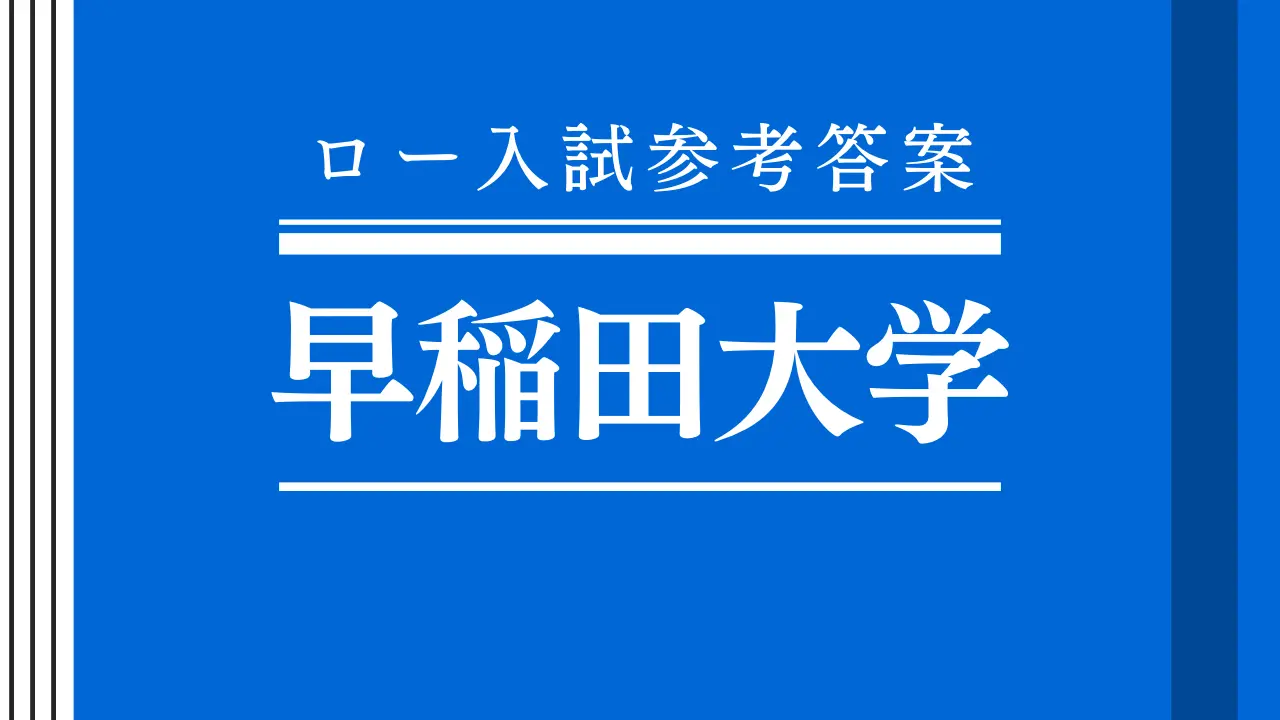
2021年 刑法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2021年 刑法
問題1
第1 甲の罪責
- 甲はA の顔面を1回殴打して口腔内裂傷を負わせており、「人の身体を傷害した」といえ、傷害罪(刑法(以下略)204条)が成立する。
- また、甲はAに対して車ごと海中に飛び込むように指示しているが、かかる行為について殺人罪(199条)が成立しないか。
⑴ 実行行為は犯罪の結果発生の現実的危険を有する行為であり、海中に車ごと転落する行為は死亡結果が生じる現実的危険性が高い。もっとも、Aは自ら車を運転して海中に転落していることから、甲が「殺した」といえるのか否かが問題となる。すなわち間接正犯の成否の問題である。
ア 正犯とは自らの意思で犯罪を実現し、第一次的な責任を負う者であるから、直接手を下さなくとも被利用者を通して因果経過を実質的に支配し、自己の犯罪事実実現の目的を遂げた者もまた正犯とすることに問題はない。したがって、行為者が被利用者に対して行為支配性を有していること、他人の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思を有していることの2つの要件を満たす場合には、この者を間接正犯として処罰することができると解する。
イ 本件において、甲とAは夫婦関係にあり、甲はAに対して日常的に激しい暴行、脅迫を加えて風俗店で働かせるなどしていた。そして前述の傷害を負わせ、「これ以上生きていても、毎日殴り続けられるだけだから、死んだ方がよい」、「自分が死ねば、お前は楽になるし、オレは保険金が入るから、お互い幸せだ」、「逃げても無駄だ、必ず探し出して殺すから」などと脅迫的な内容をAに述べAに車ごと海中に飛び込むよう命じている。ている。そして、Aを車に乗せて近くの漁港に至り、運転席に乗車させたAに対し、「昨日言ったことを覚えているな」、「乙がお前を監視しているから、逃げられないぞ」などと申し向け、さらに、ドアをロックすること、窓を閉めること、シートベルトをすることなど具体的な指示をした上、車ごと海に飛び込むように再度命じ、これによってこのことから甲はAを精神的に追い詰め、Xの命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせていたといえる。以上よりAの意思が抑圧されていたといえるため、精神的支配をしていたといえる。その後、Aに車ごと海中に飛び込むように命じ、ドアロック、窓を閉めること、シートベルトをすることなどを具体的に指示していることから、甲にAに対する行為支配性が認められるといえる。
また、甲はAを死亡させることで保険金を入手して、自己のギャンブル等で負った多額の借金の返済に当てようとしていることから、「自己の犯罪」として実現する意思を有しているといえる。
ウ よって、甲に間接正犯が成立し「殺した」といえるため、甲の行為に実行行為性が認められる。この点確かに、実際には、Aは脱出に備えてシートベルトを外し、窓を開けた状態で海に飛び込んでおり、かかる行為には死亡結果発生の現実的危険がなかったとも思える。しかし、本件現場の海は、当時、岸壁の上端から海面まで約2m、水深約4m、水温 約10度という状況であり、このような海に車ごと飛び込めば、脱出する意図が運転者にあった場合でも、飛び込んだ際の衝撃で負傷するなどして、車からの脱出に失敗する危険性は高く、また脱出に成功したとしても、冷水に触れて心臓まひを起こし、あるいは心臓や脳の機能障害,運動機能の低下を来して死亡する危険性は極めて高いものであった。したがって、かかる事情を考慮しても殺人罪の実行行為性は否定されない。
⑵ そして、Aは溺死していることから死亡結果が生じている。
⑶ もっとも、Aは転落後、自力で車から脱出し、その後漁船のスクリューに巻き込まれて溺死しているため、甲の行為とAの死亡結果の間に因果関係が認められないのではないか。
ア 因果関係は、当該行為が結果を引き起こしたことを理由に、より重い刑法的評価を加えることが可能なほどの関係を認めうるかという法的評価の問題である。そこで、因果関係の存否は実行行為の危険性が結果へと現実したか否かで判断する。
イ 本件において、車ごと海に転落する行為自体死亡結果が発生する危険性は高い。加えて、ドアをロックし、窓を閉め、シートベルトをした状態で、本件現場の海は、かつ岸壁の上端から海面まで約2m、水深約4m、水温約10度、深夜2時という状況にあったことから、車から脱出すること自体困難であるし、仮に脱出したとしてもこのような海の状況では自力で海から陸に上がることは困難であったといえ、死亡結果が発生する危険性は尚更高い状況であった。
ウ また、本件ではスクリューに服を巻き込まれるという介在事情が存在しているが、港内はそもそも漁船がに停泊するために利用される場所であるし、港内に停泊している漁船が運転を再開することはごく普通の事象であり、海に転落したAがスクリューに巻き込まれて死亡するという間接的な危険はがAを車ごと海に飛び込ませるという甲の実行行為に含まれていたといえる。
エ そのため、甲の実行行為の危険性が結果に現実化したといえるため、因果関係が認められる。
⑷ 次に、甲はAが自らの意思で自殺すると認識しており、自殺教唆(202条)の故意しかないのではないかが問題となるも、被害者に対し死亡の現実的危険性の高い行為を強いたこと自体については,Xにおいて何ら認識に欠けるところはなかったといえる。
もっとも、甲はAが車から脱出することができずに溺死すると認識していたが、客観的にはスクリューに巻き込まれることによって溺死しているため、因果関係の錯誤があり、故意(38条1項)が阻却されないか。
因果関係は構成要件要素であるところ、危険の現実化が認められる場合には、規範の問題に直面しており、反対動機を形成することができるから、故意責任を問い得る。
車から脱出することができずに溺死するかスクリューに巻き込まれることによって溺死するかという点は、殺人罪の構成要件の範囲内で符合しており、殺人行為の危険の現実化が認められるため、規範の問題に直面しており、反対動機を形成することができるから、故意は阻却されない。
よって、Xに殺人罪の故意が認められる。
⑸ 以上より、甲にはAに対する殺人罪が成立する。なお、後述の通り、乙との間で共同正犯(60条)となる。
第2 乙の罪責
- 乙は実際にAに指示はしていないが、甲の上記殺人行為の監視などの協力をしていることから、殺人罪の共謀共同正犯(60条)が成立しないか。
⑴ 共謀共同正犯の場合でも一部実行全部責任の原則から実行者以外の者にも罪責を負わせるべきである。そこで、①共謀と②その共謀に基づく実行行為がなされた場合には共謀共同正犯が成立する。共謀が肯定される要素は⑴意思連絡と⑵正犯性である。正犯性を基礎付ける正犯意思は、意思連絡の強さを前提に、人的関係。果たした役割の重要性、動機の積極性、利益の帰属などを諸要素として総合的に判断する。
⑵ 本件では、乙は甲から事情を伝えられた上で協力しており、意思連絡がある。そして、保険金の分け前を受けるという約束、甲が現場を去った後の監視という実行行為を遂行する上で重要な役割、乙も借金返済に窮していたという事情を鑑みると、乙に正犯意思があったといえ、正犯性も認められる。よって①共謀がある。そして②その共謀に基づく実行行為が行われている。
⑶ よって、乙には甲との間で殺人罪の共同正犯が成立する。
- もっとも、乙はAに見逃すよう懇願され、可哀想になり、甲の指示を無視して、脱出に備えるアドバイスをして車から離れている。こかかる離脱行為によってのことから乙にが共犯関係の解消から離脱が認められしたといえないか。
⑴ 共犯の処罰根拠は自己の行為が結果に対して因果性を与えた点に求められる。そのため離脱行為によって当初の行為がもたらす因果性を遮断したと評価できる場合には、共犯関係の解消からの離脱が認められ、離脱者は離脱行為以降に生じた結果について責任を負わないと考える。そして、因果性には物理的因果性と心理的因果性があるため、その両方を考慮すべきである。
⑵ 本件において、すでに甲による指示が行われているため因果の流れは現実に進行を始めている。そのため、離脱が認められ、結果への帰責がないとの評価を得るには、積極的な行為により行為と結果との因果性を断ち切ることが必要である。しかし、乙は単に脱出のアドバイスをしたにとどまり、その後その場を立ち去っている。甲が現場から立ち去っている以上、車の転落を止めることは可能であったし、転落後もAの救助をすることも可能であったにもかかわらず、Aを転落させることについては格別の防止措置を行なっていない。そのため、因果性を断ち切ったと評価することはできず、乙に共犯からの離脱を認めることはできないといえる。
⑶ よって、乙にもAの死亡結果は帰責させるべきである。
第3 罪数
甲には①傷害罪(204条)の単独正犯、②乙との間で殺人罪の共同正犯(199条、60条)が成立し、両者は併合罪となる。乙には②甲との間で殺人罪の共同正犯(199条、60条)が成立する。
問題2
1. 名誉毀損罪(230条1項)の「公然」とは不特定又は多数人が認識し得ることを意味する。
2. ここでもっとも、事実を特定の少数人に伝え、その後その特定の少数人が行為者の認識し得ない不特定又は多数人にその事実を伝播した場合に公然性が認められるかが問題となる。、具体例としては、Xが、放火事件があった現場でAを犯人であると思い込みAの妻と娘、近所の住人3人程度がいる前でAが放火したのを見たと発言した事例が考えられる。この事例では、事実の摘示自体は5人程度の特定少数の人に行ったにすぎず、不特定又は多数人に行ったとはいえないため公然性が認められないとも思える。
3. しかし、判例は、事実の摘示の直接の相手方が特定少数人であっても、彼らを通じて不特定又は多数人へと伝播し得る場合には、「公然」性が認められるとしている。この点について、その根拠は、230条1項が「公然」性を要件とした趣旨がは、事実が不特定又は多数人に摘示された場合には、さらにその事実が他の者にも伝播され悪評が広く社会に流布される類型的危険の存在があることに求められる。るからである。そうだとすれば、事実の摘示の直接の相手方が特定少数人であっても、彼らを通じて不特定又は多数人へと伝播し得る場合には、「公然」性があるというべきである。したがって、判例の立場からは、かかる事例でも、不特定多数の者への伝播可能性がある以上、公然性が認められることとなる。
4. しかし、判例の様に、伝播可能性によって公然性を肯定すると、公然性を要件とした意義がうしなわれてしまう。また、伝播するかどうかという相手方の意思により犯罪の成否が左右されることとなってしまい罪刑法定主義の観点からも妥当でない。したがって、伝播可能性によって公然性を肯定するのは妥当でなく、「公然」とは、不特定又は多数の者が直接に認識できる状態を意味すると考える。
このように解すると、上記事例では、直接に認識できたのは不特定多数の者であった以上「公然」の要件は満たしていないこととなり、名誉棄損罪は成立しない。
以上





