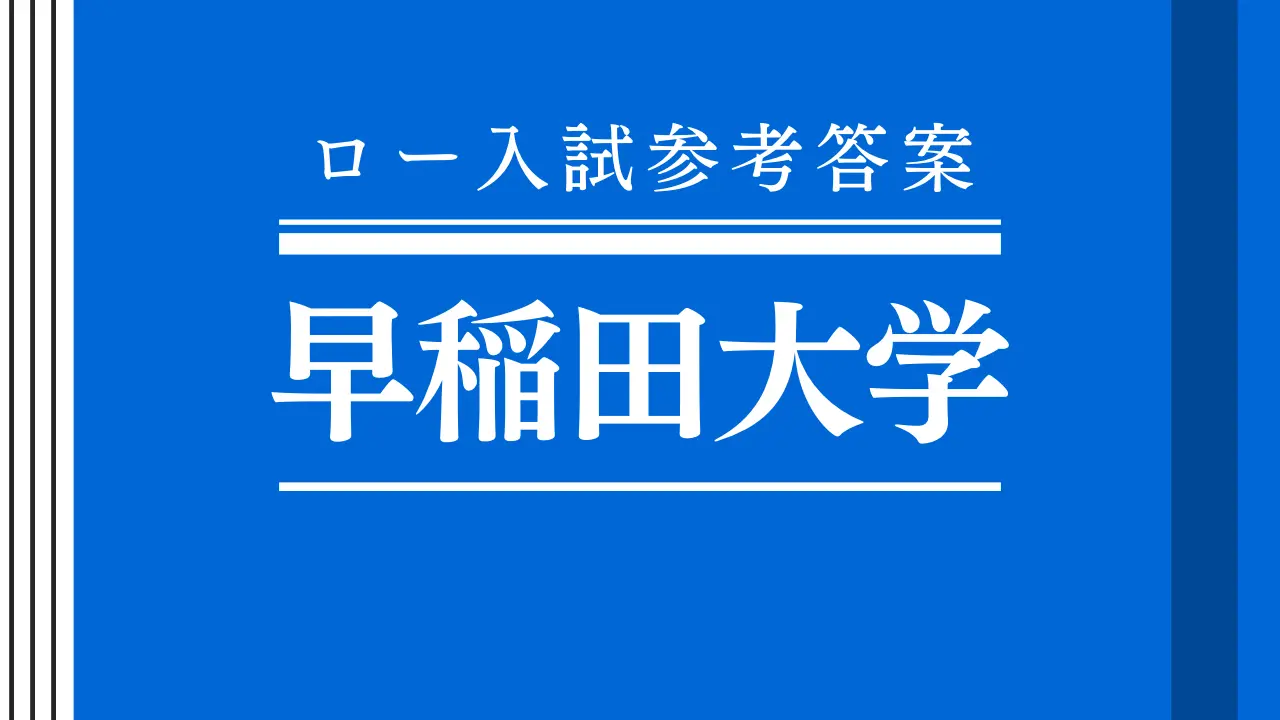
2021年 民事訴訟法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2021年 民事訴訟法
1. 問1
⑴ Xは売買契約の不存在確認の訴えを提起しようとしているところ、かかる訴えに訴えの利益が認められるか問題となる。
⑵ 判断基準
確認の訴えは、その対象が無制限であり判決に既判力しか認められず、紛争解決の実効性がある場合は限られているから、そこで、確認の訴えが紛争の抜本的な解決に資する場合に確認の利益が認められると考える。具体的には①方法選択の適否、②対象選択の適否、③即時確定の利益を基準に判断する。
⑶ 個別具体的検討
②対象選択の適否とは、確認訴訟における対象として適切か否かという問題であるところ、その対象は原則として自己の現在における権利・法律関係の確認であると解する。
本件では、売買契約の不存在確認の訴えが主張されているところ、売買契約は権利・法律関係を基礎づける事実にすぎず、権利・法律関係それ自体ではない。したがって、対象選択の適切性に欠ける。したがって、確認の利益が認められず、訴えは不適法である。
なお、原告の意思は、当該売買契約から生じた甲土地の引渡債務を免れることにあると解されるところ、そのような場合は、甲土地引渡債務の不存在確認によって同債務の不存在に既判力(民事訴訟法(以下、法令名省略)114条1項)を生じさせるべきである。
2. 問2
⑴ Yによる後訴が、前訴既判力によって遮断されるのではないか問題となる。
⑵ 既判力は、「主文に包含するもの」(114条1項)すなわち訴訟物の存否の判断に生じ、訴訟物が同一の訴えにおいて作用するのが原則である。本件においては、前訴訴訟物はXの甲土地所有権である一方、後訴訴訟物はYの甲土地所有権であることから、訴訟物を同一とした訴えといえず、前訴既判力が後訴に作用しないように思える。
もっとも、既判力が作用する場面は既判力の紛争の一回的解決という制度趣旨から次のような場合を含むと解するべきである。すなわち、①後訴訴訟物と前訴訴訟物が同一である場合に加えて②後訴訴訟物が前訴訴訟物と先決関係を有する場合、③後訴訴訟物と前訴訴訟物が矛盾関係にある場合をである。なぜなら、このような場合に既判力を作用させたほうが紛争の一回的解決という制度趣旨に合致するからである。
⑶ 前訴訴訟物はXの甲土地所有権であり、後訴訴訟物はYの甲土地所有権であるところ、共有の場合等を除いて、同一の物が別人に同時に帰属することは論理的にあり得ず(一物一権主義)、この点で両訴訟物は③矛盾関係にあるといえる。したがって、前訴既判力が作用する場面である。
⑷ 結論
以上より、受訴裁判所は前訴既判力に拘束されるから、Yが新事由を主張しない限り後訴の棄却判決をするべきである。
以上





