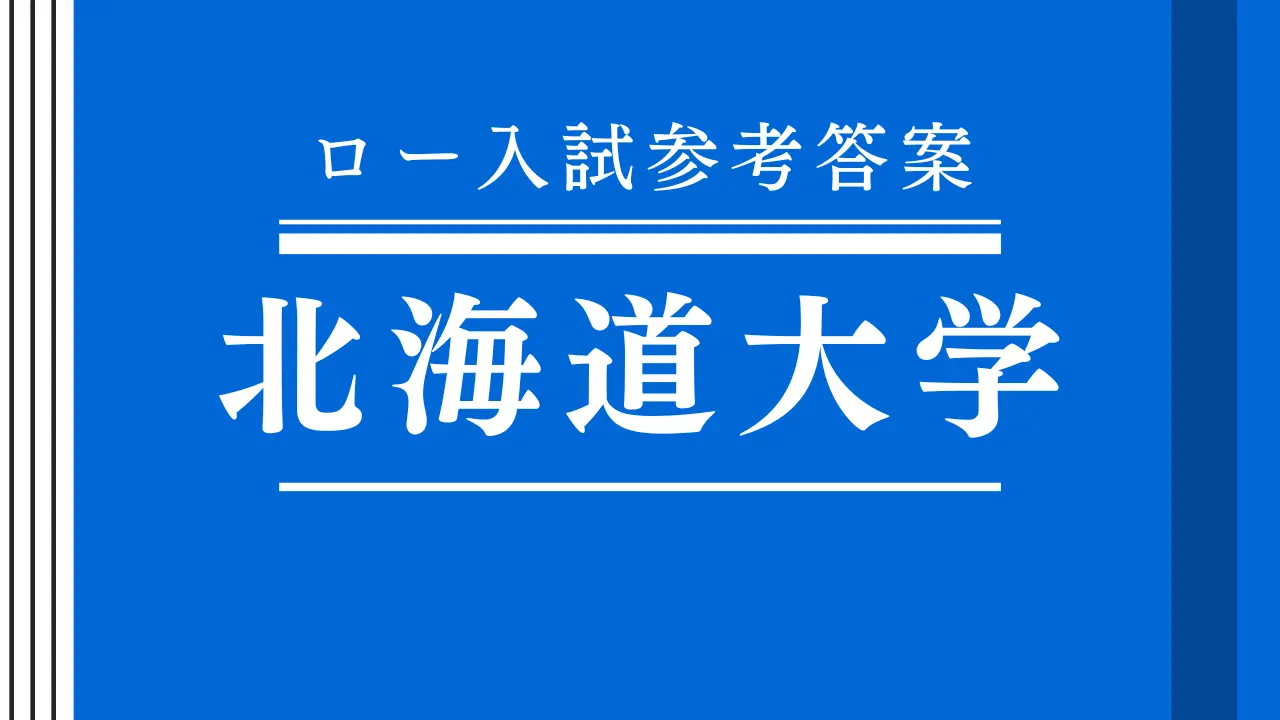
2024年 民事訴訟法 北海道大学法科大学院【ロー入試参考答案】
4/20/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
北海道大学法科大学院2024年 民事訴訟法
問1
1. 遺産確認の訴えについては、以下の通り確認の利益が認められる。
⑴確認の訴えの対象は無限定に拡大しうるから、紛争の抜本的解決に資する場合にのみ確認の利益が認められると解する。その判断においては、①方法選択の適切性、②対象選択の適切性、③即時確定の利益を要素として判断する。
ア ①方法選択の適切性
遺産確認の訴えよりも、共有持分確認の訴えによる方が適切であるとも思える。しかし、共有持分確認の訴えでは取得原因が相続であることについて既判力(114条1項)が生じず、紛争の抜本的解決に資さない。遺産確認の訴えによる方が、当該財産の遺産帰属性に既判力が生じるという点でより原告の意思に適うといえる。したがって、方法選択の適切性が認められる。
イ ②確認対象の適切性
遺産確認の訴えは過去の法律関係の確認を求めるものであり、不適切であるとも思える。しかし、遺産確認の訴えの確認対象は、当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有状態にあること、という現在の権利・法律関係であると解するべきである。したがって、確認対象の適切性が認められる。
ウ ③即時確定の利益
遺産確認の訴えにより、原告の権利・地位に生じている危険が除去されるといえるため、即時確定の利益が認められる。
⑵以上より、確認の利益は認められる。
2. 次に、以下の通り、遺産確認の訴えは固有必要的共同訴訟にあたる。
⑴訴えの提起は処分行為に類似するものであり、敗訴した場合には、権利を処分したのと類似する状態に陥るため、第一次的には訴訟物たる権利関係に関する管理処分権が実体法上共同的に帰属するかによって決すべきである。もっとも、当事者とならない者の受ける事実上の不利益、相手方の二重の応訴の負担、訴訟経済等の訴訟法的観点をも考慮するべきである。そこで、固有必要的共同訴訟か否かは、実体法的観点に加えて、訴訟法的観点も考慮して判断すべきである。
⑵実体法的観点においては、遺産は共同相続人間の共有物であり、遺産の管理処分権は共同相続人全員に帰属する。また、訴訟法的観点においては、遺産分割の審判は共同相続人全員の関与が前提となるため、遺産分割の前提として特定財産の遺産帰属性についてあらかじめ確定しておくのであれば、それは共同相続人全員の間で合一に確定しておくことが望ましい。
⑶以上の理由から、遺産確認の訴えは、固有必要的共同訴訟である。
問2
1. 裁判所が、Xの請求を全部棄却する旨の判決をすべきであると考えている理由は以下の通りである。
2. 前訴において、YはXに対し100万円の売買代金支払請求権を訴訟物とする給付訴訟を提起しているところ、Xは10万円の弁済の抗弁に加えて、Yに対する100万円の貸金返還請求権を自働債権として対当額で相殺する旨の意思表示をしており、Xの主張が認められたことで、Yの請求は全部棄却されている。
ここで、相殺の意思表示については、自働債権について「相殺をもって対抗した額について既判力」(114条2項)が生じる。そのため、XのYに対する100万円の貸金返還請求権の内、90万円の不存在について既判力が生じることとなる。
3. 次に、後訴においては、XはYに対して、上記100万円の貸金返還請求権を訴訟物とする給付訴訟を提起しており、Yは10万円の弁済の抗弁を主張している。そうすると、前訴と後訴の訴訟物が同一であるため、裁判所は100万円の貸金返還請求権の内90万円については不存在であることを前提として審理・判断しなければならない。そして、残りの10万円についてYの主張する弁済の抗弁が認められると考える場合、Xの請求は全て棄却すべきであるといえる。
4. 裁判所は、このような理由から、Xの請求を全部棄却すべきであると考えている。
以上





