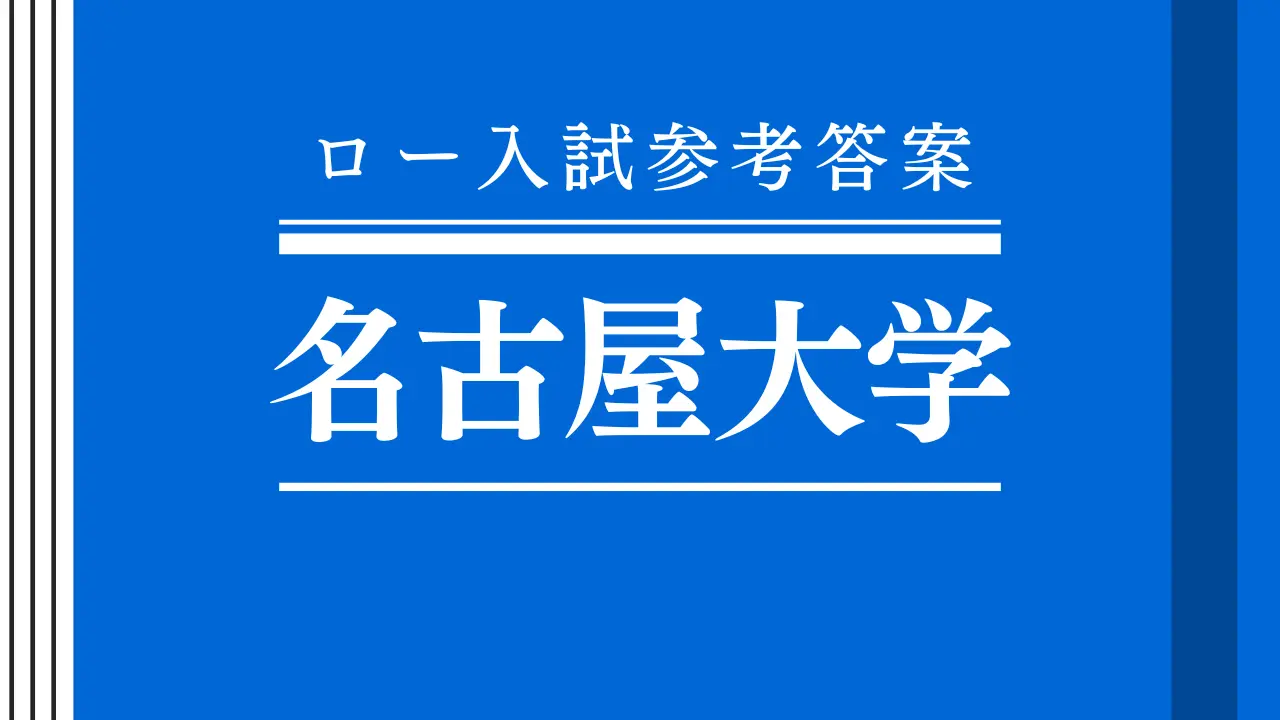
2022年 公法系 名古屋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
7/21/2024
The Law School Times【ロー入試参考答案】
名古屋大学法科大学院2022年 公法系
設問1小問(1)
地方議会は一般市民法秩序と別個の特殊な部分社会であり、一般市民法秩序と直接関連しない純然たる内部紛争に司法審査が及ばない。減給・戒告などの処分は純然たる内部紛争として司法審査が及ばない一方、除名処分は、議員の身分喪失に関わる重大事項であり、単なる内部規律の問題ではないから、司法審査が及ぶ。
出席停止の懲罰について、かつての判例は、団体内部規律の問題として司法審査が及ばないとしていた。
しかし、地方議会には議員の資格争訟の裁判権(憲法55条)や免責特権(51条)の規定がないから、国会と同程度の自律権はない。また、「地方自治の本旨」(92条)の中核たる住民自治を全うすべく、議員は住民意思を反映させるため活動する責務を負うところ、出席停止の懲罰が下されると、職責を十分に果たせず、住民自治を阻害する。そのため、地方議会の議員に対する出席停止の懲罰は、常に司法審査の対象となると判例が変更された(岩沼市議会事件)。
設問1小問(2)
法律優先の原則とは、法律の規定と行政の活動が抵触する場合、前者が優先され、違法な行政活動は取り消されたり、無効となったりすることをいい、法律による行政の原理の一内容をなす。この点で、任意規定である限り、個々の契約関係が優先するという契約自由の原則が妥当する私法とは異なる。
根拠は、民主的正当性の違いにある。法律を制定する国会は、選挙によって選ばれた全国民の代表である議員により構成され(憲法前文、43条1項)、直接の民主的正当性を有する。国会を国権の最高機関であり、国唯一の立法機関であると規定する憲法41条も、法律優先の原則を根拠づける。
一方で、行政機関は国民により直接選挙されるわけではないので、国会と比べて行政機関の活動には相対的に民主的正当性が弱い。以上より、上記原則が導かれ、私法とは異なる規律が及ぶ。
設問2
1. 女子の合格者を女子寮の収容人数に収まるよう得点調整したことは、性別に着目して男子と女子を別異に取り扱っており、平等原則(14条1項)に反しないか。
⑴ B大学は私立大学であるから、憲法上の規定が適用できないのではないか。
憲法上の各規定は、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係を規律するものではない。私人間の関係は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられ、侵害態様が社会的に許容し得る限度を越える場合に限って、例外的に法の適用による調整を図るとしている。そして、社会的に許容し得る限度を越えた場合には、私的自治に対する制限規定としての私法の一般条項の運用に際して憲法の規定の趣旨を取り込む形で調整が図られるべきである。
⑵ 「法の下」(14条1項)とは、法適用の平等のみならず法内容の平等も含み、「平等」とは個人の差異を前提とした相対的平等を指す。ゆえに、合理的な区別は許容される。では、合理的な区別といえるか。
ア 「性別」(同項後段)等のいわゆる後段列挙事由は例示であり特別な意味はないが、民主主義の理念に照らして不合理なものを限定列挙したものであり、疑わしい区別として、違憲性の推定が働くと解する。
本件でも、「性別」に着目して別異取扱いをしているから、違憲性が推定される。
イ 一方、昭和女子大判決は、㋐学生の教育と学術研究を目的とする公共的施設であることから、大学に、その目的達成のために必要な事項を制定し、在学生を規律する包括的権能を認めた。そして、私立大学については、㋑独自の伝統・校風・教育方針によって社会的存在意義が認められること、㋒学生もかかる伝統・校風・教育方針の下で教育を受けることを希望して入学するものと考えられることを根拠に、伝統・校風・教育方針を学則等において具体化し、これを実践することを認めたものと解される。
本件でも㋐の根拠は妥当する。
また、いかなる学生を合格者とするかについては、各学校の伝統や校風、教育方針等によって異なるところ、B大学の学是である「他者を敬う心と共生」を実践学習させるべく、1年次の全寮制を戦前から実施していた。B大学は、このような伝統的な学是によって社会的存在が認められると言え、㋑の根拠も妥当する。
B大学の学生は、かかる伝統的学是の下に教育を受けること自体は承認していたといえる。しかしながら、受験時においては得点調整の存在は秘匿されていたから、受験者はこの取扱いを承諾していたとはいえない。そうすると、㋒の根拠は妥当せず、昭和女子大事件判決の時ほどの裁量は認められない。
ウ そこで、本件の別異取り扱いが、B大学の学是の大学の学是の具体化と、その実践といえるかは慎重な検討を要する。すなわち、区別の目的が重要で、手段と実質的関連性が認められる場合に限って合理的な区別として許されると解する。
エ 本件では、区別の目的は、1年次の全寮制の維持であり、寮での共同生活によって他者と共生していくにはどうすればいいか、平穏な生活を送るには他者とどう向き合ってくべきかなどを経験することができ、「他者を敬う心と共生」という学是を実践学習するために不可欠といえ、目的は十分に重要である。
女子寮の収容人数内に合格者を絞ることではじめて、全寮制を全うできるのだから、目的達成のために観念的にとどまらず現実的に役立つといえるので手段適合性はある。
しかし、全寮制を維持するうえで、女子合格者が既存の寮の収容人数を越えた場合は、学校周辺の施設を寮として新たに用意したり、また、その場合には男子の合格者も含めて寮の収容人数に収まるように合格点を調整したりすることで対応可能である。したがって、男女で点数自体に差を設ける以外の方法でも目的は達成できるから、手段必要性は認められない。
2. よって、合理的な区別として許容されるとはいえないから、平等原則(14条1項)に違反する。
設問3小問(1)
1. 取消訴訟の対象となる行政「処分」(行政事件訴訟法3条2項)とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、これによって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいい、①直接的・具体的法効果性、②①を前提とした公権力性の有無により決する。なお、必要に応じて実効的権利救済の観点も考慮する。
⑴ A県通知について
A県通知は、学校教育法施行令(以下、「施行令」とする。)14条1項に基づき、国民たるDに対して、行われたものであるから、具体性・直接性は認められる。
しかし、A県通知は、特別支援学校の入学期日という一定の事実を伝達する、いわゆる観念の通知にすぎないから、法効果性が認められないのが原則である。
もっとも、就学通知は、公権力の主体であるA県教育委員会が、本施行令14条1項に基づいて、Cが就学すべき学校を指定し、その旨の通知を保護者Dにするものであるうえ、それにより、Cの教育を受ける権利(憲法26条1項)を直接形成すると同時に、保護者たるDに対し、Cへの就学義務(憲法26条2項)を具体的に形成するものである。ゆえに、国民の法的地位に影響を及ぼすといえるから、直接的・具体的法効果性が認められる(①)。
そして、A県通知は、施行令14条1項という法律上の根拠のもと、A県教育委員会が一方的に優越的地位に基づいて行うものであるから、公権力性も認められる(②)。
⑵ B市通知について
ア B市通知は、B市教育委員会からA県教育委員会に通知される(施行令11条1項)。ゆえに、行政機関相互の行為であり、直接国民の法的地に影響を及ぼしうる具体的・直接的法効果は認められず、処分たりえないのが原則である。もっとも、法の仕組みからみて、国民との関係で直接的・具体的法効果を生じさせるといえる場合には、例外的に処分となりうる。
イ たしかに、上記同様、就学すべき学校を指定するB市認定も、Cの教育を受ける権利を直接形成し、保護者Dの就学義務を具体的に形成するとも思える。
しかし、B市認定(施行令5条1項)は、その認定を基礎としてなされる保護者への通知(施行令14条1項)を通じて保護者に告知される。ゆえに、DはA県通知によってはじめて、B市認定の内容を知ることができる。したがって、B市通知自体には、国民の法的地位に影響を及ぼさず、直接的・具体的法効果が認められない(①不充足)。
また、B市通知は施行令11条1項という法律上の根拠のもと行われているが、直接的・具体的法効果が認められない以上、公権力性も認められない(②不充足)。
なお、DはA県通知時点で、争うことができるから、実効的権利救済の観点からも、この結論は妥当である。
2. 以上より、A県通知は取消訴訟の対象となる行政「処分」にあたるが、B市通知は行政「処分」にあたらない。
設問3小問(2)
1. 裁量の有無は、法律の文言と判断の性質を考慮し判断する。
⑴ B市認定の根拠法規たる施行令5条1項本文は、認定特別支援学校就学者以外の者への通知については「しなければならない」としている一方、同項かっこ書は、認定特別支援学校就学者の認定については、「その障害の状況、その者の教育上必要な支援の内容」、「適当であると認める者」と概括的に記載している。これは、具体的状況において、適宜判断することを許容しているものといえるから、認定特別支援学校就学者該当性の判断につき文言上、教育委員会の裁量が認められる。
⑵ いかなる就学予定者が認定特別支援学校での就学するにふさわしいかの判断については、障害の状況や必要な支援の内容に応じて、教育学等の学術的な知見を駆使した専門的判断が要求されるから、判断の性質上も教育委員会の裁量が認められる。
⑶ そして、施行令18条の2において、「5条…の通知をするときは、…専門的知識を有する者の意見を聴くものとする」と規定され、これは、上記判断が高度の専門性を帯びていることの証左である。現に「教育学、医学、心理学」など、横断的な学問分野が列挙され、高度の専門的判断の必要性がうかがわれる。
そして、B市認定は、入学資格を付与する側面を有するとしても、何ら義務を課すものではない。
2. 以上によれば、上記専門家の意見を踏まえたB市教育委員会の判断が尊重されるべきであるから、裁判所との関係においても、裁量が認められる。
以上





