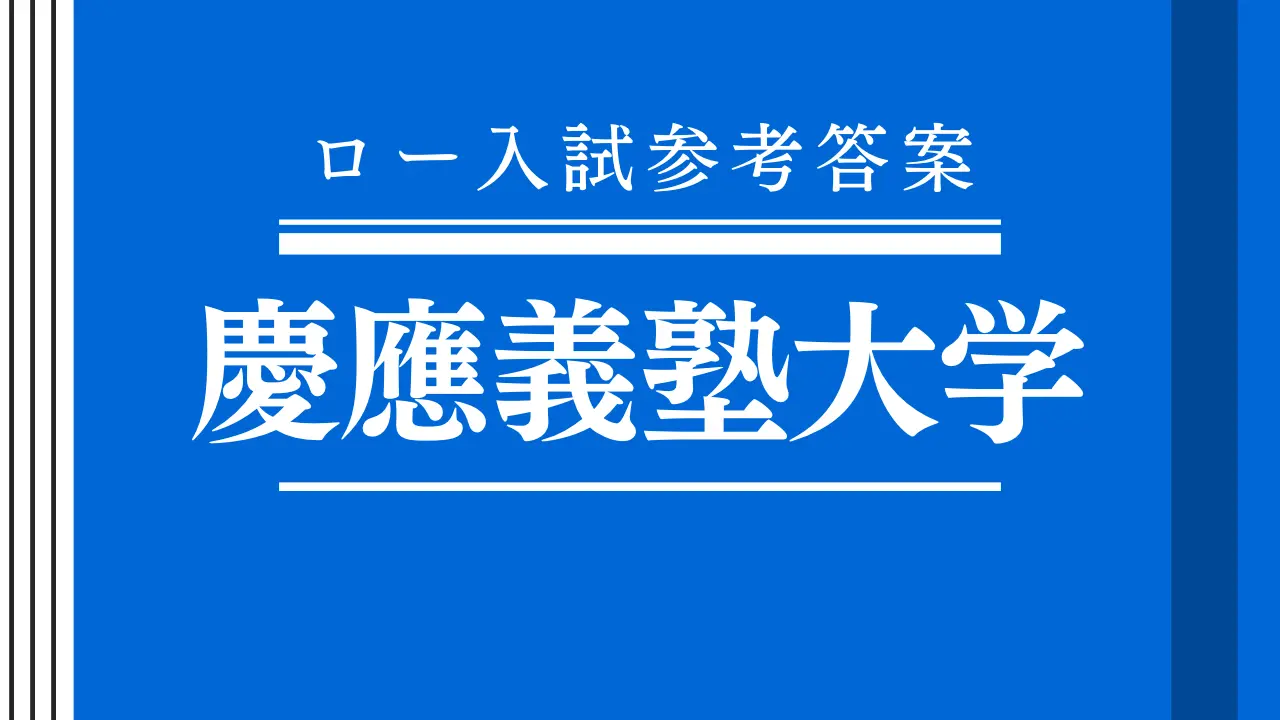
2024年 民事訴訟法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2024年 民事訴訟法
第1 問1(1)
1. Xの後訴の提起は既判力により遮断されるか。
⑴ 既判力(民事訴訟法114条1項、以下法名略)とは、確定判決の有する後訴への通有性・拘束力をいう。その趣旨は紛争の一回的解決にあり、正当化根拠は当事者への手続保障充足に基づく自己責任にある。
そして、既判力は、「主文」つまり訴訟物の存否についての判断にのみ生じ、理由中の判断には及ばない。そのように解しても紛争解決に十分であるし、審理の簡易化、弾力化に資するためである。
また、既判力が生じるのは、訴訟物の存否についての判断であるから、それが作用するのは前訴訴訟物が後訴訴訟物と同一・先決・矛盾する場合である。
⑵ 本件をみるに、本件前訴の訴訟物は、XのYに対する所有権に基づく返還請求としての甲地の明渡請求権である。他方、後訴訴訟物は、XのYに対する賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての甲地の明渡請求権である。したがって、前訴訴訟物が後訴訴訟物と同一でない。また、XのYに対する所有権に基づく甲地の明渡請求権の存否は、XのYに対する賃貸借契約終了に基づく甲地の明渡請求権の先決問題ではない。さらに、XがYに対し所有権に基づく甲地の明渡請求権を有しないことは、賃貸借契約終了に基づく甲地の明渡請求権を有することと矛盾しない。
したがって、本件では既判力は作用しない。
⑶ よって、Xの後訴の提起は既判力により遮断されない。
2. 次に、Xの後訴の提起は争点効により遮断されるか。
⑴ 争点効とは、前訴で主要な争点として争われた点についての裁判所の判断に生じる拘束力として提唱されるものである。
しかし、その要件は曖昧で、これを認めると主文についての判断にのみ効力が生じる既判力の趣旨を没却するおそれがある。また、中間確認の訴えの制度(145条)は、このような効力が認められないことを前提とする制度である。
したがって、争点効は認められるべきでない。
⑵ よって、Xの後訴の提起は争点効により遮断されない。
3. Xの後訴の提起は信義則により遮断されるか。
⑴ 信義則による後訴の遮断は、本来既判力が生じない点について、後訴を遮断するという強力な効果をもたらすものであるから、その判断は厳格になされるべきである。そこで、前訴と後訴が社会経済上同一の紛争に起因するものであって強い関連性があるか、上訴審を含む前訴において請求または主張の可能性が十分にあったか、紛争解決に対する相手方の合理的期待があるか、等を総合的に判断して判断すべきである。
⑵ 本件みるに、前訴でXはYに対し甲地につき所有権に基づく明渡請求訴訟を提起している。しかし、裁判所は、Yによる賃借権の抗弁を認めて請求を棄却する判決を下し、同判決は確定している。その後,Xは、甲地につきYの賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除したと主張して、賃貸借契約終了に基づく明渡請求の後訴を提起している。たしかに、Xの後訴での請求原因は、Yの前訴での抗弁に基づくものであり、どちらも甲地という同一の不動産の明渡しを求めるものである。したがって、Xは前訴で訴えの追加的変更をして、これを主張することもでき、後訴でこれを主張する権利はもはや失効しているとも思える。
しかし、賃料不払いを理由にした賃貸借契約の解除は前訴口頭弁論終結後に生じた事由である。またこの解除権は、前訴口頭弁論終結後の賃料不払いをも解除原因とするため、前訴訴訟物の発生原因に内在する瑕疵に基づく権利とはいいがたく、前訴の時点で行使することはXにおいて期待しがたい。したがって、賃貸借契約終了に基づく明渡請求に訴えを変更することも期待できなかったといえる。
⑶ よって、Xの後訴の提起は信義則により遮断されない。
4. 以上より、Xの後訴の提起は遮断されない。
5. 次にXの主張が遮断されないかを検討するも、前述の通り、本件は既判力の作用場面でなく、Xの主張は既判力によっては遮断されない。
6. では、Xの主張は信義則により遮断されるか。
⑴ 前述の通り、賃料不払いを理由にした賃貸借契約の解除は前訴口頭弁論終結後に生じた事由であり、この解除権は、前訴口頭弁論終結後の賃料不払いをも解除原因とするため、前訴訴訟物の発生原因に内在する瑕疵に基づく権利とはいいがたく、前訴の時点で行使することは期待しがたかった。
⑵ よって、Xの主張は信義則により遮断されない。
7. 以上より、Xの主張も遮断されない。
第2 問1(2)
1. 前述の通り、本件は既判力の作用場面でなく、Yの主張既判力によっては遮断されない。
2. Yの主張は信義則により遮断されるか。
⑴ Yは後訴において,甲地についてAと結んだ契約は使用貸借であり,賃貸借ではないと主張して争っている。しかし、Yは前訴においては、自らAとの間で15年前に賃貸借契約を締結していたと主張し、この賃借権の抗弁でもって勝訴判決を得ている。したがって、Yの後訴での主張は矛盾挙動にあたり、許すべきでない。
⑵ よって、Yの主張は信義則により遮断される。
3. 以上、Yの主張は遮断される。
第3 問2
1. 本件訴えのうち賃料相当損害金の請求にかかる部分について、訴えの利益が認められるか。
⑴ 訴えの利益とは、本案判決の必要性である。
この点、賃料相当損害金の請求について、口頭弁論終結時までの損害金請求は現在給付の請求にあたり、その訴えの利益は認められる。現に給付請求権があるにもかかわらずそれが履行されていないという状況は、それだけで訴訟によって解決すべき紛争の存在を示すものといえるためである。
⑵ 他方、口頭弁論終結後から明渡しまでの損害金請求は、事実審の口頭弁論終結時においてなお履行すべき状態にないため、将来給付の請求にあたる。この訴えの利益は認められるか。
ア 将来給付の訴えは、「あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる」(135条)。具体的には、最低限将来給付を求める基礎となる資格(請求適格)が認められる必要がある。
イ まず、請求適格は、当該請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測されること、当該請求権の成否及びその内容につき債務者に有利に働く事情の変動があらかじめ明確に予測しうる事由に限られること、この事情の変動について請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止しうるという負担を債務者に課しても格別不当とは言えないことを満たす場合に認められる。
これをみるに、本件では、不法占有を理由とする損害金の支払いを求めるものであるが、明渡しまでの損害金の支払いという給付義務の性質は、Yによる不法占有という現に生じている給付の基礎となる事実関係が継続する限り、確定的にYに課されるものである。また、Yは自宅に引き返して以降、Xとの交渉にはまったく応じず、Xの訴訟提起に至っており、Yが任意に明渡しまたは土地使用分の支払いを履行することを期待できる態度に出ているとはいえない。そのため、Yに請求異議の訴えの提起の負担を課しても格別不当とは言えない。
したがって、あらかじめその請求をする必要がある場合であるといえる。
ウ よって、口頭弁論終結後から明渡しまでの損害金請求についても、訴えの利益がある。
⑶ 以上、訴えの利益が認められる。
以上





