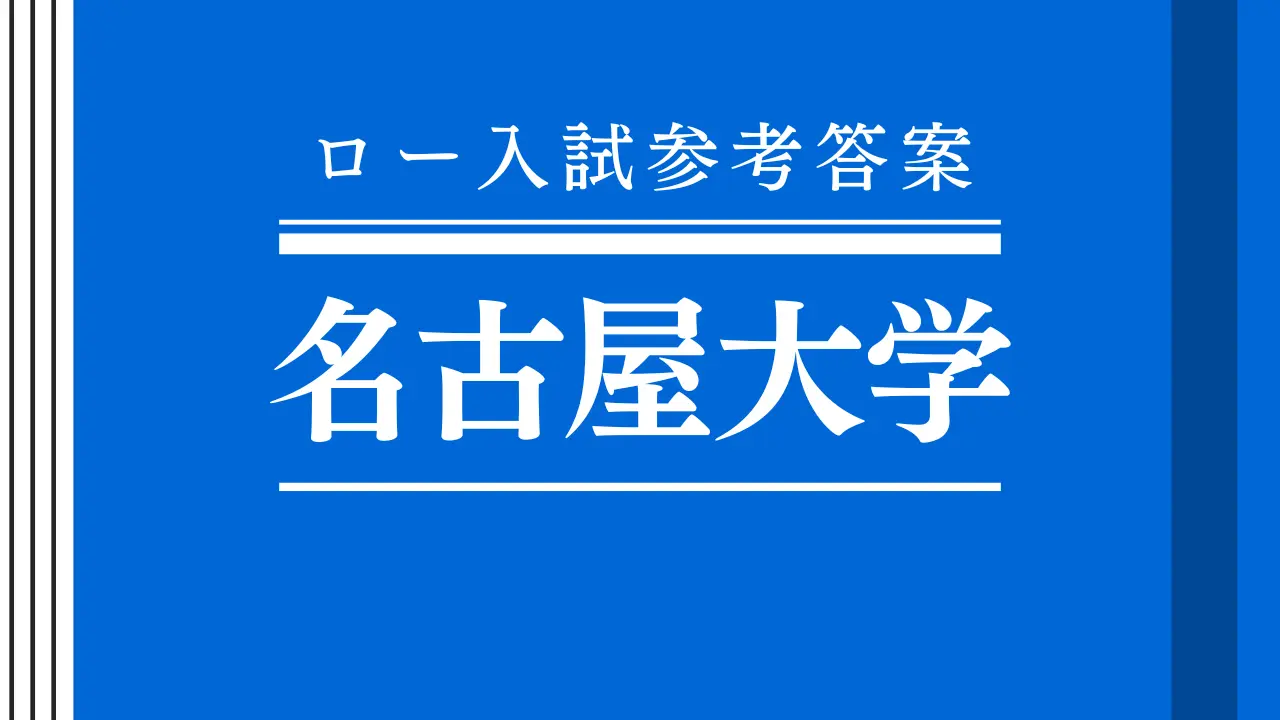
2025年 行政法 名古屋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/2/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
名古屋大学法科大学院2025年 行政法
Ⅰ⑵
行政上の代執行の対象となる行為は、義務が法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられたもので、他人が代わってなすことができるものであり、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるものである(行政代執行法2条)。
その具体例としては、違法建築物に対する除却命令に基づく建築物の除却がある。違法建築物の除却は、建築基準法9条1項という法律により直接命ぜられ、除却業者が代わってなすことができるものであり、除却以外に被執行者に対する侵害の少ない他の手段がなく、違法建築物を放置すると崩壊による周辺への危険等の著しく公益に反する事態となるため、行政代執行の対象となる行為である。
Ⅲ⑴
行政行為の職権取消しとは、行政庁が職権により当初から瑕疵のある行政行為について遡及的にその効力を消滅させることをいい、行政行為の撤回とは行政庁が瑕疵なく成立した行政行為について後発的事情を理由にその効力を消滅させることをいう。両者の効果の相違点は、職権取消しには遡及効がある一方、撤回には遡及効がないという点にある。
本件で、Bの指定医師の指定の取消し(以下「本件取消し」という。)は、瑕疵なく成立した法14条1項に基づく指定医師の指定という行政行為を、Bが人工妊娠中絶の定義または要件を満たさない多数の事案において、堕胎させたという後発的事情を理由として行政庁が指定の効力を失わせるものであるから撤回に当たる。
Ⅲ⑵
本件取消しは、法14条1項という「法令」に基づき、Bという「特定の者」を名あて人として、直接に指定医師の指定の取消しという「権利を制限」するものであるから不利益処分(行政手続法2条4号)に当たる。そして、本件取消しは、Bという「名あて人」の指定医師という「地位」を直接にはく奪する不利益処分であるから、聴聞という意見陳述の手続きを取らなければならない(13条1項1号ロ)。
Ⅲ⑶
1. 本件取消しは許されるか。
⑴まず、行政行為の撤回は、行政の公益適合性を維持するための積極行為であり、処分権限も公益適合性を踏まえて行使されるべきものであることからすれば、撤回権限は処分権限と表裏一体であるといえる。そのため、処分権限が撤回権限を基礎づけているといえるから、特別の根拠なくして行政行為の撤回は認められると解する。
もっとも、授益的処分の取消しは相手方に不利益を及ぼす。そこで、相手方に帰責性があり、又は撤回に同意したときを除いては、撤回により得られる公益と相手方の不利益とを比較衡量し、得られる公益の方が大きい場合に限り、撤回できると考える。
⑵本件取消しは、Bが、法14条1項各号の要件を満たさないにもかかわらず、多数の堕胎をさせたことを理由とするものである。かかる行為は、母性の生命健康を保護するという法の目的(1条)を著しく害するものであって、かかる行為を行っていたBには帰責性が認められる。
2. よって、本件取消しは許される。
以上





