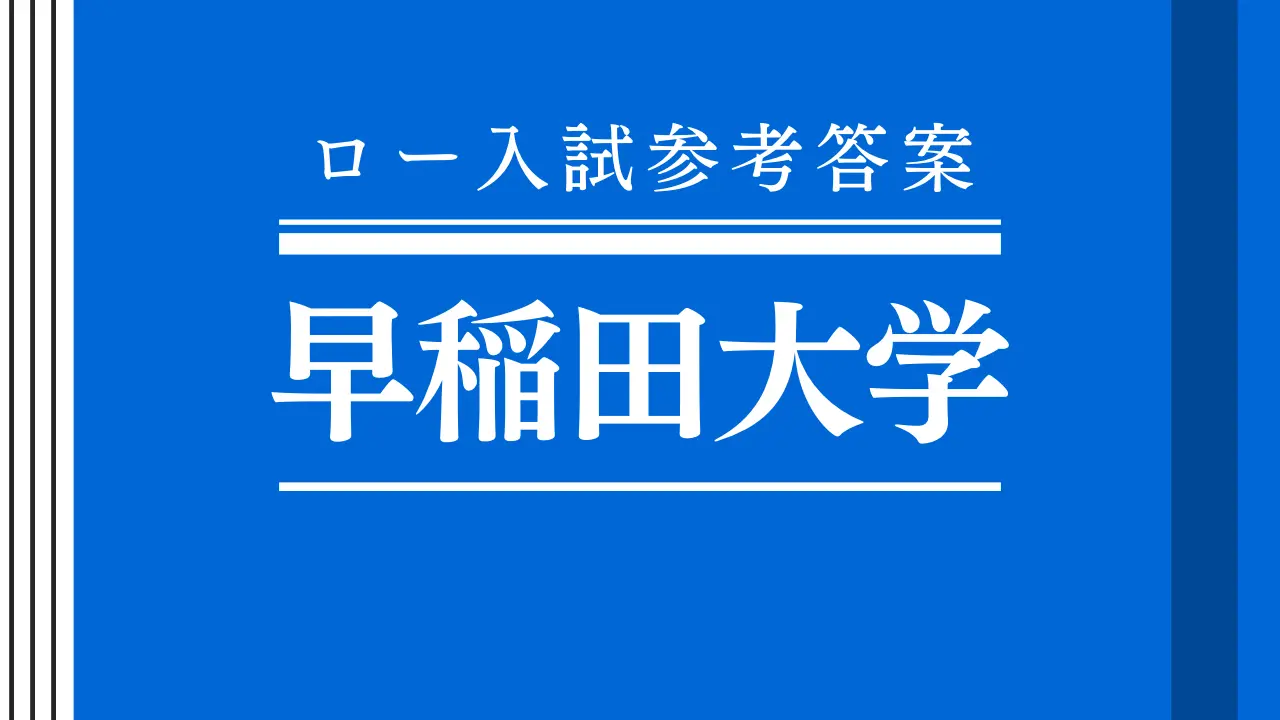
2023年 刑法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2023年 刑法
設問1
1. まず、Aに対する傷害罪(刑法 (以下、法名略)204 条)が成立しないとの結論を導くための説明として、丙はAではなく甲に対し花瓶を投げつけているから丙にはAに対する傷害の構成要件的故意(刑法38条1項本文)が認められないとの説明が考えられる。これをみるに、たしかに認識していた犯罪事実と発生した犯罪事実とが具体的に付合しない限り、故意は認められないとの考えによれば、丙はAではなく甲に花瓶を投げる認識しか有していないため、丙には故意が認められないことになる。しかし、故意責任の本質は反規範的人格態度に対する道義的非難にある。そして、この規範は構成要件の形で示されている。従って上記両事実が構成要件レベルで一致する限り、故意は認められるべきである(法定的付合説)。本件では、丙の認識と発生した犯罪事実は傷害という同一構成要件内で符合する。したがって、上記説明によって故意が否定されることはない。
2. 次に、丙は甲のサバイバルナイフによる攻撃から身を守るために花瓶を投げつけているから甲に対する関係では正当防衛(36条1項)が成立するところ、丙の行為に、Aに対する傷害の関係でも正当防衛が成立するとの説明が考えられる。しかし、A自身は何ら「不正の侵害」をおこなっていない。従ってAに対する傷害については、正当防衛は成立しえない。よってこの見解は妥当でない。
3. 丙の行為に緊急避難(37条1項)が成立するとの説明が考えられる。しかし、緊急避難における「やむをえずにした」とは、危険を回避するためも手段として当該行為以外に侵害性のより軽微な手段が存在しないことをいう。そして、本件で丙が甲による攻撃を避けるための手段として、花瓶という危険性の高い物をAに当たる可能性のある角度で投げつける行為より侵害性の低い手段が存在しなかったとは言えない。したがって、「やむをえずにした」とはいえず緊急避難は成立しない。
4. 最後に、丙の行為に一種の誤想防衛が成立し、責任故意が阻却されるとの説明が考えられる。本件で、丙は甲による攻撃に対抗するため甲に花瓶を投げつける認識で当該行為を行っている。そのため、丙の認識では、正当防衛が成立する行為によってAに対する傷害が生じたといえるため、甲は規範に直面したといえず、故意非難できない。したがって、責任故意が阻却される。よって、甲にAに対する傷害罪は成立しない。
設問2
1. 甲の罪責
⑴ 丙宅の1階の応接室の金庫の方に向かいかけた行為につき、窃盗未遂罪(43条本文、235条、243条)が成立するか。
ア 「他人の財物」とは、他人が所有し、かつ、占有する財物をいうところ、丙宅の金庫の中身は丙が所有し占有するものであるから「他人の財物」にあたる。そして、「窃取」とは、他人の占有する物をその意思に反し自己のもとへ占有移転することをいう。また実行の着手は構成要件的結果発生の現実的危険性が生じた時点で認められるところ、金庫の中身は通常財物以外考えられず、金庫に向かうことは財物を窃取する危険を著しく高める行為といえるから、甲が金庫の方へ向かいかけた時点で、金庫の中身が丙から甲のもとへ丙の意思に反し占有移転される危険性が生じたといえる。従って客観的構成要件を満たす。
イ 甲は金品を窃取するため金庫に近づいており、窃盗の故意が認められる。
ウ 甲は金庫の中身について、丙を排除し、その経済的用法に従い利用処分する意思を有しており、不法領得の意思も認められる。
エ 以上により、窃盗未遂罪が成立する。
⑵ 丙に捕まるのを避けるために、サバイバルナイフで切りかかろうとした行為につき、事後強盗未遂罪(238条、243条)が成立するか。
ア 上述より、甲は「窃盗」にあたる。
イ 「暴行」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行をいう。サバイバルナイフという殺傷能力の高い凶器で切り掛かることは、丙の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行といえる。また、甲は、丙に捕まるのを免れるため、すなわち「逮捕を免れ」るために右暴行をしている。
ウ よって強盗未遂罪が成立する。
⑶ 丁に自己の犯行を話したうえ、警察に聞かれたら一緒に飲んでいたと述べてほしいと依頼した行為に、犯人隠避罪(103条)の教唆犯(61条1項)が成立するか。
ア 後述のとおり、丁の行為に犯人隠避罪が成立する。従って丁は「犯罪を実行」している。「教唆」とは、犯行の決意を生じさせることをいう。甲は、丁に、自己の犯行を話したうえで、警察に何か聞かれたら、その日は一緒に飲んでいたと述べてほしいと依頼し、丁はこれを承諾している。従って、甲は、丁に犯人隠避の決意を生じさせたといえる。
イ もっとも、甲は自己の犯行につき、隠避の教唆をしている。甲に右のような行為をしない期待可能性がなく、不可罰とならないか。
(ア) 自身の隠避が、処罰の対象となっていないのは自身の隠避をしないことに期待可能性がないためであるが、自身の隠避であっても、他人にこれを教唆するような行為は防御権の濫用にあたり期待可能性がないとはいえない。
(イ) よって、甲について不可罰とはならない。
ウ したがって、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
⑷ 以上より、甲の行為に、①強盗未遂罪②犯人隠避罪の教唆犯が成立し、併合罪(45条前段)となる。そして、後述のとおり乙とは窃盗未遂罪の限度で共同正犯(60条)となる。
2. 乙の罪責
⑴ 乙は甲と、丙宅に侵入し金品を窃取することを共謀し、丙宅まで自動車で赴くなどしている。乙に窃盗未遂罪の共同正犯(60条)が成立しないか。
ア 前述のとおり甲には窃盗未遂罪が成立する。
イ 乙は甲と共同正犯となるか。
(ア) 共同正犯の処罰根拠は、相互利用補充関係のもと結果に対して物理的・心理的因果を及ぼす点にある。そこで、①共同実行の意思及び②事実があれば、実行共同正犯が成立する。
(イ) 甲、乙は、丙宅に侵入し金品を窃取することを共謀している。従って①は充足する。
また、甲、乙は丙宅前に自動車で赴き、甲は事前の計画通り特殊開錠器具を使って侵入し、1階応接室に立ち入り、金庫の方へ向かいかけている。乙は車中にとどまり、見張り役を務めている。従って②も充足すると思える。
(ウ) よって共同正犯が成立すると思える。
ウ もっとも、乙は甲が丙宅に侵入した後、「俺は帰るぞ」といって、自動車を発進させて逃げている。そのため、かかる離脱行為によって乙に共犯関係の解消が認められないか。
(ア) 上記のとおり共同正犯の処罰根拠は結果に対して物理的・心理的因果を及ぼす点にある。したがって、離脱行為によってかかる物理的・心理的因果性が遮断されれば共犯関係の解消が認められ、離脱行為以降に生じた結果について責任を負わないと考える。
(イ) 本件では、乙は消防車のサイレンを聞き、火事で警察が来たりするとまずいと思い、甲に電話をかけて、「今日はやめた方がよい」と告げている。これに対して、甲は「大丈夫」だと言ったので、乙は、「俺は帰るぞ」と言って自動車を発進させて逃げている。甲は、乙が自動車を発進させる音を聞いたが、計画通り犯罪を遂行することとしている。従って、乙の離脱の意思の表明に対し、甲は黙示的に了承しているといえる。
しかし、この時すでに甲は丙宅に侵入している。従って、住居侵入はすでに既遂に至っており、窃盗の危険も相当程度高まっている。従って乙が因果性を遮断するためには、その後の犯行を防止するための積極的な措置が必要であるが、乙は電話で甲に犯行を中止するよう勧めるにとどまり、それ以上の措置はとっていない。
(ウ) よって、共犯関係の解消は認められない。
エ 以上、甲に窃盗未遂罪が成立する。
⑵ さらに、強盗未遂罪の共同正犯が成立しないか。
ア 前述のとおり甲の行為に強盗未遂罪が成立する。
イ では、共同正犯が成立するか。
(ア) これをみるに、侵入盗において、窃取行為が完了する前に被害者に発見された場合に、被害者に対して強盗行為に及ぶこと自体はそれほど特異なことではなく、本件でも甲乙は、侵入等の共謀をしているから甲による強盗行為も共謀に基づく実行行為と評価できないことはない。しかし、乙は、甲が強盗に及ぶ前に現場から離脱しており、乙には強盗罪の故意が認められない。よって、乙には強盗未遂罪の共同正犯は成立しない。
(イ) この点、たしかに、共同正犯の成立には、特定の構成要件を共同して実現することが必要である。ただし、各々が実現した構成要件が重なり合うものであれば、その限度で共同正犯が成立すると考える。
そして、窃盗未遂と強盗未遂は、財産犯という性質や意志に反する占有移転という行為態様の点で、窃盗未遂の限度で重なりあう。従って、窃盗未遂の限度で共同正犯関係となる。
(ウ) よって窃盗未遂の限度で共同正犯となるにとどまる。
⑶ 以上より、乙の行為に、窃盗未遂罪の共同正犯が成立する。
3. 丁の罪責
⑴ 警察に甲の行動を尋ねられた際に、嘘を述べた行為につき、犯人隠避罪が成立するか。
「隠避」とは、蔵匿以外の方法による、官憲による身柄の拘束を免れさせる性質の行為をいう。
ア 本問では、たしかに、甲はすでに逮捕されていた。しかし、犯人隠避罪の保護法益は国家に刑事司法作用にあるところ、丁が、警察に対し、「その日は甲と一緒に朝まで飲んでいたので、甲はその事件の犯人ではない」と嘘のアリバイを述べることは、甲の逮捕の理由について警察を錯誤に陥らせ、身柄の拘束を免れさせうる行為であり、国家の刑事司法作用を害する。従って、甲がすでに逮捕されているからといって同罪の成立が否定されることにはならない。
イ 以上より、犯人隠避罪が成立する。
⑵ さらに上記行為に証拠偽造罪(104条)が成立しないか。
ア 丁のした行為は虚偽供述にあたる。参考人の虚偽供述が「偽造」にあたるかが問題になる。
(ア) 虚偽供述は偽証罪(169条)に限って処罰するのが刑法典の建前である以上、捜査官と相談しながら虚偽の供述内容を創作、具体化させ、それを供述調書の形式にするなど、証拠方法の作出にあたるような場合でない限り、「偽造」とはならない。
(イ) 本件では上記のような特段の事情はなく、丁は単に虚偽供述したにとどまる。
(ウ) よって「偽造」したといえない。
イ 以上、証拠偽造罪は成立しない。
⑶ 以上より、丁の行為に犯人隠避罪が成立する。
以上





