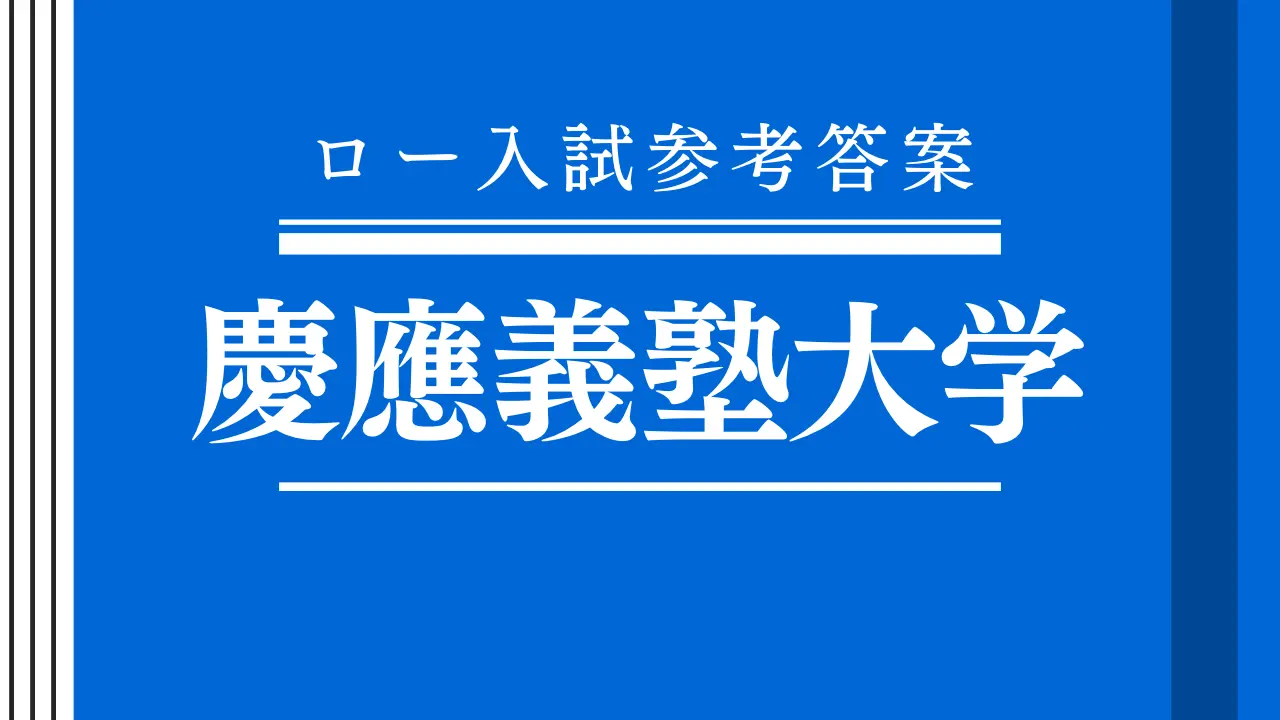
2023年 民法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2023年 民法
設問1
1. AはCに対して、乙契約に基づきブリの代金50万円の支払いを請求できないか。
⑴ かかる請求は、売買契約(民法(以下、略)555条)に基づく代金支払請求であるところ、AはCと、2022年8月5日にαの中のブリ100尾を50万円で販売することを合意している。
⑵ もっとも、Cから536条1項に基づき反対給付の履行を拒絶するとの反論が考えられる。かかる反論は認められるか。
これをみるに、本問では、乙契約はブリという不特定物についての売買契約、すなわち「債権の目的物を種類のみで指定した場合」(401条1項)に当たり、Aは、「物の給付をするのに必要な行為を完了し」(同条2項)ておらず、債権の特定が生じていないからAは、他のブリを調達する義務を負い、「債務を履行することができなくなった」(536条1項)場合に当たらないとも思える。しかし、乙契約において引き渡すべきブリは、αという生簀の中にあるブリに限定されており、Cの債権は、α内という制限の付されたいわゆる制限種類債権であったといえる。そして、α内のブリは、8月11日に全滅しており、AはCにα内のブリを引き渡すことができなくなっている。そのため、「債務を履行することができなくなった」といえる。
そして、α内のブリの全滅は、プランクトンの異常発生という不可抗力によるものであり「当事者双方の責めに帰することができない事由」(536条1項)による。
以上より、Cの反論が認められCは、不能となったα内のブリの引渡し債務の反対給付である代金50万円の支払いを拒むことができる。
⑶ したがって、Aの上記請求は認められない。
2. AはBに対して、甲契約に基づきブリの代金50万円の支払いを請求できないか。
⑴ かかる請求も、売買契約に基づく代金支払請求であるところ、AはBと、2022年8月1日、α内のブリ100尾を50万円で販売することを合意している。
⑵ もっとも、Bから、Cと同様に536条1項による反論が考えられる。かかる反論は認められるか。
これをみるに、たしかに上記のように、α内のブリは全滅しておりAのブリの引渡し債務は履行不能になっている。しかし、甲契約では、ブリの引取りについて、8月8日にBが水槽付のトレーラー数台で引取りにきて、Aの従業員が生簀からブリを生きたまま B のトレーラーに移すことと合意されていた。そのため、Bへのブリの引渡しについては、「債務の履行について債権者の行為を要するとき」(493条但書)にあたるところ、A は、8月8日にブリ100尾を引渡し用の網に取り込んで、B が引取りに来ればいつでもそのブリ100尾を引き渡すことができるように準備をした上で、Bに引取りに来るよう催告しており、「弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告」(口頭の提供)をなしている。しかし、Bは、同日、引取用のトレーラーが調達できず、引取りに行けなかったのであり、「債権者が債務の履行を…受けることができない場合」(413条の2第2項)にあたる。そして、α内のブリが全滅したのは、8月11日であるから、本件のブリの引渡し債務の不能は、Aによる口頭の提供という「履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰すことができない事由によってその債務の履行が不能となったとき」にあたる。したがって、本件ブリの引渡し債務の不能は、413条の2第2項によって債権者Bの責めに帰すべき事由によるものとみなされるため、本件では536条1項ではなく同条2項が適用され、Bは反対給付である代金50万円の支払いを拒むことができない。
以上より、Bの反論は認められない。
⑶ したがって、Aの上記請求が認められる。
第2 設問2
1. AはBに対してブリ100尾の引渡しを拒絶できるか。
⑴ Aが100尾の引渡しを拒絶する論拠としては、まず、ブリの死亡による履行不能の主張が考えられる。
これをみるに、たしかに、Aは8月8日にブリ100尾を引渡し用の網に取り込んで、B が引取りに来ればいつでもそのブリ100尾を引き渡すことができるように準備をし、「物の給付をするのに必要な行為を完了」(401条2項)しており、ブリの特定が生じている。そのため、特定したブリが全滅しているならAのBに対する債務は不能であるといえる。しかし、Aは、8月8日の夜に引渡し用の網を取り外して、100尾のブリをα内に解放しており、これによって一旦生じた特定は解消されている。そのため、α内にブリが100尾残っている以上、AのBに対する債務は不能になったとは言えない。
よって、上記論拠によって、100尾の引渡しを拒絶することはできない。
⑵ 次に、CとCに残ったブリ100尾の引渡しをする旨の合意をしたことによって、Bに対するブリの引渡し債務は不能になったとの主張が考えられる。
これをみるに、α内に残ったブリは100尾であるから、Bに対するブリ100尾の引渡し債務とCに対するブリ100尾の引渡し債務は、一種の二重譲渡の状態になっているといえる。もっとも、動産の対抗要件は、引渡し(178条)であるから、Cと引渡しの合意がなされたに過ぎない本件では、Cに確定的に所有権が移転したとはいえず、かかる主張は認められない。
⑶ 以上より、Aは100尾の引渡しを拒絶することができない。
2. AはBに対しブリ50尾の引渡しを拒絶できるか。
⑴ 50尾の引渡しを拒絶する論拠としては、665条の2第3項の類推適用によってBとCはそれぞれ50尾ずつの引渡ししか請求できないとの主張が考えられる。
これをみるに、665条の2第3項は混合寄託において寄託物の一部が滅失した場合の規定であるが、本件BCの債権は、ともにα内のブリという同種の物の引渡しを受ける権利であり、Aは引渡し日までBCのために当該ブリを管理する義務を負う。そのため、BCとの契約成立後引渡しまでのAによるブリの管理は、Aを受寄者、BCを寄託者とするブリの混合寄託と同視できる。したがって、本件では665条の2第3項の類推適用を認めるべきである。
以上より、本件では、65条の2第3項の類推適用が認められ、BとCは、自己の引渡しを受けることのできたブリの数の割合に応じて残ったブリから引き渡しを受けることができる。したがって、BとCはどちらも100尾の引渡しを受けることができたから、残った100尾のブリを1対1の割合で案分することになり、Bは50尾を超えてブリの引渡しを受けることはできない。
よって、Aは、上記論拠によってBに対しブリ50尾の引渡しを拒絶できる。
以上





