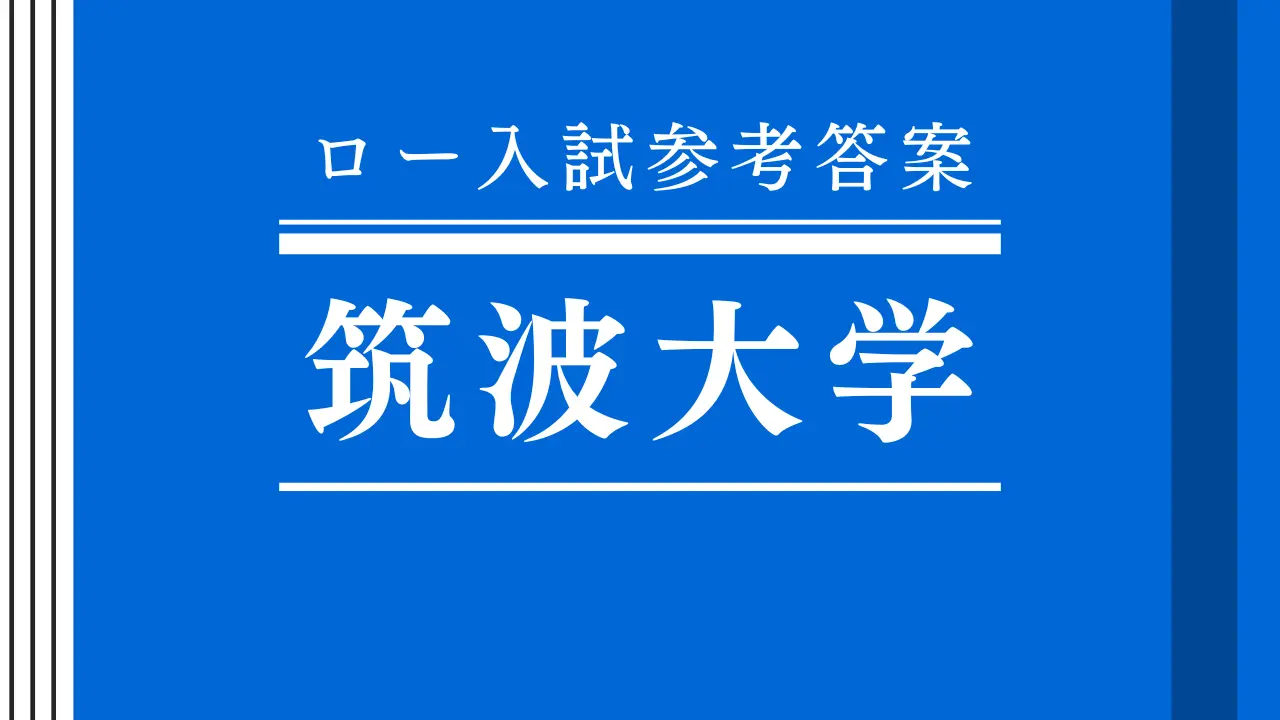
2024年 刑法 筑波大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/30/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
筑波大学法科大学院2024年 刑法
1. 甲がステーキ用牛肉を口に入れて飲み込んだ行為
⑴甲が代金精算前にステーキ用の牛肉を食べた行為は、窃盗罪(刑法(以下略)235条)が成立しないか。Aスーパーマーケットの占有下にあった牛肉を食べることによって自己の占有に移転しているため、「他人の財物」を「窃取」したといえる。
⑵もっとも、牛肉の代金は後で払うつもりであったことから、不法領得の意思がなかったとして、窃盗罪が成立しないのではないか。
窃盗罪が成立するには、故意の他に不法領得の意思が主観的構成要件として要求される。不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用処分する意思のことをいう。
本件において、被害者であるAは、単に商品を売買により金銭に交換するということにとどまらず、商品の適正な管理のために商品と代金の交換の手順を定めているのであって、たとえ短時間の後に交換価値に相当する金銭が支払われたとしても、それは手順が守られた支払いとはもはや社会通念上別個のものというべきである。したがって、Aにおけるこのような主観的利益は財産的利益として客観的にも保護されるべきものであるところ、甲も、Aがこのような利益を有していることを知ったからこそ、その手順を守らないことが動画視聴者の興味を惹くような面白い場面になるとして、本件行為に及んでいる。この行為は権利者を排除する意思があったといえる。
また、甲の行為は動画視聴者の興味を惹くような場面そのものであるとともに、このような場面を作出するための行動であるから、甲は、正に、牛肉という財物自体を用いて、これから生ずる動画視聴者の興味を惹くような面白い場面という効用を享受する意思を有していたというべきである。
したがって、甲には不法領得の意思が認められる。
⑶よって、甲には窃盗罪が成立する。
⑷そして、乙は実行行為者ではないが、かかる行為について甲と共謀が成立しており、その共謀に基づく実行行為が本件の甲の行為であったため、共謀共同正犯が成立する。
よって、乙は甲との間で窃盗罪の共同正犯(60条)が成立する。
2. 乙がBを投げ飛ばした行為
⑴乙は、甲との窃盗行為後に捕まりたくないという一心でBを投げ飛ばして失神させている。乙に事後強盗罪(238条)が成立しないか。
ア 本罪の成立要件は、①窃盗が、②窃盗の機会に、③財物の取り返しや逮捕を免れる等の目的で、④暴行・脅迫をすることである。②について、時間的場所的接着性などを考慮し、窃盗犯人に対する追及が継続していたか否かで決すべきである。④について、本罪は強盗として評価されるため、本罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足る程度のものである必要がある。
イ ①について、乙は①窃盗犯である(①充足)。
➂について、乙は、スーパーマーケットの店員Bに通報等をされ、③逮捕されることを免れる目的で投げ飛ばしている(➂充足)。
②について、かかる行為は窃盗後すぐにAスーパーにおいて、甲と乙の上記窃盗行為を見て近づいてきたBに対して行っており、追及が継続しているから、窃盗の機会といえる(②充足)。
④について、Bを一本背負いで投げ飛ばし、結果的に頭部を強打して失神する程度の暴行であったため、相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行であったといえる(④充足)。
ウ そのため、乙には事後強盗罪が成立する。
⑵また、甲は上記のように窃盗犯であり、乙に何とかしてくれと頼んでいるため、共謀が成立しているといえ、同罪の共同正犯(238条、60条)が成立するといえる。
⑶そして、甲ら「強盗」が強盗の機会にBに失神という傷害を負わせているため、強盗致傷罪の共同正犯(240条前段、60条)が成立する。
3. 甲が本件ポリ袋を落とした行為
⑴甲は覚醒剤が入っていないのに入っていると見せかけた本件ポリ袋を交番の前に落とし、不要な公務を警察官C及びDに行わせた。暴行に至らない偽計による場合、公務執行妨害罪(95条1項)は成立しない。それでは、偽計業務妨害罪(233条後段)が成立しないか。公務は「業務」に含まれるかが問題となる。
この点について、強制力を行使する権力的公務については威力・偽計は実力で排除できるが、そうではない非権力的公務についてはそのような実力はない。しかも、非権力的公務は一般私人の業務と区別する必要がなく、「業務」に当たるとしても無理はない。したがって、非権力的公務のみが「業務」に含まれるとするのが妥当である。なお、権力性の有無は個別具体的に判断すべきである。
本件において、甲を被疑者とする覚醒剤所持の事案が認知され、甲に対する職務質問等のため、C及びDが現場に臨場するなどして職務に従事し、これらの警察職員は、この間、刑事当直、警ら活動、交番勤務等当時従事すべきであった業務を行うことができなかった。かかる業務は非権力的公務であるため、「業務」にあたる。
したがって、甲には偽計業務妨害罪が成立する。
⑵乙は甲との間でかかる行為の共謀を遂げているため、偽計業務妨害罪の共同正犯が成立するとも思われる。しかし、乙は、甲が交番に近づいていると、撮影するふりをして密かにその場から立ち去っている。このことから、乙に共犯からの離脱が認められないか。
共犯の処罰根拠は、自己の行為が結果に対して因果性を与えた点にある。そのため、後の結果と自己の行為との因果性が断ち切られたと評価できれば共犯関係からの離脱を認めてもよい。 よって、離脱の認定は、因果性(物理的因果性、心理的因果性)の除去があるかどうかによることになる。
本件において、乙は甲に立ち去ることを告げず、撮影するふりをして密かに立ち去っていることから、甲は乙が撮影していると誤信しており、甲が乙と犯罪を遂行させる意思は継続している。また、ポリ袋を回収するなどの措置も何ら行っていない。そのため、心理的にも物理的にも因果性の除去があったとはいえない。
したがって、共犯からの離脱をしたとはいえず、乙は偽計業務妨害罪の共同正犯の罪責を負うべきである。
⑶以上より、甲と乙には偽計業務妨害罪の共同正犯が成立する。
4. 罪数
甲と乙には、①窃盗罪、②事後強盗罪、③強盗致傷罪、④偽計業務妨害罪が成立し、いずれも共同正犯が成立する。①は②に吸収され、これらは③に吸収される。そして、③と④は併合罪(45条前段)となる。
以上





