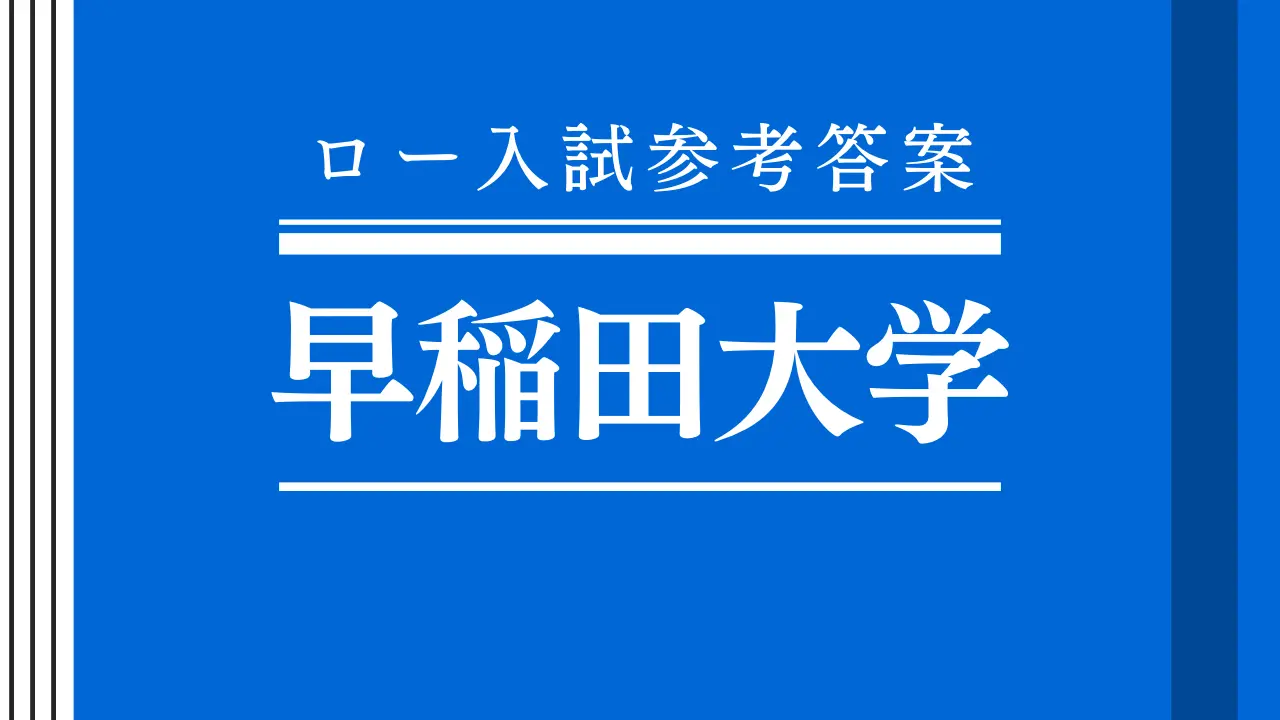
2024年 刑法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2024年 刑法
設問1
1. 甲はBが占有していた手帳を、カバンに入れて休憩室に移動しているため、「他人の財物」(刑法(以下略)235条)を第三者の占有下から自己の占有下へと移転した、すなわち「窃取」したといえる。
また、「他人の財物」を「窃取」することの故意(38条1項本文)にある。
よって、窃盗罪の成立が考えられる。
2. しかし、12頁を撮影した後、元の場所に戻しており、持ち出した時間は約5分であったため、不法領得の意思がなく、窃盗罪が成立しないのではないかが問題となる。
窃盗罪の成立には、主観的構成要件として、不法領得の意思が必要となる。その具体的内容は、不可罰的な使用窃盗と窃盗罪との区別、また、窃盗罪と毀棄罪との区別との観点から、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従いこれを利用・処分する意思である。
本件において問題となるのは、前者の権利者を排除して他人の物を自己の所有物とする意思、すなわち権利者排除意思があるか否かである。本件で、甲の行為は手帳の内容をスマートフォンで撮影し、SNS上で暴露してやろうと考えていた。ここで、Bの保有する営業上の情報は他者に知られないことで価値が高まるという性質であるところ、情報が共有された場合、かかる情報の記載された手帳についても価値が大きく毀損されるといえる。したがって、権利者を排除して他人の物を自己の所有物とする意思があるといえる。また、利用処分意思についても認められる。
よって、甲につき不法領得の意思が認められる。
3. 以上より、甲には窃盗罪が成立する。
設問2
1. 甲及び乙は、Bに対して暴行を加える旨の共謀を遂げ、乙が第1暴行を加えている。その暴行によって生じた急性硬膜下血腫が原因でBは死亡しているため、甲と乙につき傷害致死罪の共同正犯(205条、60条)が成立が考えられる。しかし、Bが意識を回復したときに、治療用の管を抜くなどして暴れ、安静に努めなかったことなどが相まって容態が急変して死亡するに至っていることから、乙による第1暴行とBの死亡との間には因果関係が認められないのではないか。
⑴因果関係を判断する趣旨は、偶然的な結果を排除し、適正な帰責範囲を確定することにある。そのため、因果関係は条件関係に加え、法的因果関係も認められることを要する。法的因果関係は、実行行為の危険性が結果へと現実化したか否かで判断し、その際には介在事情の異常性と結果への寄与度を中心に諸事情を総合的に判断して決すべきである。
⑵まず、甲及び乙の行為がなければ、Bが死亡することはなかったから条件関係がある。
次に、甲及び乙の行為により、Bが受けた傷害は、それ自体、死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であって、仮にBの死亡の結果発生までの間に、Bが医者に指示に従わずに安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、乙の暴行による傷害とBの死亡の間には因果関係があると解すべきである。
⑶したがって、因果関係は認められ、第1暴行は傷害致死罪の共同正犯の構成要件に該当する。なお、第2暴行は、Bの死因となった急性硬膜下血腫の傷害に対しては何ら影響を及ぼすものではなかったため、傷害罪の共同正犯の構成要件に該当するにとどまる。
2. もっとも、第1暴行はBの急迫不正の侵害に対する反撃であるため、正当防衛(36条1項)の成否が問題となる。正当防衛の成立要件は、①急迫不正の侵害があること、②防衛の意思、③手段としての相当性であるところ、第1暴行は全ての要件を満たす。一方、第2暴行はすでにBが動かなくなった後に加えた暴行であるため、急迫不正の侵害がなく、正当防衛が成立しない。そのため、第1暴行と第2暴行が一体の防衛行為とみなして、過剰防衛(同条2項)が成立しないかが問題となる。
⑴人間の行為は、客観面と主観面の統合体であるから、2つの行為が客観的にみても主観的にみても関連性が強い場合には、行為の一体性を肯定すべきである。すなわち、各行為が時間的場所的接着性を有することを前提として、侵害の継続性、防衛の意思等の事情を踏まえて行為の一個性を判断すべきである。
⑵本件において、乙の第2暴行は第1暴行の数秒後に行われており、時間的場所的接着性は認められる。そして、侵害自体はすでに終了していたものの、第2暴行は急迫不正の侵害に対する一連一体の暴行というべきであり、第1暴行と第2暴行は同一の防衛の意思に基づく1個の行為と認めることができるから、全体的に考察して一個の過剰防衛として傷害致死罪の成立を認めるのが相当である。
3. ここで、甲については、乙の第1暴行によってBが動かなくなり、その後で乙が第2暴行に及んだことを認識していなかったものである。そうすると、、甲には「甲・乙によって正当防衛にあたる反撃行為がなされている」という事実の認識しかなく、犯罪事実の認識が認められないため、責任故意が否定される。また、甲は乙とは反対方向を向いてBを押さえつけていたのであり、乙による第1暴行を認識していなかったことにつき過失は認められない。
4. 以上より、甲は不可罰となり、乙は傷害致死罪が成立し、過剰防衛によって刑が任意的に減免されうる。
以上





