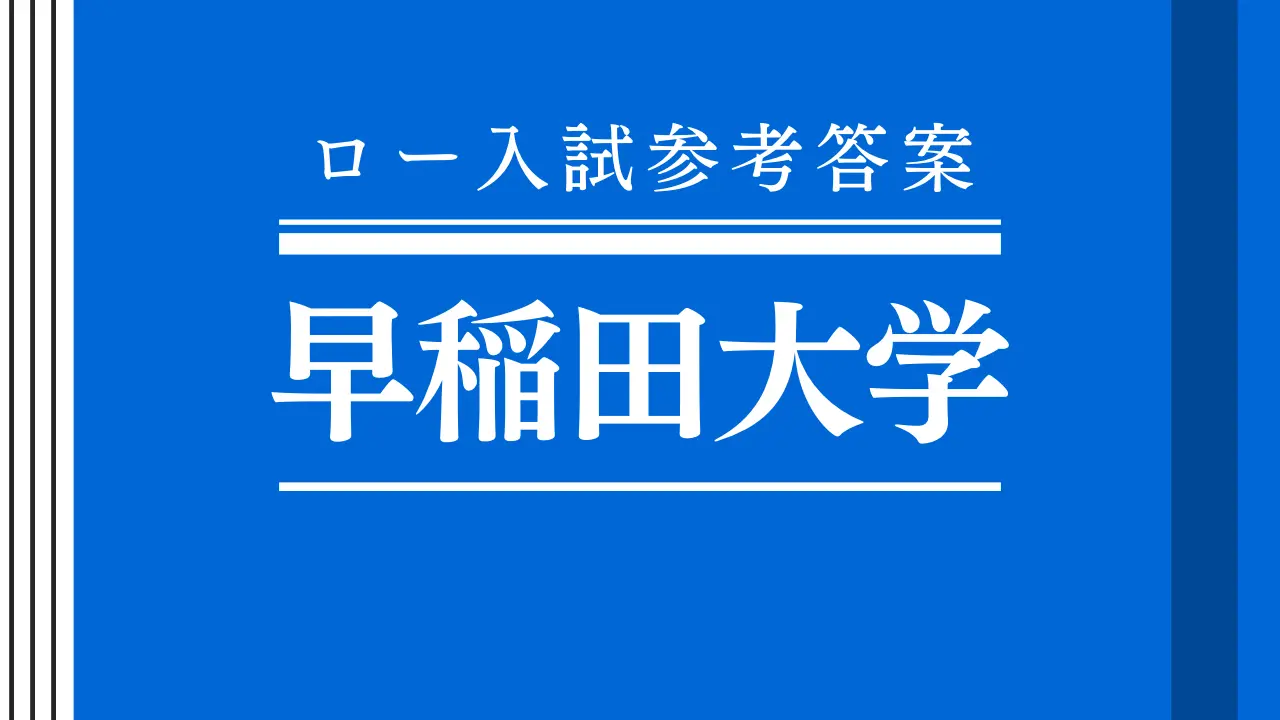
2025年 民事訴訟法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2025年 民事訴訟法
設問1
1. 既判力は「主文に包含するもの」(114条1項)につき生じる。これは、紛争の蒸し返し防止に必要十分な範囲である訴訟物の存否についての判断をいうと解する。
そして、既判力は「当事者」(115条1項1号)間に生じる。また、事実審の口頭弁論終結時まで当事者は攻撃防御方法を提出でき、手続保障に基づく自己責任を問えるので、既判力の基準時は事実審の口頭弁論終結時と解する(民執35条2項参照)。
よって、本件前訴の既判力は、前訴訴訟物たるXの本件土地の所有権の不存在、及び、所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権移転登記請求権の不存在という判断につき生じる。
2. 既判力が生じると、前訴事実審口頭弁論終結時における訴訟物の存在又は不存在の判断に矛盾抵触する後訴当事者の主張ないし裁判所の判断を排斥するという機能が前訴当事者間において営まれる。そうすると、類型的には、既判力は、訴訟物が同一、先決、又は矛盾関係にある後訴に作用する。
前訴の訴訟物のうち、Yの本件土地の所有権部分については、後訴訴訟物たるXの本件土地の所有権と矛盾するから、前訴において生じた上記既判力は、後訴に作用する。
3. 当事者が基準時前の事由をもって基準時における判断を争う主張をすることは、既判力によって遮断される。
本件では、Xが後訴において、Yが本件土地を所有するとの主張に対し、自己が前訴事実審口頭弁論終結前に本件土地を所有していることを理由として否認する(161条2項、規則79条3項)ことが排斥される。なぜなら、前訴の事実審口頭弁論終結時におけるXの本件土地の所有権の不存在と矛盾するからである。これに対して、前訴事実審口頭弁論終結後に本件土地の所有権を取得したことを理由として否認することは、前訴基準時後の事由であるから、排斥されない。後訴裁判所は、以上の事実認定を前提に裁判することになる
4. 他方で、Xが前訴で勝訴していた場合には、Yの後訴の請求原因における前訴基準時前に本件土地を所有していたとの主張が排斥される。なぜなら、前訴事実審口頭弁論終結前にXが本件土地を所有していたこと事実と矛盾するからである。その結果、裁判所はYから新たに本件土地の取得原因事実が主張されない限り、Yの訴えを棄却することになる。
設問2
1. 裁判所が、当事者が主張していないBからCへの贈与の事実(以下、本件事実)を本件訴訟の判決の基礎とすることは、弁論主義に反しうる。
2. ここで、弁論主義とは、裁判資料の収集提出を当事者の責任かつ権能とする建前を意味し、当事者が主張していない事実を裁判所が判決の基礎としてはならない(第1テーゼ)。
その趣旨は、私的自治を訴訟法にも反映することにあり、当事者意思を尊重し、不意打ちを防ぐ機能を営む。そこで、弁論主義の適用される事実とは、訴訟の勝敗に直結する事実である主要事実、すなわち、訴訟物たる権利法律関係の発生、変更、消滅を定める法規の要件(要件事実)に該当する具体的事実を意味すると考える。
他方、間接事実と補助事実については、証拠と同様の機能を有するので、裁判所の自由心証(247条)を害さないためにも弁論主義の適用される事実には含まれないと考える。
本訴訟の訴訟物は、Xの本件土地の所有権である。ここで、BからCへの贈与の事実は、所有権という権利の取得・喪失という新たな法律効果を発生させる(民法549条、176条)事実なので、主要事実である。BがCに贈与する契約は、Bの所有権を、Cに移転するという合意である。これにより、Cが所有権を取得する反面、Xの所有権の取得が障害されるので、権利の発生を障害する事実であり、主要事実である。
3. よって、本件事実には弁論主義の適用があり、XもYも主張していない以上、裁判所が これを認定し、請求を棄却することはできない。
以上





