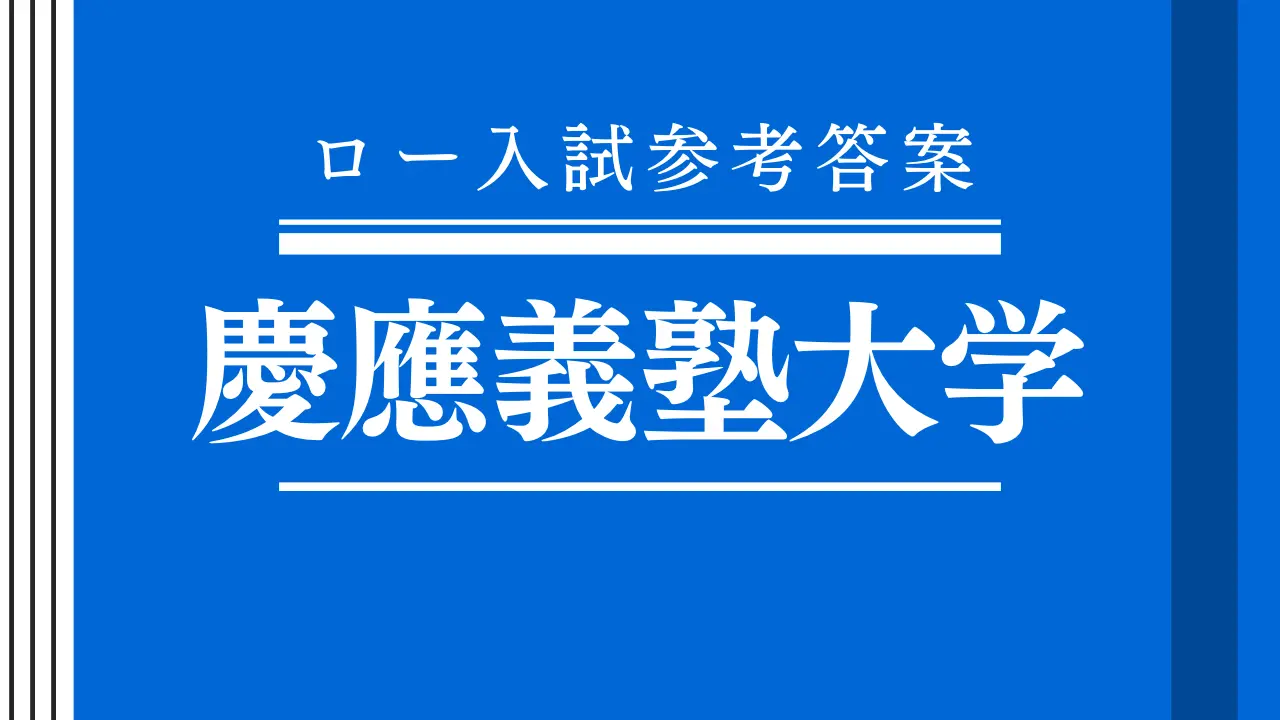
2025年 民事訴訟法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2025年 民事訴訟法
問1
1. 裁判所との関係
⑴本件陳述に裁判上の自白が成立する結果、裁判所拘束効及び不要証効(179条)が認められないか。
⑵裁判上の自白とは、一方当事者が口頭弁論期日又は弁論準備手続期日において行う事実の陳述であって、相手方当事者の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述のことをいう。
そして基準の明確性から、自己に不利益な事実とは、相手方当事者が証明責任を負う事実をいうと解する。
また、弁論主義の趣旨は私的自治の訴訟法的反映であると解されるところ、当事者の意思は主要事実の認定に及ぼせば足りる。したがって、事実は主要事実を意味し、主要事実についてのみ裁判上の自白が成立する。
⑶まず、本件陳述は口頭弁論期日における陳述である。そして規範的要件においては、それを基礎づける具体的事実(評価根拠事実)に攻撃防御が集中すると考えられるから、これが主要事実となると解される。また過失は規範的要件であり、その評価根拠事実が主要事実であるところ、本件陳述は過失の評価根拠事実である「事故当時は赤信号であった」との主要事実を陳述しているのであるから、これは事実の陳述に当たる。
そして過失相殺は公益的な制度であるから、当事者が過失の評価根拠事実を主張すれば過失相殺を裁判所は認定できるが、過失相殺は抗弁であるから本件陳述の内容は相手方当事者たるYが証明責任を負う事実であり、自己に不利益な事実の陳述である。
そして、本件陳述は、事故当時信号が赤であった事を内容とするYの陳述と社会通念上一致している。
したがって、本件陳述には裁判上の自白が成立する。
⑷そして、弁論主義第2テーゼにより、裁判所は当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎に採用しなくてはならない。そのため、裁判上の自白には、裁判所拘束力が認められるところ、本件陳述にも裁判所拘束力が生じる。
⑸また、以下の通り、X2との関係においては事故当時、赤信号であったことが「当事者が自白した事実」(179条)にあたり、これについて不要証効が生じる。
2. X1との関係
⑴裁判上の自白に裁判所拘束力が生じる結果、自白の相手方は、裁判所により自白内容と異なる認定がなされることはないと信頼し、証拠保全をやめることが考えられる。そのため、このような相手方の信頼を保護する必要があり、裁判上の自白がなされた場合には、信義則上自白を撤回することができないという当事者拘束力が生じる。
本件においては、本件陳述には裁判上の自白が成立しているから、X2との関係では、当事者拘束力が生じている。
⑵もっとも、X2の共同訴訟人たるX1との関係でも上記の効力が生じるか。
まず、本件訴訟の訴訟物はX1とX2とで共通であることから、「訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき」にあたり、本件訴訟は、通常共同訴訟に当たる。
そして、「共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない」(共同訴訟人独立の原則、39条)のであり、裁判上の自白もこれと別に解する必要はない。
したがって、X2との関係においては当事者拘束力は生じない。また同様に不要証効は生じない。
よって、本件陳述は共同訴訟人であるX1にとって何らの意味も持たない。
問2
1. 控訴(民事訴訟法(以下略)281条1項本文)が適法に行われるためには、控訴の利益を要する。そして、処分権主義(246条参照)の下で自ら求めた判決を得た者に不服はなく、上訴を認める必要性がないという自己責任、および不服を求める基準としての明確性が求められることから、原審における当事者の申し立てと原判決の主文とを形式的に比較し、判決が申し立てよりも小さい場合に上訴の利益を認めると解する。
もっとも、全部勝訴の場合であっても、後訴で自己責任を問うことが不当である場合には、例外的に控訴の利益を認めるべきである。特に、黙示の一部請求につき全部勝訴の判決を受けた当事者については、別訴として争うことができない場合にはその訴訟で主張しておかないと訴訟上で主張する機会を失う不利益を被ることになるため、例外として請求拡張のための控訴の利益を認めると解する。
2. 本件の原審で、X1は、損害賠償請求権500万円のうち200万円を一部請求している。そうだとすれば、原審における訴訟物は、X1のYに対する不法行為に基づく損害賠償請求権500万円のうち200万円である。そして、原審における判決の主文は、介護費用300万円についてまでは含まれておらず、介護費用300万円を追加主張するための控訴と比較して、量的に小さいといえ、控訴の利益が認められるように思える。
しかし、数量的に可分な債権の一部請求訴訟については、試験訴訟の必要があること、訴訟外で債権の分割行使が認められていること、明示を要求すれば被告に不意打ちにならないことから、一部である旨が明示されていれば、その一部のみが訴訟物を構成し、既判力(114条1項)は残部に及ばないと解するところ、原審におけるX1の請求は、一部である旨を明示しているため、残部にあたる介護費用については別訴で争うことが可能である。そのため、控訴で主張しておかないと訴訟上で主張する機会を失う不利益を被ることになるとはいえず、請求拡張のための控訴の利益が認められない。
3. したがって、X1は、介護費用300万円を追加請求するために控訴することはできない。
以上





