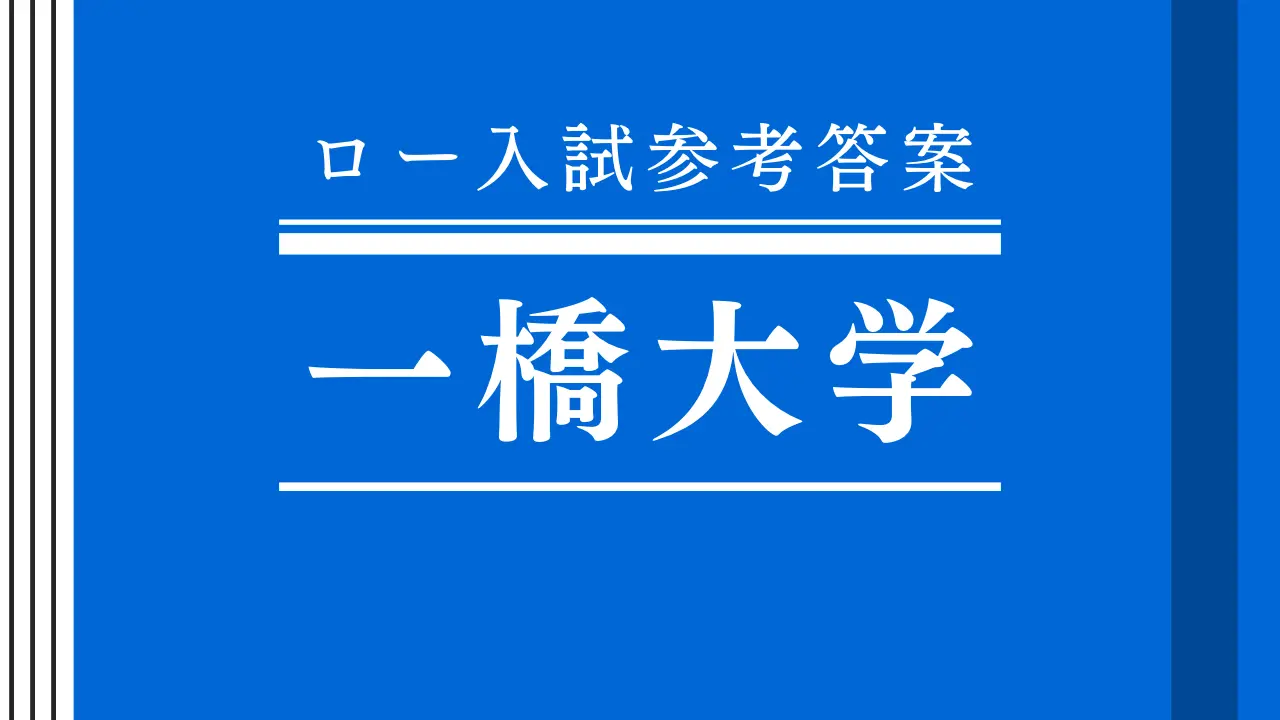
2021年 刑事系/刑法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2021年 刑事系/刑法
第1問
第1 Xが、灰皿の上で人形を燃やしたまま放置し家を全焼させた点につき、不作為の現住建造物放火罪(刑法(以下略)108条)が成立しないか。
1. まず、「現に人が住居に使用し」ている建造物、すなわち現住建造物とは、現に人の起臥寝食の場所として日常使用されている建造物をいう。
本件では、確かに、X宅にはXとAが暮らしていたが、Aは3ヶ月前から実家に戻っており、犯人であるAは「人」に含まれないところ、現住建造物とは言えないとも思える。
しかし、Aが3ヶ月前から実家に戻っているとしても、それは反省を促すための一時的なものにすぎず、AがX宅に戻ってくる可能性がある以上、起臥寝食の場所として日常使用されていることには変わりないから、現住建造物にあたる。
2. では、人形を燃やしたまま放置した不作為が「放火して」といえるか。不作為が実行行為たりうるかが問題となる。
⑴ 実行行為とは、特定の構成要件に該当する法益侵害の現実的危険性を有する行為をいうところ、不作為によっても法益を侵害しうるから、不作為も実行行為たりうると解する。もっとも、自由保障の見地から、不作為が作為と構成要件的に同価値である場合に限り、不作為は実行行為にあたると解する。具体的には、法的作為義務の存在、及び作為の可能性・容易性が必要と解する。
⑵ 本件で、人形にライターで火をつけたのはXであり、人形の火が家に燃え移る危険はXの帰責性ある行為によって作出されたものといえる(先行行為)。また、当時X宅にはXしかおらず、人形の火を消化することはXにしかできなかったといえ、排他的支配がある。そして、人形は木製であり燃えやすく、全長60cmもの大きさであるにも関わらず、直径約10cm、高さ約4cmの小型の灰皿の上において燃えたまま放置している。さらに、灰皿は、居間の可燃性の壁である北側ベニヤ板壁から約90cm、西側の壁から約125cmの地点の畳の合わせ目付近にある。そのような状況であれば、燃えカス等が床に落ちて畳が燃えたり壁に燃え移ったりすることは十分に予想できるのであり、条理上Xには人形の火が家に燃え移らないように阻止するための一定の措置をとるべき作為義務が認められる。
そして、Xは居間にいるところ、ただちに119番通報したり、近所の住民に消化作業の協力を求めたりすることは、可能かつ容易であるから、作為の可能性・容易性もある。
よって、それらの措置をとることなくXが人形を燃やしたまま放置した不作為は、現住建造物放火罪の実行行為にあたり、「放火して」といえる。
3. 「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物に移り、目的物が独立して燃焼を継続する状態をいうところ、本件では全焼しており、目的物たるX宅が独立して燃焼を継続する状態に至っているといえ、「焼損した」といえる。
4. 次に、X宅は「焼損」しているが、Xが消化しようとしてラグマットを被せたという介在事情が存するところ、放火行為と焼損との間に、因果関係が認められるか。
⑴ 因果関係は、発生した結果につきいかなる範囲で行為者に帰責できるかという客観的帰属の問題であるところ、不作為の因果関係は、期待された行為がなされていたら結果を回避できたことが合理的な疑いを超える程度に確実であり、期待される作為によって解消されるべきであった危険が結果に現実化したときに認められる。
⑵ 本件で、Xが燃えている人形を放置せずに119番通報するなどしていれば、家が全焼することは合理的疑いを超える程度に確実であったといえる。
また、確かに、Xが火を消し止めるためにラグマットを被せたが、そのラグマットは易燃性素材のポリプロピレン製であり、火が燃え広がってしまったという介在事情がある。そして、Xの家の畳は防炎加工が施されていたため、人形の火が畳表に引火した状態で放置した場合でも、全焼に至るまでには数日間を要し、または自然に鎮火した可能性もあった。とすると、「焼損」するに至った主たる原因は、上記介在事情にあり、放置したという不作為の危険が現実化したとは言えないとも思える。
⑶ しかし、上記不作為も上記介在事情も、いずれもXがおこなったことであり、第三者が介在したものではない。また、火を消そうとして布やマット等を被せてしまった結果、かえって火が燃え広がってしまったという事態はよくあり得る。とすれば、上記不作為と上記介在事情があいまった結果、全焼するに至ったといえ、不作為の危険が現実化したといえる。
⑷ よって、因果関係が認められる。
5. したがって、現住建造物放火罪が成立する。
第2 Xがラグマットを被せた結果、火が燃え広がり、「108条に規定する物」であるX宅を全焼させた行為は、過失により出火した、すなわち「失火により」「焼損した」として、失火罪(116条1項)が成立する。
第3 罪数
以上より、現住建造物放火罪と失火罪が成立し、併合罪(45条)となる。
第2問
第1 Xが、鞄の鍵を開けさせた上、Aが居間に行っている隙にスーパーIを持ち出して逃走した行為につき、詐欺罪(刑法(以下略)246条1項)が成立するか。
1. まず、スーパーIは、1万円札を精巧に模した紙幣様の紙片で法禁物であるところ、かかる法禁物も「財物」たりうるか。
⑴ 「財物」とは、有体物をいう。そして、法禁物であってもその没収には一定の手続が必要であるところ(19条、刑事訴訟法490条以下参照)。このような没収制度の存在は、法禁物も所有の対象である財物たりうることを前提としている。
よって、法禁物も「財物」にあたると解する。
⑵ 本件でも、スーパーIは「財物」にあたる。
2. もっとも、Xは、「俺は最新の技術に詳しいから、お前の持っているスーパー1が本当に通用するかどうか確かめてやってもいいぞ」、「すべて検査する必要がある」と持ち掛けて、A宅においてAが目を話した隙に持ち去っている。もっとも、上記持ち掛けた行為が「欺」く行為といえるか。
⑴ 「欺」く行為といえるには、それが処分行為に向けられていることが必要である。そして、処分行為とは、錯誤による瑕疵ある意思表示に基づいて、財物の占有を終局的に相手方に移転させる行為をいう。
⑵ 本件では、確かに、Aは目を話すのは一瞬だから大丈夫だろうと考えてわずか5分間スーパーIから目を離したにすぎず、居間と玄関の距離は僅かであると考えられるため、占有の客観的事実と占有の意思がみとめられ、AにスーパーIの占有がある。また、スーパーIは容易に持ち運べる大きさであり、XはスーパーIをもってタクシーでホテルまで移動していることを踏まえると、占有が終局的にXの支配領域内に移転したといえる。
⑶ しかし、Aが玄関から離れて、スーパーIから目を離したのは、孫から呼ばれたためであり、Xが、Aがその場を離れるように申し向けた結果ではない。また、スーパーIが通用するか確かめる旨の持ち掛け、及び全てを検査する必要がある旨の持ち掛けは、XがA宅でスーパーIを目に掛かるきっかけを作ったに過ぎず、Aの処分行為に向けられているとは言えない。
⑷ よって、「欺」く行為とはいえない。
3. 以上より、詐欺罪は成立しない。
第2 では、上記行為につき、窃盗罪(235条)が成立するか。
1. 「他人の財物」とは、他人が所有する財物をいうところ、スーパーIは、A所有であり、「他人の財物」にあたる。
2. 「窃取」とは、他人が占有する財物をその意思に反して自己又は第三者の占有に移転することをいうところ、前述同様、Aの占有が認められ、その意思に反してXの占有支配下に移転しており、「窃取」といえる。
3. また、不可罰的な使用窃盗との区別のために、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞う意思が、毀棄隠匿罪との区別のために、財物の経済的用法に従って利用処分する意思(両者をあわせて不法領得の意思)がそれぞれ必要と解する。
本件では、スーパーIを持ち去ることは、社会通念上、使用貸借または賃貸借によらなければ使用できないような形態において財物を利用する意思があるといえる。そして、Xは、自分のものにしようとして持ち去っているから、財物それ自体を何らかの用途に用いる意思があったといえる。
よって、上記不法領得の意思が認められる。
4. 因果関係、故意(38条1項本文)も問題なく認められる。
5. 以上より、窃盗罪が成立する。
第3 Xは、ホテルHに乗り込んできたAを殴打しているが、かかる行為につき強盗罪(236条1項)は成立しない。なぜなら、前述の通り、スーパーIの占有は既にXに移転しており、Xによる暴行は奪取の確保のための暴行とはいえないからである。
第4 では、同じく、事後強盗罪(238条)が成立しないか。
1. 前述の通り、Xは「窃盗」にあたる。
2. また、Xは、スーパーIが取り返されると思って殴打したと考えられ、「取り返されることを防」ぐ目的がある。
3. では、Xの殴打行為が「暴行」にあたるか。
⑴ 「暴行」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行をいうところ、XはAを警棒という凶器を使って太腿を強打しており、反抗を抑圧するに足りる暴行といえる。
⑵ もっとも、事後強盗罪は財産犯であるところ、かかる「暴行」は窃盗の機会の継続中. に行われることが必要と解する。具体的には、時間的場所的近接性を基礎に、被害者等から容易に発見され、財物を取り返されあるいは、逮捕されうる状況が継続していたか否かで判断する。
本件では、XはA宅からタクシーでホテルHまで移動しており、窃盗行為から相当程度の時間を要していると考えられる。また、ホテルHに移動したことでXは、Aの支配領域から脱していたといえる。さらに、AがXを追跡したのはAが玄関を離れてから5分以上後のことであり、窃盗行為を現認してそのまま追跡し続けたわけでもない。とすれば、上記暴行は、被害者等から容易に発見され、財物を取り返されあるいは、逮捕されうる状況が継続していた状況、すなわち、窃盗の機会の継続中にされたものとはいえない。
⑶ よって、「暴行」にあたらない。
4. 以上より、事後強盗罪も成立しない。
第5 では、強盗罪(236条2項)が成立するか。
1. Xの暴行は、Aによる処分行為に向けられたものではないが、「暴行」といえるか。処分行為の要否が問題となる。
⑴ 強盗利得罪は被害者の反抗を抑圧して財産上の利益を取得する犯罪であるところ、処分行為は予定されておらず、処分行為は不要と解する。ただし、処罰範囲を限定すべく、「暴行」は、具体的かつ確実な利益移転に向けられていることを要すると解する。
⑵ 本件では、ホテルHの部屋にはXとAしかおらず、そのほかに人は存在しない。スーパーIは法禁物であるところ、Aが通報したり他人に相談したりすることは想定し難い。とすれば、偽札であるスーパーIを入手して使用することで、商品の購入などができる利益を獲得できるといえ、利益移転の具体性・確実性がある。
⑶ よって、「暴行」にあたる。
2. そして、Xは、偽札であるスーパーIを入手して使用することで、商品の購入などができる利益を獲得できるという財産上の利益を得ている。
3. 以上より、2項強盗罪が成立する。
第6 また、Aは上記暴行により、重症を負っているところ、結果的加重犯として、強盗致傷罪(240条前段)が成立する。
第7 XがスーパーIを入手した点に付き、偽造通貨収得罪(150条)が成立するかも問題となるが、成立しない。
なぜなら、XはスーパーIを自分のものにしようと考えているのであり、偽造通貨を真正なものとして流通におく目的たる「行使の目的」が認められないからである。
第8 罪数
以上より、窃盗罪と強盗致傷罪が成立し窃盗罪は強盗致傷罪に吸収される。したがって、Xは強盗致傷罪について罪責を負う。
以上





