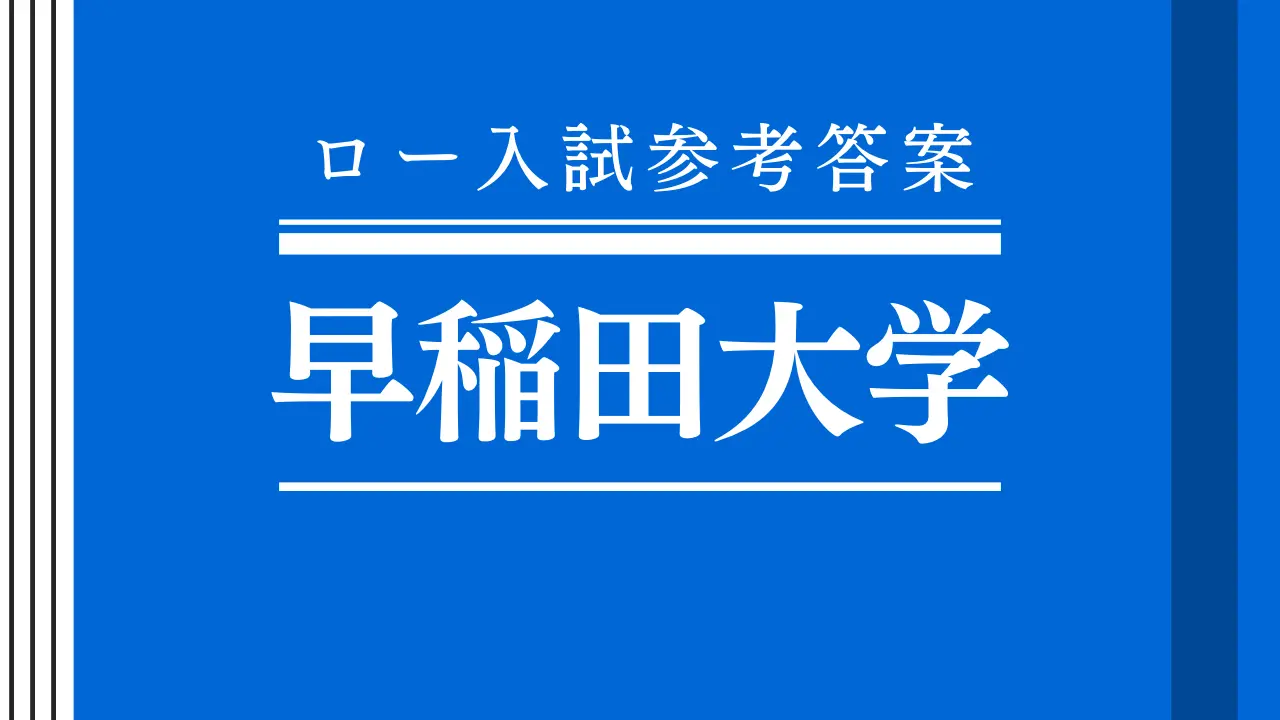
2023年 民法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2023年 民法
民法
問題1 設問1
1. BはAに対し、履行不能による損害賠償請求(民法415条1項本文、同条2項1号、以下法名略)をすると考えられる。この請求は認められるか。
⑴ これをみるに、AはBと甲土地の売買契約(555条)を締結しており、Bに対して甲土地の引渡し及び所有権移転登記を行う債務を負っていた。しかし、その後、AはCに対し甲土地を代金1600万円で売却している。これによって、本件契約につきAの上記「債務の履行が不能」(415条1項本文,2項1号)になったといえるか。Cは甲土地の所有権移転登記を具備しているところ、Cが「第三者」(177条)にあたり登記具備によって甲土地の所有権を確定的に取得したといえるかが問題となる。
ア この点、177条の趣旨は、登記による画一的処理によって取引安全を図る点にあるところ、「第三者」とは、物権変動の当事者又はその包括承継人以外の者で登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者をいう。これをみるに、Cは本件契約の当事者又はその包括承継人以外の者である。また、Cは甲の所有者であったAから甲土地を購入しており、Bとは対抗関係にあるし、Cが背信的悪意者と認められる事情はない。従って、Cは「第三者」にあたる。
イ そして、不動産の二重譲渡がされた場合、第二譲受人が対抗要件を備え、当該物の完全な所有権を取得した時点で、売主の第一譲受人に対する債務は履行不能となる。
ウ 本件をみるに、第二譲受人Cは2022年6月20日に甲土地の所有権移転登記を備えている。従って、この時点でCは甲土地の所有権を確定的に取得し、本件契約のAの債務は履行不能になったといえる。
エ よって、本件契約のAの「債務の履行が不能」になったといえる。
⑵ そして、Bは甲土地を取得できなくなる「損害」(415条1項本文)を被っている。また、この損害は上記履行不能に「よって」生じたといえ因果関係が認められる。さらに、Aはより高い代金での購入を申し出たCに対し進んで甲土地を売却し移転登記手続をしたのであり、履行不能につき「責めに帰することができない事由」(同項但書)があるとはいえない。
⑶ 従って、BはAに対し、上記損害の賠償を請求できる。
2. では、BはAに対し、いくらの賠償を請求できるか。
⑴ この点、本件では、415条2項1号の要件を満たし、Bは填補賠償を請求できる。そのため、損害は甲土地の時価相当額と捉えられるところ、どの時点の時価を考慮できるかが問題となる。
⑵ ここで、賠償請求できる損害の範囲につき、416条1項は相当因果関係の原則を定めている。また、同条2項は、右因果関係の有無を判断する際に考慮できる事情の範囲を定めており、履行不能による損害賠償については、履行不能時に「予見すべきであった」特別の事情につき考慮できるとしている。
そして、履行不能における損害賠償算定の基準時については、原則として履行不能時の時価とするべきである。金銭賠償の原則(417条)から、損害賠償請求権の金銭的評価が可能となる時点で損害賠償額の算定をするのが妥当だからである。そのため、本問では、損害賠償額は、AのBに対する債務が履行不能になった時点である2022年6月20日の甲土地の価格相当額である1600万円となるのが原則である。
ただし、目的物の価格が高騰しつつあるという特別の事情があり、債務者が履行不能時において、その事情について予見可能であった場合には、右事情は「特別の事情」として考慮すべきであり、債権者は上昇した価格を請求できる。
⑶ 本件をみるに、甲土地の価格が、本件契約の前から上昇し続けているという事情があった。そして、Aは、本件契約後により高い値段で購入したいというCに対し甲土地を売却していることから、甲土地の価格が上昇し続けていたという事情を認識していた。そのため、Aは履行不能時においても今後も甲土地の価格が上昇することを予見可能であったといえる。したがって、416条2項が適用され、本件における損害賠償額は、甲土地の現在の価格である1700万円となる。
⑷ 以上より、BはAに対し、履行不能による損害賠償請求として、1700万円の損害賠償請求ができる。
問題1 設問2
1. BはDに対し、甲土地所有権(206条)に基づく返還請求としての土地明渡請求及び所有権に基づく妨害排除請求としての所有権移転登記抹消登記請求ができるか。
⑴ かかる請求が認められるためには、①Bが甲土地を所有していること、そして、➁Dが甲土地を占有していること及び③甲土地にD名義の所有権移転登記が存在すること、が認められる必要がある。これをみるに、まず、Bは甲土地の所有者であるAから甲土地を購入している(①充足)。また、Dは甲土地の引渡しを受け甲土地を占有している(➁充足)し、CからDへ所有権移転登記も行われている(③充足)。
⑵ しかし、Dは、Cから甲土地を購入し、対抗要件を具備している。そのため、Dは「第三者」にあたり、Bは甲土地所有権を喪失しないか。本件で、Cからの転得者Dは本件契約の存在およびBが甲土地を購入できないと苦境に陥ることを知っており、甲土地をBに高値で売りつけることを目的としてCから甲土地を購入していた。従って、Dは自由競争の範囲を逸脱する背信的悪意者にあたり、信義則上Bの登記の欠缺を主張できない。よってDは、「第三者」(177条)にはあたらない。
⑶ もっとも、本件では、上記のとおりCは本件契約の存在を全く知らず、「第三者」にあたる。加えてCは甲土地の登記を備えている。この場合、BD間でも177条の適用があるか。
ア 二重譲渡において、第二譲受人は「第三者」にあたり、転得者のみが背信的悪意者にあたるような場合、法律関係の早期安定と簡明さの見地から、第二譲受人が登記を備え確定的に権利を取得した時点で第一譲受人は権利を失い、転得者も当該物の所有権を有効に取得できると解するべきである(絶対的構成)。
イ 本件では、Cが登記を備え、甲土地の所有権を確定的に取得しているため、BD間で177条の適用はない。
⑷ よって、甲土地の所有権はDに帰属し、BはDに対し上記請求をすることはできない。
2. Bは、Dに対して、詐害行為取消請求としてAC間の売買契約を取り消し、甲土地の登記名義をAに回復することを請求(424条1項本文、424条の5第1号)できるか。
⑴ これをみるに、BはAに対して上記の通り履行不能による損害賠償請求権を有している。従って、Bは「債権者」(424条1項本文)であり、Aは「債務者」である。そして、Aは甲土地をCに売却すれば、Bを害することを「知って」Cに対する売却を行なっている。また、Cへの売却は「財産権を目的」(同条2項)とする行為である。さらに、BのAに対する損害賠償請求権は、本件契約というCへの売却の「前の原因」に基づく債権である(同条3項)し、「強制執行により実現」(同条4項)できる。加えて、「転得者」DはBを「害することを知っていた」(424条の5第1号)。
もっとも、Cは本件契約の存在を知らず、Bを「害することを知らなかった」(同条1項但書)といえる。
⑵ よって、上記請求は認められない。
問題2 設問1
1. Bに対する請求
⑴ まず、AはBに対し,金銭消費貸借契約(587条)に基づく貸金返還請求をすると考えられる。
AとBは、700万円の金銭消費貸借契約を締結し、AはBに上記契約に基づき700万円を交付している。そして、かかる返済期限は到来している。
よって、Aの上記請求は認められる。
⑵ 次に、本件では融資の返済期限が経過しているため、AはBに対し、履行遅滞に基づく損害賠償請求(415条1項本文)として遅延損害金の支払いを請求すると考えられる。
本件では、Bは返済期限が経過したのも関わらず、返済をしていない。従って「債務の本旨に従った履行」をしなかったといえる。本件債務は金銭債務であり、特約のない限り損害賠償の額は法定利率によって定められる(419条1項本文)。なお、Aはこれについて損害の証明を要せず、(同条2項)Bは不可抗力をもって抗弁とすることはできない(同条3項)。
よって、Aの上記請求は認められる。
⑶ 次に、AB間で上記消費貸借契約について利息支払いの合意がされている場合には、AはBに対し、利息契約に基づく利息請求ができる。
⑷ 以上、AはBに対し、700万円の返還及び、返済期限から支払い済みまでの法定利率による遅延損害金の支払い(特約がある場合はその利率による)を請求できる。また、利息契約がある場合には利息の請求もできる。
2. Cに対する請求
⑴ AはCに対し、保証契約(446条1項)に基づき、Bに対する融資金及びその遅延損害金の支払いを請求すると考えられる。
これをみるに、AはCとの間でBへの融資に係る保証契約を締結している。また、この契約は書面によって締結されている(同条2項)。そして、Bの債務は、「事業のために負担した貸金債務」(465条の6第1項)であるところ、Cは保証債務を履行する意思を適式に作成する手順を経た公正証書によって表示している。
よってAはCに対し、上記請求をすることができると思える。
⑵ これに対し、Cは、まず主債務者であるAに対し催告すべき旨の主張(催告の抗弁、452条)、さらに、主債務者に弁済する資力があり、かつ、執行が容易であることを立証して、まず主債務者の財産について執行すべき旨の主張(検索の抗弁、453条)をすることができる。もっとも、本件では明らかでないがCの保証契約が連帯保証契約の場合には、かかる主張をすることは認められない(454条)。
問題2 設問2
1. AはDに対し、DがCの保証債務を相続(896条)したことを主張してその履行を請求できないか。
⑴ この点、DとCは事実上の婚姻状態にあったといえるが、相続制度は戸籍による画一的処理が行われ法的安定性が重視されるから、事実婚状態であったとしてもDに890条は準用されず、DはCを相続しない。
⑵ もっとも、事実婚状態であっても財産分与(768条)の類推適用は認められるから、さらに事実婚の夫婦の一方の死亡による事実婚状態の解消についても、財産分与の規定が類推適用されないかが問題となる。しかし、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところといえ、これを認めることはできない。
⑶ 以上より、AはDに対し、DがCの保証債務を相続したことを主張してその履行を請求できない。
2. AはDに対し,761条の適用によりDがCと連帯債務を負っていたことを主張して,その履行を請求できないか。
⑴ この点、761条の趣旨は夫婦生活の便宜を図る点にあるところ、その趣旨は内縁夫婦関係にも妥当する。従って、CD間で761条は適用されると考える。
⑵ では、Bの債務を保証することは、CDの「日常の家事」の範囲内といえるか。
ア 当該契約が夫婦の日常の家事の範囲内といえるか否かは、内部的な事情や個別的な目的だけでなく、法律行為の種類・性質等も考慮して判断するべきである。
イ CはCDの息子のBの債務の保証をしている。そして、Bは事業用資金の融資を受けているところ、かかる目的は夫婦の共同生活に通常必要なものとはいえない。また、700万円という債務額は極めて多額であり、外形上も日常の家事に関する債務とはいえない。
ウ よって、Bの本件債務の保証は日常の家事の範囲内とはいえない。
⑶ したがって,761条に基づく請求も認められない。
3. 以上より、AはDに対し請求をすることができない。
以上





