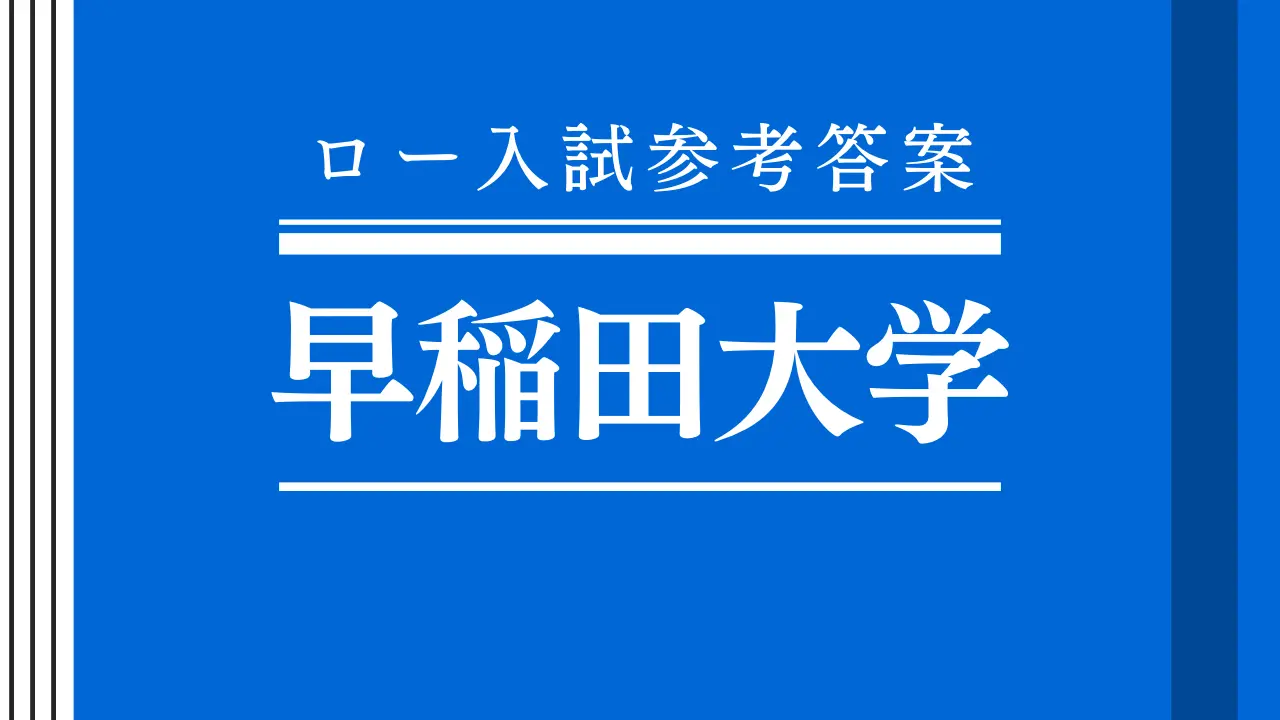
2022年 刑法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2022年 刑法
第1 甲が素手でAの顔面を殴った行為に、傷害致死罪(刑法(以下略)205条)が成立するか。
1. 構成要件該当性について
⑴ まず、かかる行為は、顔面という人の身体の枢要部を攻撃し、人の生理的機能に障害を加えるものであるから、傷害罪の実行行為にあたる。
⑵ 次に、本件では、Aの死亡結果が生じているところ、Aの脳に、Aも知らない病変があったために、甲による殴打で脳組織の破壊が生じ、Aの死に至ったものであるから、上記行為と死亡結果との間に因果関係が認められないのではないか。因果関係の判断基準が問題となる。
ア そもそも、因果関係は、実行行為から生じたと言える結果に帰責範囲を画する機能を有するところ、実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為である。そこで、①条件関係があることを前提として、②実行行為の有する危険性が結果に現実化したと言える場合に、因果関係が認められると解する。
イ まず、甲による殴打行為がなければ、Aの死亡結果は生じていないと言えるから、条件関係が認められる(①充足)。
次に、本件では、Aの脳にAも知らない病変があったという、行為時の特殊事情が存在しているが病気や特異体質を抱えて生きる人の法益保護を健常者よりも切り下げるべきではない。そのため、かかる事情も行為の危険性の基礎事情として考慮すべきであるところ、甲の上記行為には、かかる事情と相まって脳組織の破壊が生じ、死亡結果が発生する危険性が内在していたといえる。
従って、実行行為の危険性が結果へと現実化したといえる(②充足)。
よって、因果関係が認められる。
⑶ そして、結果的加重犯である傷害致死罪につき、加重結果の故意は不要で、基本犯にのみ故意が認められれば良いと解される。また、基本犯に加重結果発生の危険が内包されているため、重い結果につき過失も不要であり、基本行為と加重結果との間に因果関係があれば良いと解される。
本件では、甲は、基本犯たる暴行につき認識しており、上記の通り、因果関係が認められる。
⑷ 従って、構成要件該当性が認められる。
2. 違法性について
⑴ 本件では、甲は、Aがいきなり素手で殴りかかってきたことに対応して上記行為に及んでいることから、正当防衛(36条1項)が成立し、違法性が阻却されないか。
ア まず、Aがいきなり素手で殴りかかってきていることから、法益侵害の危険が切迫しているといえ、「急迫不正の侵害」が認められる。
イ 次に、「防衛するため」と言えるためには、防衛の意思が必要であり、その内容は、急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態を指すところ、本件では、自身の身を守るために上記行為に及んでいることから、急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態にあったといえ、「防衛するため」と言える。
ウ そして、「やむを得ずした行為」とは、防衛行為として必要性、相当性を有する行為をいうところ、本件では認められるか。
まず、甲は何らかの防衛行為に出る必要があったと言えるため、防衛行為の必要性が認められる。
そして、甲は素手で殴りかかってきたAに素手で対抗しているにすぎない。確かに、顔面という身体の枢要部を殴打することまでは不要であったとも思えるが、咄嗟の判断で身を守るべく顔面を殴ることも異常なことではなく、また、枢要部以外を殴打しても、Aの阻止が奏功するとは考え難い。
従って、素手で顔面を殴打したことは、必要最小限度の手段の一つといえる。
また、本件殴打は、結果として死亡結果をもたらしたものではあるが、甲が予見し得ない被害者の素因を行為者の不利な方向に考慮する言われはなく、それ自体は致命的有形力の行使とは言えないものであり、危険性の不均衡もないといえる。そのため、防衛行為の相当性が認められる。
従って、甲の行為は、「やむを得ずした行為」と言える。
エ よって、正当防衛が成立し、違法性が阻却される。
3. 以上より、甲の上記行為に、傷害致死罪は成立しない。
第2 甲が倒れているAの腹部を踏みつけた行為に、傷害罪(204条)が成立するか。
1. まず、かかる行為は、腹部という身体の枢要部を攻撃し、人の生理的機能に障害を加えるものであるから、傷害罪の実行行為にあたる。そして、ろっ骨骨折という傷害結果が生じており、因果関係、故意(38条1項)も認められる。
2. そして、Aは既に意識を失っていることから、「急迫」(36条1項)不正の侵害が認められず、正当防衛は成立しない。
3. 従って、甲の上記行為に、傷害罪が成立する。
4. もっとも、甲の上記2つの行為は時間的場所的に連続して行われているところ、上記二つの行為が一連一体として評価されれば、両行為全体として過剰防衛(36条2項)が成立することになる。では両行為は、一連一体といえるか。防衛行為の一体性が問題となる。
⑴ 行為は、客観面と主観面の統合であるから、二つの行為が客観的に見ても主観的に見ても強い関連性を有する場合には、行為の一体性を肯定するべきである。そこで、防衛行為の一体性は、侵害の継続性、防衛の意思の連続性、暴行態様の変化などを考慮して一連一体の行為といえるかで判断すると考える。
⑵ 本件では、確かに、甲の両行為は、時間的場所的近接性があり、一体のものすべきとも思える。しかし、Aはすでに意識を失っておりAによる侵害は終了していた。そして、甲はそれを認識していたものの、Aがいきなり殴りかかってきたことに対する怒りが収まらず、倒れているAの腹部を踏みつけるなどの過剰な行為に及んでいることから、急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態にはなく、防衛の意思が認められない。
従って、甲の両行為は、分断して考えるべきであり、過剰防衛は成立しない。
第3 乙が、Aの内ポケットにあった財布を取り出した行為に、窃盗罪(235条)が成立するか。
1. 構成要件該当性について
⑴ まず、「他人の財物」とは、他人が所有する財物をいうところ、本件財布は、甲、乙のものではなく、「他人の財物」にあたる。
⑵ 次に、「窃取」とは、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して、自己又は第三者の占有に移す行為をいう。もっとも、本件では、Aが死亡した後に財布を取得していることから、Aの占有が認められず、「窃取した」とは言えないのではないか。
ア この点、死者には事実上の支配も占有の意思も認められないため、死者の占有は認められないと解する。もっとも、被害者が生前有していた占有は、①被害者を死亡させた犯人との関係では、②死亡と時間的場所的近接性が認められる限り、なお刑法的保護に値するといえるので、かかる場合には、被害者の生前の占有に対する侵害が認められ、「窃取した」といえると解する。
そして、①については、直接死亡させた者のみならず、死亡していることを認識しつつ、犯人と共謀して財物を奪取した者も同様と解する。
イ 本件では、乙は、Aを死亡させた直接の犯人ではないが、犯人である甲と共に行動しており、Aが死亡していることを認識しつつ、後述の通り、甲と共謀して、財物を取得しているといえる(①充足)。
そして、乙は、Aが死亡していることを確認して、その場で上記行為に及んでいることから、死亡と取得行為との間に、時間的場所的近接性が認められる(②充足)。
従って、「窃取した」といえる。
⑶ もっとも、不法領得の意思が認められるか。
ア この点、不可罰な使用窃盗と区別するべく、権利者排除意思が必要と解する。また、利欲犯的性格ゆえに重く処罰される窃盗と器物損壊とを区別すべく、利用処分意思を要すると解する。
イ まず、財布を持ち去る行為は、所有者による財布の利用を排除するものであるから、権利者排除意思が認められる。
次に、利用処分意思とは、財物それ自体を何らかの用途に、利用処分する意思をいうところ、乙は、物取りがAを殺害したように見せかけることを目的として、上記行為を行っており、かかる効用は、財布が現場からなくなっていれば得られる効用であり、財物それ自体から生じる効用ではない。そのため、利用処分意思が認められない。
従って、不法領得の意思は認められない。
2. よって、上記行為に、窃盗罪は成立しない。
第4 では、上記行為に、器物損壊罪(261条前段)は成立しないか。
1. 「損壊」とは、物の効用を喪失させる一切の行為をいう。そして、財布を持ち去ることにより、Aによる使用が不可能となるのであるから、かかる時点で効用が喪失しているといえ、持ち去る行為は「損壊」にあたる。
2. 従って、上記行為に、器物損壊罪が成立し、後述の通り、甲と共同正犯(60条)となる。
第5 同行為に、乙について証拠隠滅罪(104条)が成立するか。
1. 構成要件該当性
⑴ まず、甲による傷害罪についての発覚を防ぐため、上記行為に及んでいることから、「他人の刑事事件」といえる。
⑵ 次に、「隠滅」とは、証拠の顕出を妨げ、若しくはその価値を減少・滅失させる一切の行為をいうところ、Aの財布がなくなることにより、物取りによる犯行と見せかけることが可能となるため、上記行為は、甲による犯行における証拠の顕出を妨げる行為といえる。従って、「証拠を隠滅」する行為と言える。
2. よって、上記行為に、乙につき、証拠隠滅罪が成立する。
第6 甲が、乙に対し、財布を持ち帰って燃やして欲しいと依頼した行為に、器物損壊罪の共同正犯が成立するか。
1. 構成要件該当性
⑴ 甲は実行行為を行なっていないところ、共同正犯が成立するか。
ア この点、60条が一部実行全部責任を定めるのは、相互利用補充関係が認められることにより、法益侵害に対する因果性が高まった点にある。そして、実行行為を行わずとも、法益侵害に対する因果性を高めることができる。そこで、①正犯意思に基づく共謀、②共謀に基づく実行行為が認められる場合には、実行行為を行わずとも、共謀共同正犯が成立すると解する。
イ 本件では、甲と乙の間で、意思連絡が認められる。また、甲は自らAの死因を形成しており、その発覚を恐れて、乙に財布を持ち帰るように依頼していることから、固有の利益を有し、かつ、首謀者といえる。従って、正犯意思が認められる。従って、正犯意思に基づく共謀が認められる(①充足)。
そして、前述の通り、乙による実行行為が認められる(②充足)。
従って、共謀共同正犯が成立し得る。
⑵ さらに、甲には、同罪の故意が認められる。
2. よって、甲の上記行為に、器物損壊罪の共同正犯が成立する。
第7 同行為に、甲について、証拠隠滅罪の教唆犯(61条1項)が成立するか。
1. 甲は、Aへの傷害罪の犯人であるところ、証拠隠滅罪の教唆犯が成立するか。
この点、自己の犯罪の証拠を隠滅しても同罪の成立が否定される根拠は、期待可能性の欠如にある。そして、他人を教唆してまでその目的を遂げようとする場合には、もはや類型的に期待可能性がないとは言えない。
そこで、犯人が証拠隠滅を教唆した場合には、同罪の教唆犯が成立すると解する。
2. よって、上記行為に、甲について、証拠隠滅罪の教唆犯が成立する。
3. なお上記行為は、甲の利益のために行われているものではあるが、犯人については、証拠隠滅罪の主体から除外されているため、共同正犯とはなり得ない。
第8 罪責
1. 以上の通り、甲の各行為について、①傷害罪、②器物損壊罪の共同正犯、③証拠隠滅罪の教唆犯が成立し、②と③は、一つの行為により行われているため、観念的競合、これと①が併合罪(45条後段)となり、甲はかかる罪責を負う。
2. そして、乙の行為に、器物損壊罪の共同正犯、証拠隠滅罪が成立し、両者は観念的競合となり、乙はかかる罪責を負う。
以上





