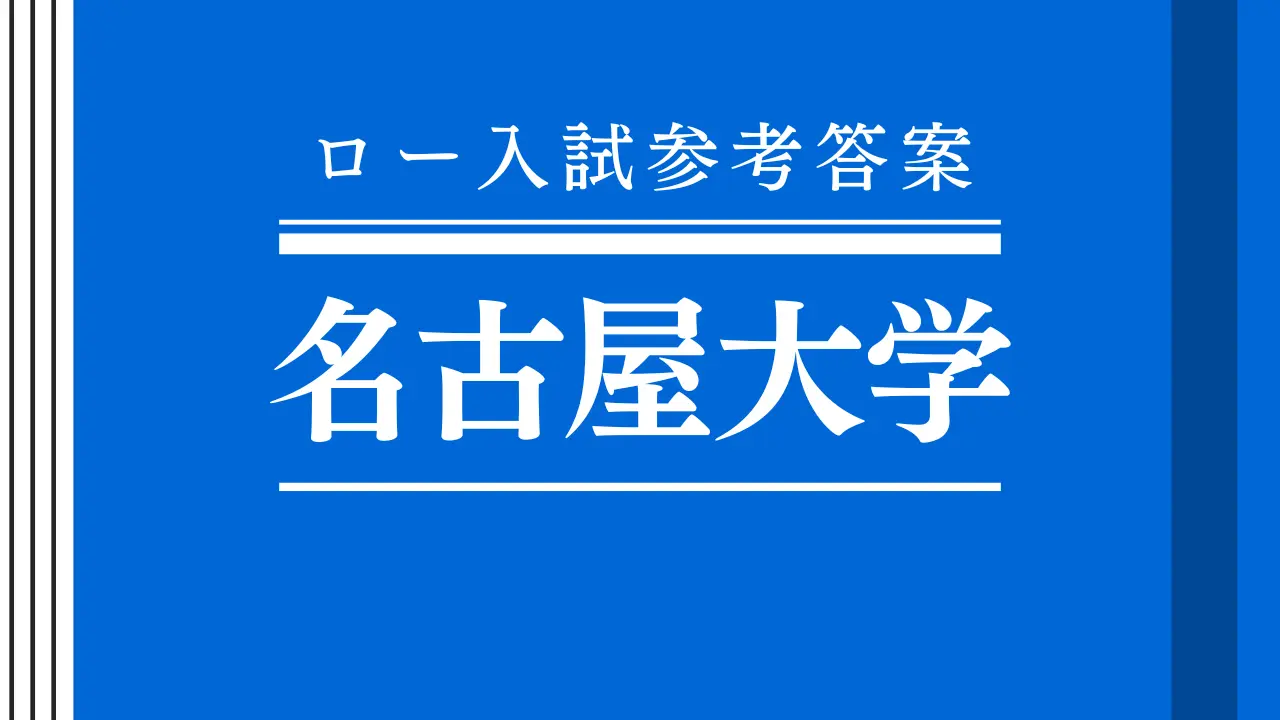
2022年 民事系 名古屋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/12/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
名古屋大学法科大学院2022年 民事系
設問Ⅰ
小問1
公道に至るための土地の通行権は、要役地が「他の土地に囲まれて公道に通じない土地」(民法(以下、法令名省略。)210条)である場合、法律上当然に発生する権利である。この権利は「物件」であるが、囲繞地の所有者は177条にいう「第三者」にあたらないから、その取「得」を対抗するにあたり、囲繞地通行権の登記も要役地の所有の登記も不要である。要役地の権利者は、承役地の権利者に損害に応じた償金を支払わなければならない(212条)。
一方で、通行地役権は、地役権設定契約によって生じる権利である(280条)。通行地役権を第三者に対抗するには登記又は利用状況の存在及び認識可能性が必要となる(177条)。承役地の権利者は、合意によって無償で通行権を認めることができる。
小問2
15歳未満の普通養子縁組を行うには、養子に入ろうとする者の法定代理人の承諾があればすることができる(797条1項)。
一方で、特別養子縁組には家庭裁判所の審判が必要となる(817条の2第1項)。そして、当該審判においては、817条の7の定める「特別の事情」の存否や「この利益のために特に必要がある」場合に当たるかいなかの審査が行われる。
要件にかかる差異がある理由は、特別養子縁組が親子関係を消滅させる離縁型の縁組である点にある。
設問Ⅱ
1. Aは、㋐追完請求権(559条、561条)との同時履行(533条)、㋑修補に代わる損害賠償請求権(559条、564条、415条)との同時履行(533条)、㋒解除(559条、564条、541条)の主張をし得る。
2. ㋐の当否
追完請求権(559条・562条)は、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」場合に発生する(562条1項)。
まず、2021年10月25日、「目的物」たる本件増築部分が「引き渡され」ている。
本件請負契約においては、(1)・(2)の取り決めが明示的になされているが、天井の高さについて明示的な取り決めはない。もっとも、Aは、天井の高さについて、Bに対して強い希望を出している。増改築契約において、天井の高さは重要な要素であり、注文者の希望通りの高さの増改築を行うのが通常である。そうすると、合理的に推認されるA及びBの意思は、Aの希望通りの天井の高さの増改築をするというものと言え、天井の高さは本件請負契約の内容となっていたといえる。
一方で、引き渡された増築部分は、天井の高さがАの強く希望した高さよりも 10 センチメートル低いものであり、また、耐震壁の壁量が不足している。これらの本件不具合は、「引き渡された目的物が…品質…に関して契約の内容に適合しない」場合にあたる。この点につきAに帰責事由はないから、Aは、追完請求権を有している。
そのため、Aは、修補がされるまで、残代金の支払いを拒むことができる。
3. ㋑の当否
Bは契約内容通りの工事を行っていないから債務不履行が認められるし、本件請負契約では、仕事が契約内容通りになされないリスクは、完全にBが負っていたといえるから、債務不履行につき、Bに帰責性が認められる。よって、Bは損害賠償請求権を有している。そのため、損害賠償がなされるまで、残代金の支払いを拒むことができる(533条)。
4. ㋒の当否
Bは、契約内容通りの工事を行っていないから、「債務を履行しない」といえる(541条1項本文)。
もっとも、債務不履行が「軽微」である場合には解除できない(541条ただし書)。「軽微」であるかは、「契約及び取引上の社会通念に照らして」判断する。Aは、締約時、天井の高さについて、Bに対して強い希望を出している。たしかに、本件不具合があっても、Aは美容室を運営することが可能であり、契約の目的は達成できるが、当初の天井の高さは美容室の居心地に強い影響を及ぼすことから、美容室の運営が可能であっても、Aの望む形での運営が不可能になってしまう。また、増築契約において、天井の高さは重要な要素であり、注文者の希望通りの高さの増改築を行うのが「取引上の社会通念」である。耐震構造の不備は美容室の従業員や利用者の生命身体にかかわるものであるから、合意の通りの耐震構造を備えていることは、当事者双方が重視していたものと考えられ、社会通念上も重要である。よって、これらの債務不履行は「軽微」とはいえない。
よって、Aは本件請負契約を解除できる。解除によって未履行債務は消滅するから、Aは、残代金の支払いを拒むことができる。
設問Ⅲ
小問1
営業能力を特に制限されている主体として未成年者がいる。未成年者は、民法上、「営業を許された」場合に営業の行為能力を有する(6条1項)ところ、かかる未成年者の法律行為は法定代理人によって取り消される恐れがある(同条2項)。そこで、商法5条は未成年者が営業を行う際に「登記」を必要とする旨規定した。その趣旨は、営業行為の取消により取引の安全が害される危険を公示の機能によって緩和する点にある。
小問2
手形には、法律上当然に認められるが故に、手形に記載がなくても指図証券性が認められている(手形法11条1項)。したがって、手形に指図文句がなくとも、同条項により当然に指図証券性が認められるため、裏書によって譲渡することができる。
その理由は、制度として為替手形や約束手形(77条1項・11条1項)があらかじめ流通に置かれることを想定して設計されている点にある。
設問Ⅳ
1. 「新設分割後、新設分割株式会社に対して債務の履行…を請求することができない新設分割株式会社の債権者」(会社法810条1項2号)は、債権者異議手続に参加することができる(同条項)。そして、同手続が可能な場合においては、消滅株式会社等は同条第2項各号に掲げる事項を債権者に催告する必要があり(同条2項)、異議を述べた場合には、消滅株式会社等は当該債権者に弁済をしなければならず(同条5項)、催告のない場合は、分割の効力発生日に有した財産の価格を限度に連帯債務として債務の履行を請求することができる(会社法759条2項・810条2項)。
さらに、詐害的会社分割に当たる場合には、かかる残存債権者は承継会社に直接債務の履行を請求することができる(会社法764条4項)。
2. A社Y社間の新設分割において、本件クラブ会員に対する預託金返還債務は承継債務に含まれていなかったのであるから、Xは残存債権者(会社法810条1項2号)にあたる。
したがって、XはA社に対して預託金の返還請求をすれば足りるのであり、債権者異議手続に参加することはできず、原則としてY社に対して預託金の返還請求権を行使することはできない。もっとも、本件新設分割が詐害的会社分割にあたる場合には、Y社に対しても預託金の返還請求をすることができる。
設問Ⅴ
人的分割とは、分割会社の株主が、設立会社の発行する株式の全部または一部を、切り出す事業の対価として受け取る形態による会社分割のことをいうところ、現行法においては、規定上人的分割の制度が廃止されている。
もっとも、現行法においても、実質的に人的分割を行った場合と同様の効果を得ることができる。分割会社は、新設分割計画の定めにより、会社分割の効力発生と同時に、分割対価として受けた承継会社又は設立会社の株式を、剰余金の配当又は全部取得条項付種類株式の取得の対価として株主に交付することができる(会社法758条8号・763条1項12号)。
以上





