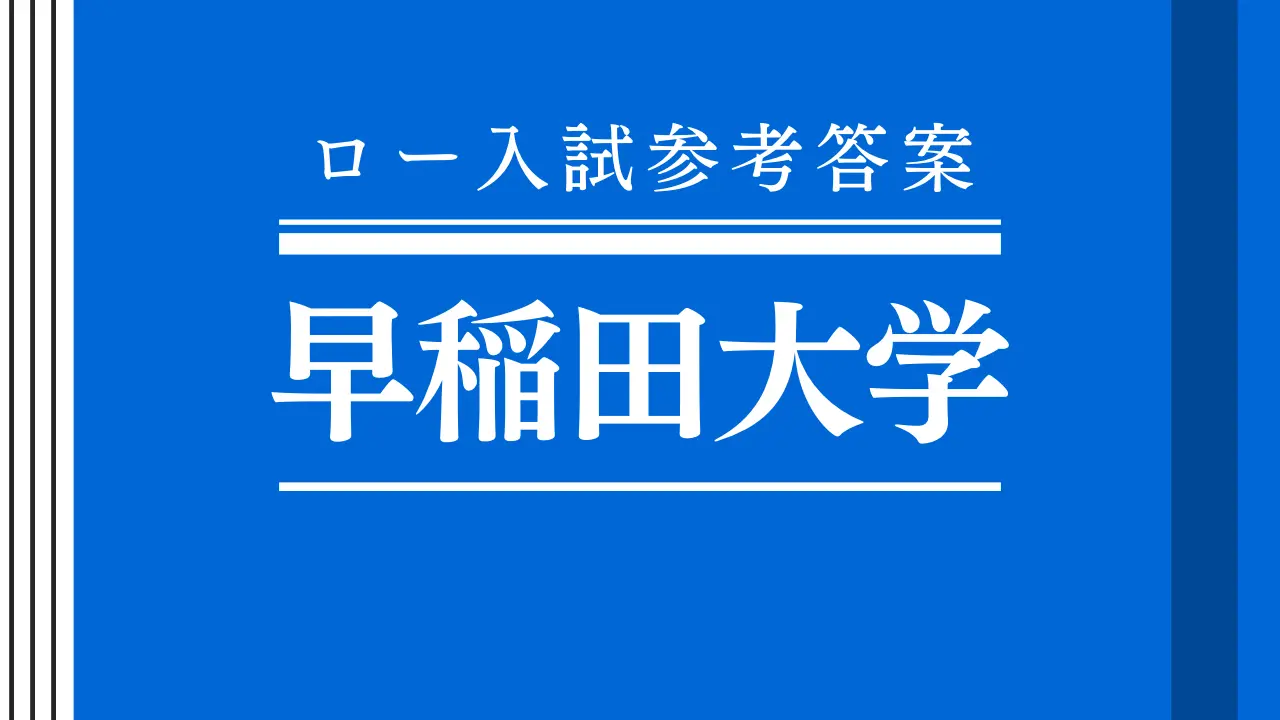
2021年 民法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/30/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2021年 民法
第1 問題1
1. 小問1
⑴CはBに対して、甲土地所有権に基づく返還請求権妨害排除請求を根拠として、乙建物の収去甲土地明渡しを請求することができるか。
上記請求が認められるには、Cが甲土地所有権を有していること、Bが甲土地を占有していることが必要である。
Cは、元所有者Aとの間で甲土地につき売買契約(555条)を締結し、甲土地の所有権を取得した(176条)。また、Bは甲土地上に乙建物を所有することで甲地を占有している。
よって、上記請求の請求原因事実の存在は認められる。
これに対してBは占有権原の抗弁として甲土地の賃借権を反論する。
⑵これに対し、Bは甲土地につき賃借権という占有権原を有していると反論することが考えられる。
まず、AB間では、Aの所有する甲土地につき賃貸借契約(601条)が締結されているから、Bは甲土地につき賃借権を有効に取得している。
⑶では、BはCに対して上記賃借権を対抗することができるか。
この点、不動産の賃貸借権を対抗するためには登記が必要である(民法(以下、法令名省略)605条)。もっとも、「土地の上に賃借権者が登記されている建物を所有」していれるならば、賃借権を第三者に対抗することができる(借地借家法10条1項)。
⑷Bは甲土地の賃借権について登記を具備した事実があれば、かかる登記をもってCに賃借権を対抗できる(605条)。また、かかる登記を具備していなくても、Bが乙建物の所有権を具備しているのであれば、Cに対して賃借権を対抗することができる(借地借家法10条1項)。
一方で、Bが甲土地賃借権の登記も乙建物所有権の登記もいずれも具備していない場合は、Cに甲土地の賃借権を対抗することができない。
以上より、前者の場合であればCはBに対して上記請求をすることができず、後者の場合であれば上記請求をすることができる。
2. 小問2
⑴CはBに対して、賃貸人たる地位に基づいて甲土地につき、賃貸借契約(601条)に基づくの賃料を請求をすることができるか。かかる請求は、BがCに対して甲土地賃借権の対抗要件を具備していることを前提としたものであると考えられるから、以下では、Bが605条ないし借地借家法10条1項の対抗要件を具備していることを前提に検討する。
⑵「前条、…による賃借権の対抗要件を備えた場合」、「その不動産が譲渡されたときは」「その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する」(605条の2第1項)。もっとも、かかる賃貸人たる地位の移転は賃貸物の「所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない」(同条2項)。
⑶本件では、これを本件に鑑みる。まず、Bは605条ないし借地借家法10条1項の対抗要件を具備しておりいるといえる。また、賃貸目的物である甲土地がAからCに「譲渡」されている。
したがって、Cが甲土地の所有権移転の登記を具備していればCはBに対して賃貸人たる地位の移転を主張して上記賃料請求ができる一方し、かかる登記を具備していなければCはBに賃貸人たる地位の移転を主張できず、その結果上記賃料請求ができない。
3. 小問3
⑴EはCに対して、甲土地所有権に基づく返還請求権妨害排除請求権を根拠として、丙建物の収去甲土地明渡請求をすることができるか。
上記請求が認められるには、Eが甲土地所有権を有していること、Cが甲土地を占有していることが必要である。
⑵Cはこれに対して占有権原の抗弁として法定地上権の成立を主張できないか。
⑶法定地上権が成立するには①抵当権設定当時に「土地及びその上に存する建物が同一人の所有に属する場合」で、②「その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったとき」に発生する(388条)であることが必要である。
⑷本件では、Dによる抵当権設定当時には甲「土地」及び「その上に存する」乙「建物」はCという「同一人の所有に属」しているから、本要件を充足し、法定地上権が発生するように思える。
⑸もっとも、競売時において乙建物は消失し、丙建物が新たに建築されているところ、かかる丙建物に法定地上権が成立するか問題となる。
この点、土地建物に共同抵当権を設定した抵当権者の意思は、更地としての土地の価値を把握しようとした点にある。とするとそうであるならば、土地建物が共同抵当に入れられておりいる場合で、建物がを建替えられた場合に、法定地上権を発生させるとするのは、土地の価値を著しく減少させ、抵当権者の意思を不当に害する結果になる。
したがって、土地建物が共同抵当に入れられており、建物が建替えられたかかる場合には新建物の抵当権設定を受けた等の特段の事情がない限り、法定地上権は成立しないと考える。
⑹これを本件に鑑みる。たしかに、抵当権設定当時は甲土地乙建物の所有権はCに帰属しており、388条により法定地上権が発生するとも思える。しかし、本件では、乙建物が火災により焼失し、丙建物が再建築されたという特殊事情がある。Dによりは抵当権設定当時土地建物がを共同抵当に入れられており、その意思は甲土地の更地としての価値を把握しようとしていたものといえる。そして、乙建物が家裁により焼失し、丙建物が再建築されているため、建物が建替えられた場合といえる。また、新建物の抵当権設定を受けた等の特段の事情もない。
したがって、法定地上権は成立しない。
⑺以上より、Cは占有権原の抗弁として法定地上権の成立を主張できず、EはCに対して丙建物の収去土地明渡請求をすることができる。
第2 問題2
1. 小問1
⑴設問前段
小問1請負契約の報酬の支払い時期は「仕事の目的物の引渡し」の時期である(633条)。したがって、本件における報酬債務の弁済期は、BがAに本件請負契約の目的物である甲建物という「仕事の目的物」を「引渡し」た時であり(633条)、この時からAは履行遅滞(412条1項)に陥る。したがって、Bが甲建物をAに引き渡した時点から遅延損害金を請求することができる。
⑵設問後段
ア Bは留置権(295条)を主張して乙建物を留置することはできるか。
イ この点、留置権を主張するためには、①被担保債権の弁済期が到来していることと②「その物に関して生じた債権を有する」といえることが必要である(同条1項)。そして、留置権の本質は物の返還を拒絶して心理的圧迫を加えることで被担保債権の弁済を促す点にあるから、「その物に関して生じた債権」といえるには、引渡義務と被担保債権とが同一の法律関係から生じていることを要する。
(ア)本件では、①については、前述の通り、BがAに対して甲建物を引き渡すことが必要である。
(イ)②については、「その物に関して生じた債権」とはいかなる関係をいうのか問題となるところ、留置権の本質が物の返還を拒絶して心理的圧迫を加えることで被担保債権の弁済を促す点に鑑み、引渡義務と被担保債権とが同一の法律関係から生じていることを指すと解する。
また、本件における被担保債権はBのAに対する請負契約に基づく報酬債権であり、同債権と乙建物の返還義務は同一の本件請負契約から生じているといえる。
したがって、乙建物占有者Bは「その物に関して生じた債権」を有するといえ、留置権を主張して乙建物の引渡しを拒むことができる。
2. 小問2
⑴設問後段
Cは、落ち度という「過失」によってDを負傷させその身体という「他人の権利」を「侵害」していることから、Dに対して「これによって生じた」治療に要する費用など 250 万円の「損害」を賠償責任を負う(709条)。とすると、使用者は、その被用者が事業の執行について第三者に与えた損害につき使用者責任を負う(715条1項)ところ、本件では、被用者Cが使用者Bの事業たる建設業という「事業」のためにCという「他人」を「使用する者」であるBは、甲建物修補工事という「事業の執行」について「第三者」中に過失によってDを負傷させることで生じさせている(715条1項本文)。そして、Bが「相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」(同条項但書)にもあたらない。、損害賠償責任を負うに至っていることから、使用者たるBは使用者責任としてかかるしたがって、Bは715条1項に基づき上記損害を賠償する責任を負う(同条項)。
⑵設問前段
「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない」(716条)。AはBと請負契約を締結しているに過ぎない。したがって、「注文者」Aは「請負人」Bの従業員Cが「第三者」Dに加与えた損害につき、「注文又は指図について」Aという「注文者に過失があった」とはいえない以上、賠償責任を負わない(716条)。
⑶結論
以上より、DはBに対して損害賠償を請求することができるものの、Aに対しては損害賠償を請求することはできない。
3. 小問3
⑴BはCに対し、使用者の被用者に対する求償権(715条3項)を行使して、250万円の支払請求をすることができるか。715条1項の使用者責任として被害者に損害賠償をした使用者は、被用者に対して求償権を有する(同条3項)。もっとも、損害であるの250万円全額の請求ができるか問題となる。
⑵この点、たしかに、使用者責任の代位責任たる性質に鑑みれば、全額求償できると解するべきとも思える。しかし、被用者の不法行為について、使用者に責任の一端がある場合があり、かかる場合にまで全額求償を認めるのは被用者にとって酷である。したがって、損害の公平な分担という見地から信義則(1条2項)上相当と認められる限度に求償額が限定されると考える。
⑶これを本件に鑑みる。本件では、Cがその落ち度によってDを負傷させるに至っているものの、建設業事業者Cには、一般に事故発生防止策を構築し、従業員を監督・指導して第三者に被害を与えないようする注意義務があると解するべきである。
それにもかかわらず、Cはその落ち度によってDを負傷させ、かかる注意義務に違反しているから、BC間の損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に求償権が限定される。したがって、かかるBの注意義務違反を加味して求償権の範囲を確定するべきである。
⑷結論
以上により、BはDに対して250万円全額の求償をできない。
以上





