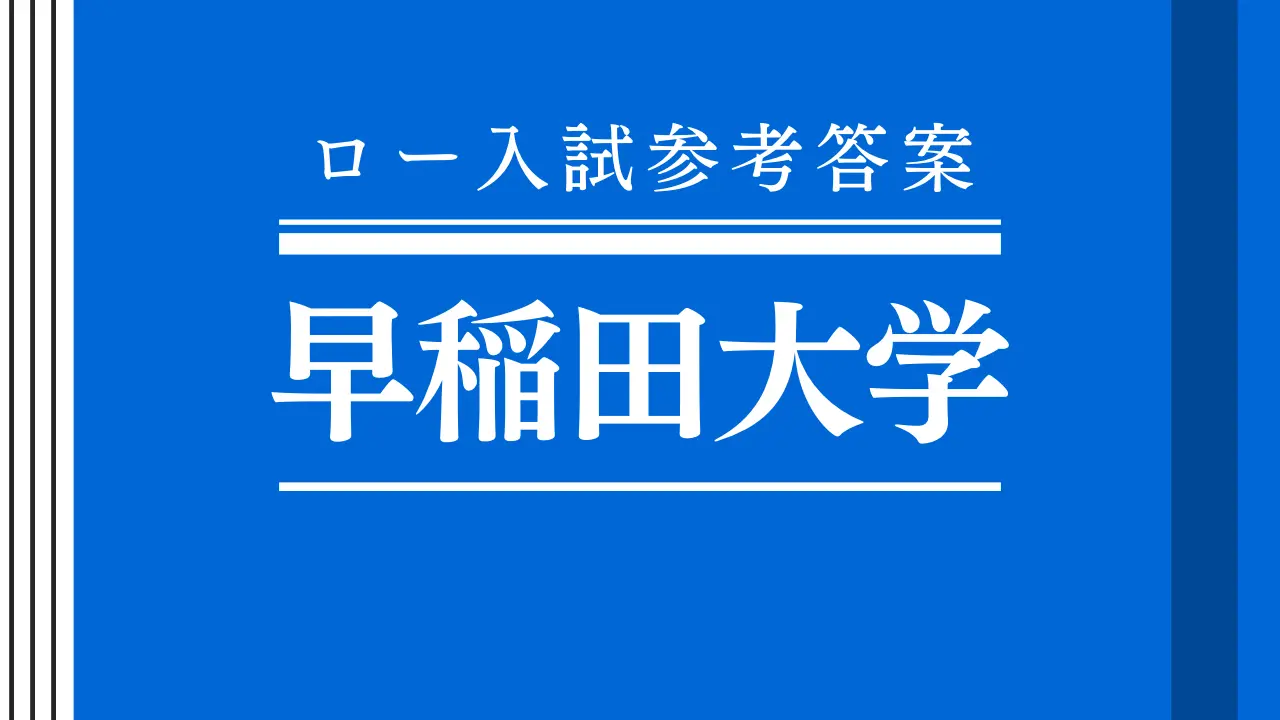
2022年 民事訴訟法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2022年 民事訴訟法
問題
1. 問題の所在
Xは、Yを被告として、本件売買代金の支払いを求める前訴を提起している。そして、前訴が確定した後に、Yは、Xを被告として、本件売買代金債務の不存在の確認を求める後訴を提起している。そこで、後訴におけるYの主張が前訴の既判力(民事訴訟法(以下、略)114条1項)によって制限されるのではないかが問題となる。
2. 前訴の既判力が生じる範囲
既判力とは、確定判決の判断に与えられる通用性ないし拘束力をいう。この既判力の目的は紛争解決基準の安定にあり、その正当化根拠は当事者に対する手続保障があったことにある。そして、既判力は、訴訟物に限って既判力を生じさせることで弾力的で迅速な審理を可能にするという観点から、「主文に包含するもの」(114条1項)、すなわち訴訟物に限って生じる。また、既判力の基準時は、事実審の口頭弁論終結時である(民事執行法35条2項参照)。なぜなら、当事者が主張と証拠を提出できるのはこの時点までであり、裁判所が判決によって確定する権利関係もこの時点のものだからである。
本件では、前訴の訴訟物は本件売買契約に基づく売買代金請求権であり、認容判決が確定している。
したがって、前訴の既判力は、口頭弁論終結時である2020年2月20日時点における本件売買契約に基づく売買代金請求権の存在について生じる。
3. 前訴の既判力の後訴への作用
では、既判力が作用する場合とはどのような場合か。
この点、既判力の消極的作用により、後訴において、前訴における既判力ある基準時の判断と矛盾する権利関係を基礎付ける主張が当事者に許されず、裁判所もそれについて判断することができなくなる。また、既判力の積極的作用により、後訴の論理的先決問題となる前訴の訴訟物についての判断を前提として後訴裁判所がその訴訟物について判断しなければならなくなる。したがって、前訴と後訴の訴訟物が同一・矛盾・先決関係にある場合、前訴の既判力が後訴に作用することになる。
本件では、後訴の訴訟物は本件売買契約に基づく売買代金請求権であり、前訴訴訟物と同一である。したがって、前訴の既判力は後訴へ作用し、後訴では前訴既判力と矛盾する主張、判断が許されなくなる。
4. Aが生前にXに対して相殺の意思表示をしていた場合
まず、Aが生前にXに対して相殺の意思表示をしていた場合をみる。この点、Aによる相殺が基準時前の事由となる場合、前訴の既判力によって当該主張は遮断されることとなる。
相殺は、意思表示によってその効力を生じる(民法506条1項)。そして、Aが死亡したのは2019年9月10日であるから、Aが生前にXに対して相殺の意思表示をしていたことは基準時前の事由である。
したがって、Aが生前にXに対して相殺の意思表示をしていたという主張は前訴の既判力によって遮断される。
なお、Yが本件メモを発見したのは2020年4月15日であり、前訴においてAによる相殺の主張をすることは困難であったといえるものの、当事者の知・不知のような主観的事情によって既判力を緩和することを認めると、後訴裁判所ではその点に関する煩雑な審理を余儀なくされることになり、法的安定性の確保という既判力制度の趣旨を害することになるため、やむを得ない。
5. Aが相殺の意思表示をする前に死亡していた場合
次に、Aが相殺の意思表示をする前に死亡していた場合をみる。この場合、Yは、Aの相続人(民法896条本文)であり、Aの債権債務を包括承継しているため、相殺の意思表示をすることが考えられる。
ここで、相殺は、意思表示によって行われ、(民法506条1項)相殺の意思表示は、相殺適状のときに遡ってその効力を生じる(同条2項)。そのため、相殺のような形成権について、前訴の基準時前に形成原因が発生したが基準時後に形成権を行使した場合には、形成原因発生時か形成権行使時かいずれの時点をもって考えるかが問題となる。
この点、事実審の口頭弁論終結時が既判力の基準時とされる根拠は、その時点までは事実主張が可能であったという点に求められ、その背景には、主張可能な事実は当然に前訴においても主張すべき、という考え方がある。そうだとすれば、形成権についても、その主張が可能であり、かつ主張すべきであったと評価できる場合には、遮断を認めても、既判力の対象を基準時における権利関係とした趣旨に反するものではない。そこで、形成権が基準時前に発生していた以上、意思表示をして法律効果を発生させておくべきであったと評価できる場合には、形成原因発生時をもって考えるべきであり、後訴における形成権の行使は、前訴の既判力によって遮断されると解する。
これをみるに、相殺は、相殺権者の側でも自働債権の消滅という形で出捐をする弁済方法の一種ともいえ、その行使の有無や時期については相殺権者の自由を尊重すべきである。また、相殺権は、訴訟物たる権利に内在する瑕疵に基づくものではない別個独立の権利であり、これが行使されたからといって前訴の勝訴当事者の地位が無に帰するわけではなく、むしろ相殺権者の実質敗訴を前提とするものである。また、後訴の中心的な争点も、自働債権の存否であって、前訴における争点の蒸し返しとはいえない。さらに、Yが本件メモを発見したのは2020年4月15日であった。これらの事情からすると、前訴の基準時までに相殺の意思表示をすべきであったとまでは評価することができない。
したがって、相殺の主張は前訴の既判力によって遮断されない。
6. Yが後訴においてなすべき主張
以上より、Aが相殺の意思表示をする前に死亡していた場合にYが相殺の意思表示を行うことは前訴の既判力と矛盾せず主張することが許されるから、Yは、後訴において、本件工事代金債権を自働債権、本件売買代金債権を受働債権とする相殺の主張をすべきである。
以上





