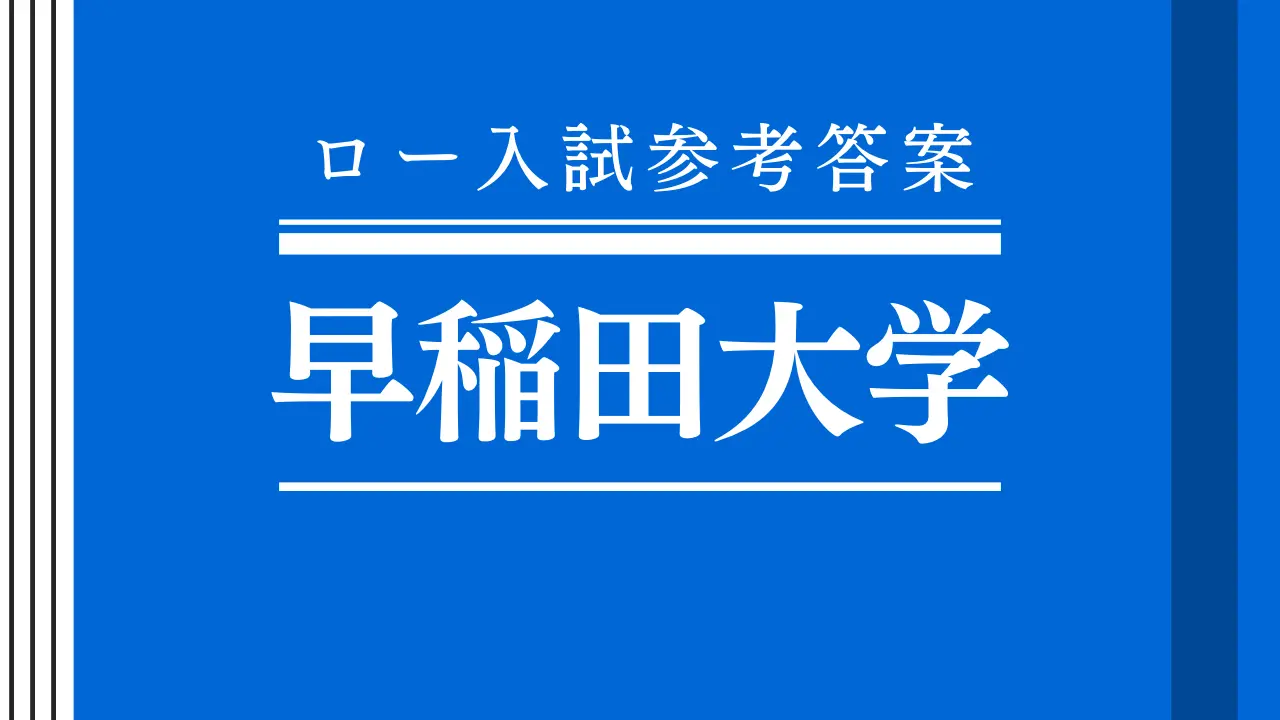
2025年 刑事訴訟法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2025年 刑事訴訟法
(1)の書面について
1. 裁判所が、証拠調べを認めるためには、証拠能力が認められることを要する。
2. (1)は、「公判期日における供述に代」わる「書面」(刑事訴訟法(以下略)320条)として、法律的関連性が否定され、証拠能力が認められないのではないかが問題となる。
3. ⑴伝聞法則(320条)で法律的関連性が否定されるか。
伝聞法則の趣旨は、供述証拠は知覚・記憶・表現・叙述の過程を経て証拠となるところ、各過程には類型的に誤りが介在しやすいから、反対尋問(憲法37条2項前段、法304条2項、規則199条の4)、宣誓(354条)、裁判所による観察等を通じて、内容の真実性を担保する点にある。320条1項は、それを担保できない伝聞証拠の証拠能力を原則として否定することで事実認定の正確性を損なうおそれを排する趣旨だから、かかる担保の必要がないならば証拠能力を否定する必要はない。
そこで伝聞証拠とは、公判廷外供述を内容とするもののうち、要証事実との関係で内容の真実性が問題となるものをいうと解する。
そして328条は、供述が別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体を立証し、公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ることが、主要事実との関係では伝聞証拠となりえないことを注意的に規定したものである。もっとも、他人の矛盾供述を用いて証明力を減殺する場合、その内容の真実性が問題となるから、これを「証拠」に含めれば、反対尋問権の保障(憲法37条2項)、直接主義の要請などの伝聞法則の趣旨が没却される。そこで、「証拠」とは自己矛盾供述のみをいうと解する
⑵(1)の要証事実は被告人側の立証趣旨通り、Aの供述の信用性である。(1)は、供述主体がBであり、証言者Aの供述を内容としないから、自己矛盾供述に当たらず、328条により証拠能力を認めることはできない。
4. 上記の通り証言の信用性を立証するために、他人の供述を用いることはできないから、(1)は、法律的関連性を有さず、証拠能力を有さない。
5. 従って、裁判所は、証拠調べ請求を認めるべきではない。
(2)の書面について
1. (2)は、Aの証言と矛盾する内容の供述をKが録取した書面である。そこで、供述録取書が上記にいう弾劾証拠にあたり、328条により証拠能力が認められるかが問題となる。
2. 328条の上記趣旨からすれば、供述の録取過程の正確性について担保のない供述録取書については、328条を根拠に証拠能力を認めることはできない。録取過程が正確でない場合には、証人の供述と矛盾する同人の供述があるとは限らず、自己矛盾供述が存在することについても立証を要するからである。
そして、録取過程の正確性を担保する方法としては、署名または押印が必要であると解する。
3. (2)には、Aの「署名・押印」がないため、録取過程の正確性につき担保を欠く。そのため、(2)に証拠能力は認められない。
4. よって、伝聞法則の適用があり、法律的関連性を欠くといえ、この点から証拠調べ請求は却下されるべきである。
以上





