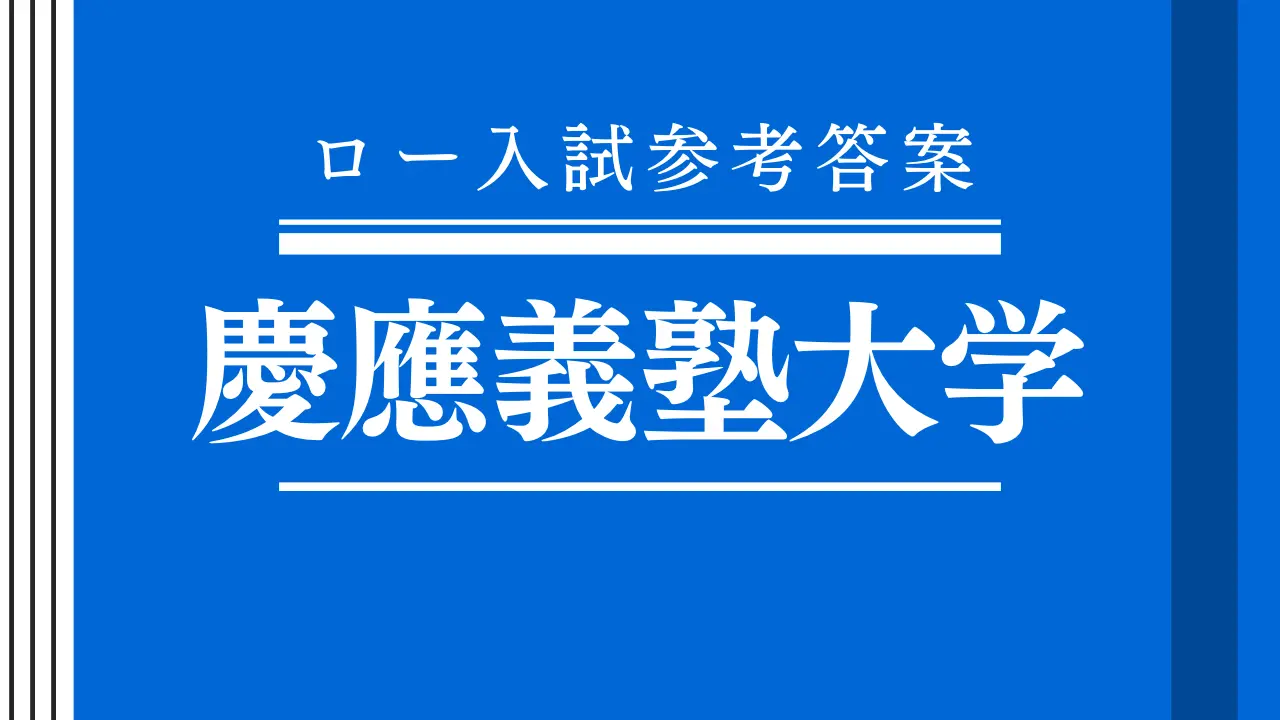
2021年 民事訴訟法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2021年 民事訴訟法
第1 問1
1. 前段
Xが当該消費貸借契約から1ヶ月後に、あらかじめ期限到来後の支払いを求める訴えは、将来給付の訴え(135条)に該当する。かかる訴えは認められるか。
⑴ そもそも、将来給付の訴えについて、原則として訴えの利益は認められないが、①将来給付を求める基礎となる資格があり、②「あらかじめその請求をする必要がある場合」(民訴法(以下略135条)に例外的に訴えの利益が認められる。
そして、135条の趣旨は原告が将来将来の強制執行のためにあらかじめ債務名義を取得する利益を優先させ、将来生じる不確定要素の立証及び起訴責任を被告に転嫁することにある。そのため、①は、㋐請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が既に存在し、その継続が予測され、㋑請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動としては、あらかじめ予測し得る事由に限られ、㋒請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止し得るという負担を債務者に課しても格別不当とはいえない場合にのみ認められると解するべきである。
②については、履行期が到来してもそのときに任意の履行が期待できないと判断されるような事情がある場合に認められると解するべきである。
⑵
ア 本問では、訴訟物たる消費貸借契約に基づく貸金返還請求権は、無利子2000万円という額が確定しており、それがYの弁済まで継続して存在することが予測される性質を持つ(㋐充足)ものの、請求権の成否について債務者Yに有利な事情としては、弁済、契約の解除、取消、相殺などあらかじめその予測がし得る事由に限られるといえる(㋑充足)。請求異議の訴えにおいても、弁済した上で既に弁済をしたとして受領書などの書面を証拠として提出するなど、書面の提出によって上記弁済などの事情の発生を簡単に証明することができるから前述の負担を債務者に課しても不当とは言えない(㋒充足)。
イ もっとも、XはYの子供のころのトラブルを想起して貸付について返済がなされるか否かを案じているのみであって、Yがすでに貸金返還債務の存在を争っているような事情もない。そのため、履行期到来後に任意の履行が期待できないとする事情もない。したがって、②の要件を充足しない。
⑶ したがって、かかる将来給付の訴えは、訴えの利益が認められず、不適法却下となる。
2. 後段
確認の利益の存否が問題となる。
⑴ 確認の訴えとは、その範囲が理論上無限定となるため、裁判所の司法資源を割くに値するかという観点から、原告の権利または法律的地位に危険・不安が存在し、その危険・不安を除去する方法として原告・被告間で法律関係の存否の判決をすることが有効・適切である場合に認められる。具体的には、対象選択の適切性、方法選択の適切性、即時確定の利益という観点からで判断する。
⑵ たしかに、本件の貸金債権は現在の法律関係であり、対象選択は適切といえる。また、将来給付の訴えが提起できない以上、確認の訴え以外の紛争解決形態がなく、方法選択も適切といえる。
しかし、Yが子供の頃からトラブルを引き起こす人間であったことが判明しているが、Yが本件の貸金債権の存否を否定していない以上、Yが本件契約の債務を履行しない可能性が高いとまでは到底いえない。そのため、原告の地位に危険や不安が生じているとはいえない。よって、即時確定の利益はきわめて小さい。
⑶ よって、即時確定の利益がなく、本件訴えは不適法却下となる。
第2 問2
1. Xは残額1500万円の給付を求める(以下、後訴)において、500万円の支払請求を棄却した前訴の既判力が作用しないか。
⑴ 既判力は、相殺の抗弁(114条2項)の成否を除き、「主文に包含するもの」、すなわち訴訟物たる権利関係の存否についてのみ生じる(114条1項)。そのため、判決理由中の判断には既判力は生じず、後訴裁判所で改めて審理判断される。
そして、原告が一部請求であることを明示していた場合は、訴訟物は債権の一部に限定されると解するべきである。なぜなら、一部であることが明示されていれば、残部請求がされないという被告の合理的期待は生じないからである。
⑵ 本問では、Yは2000万円の債権の一部として500万円の支払いを求める訴えを提起している。これは、一部請求の明示と見ることができるため、前訴の訴訟物は貸金債権のうち500万円の部分のみである。したがって、前訴の既判力は、貸金債権のうち500万円の不存在について生じている。他方、「2000万円は借りたのではなくもらったものだ」というYの主張が認められたことは、理由中の判断に過ぎないため、既判力は生じない。
⑶ したがって、Xが後訴で残部の1,500万円を請求することは既判力には抵触しない。
2. では、後訴で1,500万円を請求することは、信義則(2条)に反しないか。
⑴ 数量的一部請求の当否を判断するためには、債権全部について審理判断することが必要である。そのため、一部請求を全部または一部棄却する旨の判決は、債権全部について行われた心理判断の結果に基づくものである。したがって、上記の判決が確定した後に残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、実質的には前訴で認められなかった請求・主張の蒸し返しであり、前訴で紛争が解決したとの被告の合理的期待に反し、被告に二重の応訴の負担を強いるものとなる。
⑵ 本問では、後訴の訴訟物は前訴の訴訟物である貸金債権の残部である。そのため、前訴裁判所は貸金債権全部の存否について審理判断している。さらに、不当な蒸し返しではないとする特段の事情もない。
⑶ したがって、Yがかかる請求をすることは、信義則に反し、許されない
3. したがって、Xは残額の1,500万円を訴訟によって回収することはできない。
以上





