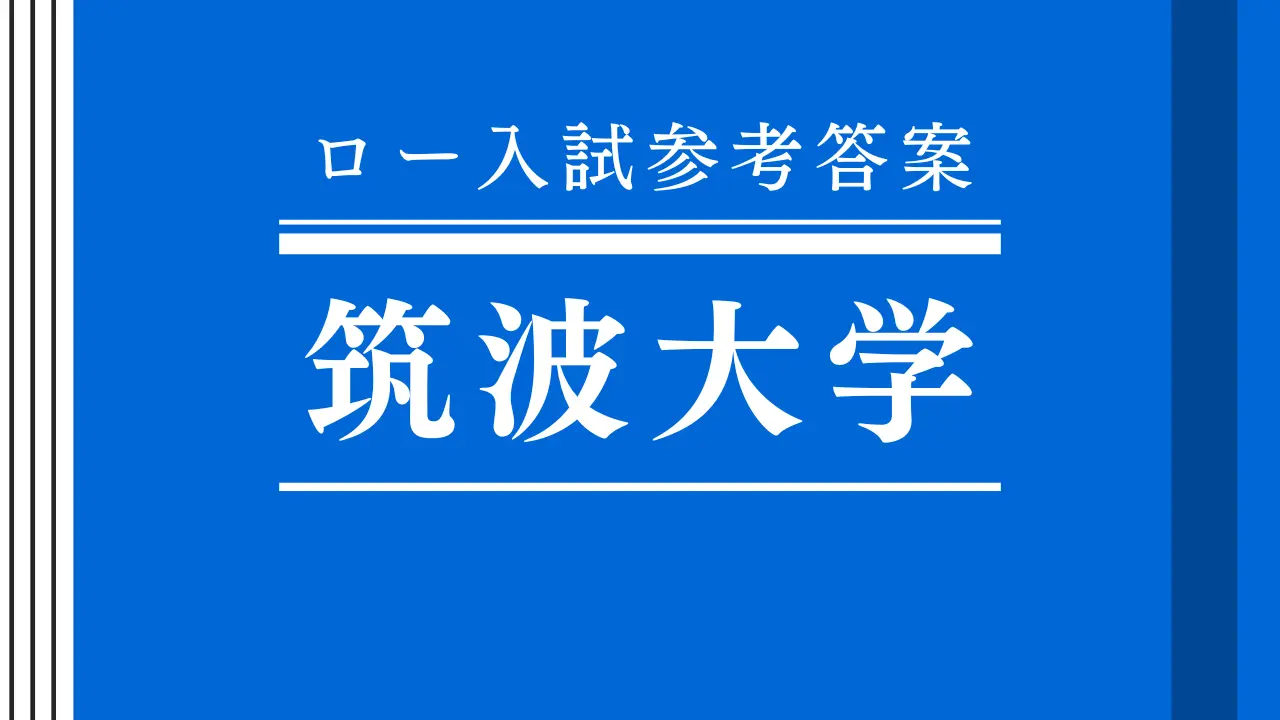
2022年 民事法 筑波大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/30/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
筑波大学法科大学院2022年 民事法
民法
第1問
設問(1)
1. Bは、Cに対し、所有権に基づく返還請求として乙の引渡しを求めている。かかる請求は、認められるか。
⑴ BとAは甲倉庫内にあるものすべてについて、譲渡担保を設定している旨の譲渡担保契約を締結している。右集合動産譲渡担保は、場所によって範囲が特定され、有効である。
⑵ もっとも、AとBとの間では、Aは鋼材を通常の営業の範囲内で処分することができる旨の約定がされている。本件契約①は、甲倉庫内の鋼材10本を代金100万円で売買する契約であるが、Cはそれ以前にも毎月Aから鋼材10本を購入しており、本件契約①はAの通常の営業の範囲内であるといえる。
したがって、本件契約①によりその目的物である鋼材は集合物から離脱し、Cに帰属したものといえる。Cは右鋼材を用い、乙を製作している。
2. 以上、乙はCに帰属し、Bの請求は認められない。
設問(2)
1. Eは、Dに対し、売買契約に基づく代金支払請求(民法(以下、略)555条)をしている。かかる請求は認められるか。
⑴ これをみるに、Aは、2022年8月3日、甲倉庫内の金属粉末15袋を代金20万円で売却したところ、同年9月30日、Aはかかる代金債権をEに代金15万円で譲渡した。そして、Aは、Dに対し、同月22日確定日付のある譲渡通知を行った。
⑵ もっとも、Dは、本件契約➁は解除されたため、Eの請求は認められないと主張している。かかる主張は、認められるか。
Aの売却した金属粉末には不純物を含む金属粉末が含まれており、債務の履行を怠ったといえる。そして、Dは、2022年8月25日に、同年9月5日までに不純物を含まない金属粉末15袋を引き渡すよう求め、「相当期間を定めてその履行の催告をし」(541条)た。その後、Aは同日まで引き渡さなかったため、Dは本件契約②の解除の意思表示をしたしたがって、右解除は有効である。
⑶ Dは、Eに対し、上記解除を対抗できるか。
ア 双務契約上の債権が譲渡された場合、譲受人の対抗要件具備時までに反対債務が未履行だったならば、その後に反対債務が債務不履行に陥り、解除権が発生する可能性はあったものといえる。
そこで、対抗要件具備時までに反対債務が未履行だった場合は、債務者は譲受人に対して解除を対抗できると解するのが相当である(468条1項)。
イ これをみるに、2022年8月22日に、Aによる譲渡通知がDのもとに届き、譲受人Eは同日債務者対抗要件を備えている。この時点でAのDに対する金属粉末の引渡債務は未履行である。
ウ よって、Dは、Eに対し、解除を対抗できる。
2. 以上、Eの請求は認められない。
第2問
1. AのEに対する請求
Aは、Eに対し、不法行為による損害賠償請求(709条)をすることができるか。
⑴ DはAに自転車を衝突させ、Aの生命・身体の安全という「法律上保護される利益」を「侵害」した。Aは自己から半年を経過した現在においても意識不明の状態にあり、Aは「損害」を被っている。Eは猛スピードで自転車を走行させ、結果Aとの衝突を避けられなかったのであるから、Eに「過失」がある。
⑵ Aの損害とEの侵害行為は因果関係を有するか。
ア 損害と侵害行為の間に相当因果関係が認められる場合に、侵害者はその責任を負いうる(416条参照)。
イ Aの現在の容体は2度にわたる頭部への衝撃が脳の疾患に作用したことに起因している。このうち2度目の衝撃は、救急車が急ブレーキをかけた際にAが救急車内の寝台から落下し、頭部を打ちつけたことによるものである。病者が救急車に乗せられ病院に搬送されることは当然に予定される事情であり、その過程で道を急ぐ救急車が急ハンドル・急ブレーキをすること自体稀ではないので、右介在事情の異常性は高くない。したがって、2度目の衝撃によるAの頭部へのダメージもEの侵害行為との相当因果関係の範囲内にあるというべきである。
ウ よって、Aの損害は全てEの侵害行為と因果関係を有する。
⑶ Aは路側帯から車道へと飛び出し,Eの自転車と衝突している。しかし、Aは事故時点で5歳であり、事理弁識能力を有しなかったと認められるので、A自身の過失は過失相殺(722条2項)の対象とならない。
⑷ Aが事故にあった際、DはAの手を放し、Aから目を離して電話をしている。Dの過失は過失相殺の対象とならないか。
ア 過失相殺の趣旨は損害の公平な分担にある。そこで、被害者と身分上、生活関係上一体をなす関係にある者の過失は、過失相殺において考慮可能である。
イ DはAの親ではないものの、Aを養育し、Aの未成年後見人にも就任している。したがって、AとDは身分上、生活関係上一体にある。Aが事故にあった際、DはAの手を放し、Aから目を離して電話をしていて、Dに過失があるといえる。
ウ よって、Dには過失があり、過失相殺の対象となる。
⑸ 以上、Aの、Eに対する請求は認められる。もっとも、Aの現在の容体はAの先天的な脳の疾患にも起因するものであるから、損害の公平な分担から賠償額は素因減額される。また、上記のとおりDの過失による過失相殺がされる。
2. AのGに対する請求
⑴ Eは16歳であり、責任無能力(712条)とはいえない。したがって、Aは714条1項に基づき、Gに対して損害賠償請求することはできない。
⑵ もっとも、Aは、Gに対し、一般的な監督義務違反を理由に損害賠償請求(709条)できないか。
ア 未成年者は一般に賠償の資力を有しないことから、親権者が714による責任を負わない場合一切責任を負わないとすると、被害者の救済にかける。
そこで,未成年者が責任能力を有する場合でも、親権者が一般的な監督義務を怠り、これと被害者の損害に因果関係がある場合は、親権者は不法行為責任を負うものと解する。
イ これをみるに、GはEの唯一の親権者である。Eは学校を無断で欠席したり、乱暴に自転車を運転したりするなど、すさんだ生活をしていた。Gは右Eの生活状態を認識し、一度だけ、Eに対して、しっかりとした生活を送り、交通ルールを守って自転車に乗るよう注意をしているが、それ以降現在に至るまで注意をしていない。したがって、Gは一般的な監督義務を果たしたとはいえない。
ウ そして、Gの義務違反とAの損害は因果関係を有する。
エ よって、AはGに対し、損害賠償請求できる。
⑶ 以上、AのGに対する請求は認められる。もっとも、賠償額はAの疾患により素因減額されるほか、Dの過失による過失相殺の対象となる。
3. DのEに対する請求
⑴ DはAの親権者ではないが、Aを養育している。もっとも、現時点でAは死亡しておらず、711条を類推適用することはできない。
⑵ Dは、Eに対し、自身の精神的苦痛を損害として、709条により損害賠償請求できないか。
ア 判例は、被害者の近親者が被害者の死亡にも等しい精神的苦痛を被った場合は、709条、710条に基づいて損害賠償請求をすることを認めている。そしてこの理は、被害者の法律上の近親者には当たらないものの、それと同等の生活関係を有する者にも当てはまる。
そこで、被害者と近親者と等しい密接な生活上の一体的関係を有する者が、被害者の死亡にも比肩する精神的苦痛を被った場合も、損害賠償請求が認められる。
イ Dは、Aの母Cの夫であり、Aと養子縁組はしていないものの、Cの死後も同居を続けて養育していた。DはAの未成年後見人に就任し、Aに対して愛情を注ぎ、AもDを実の父のように慕っていた。したがって、DはAの親権者にも等しい生活上の関係を有する。
そして、本件では、は意識不明の状態で、容体が回復する見込みはなく、DはAの死亡にも等しい精神的苦痛を被っている。
ウ よって、DのEに対する請求は認められる。
⑶ 以上、DのEに対する請求は認められる。もっとも、Dの過失による過失相殺の対象となる。
4. DのGに対する請求
Gは、自己の一般的な監督義務違反により、Aの容体へ責任を負っている。
よって,Dは、Gに対しても、自己の精神的苦痛を理由とする損害賠償請求をすることができる。ただし、D自身の過失による過失相殺の対象となる。
民事訴訟法
設問(1)
1. Yは、題意の主張をすることができるか。Yの主張が既判力(民事訴訟法(以下、略)114条1項)に抵触するかが問題となる。
既判力とは、前訴確定判決に与えられる後訴への通用性ないし拘束力をいう。その趣旨は、紛争の一回的解決という制度的要請にあり、正当化根拠は手続き保障充足に基づく自己責任にある。そして、既判力は、前訴既判力が後訴訴訟物と同一・矛盾・先決のいずれかの場合にあるときに作用する。なお、既判力は、「主文に包含するもの」(114条1項)すなわち、既判力の範囲に生じる。
⑴ これをみるに、前訴確定判決の既判力は、本件売買契約に基づく代金支払債務の存在に生じている。後訴の訴訟物も、本件売買契約に基づく代金支払債務であり、当事者はXとYであるから(115条1項1号)、既判力が作用する。
⑵ そして、既判力の基準時は、当事者に手続保障が与えられる口頭弁論終結時である。したがって、当事者は、前訴口頭弁論終結時点以前の事由に基づく主張をすることができない。
⑶ 本件では、たしかに、前訴では、売買代金の弁済の有無のみが争点であったところ、無効の主張は、Yの本件絵画の所有権の不存在ないし返還義務の存在をも内方する主張で、弁済の主張よりもYの不利となる。したがって、前訴でYが主張しかなったのには、一定の合理性がある。
しかし、前訴訴訟物たる本件売買契約が虚偽表示により初めから無効であったとの主張は、訴訟物たる権利の発生原因に内在する瑕疵に基づく主張である。右主張を認めると、前訴勝訴当事者であるXの地位が無に帰し、紛争の蒸し返しを認めることになる。前訴口頭弁論終結時点以前の事由に基づく主張にあたる。
2. よって、Yの主張は既判力に抵触し、許されない。
設問(2)
1. Yは題意の主張をすることができるか。Yの主張が既判力に抵触するかが問題となる。
2. 前訴の口頭弁論終結後も、解除原因たる債務不履行が継続している場合は解除権は基準時以降も継続的に生じている事由に基づく権利といえ、その行使を認めても前訴勝訴当時者Xの地位を無に帰すものといえず、紛争の蒸し返しにはあたらない。
3. よって、Yの主張は既判力に抵触せず、許される。
以上





