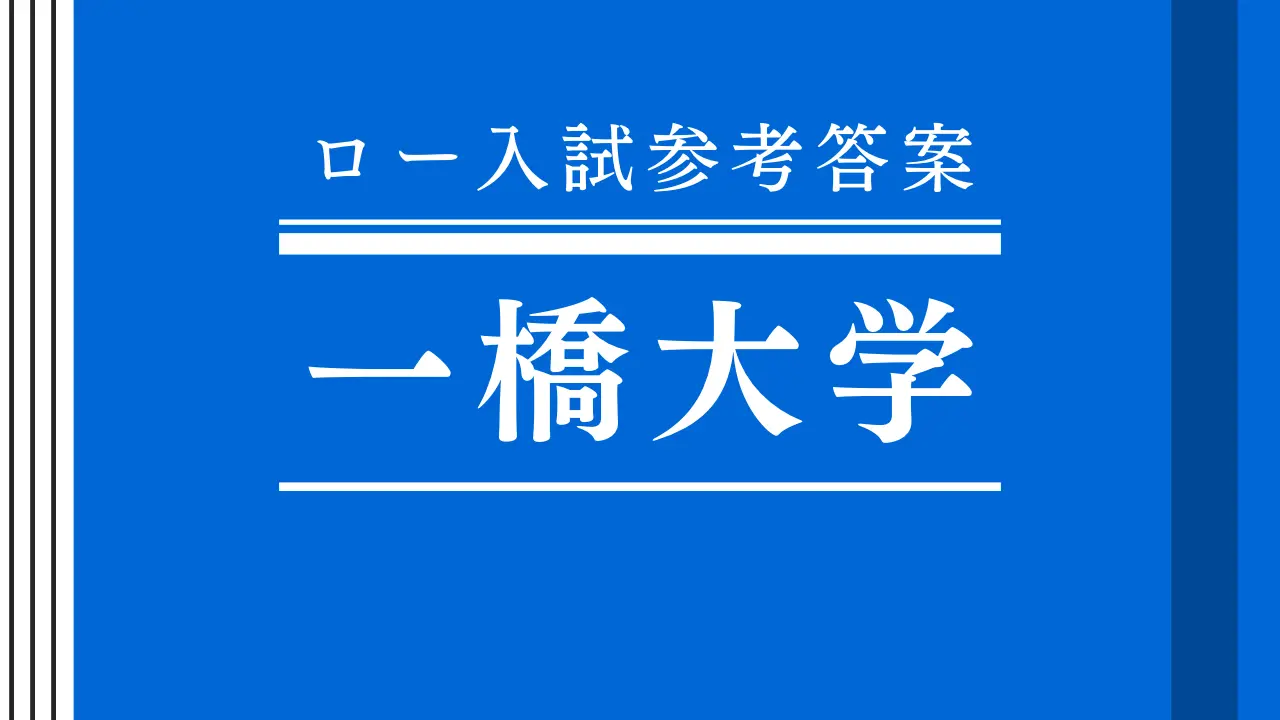
2021年 民事系/民法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2021年 民事系/民法
第1問(1)
1. まず、民法121条、121条の2第1項(以下法名略)によれば、CはAに対し、売買代金の返還を請求できる。
2. 次に、甲建物は滅失しているところ、AはCに対し、甲建物の返還に代わる時価の支払請求(415条1項本文)をすることができるか。
⑴ 121条の2第2項によれば、債務の履行として給付を受けた者の返還義務が現存利益の限度に減縮されるのは、給付が無効な無償行為に基づく場合に限られている。従って売買契約が無効となった場合、当事者は給付を受けた利益の全額を返還するべきである。
そして、給付の目的物が滅失し、給付を受けた者がその代位物を取得している場合は、給付された物の時価でなく代位物の返還によるべきであると考える。
⑵ もっとも、代位物は給付された物と経済的に必ずしも等価値でない。例えば、本件のように代位物が債権の場合は、その行使に実質的な負担があり、同額の金銭と経済的には等価ではない。従って、完全な原状回復を徹底するならば、返還に代わる時価の支払いによるべきとの批判が考えられる。
⑶ しかし、仮に契約が始めから締結されなかった場合、目的物が給付者の下で滅失し、代位物に転化していたはずである。従って、代位物の取得による実質的経済的な差損も、本来給付者が負うべき負担である。そこで、契約無効の遡及効により、右状態に回復させるのが当事者の衡平の見地からみて妥当というべきである。
⑷ 本件では、甲建物は第三者の放火により滅失し、Cは第三者に対する不法行為(709条)による損害賠償請求権を取得する。従ってCは右請求権をAに返還するべきである。
⑸ よってAはCに対し、甲建物の時価の支払請求はできず、上記請求権の譲渡を請求できるにとどまる。
第1問(2)
1. Cは、本件契約の錯誤取消し(95条1項2号)を主張すると考えられる。
⑴ 甲建物はBの設計によるものでなく、Cは甲建物がBの設計によるものと誤信していたからCには「錯誤」(同項柱書)あった。そして、右錯誤がなければ、Cも甲建物を買うことはなかったといえ、錯誤は「重要」である。また、甲建物がBの設計であることに基づいてCは購入を決め、代金額等も決定したと考えられることから、錯誤は「法律行為の基礎とした事情について」(同項2号)の錯誤といえる。さらに、CはAの、甲建物はBが設計したとの説明を受けてこれを購入したのだから、「法律行為の基礎とされていることが表示」(同条2項)されていたといえる。
⑵ そして、仮にCが「重大な過失」(同条3項柱書)により錯誤に陥っていたとしても、Aも「同一の錯誤」(同項2号)に陥っていたといえるので、Cの主張を妨げない。
⑶ よって、Cの主張は認められる。
2. では、契約の清算はどのようにされるか。
⑴ 民法121条、121条の2第1項によれば、CはAに対し、売買代金の返還を請求できる。
⑵ また、詐欺取消しの場合と同様、AはCに対し、甲建物の時価の支払請求はできず、上記請求権の譲渡を請求できると解するべきである。
ア この点、詐欺の場合と比し、取消権者の相手方の帰責性が小さい錯誤取消しの場合は、代位物でなく時価全額の返還が認められるべきとの反論が考えられる。
イ しかし、原状回復義務は、121条の2第2項、3項のような明文のある場合は格別、原則として当時者の帰責性などに左右されるべき性質のものでなく、画一的に元あった状態の復元が徹底されるべきである。従って取消事由が何であっても、代位物がある場合はその返還によるべきである。
ウ 従って、AはCに対し上記請求ができる。
第2問(1)
1. まず、Bは、甲は自己が所有していると反論して、Dの請求を拒むことが考えられる。
⑴ これをみるに、BはAより甲を代金1500万円で買い受けている。そのため、Bの反論が認められると思える。
⑵ しかし、これに対し、Dは、自己がCより甲を取得し、その登記を備えた以上、177条の適用によりBは確定的に甲の所有権を喪失していると再反論すると考えられる。
ア 177条の趣旨は、不動産をめぐる紛争を登記の有無により画一的に解決し、不測の損害の発生を防ぐ点にある。そこで、「第三者」(177条)とは、物権変動の当事者またはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者をいうと考える。
イ 本件では、まずCはAB間の売買の当事者及びその包括承継人ではない。また、CはAより甲を贈与されている。この点、CがAB間の売買につき善意だった場合、Cが登記を備えた時点で、Bは確定的に甲の所有権を喪失するので、Dは当然Cから甲の完全な所有権を取得できる(絶対的構成)。
ウ しかし、CはAが債務超過に陥り、金策に困っている窮状を知りながらこれを譲り受けている。そのため、CがAB間売買について悪意だった場合、Cは自由競争の範囲を逸脱する背信的悪意者に当たり、「第三者」たり得ない。
エ 仮にCが背信的悪意者に当たる場合、Dはその転得者にあたる。このような場合、BD間に177条の適用があるか。
(ア) この点、背信的悪意者であっても完全な無権利者ではなく、登記の欠缺を主張できないに過ぎない。また信義則違反の判断は個別に行うべきである。従って、その転得者は、自らが背信的悪意者に当たる場合でない限り、「第三者」に当たる(相対的適用)。
(イ) 本件でも、D自身が背信的悪意者に当たらない限り、Dは177条で保護される。
オ よって、CとDが共に、AB間の売買の背信的悪意者に当たらない限り、Dの再反論は認められる。
(1). 以上より、CとDが共に、AB間の売買の背信的悪意者に当たらない限り、Bの反論は認められない。
2. 次に、1の反論が認められない場合、BはAC間贈与の詐害行為取消し(424条1項本文、424条の5第1号)を反論として、Dの請求を拒むことが考えられる。
⑴ BはAに対し、甲の売買の債務不履行による損害賠償請求権を有しているので、「債権者」(424条1項本文)に当たり、Aは「債務者」にあたる。そして、Aは自己が債務超過にあることを認識しつつ、Cに甲を贈与し、「害することを知ってした」といえる。また、AC間贈与は「財産権を目的」とする行為(同条2項)である。さらに、AB間売買は、AC間贈与より前に行われ、BのAに対する賠償請求権は「前の原因」(同条3項)であるし、「強制執行により実現」(同条4項)できる。加えて、CはAの債務超過を認識し、Aの一般債権者を「害することを」知っていた(同条1項ただし書)といえる。
⑵ しかし、Dに転得によりBを含むAの一般債権者を害することの認識があったかは不明である。認識があった場合は「害することを知っていた」(424条の5第1号)といえる。
⑶ よって、Dに転得によりBを含むAの一般債権者を害することの認識があった場合には、Bの反論は認められる。
3. 最後に、1の反論が認めらない場合、Bは留置権(295条1項)の成立を主張して、Dの請求を拒むことが考えられる。
⑴ BはAに対し、債務不履行による損害賠償請求権という債権を取得する。
⑵ では、Bの上記債権は甲に「関して生じた債権」(295条1項本文)といえるか。
ア 留置権の趣旨は、物の占有を債権者のもとに留めることで、債務者に弁済を促すことにある。そこで、債権が物に関して生じたといえるためには、留置権の成立時点で、物の引渡権者と債務者が一致する必要がある。
イ 本件で甲の引渡しを請求しているのはDである一方、賠償請求権の債務者はAである。
ウ よって、Bの上記債権は甲に「関して生じた債権」(295条1項本文)といえない。
⑶ したがって、 Bの反論は認められない。
4. 以上より、上記一定の場合のみ、BはDの請求を拒める。
第2問(2)
1. BはAB間の売買契約を解除して、解除に基づく原状回復請求(545条1項)として500万円の返還を請求できる。
⑴ 上記のとおり、CDが共にAB売買の背信的悪意者でない限り、AのBに対する甲引渡債務は「履行が不能」(542条1項1号)である。これは、Bの「責めに帰すべき事由」(543条)によるものではない。よって、Bは契約解除できる。
⑵ 従って、BはAに500万円の返還を請求できる(545条1項本文)。
2. また、Bは履行不能による損害賠償請求として、Aに500万円の支払いを請求できる。
上記のとおり、CDが共にAB売買の背信的悪意者でない限り、AのBに対する甲引渡債務は「履行が不能」(415条1項本文)である。そして、Bが支払った500万円は「これによって生じた損害」である。AはBへの売り渡しの事実を認識しつつ、Cへ甲を贈与しており、履行不能は、Aの「責めに帰することのできない事由」(同項ただし書)によらない。
3. もっとも、Aは無資力であり上記請求が認められても500万円を回収できる可能性は低い。そこで、BはAC間の贈与について詐害行為取消請求をし、甲の価額のうち500万円を自己に支払うようCに請求できないか。
⑴ DがBを「害すること」(424条の5第1号)を知らなかった場合は、Cのみが「害すること」(424条1項ただし書)を知っているといえ、甲の返還は「困難」(424条の6第1項後段)となるから、BはCに対し、Aにその価額を償還をするよう請求できる。さらに、BはCに対し、500万円を直接自己へ支払うよう請求できる(424条の9第2項、1項)。
⑵ よって、上記の場合には請求できる。
4. BはAに対して、債権侵害の不法行為による損害賠償(709条)を請求できるか。
⑴ AC間の贈与及びCD間の甲の譲渡により、Bは甲を取得できなくなり、Bの「権利」は「侵害」されている。そして、これによって、BにはAに支払った代金500万円分の「損害」が生じており因果関係も認められる。また、Aは、Bとの売買契約後に甲をCに譲渡しており、Bの権利を害することについて悪意である。
⑵ よって、500万円の賠償請求が認められる。
以上





