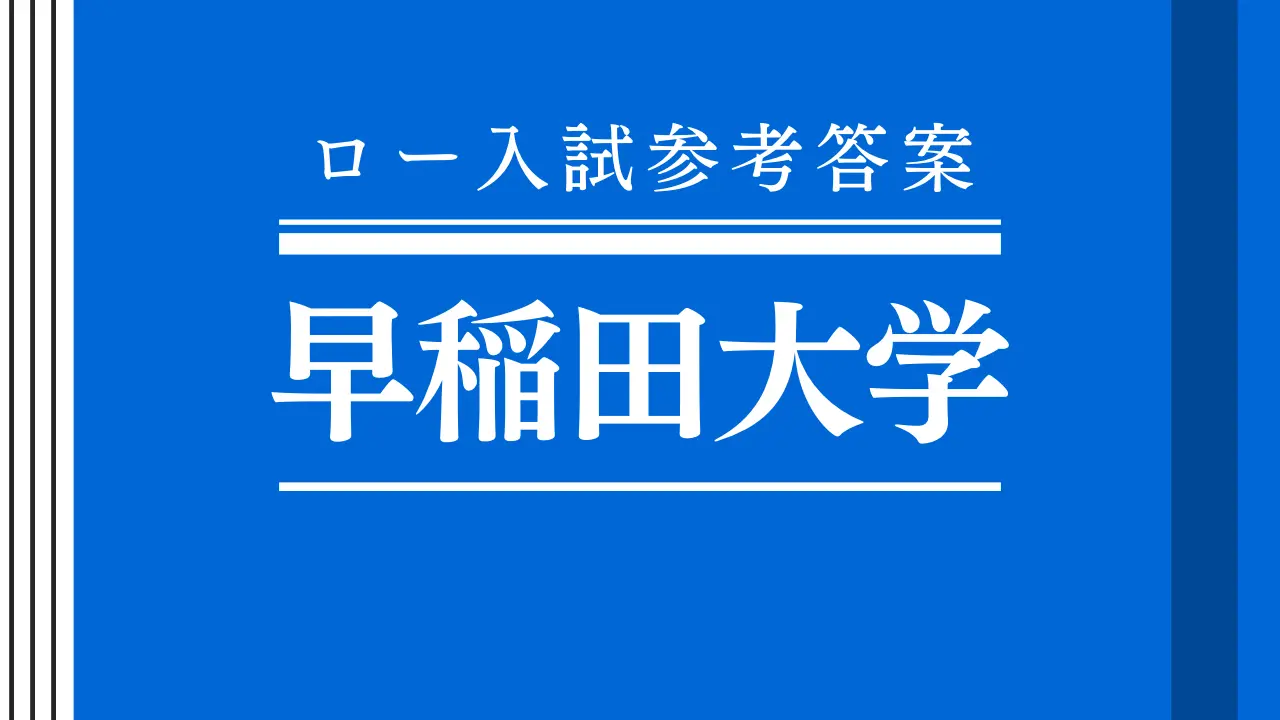
2023年 憲法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2023年 憲法
作成:The Law School Times編集部
憲法
1. 憲法(以下、法名省略)29条1項について
⑴ 私は、市長の指定処分が29条1項の財産権を不当に制約するものとして違憲であると主張し指定処分の取消を求めるようXに対して助言する。
ア 29条1項は、私有財産制のみならず、個人が現に有する具体的な財産上の権利も財産権として保障しており、かかる「財産権の内容は・・・法律で・・・定め」られる(29条2項)ものである。Xは、特定遊歩地域に含まれるXの所有地について、民法206条に基づき自由に「使用」するという具体的な財産権を有していた。
イ 本件で問題となっているA市観光促進条例(以下、「本件条例」という)は、3条本文. において2条に基づいて指定を受けた特定遊歩地域に含まれる500㎡を超える土地の所有者、管理者は海岸線の水際から10mの土地を通行させることを義務付けている。当該条例は、特定遊歩地域については一般人の通行を甘受することを義務付け、Xが所有地を自由に使用する権利を妨げるものであるから、上記の財産権は制約されている。
ウ 条例によって財産権を制約すること自体が29条2項に反し違憲であると主張できないか。
29条1項が財産権を定め、同条2項が財産権の制限は法律によってなされることを定めている点で、条例によって財産権を制限することは29条2項に反すると主張することが考えられる。しかしながら、同項は、財産権それぞれの財産の性質に応じてその制約を加えることを許容しているのであり、それには地域の特性に応じた規制を実現することも必要であるといえる。したがって、憲法は、条例による財産権の制限も、法律に反しない限度においては許容していると解される(奈良県ため池事件参照)。本件条例は、特定の法律に反する内容のものとはいえない、かつ観光地であるA市の特性に応じて、同市の観光を促進するという目的を持つ(本件条例1条参照)ものであるので、条例による制約になじむと言え、上記の違憲主張は認められない。
エ 上記制約は正当化することができず違憲であると主張できないか。
(ア) 本件条例3条本文は、特定指定地域の財産権を制約するものであり、このような制約は正当化されえないため、当該規定は29条1項に反し、違憲であると主張することが考えられる。29条2項は同条1項に定める財産権の内容を「公共の福祉」に適合するように法律によって定めるとしており、本件条例による財産権の制約はこの「公共の福祉」の観点に適合するものといえるかが問題となる。
財産権は、私有財産制を敷く我が国において、私人の財産の自由を保障する観点から重要なものであるといえる。そして、その中でも、所有権は、物の使用収益を自由に行うことを実現するものであり、その重要性は高い。もっとも、財産権は、社会生活において、他人の権利や法益と衝突することもありうる。そのことから、前述したA市の反論のように財産権が「公共の福祉」の観点から、制約されることも、その制約の合理性が認められる場合には許容される。これらのことから、財産権に対する制約が29条2項にいう「公共の福祉」に適合するものであるか否かについては、当該規制の目的、必要性、内容、この制約によって制約される財産権の性質を勘案して、比較衡量されるべきである(証券法164条1項事件参照)。
(イ) 確かに、本件条例は、1条に定めるように、「A市の観光業を促進」することを目的としており、観光地においてその観光資源の活用は重要な問題であるから、かかる目的には一定の重要性が認められる。また、このような観光資源の活用は、個人が行うことは困難であり、これを地方公共団体であるA市が行うことに意義は認められる。そして、A市の観光地は海岸線の風光明媚に特長があることから、海岸線を遊歩することができなければ観光客が大幅に減ることが見込まれるため、A市の観光資源を活用するために、海岸線を観光客が遊歩することの便宜を図ることは、上記目的に適合するものである。さらに、特定指定地域についても500㎡を超える土地が対象となっており、規制対象が観光に与える影響の大きい土地に限られていること、また、土地のうち10mを一般人の通行に供することを義務付けてもそれは単なる一部分にすぎないことから、財産権に対する制約の程度は強くないとも思える。以上のようなことをもって、本件条例3条本文による制約が「公共の福祉」に適合しているとA市は主張することが想定される。
しかし、本件条例による制約の対象となる権利は、上記のように財産権の本質的な権利である。また、観光業の促進という目的は、あくまで同地域における興行に過ぎず、生命・身体のような法益に比肩するほどの重要性をもつものではない。そうであるにもかかわらず、上記のような財産権の本質的な部分を制約することは、目的との関係で是認することができない。また、本件条例第5条は、3条によって通行させる義務を負っている者が一般人の通行を妨げた場合に罰金を科すと定めている。このように、本件条例による制約は、通行させることを義務付け、その実現のために罰則を持って対応しており、規制の態様も強度が高いものであるといえる。これらのことから、このような財産権の制約は正当化されえない。
⑵ 以上より、本件条例3条本文による規制は、29条1項を不当に制約するものとして、違憲無効であり、無効な条例に基づく本件指定処分は、取り消されるべきである。
2. 29条3項について
⑴ 仮に本件条例が29条1項に適合するとしても、損失補償が必要な場面で損失補償についての規定を定めていないことが29条3項に反し違憲であると主張するようXに助言できないか。
⑵ 「補償」が必要なのは、財産権に対して特別の犠牲を課す場合である。そして、侵害行為が財産権に内在する社会的制約として受任すべき限度を超えて財産権の本質的内容を侵すほど強度なものと言える場合に、特別の犠牲が認められる。具体的には、規制目的、侵害行為の個別性、侵害の強度、財産権の性質等を考慮して判断する。
⑶ 確かに、本件条例の目的は、観光業の促進という積極目的であり、受任限度を超えているとも思える。しかし、本件条例は、特定指定地域に指定された土地の所有者・管理者に対して、一般人に海岸線沿いの10mの通行に供させることを義務付けるものであり、その制約は特定人を対象としているといえる。また、対象となる財産は建設業を営むXにとって生存に不可欠な財産であり、これを一般人の通行に供することは、その所有権の行使を著しく困難にするものである。また、かかる制約には期間が定められておらず、条例が廃止されない限り永久に制約を受け続けることとなる。以上時から、本件制約は財産権に内在する社会的制約として受任すべき限度を超えて財産権の本質的内容を侵すほど強度なものといえ、特別の犠牲が認められる。よって、損失補償は必要である。
⑷ 本件条例には損失補償規定が定められていないため、該条例全体が違憲無効となるようにも思われる。しかしながら、条例が特別の犠牲を課すものであった場合、その補償の額は、自ずと決定されるものであり、具体的な算定基準等を法令で別途定めなくとも、損失の補償を行うことは可能である。このことから、損失補償規定が存在しない場合であっても、29条3項を根拠に、損失補償を求めることは可能である。このことから、損失補償規定が定められていないことは29条3項に反し、当該法令が違憲であることを意味しない。本件条例も、損失補償規定は定められていないが、これを否定する規定が存在するものでもない。したがって、損失補償規定の不存在を理由に本件条例が違憲無効とはならない。
⑸ 以上より、本件条例は29条3項を理由に違憲となるものではない。よって、かかる主張をすることをXに助言すべきではない。
以上





