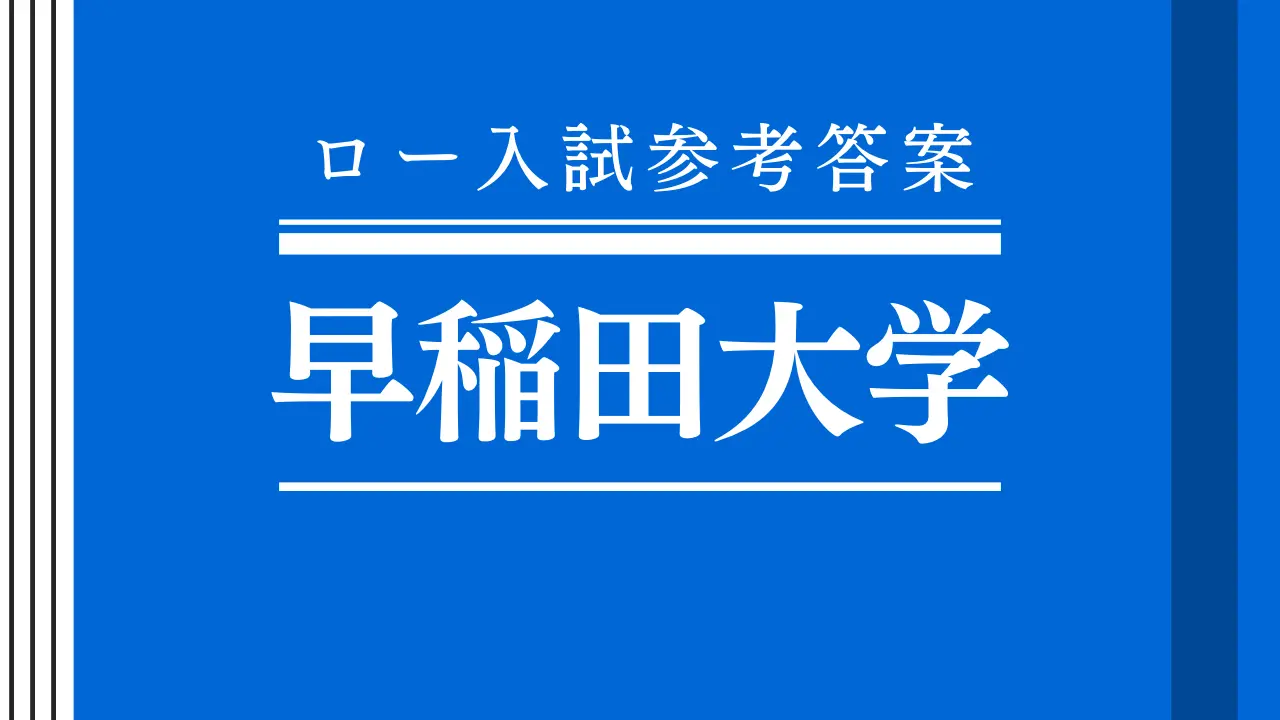
2025年 民法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2025年 民法
問題1
設問1
1. Dは、Cに対して、所有権(206条)に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求をしている。その要件は、Dが土地を所有していることと、Cが占有権原なく、土地上に建物を所有して土地を占有していることである。
2. Aは、1980年4月1日、甲土地を所有していた。そして、Aは、2024年8月1日、Dに対して甲土地を売却しており(555条)、これにより甲土地の所有権は移転している(176条)。もっとも、Cの前主たるB又はCが甲土地を時効取得(162条)していたとすれば、Dは所有権を取得しない可能性がある。そこで、BないしCが甲土地を時効取得しているか、及び取得時期が問題となる。
3. ⑴Bは、1981年2月1日及び、2001年2月1日経過時に甲土地を占有していたから、この間の占有が推定され(186条2項)、これを覆す事情もない。
⑵「所有の意思」があるかは、外形的客観的に決せられるべきなので、占有取得の原因や占有の態様などの客観的性質から判断する。甲土地の「占有者」であるBは、「所有の意思」を有していると推定される(186条1項)。また、Bは、1981年2月1日より乙建物での居住を開始するとともに、以後、甲土地の固定資産税を支払っており他主占有事情は見当たらない。もっとも、Bは、Aから甲土地を無償で借り受けたのであり、その性質上占有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得している。他主占有権原に基づく占有であることから、Bに所有の意思があるとの推定は覆る。
⑶よって、Bに「所有の意思」は認められず、これにより甲土地を時効取得することはない。
4. ⑴では、Cが時効取得するか。
⑵まず、「被相続人」たるBに配偶者や子はなく「887条の規定により相続人となるべき者がない場合」にあたり、Bの両親はすでに死亡しているから889条1項1号にあたる者もいないため、Bの妹であるCは、Bの相続人となる(889条1項2号)。他に相続人がいないことから、Bの死亡により(882条)、CはBを包括承継している。
⑶占有開始の起算点は、事実的支配の開始時点をいうと解する。そのため、相続人が事実的支配を開始するまで占有は認められない。
Bの死亡した2001年3月1日時点にはCには観念的占有しか認められない。乙建物を取り壊して丙建物を新築し、丙建物に入居した2002年5月1日時点で事実的支配が認められ、同日から20年経過した時点である2022年5月1日経過時の占有も認められるから、その間の占有が推定され、これを覆す事情はないから、2002年5月1日を起算点とした20年間の甲土地の占有が認められる。
⑷ア 前主Bの占有は他主占有であるから、合わせて主張すれば、「所有の意思」は認められない。そこで、Cは、独自の占有を主張することになる(187条1項)。
イ ここで、文言上特定承継に限定されていないし、そう限定すべき理由もないから187条1項の「承継」には包括承継が含まれると解する。そのため、Cは自己の占有のみを主張して、時効完成を主張し得る。
相続は包括的承継(896条本文)ゆえ、占有の性質も承継するので、原則としてCの占有は他主占有であり、「所有の意思」を有しない。
ここで、相続が185条にいう「新たな権原」に当たれば、占有は自主占有に転換されるが、相続は包括的承継なので、原則として占有の性質を変更させる「新たな権原」には当たらない。もっとも、相続人の事実的支配が外形的客観的にみて相続人独自の「所有の意思」に基づくものといえるならば、相手方は時効障害の措置をとれるから、このような場合、相続が「新たな権原」に当たると解する。
Cは、2002年5月1日、乙建物を取り壊して丙建物を新築し、丙建物に入居している。また、Cは、それ以降、丙建物に継続して居住するとともに、甲土地の固定資産税を支払っている。これらの行為は、所有者でなければ通常取らない行動であり、Aとしては、かかるCの行動に異議を唱えるなどの時効障害の措置を講じることができた。よって特段の事情が認められ、相続が「新たな権原」に当たる。
よって、Cの占有は自主占有に転換しており、「所有の意思」があるといえる。
⑸「平穏」・「公然」は186条1項により推定され、これを覆す事情もない。
⑹以上より、援用の意思表示(145条)により、2002年5月1日、Cは甲土地を時効取得する。
5. ⑴もっとも、Dが「第三者」(177条)に当たるならば、登記が必要である。では、Dは第三者にあたるか。
⑵取得時効は原始取得であり、その効果は遡及効(144条)であるから、時効完成後の譲受人は、無権利者からの譲受人といえる。もっとも、実質的には、時効完成時に物権変動を観念できるから、占有者と譲受人は、譲渡人を起点とした二重譲渡類似の関係に立つといえる。また、占有者は、時効完成後は登記を備えられるのだから速やかに登記を具備すべきであり、これを怠ったときにはその不利益を甘受すべきである。そこで、譲受人は、原則として、占有者との関係で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」にあたり、登記なくして対抗できないと解する。
Dは、時効完成後の2024年7月1日にAから甲土地を買い受けているから、原則として「第三者」にあたる。
もっとも、自由競争の枠内になく、登記欠缺を主張することが信義則(1条2項)に反する背信的悪意者は、「第三者」に当たらない。背信的悪意者というには、①悪意②背信性が認められる必要がある。①悪意とは、物権変動の事実を知っていたことを意味するのが原則である。もっとも、物権変動の原因が時効取得のときには、時効取得の要件を正確に把握することは極めて困難なので、例外的に①悪意の対象は、多年に渡って占有していることをいうと解する。
⑶Dは、2005年6月から甲土地の隣地に居住しており、Cが多年に渡って甲土地を占有していることにつき悪意である。また、2024年8月1日、Dは、Cに対し、甲土地を時価の約2倍である3000万円で買い取るように迫っており、長年DはCと不仲であることから、不当な高値でCに売却する意思のもとに、Cの生活の本拠である甲土地を買い受けたとものと推認され、背信性も認められる。
⑷よって、Dは「第三者」に当たらず、Cは、登記なくしてAの所有権喪失を対抗できる。
6. よって、Dの請求は認められない。
設問2
1. Eは、Cに対して、所有権(206条)に基づく返還請求権としての建物収去土地明渡請求をしている。
2. Eは、2024年9月1日、Dから甲土地を買い受けている。ここで、Dは背信的悪意者であるものの、背信的悪意者は信義則(1条2項)上、権利を対抗できないだけであって、物権を一応有効に取得しているから、無権利者ではない。Dは不完全ながらもAから一応有効に甲土地の所有権を取得しているから、Eに甲土地の所有権は移転しているといえる。もっとも、Cの甲土地の時効取得によるAの所有権の喪失をEに対して対抗できるならば、Aは所有権を喪失しているから、Eは所有家を取得できない。
3. ここで、時効完成後の譲受人であるEは、原則として「第三者」に当たる。また、Eは、新たにこの町に引っ越してきた者であり、Cが丙建物に長年居住してきたことを知らないから、背信的悪意者に当たることはない。更に、信的悪意者たるDの地位を承継しているからEも背信的悪意者であるとも思われるが、信義則違反は個別的に判断すべきであるから、背信的悪意者たる地位は承継しない。
よって、Eは「第三者」にあたり、Cは、Eに対して、甲土地の時効取得によるAの所有権喪失を登記なくして対抗できない。
以上より、Eの請求は認められない。
問題2
設問1
1. CはBに対して、消費貸借契約(587条)に基づく貸金返還請求として、3000万円の支払を請求する。
2. Aは2022年5月20日、Bに対して弁済期を2024年5月20日として3000万円を貸し付けており、
弁済が譲渡前であり、既に消滅した債権の一部分は譲り渡すことはできず、本件譲渡は1200万円部分で有効であり、その限度でCは請求権を有する。
Cからの反論として、履行拒絶の抗弁権がある。譲受人が悪意又は重過失の場合には、債務者はこれに対抗できる(466条3項)。本件では、Eは「重大な過失がなかった」とされており、「重大な過失によって知らなかった譲受人」にあたる。よって、履行拒絶の抗弁権が認められるといえよう。
また、債務者対抗要件(467条1項)を備える前であることを認定し、履行拒絶が可能であるとすべきである。
さらに、468条1項によれば、通知到来の対抗要件具備前の弁済による債務消滅事由をもって、1800万円分の債務消滅を対抗でき、その部分の請求が認められない旨を主張することができる。467条1項によれば全額の履行を拒めるため、468条1項による場合を主張する実益がないとも思えるが、譲渡自体は債務者の側から認めた上で未弁済部分に債務を限定するという場合があるほか、問題文中の事実に即した論述として、468条1項をも述べるべきといえよう。
設問2
まず、本件譲渡は弁済がなされる前になされており、Cは3000万円全額について請求権を取得している。
Cからの反論として、履行拒絶の抗弁権がある。譲受人が悪意又は重過失の場合には、債務者はこれに対抗できる(466条3項)。本件では、 Eは「知らされていた」とされており、悪意の「譲受人」にあたる。よって、履行拒絶の抗弁権が認められるといえよう。
また、債務者対抗要件(467条1項)を備える前であることを認定し、履行拒絶が可能であるとすべきである。
さらに、468条1項によれば、通知到達の対抗要件具備後の弁済による債務消滅事由をもっては、1800万円分の債務消滅を対抗できず、その部分の請求が認められない旨を主張することができない。
以上





