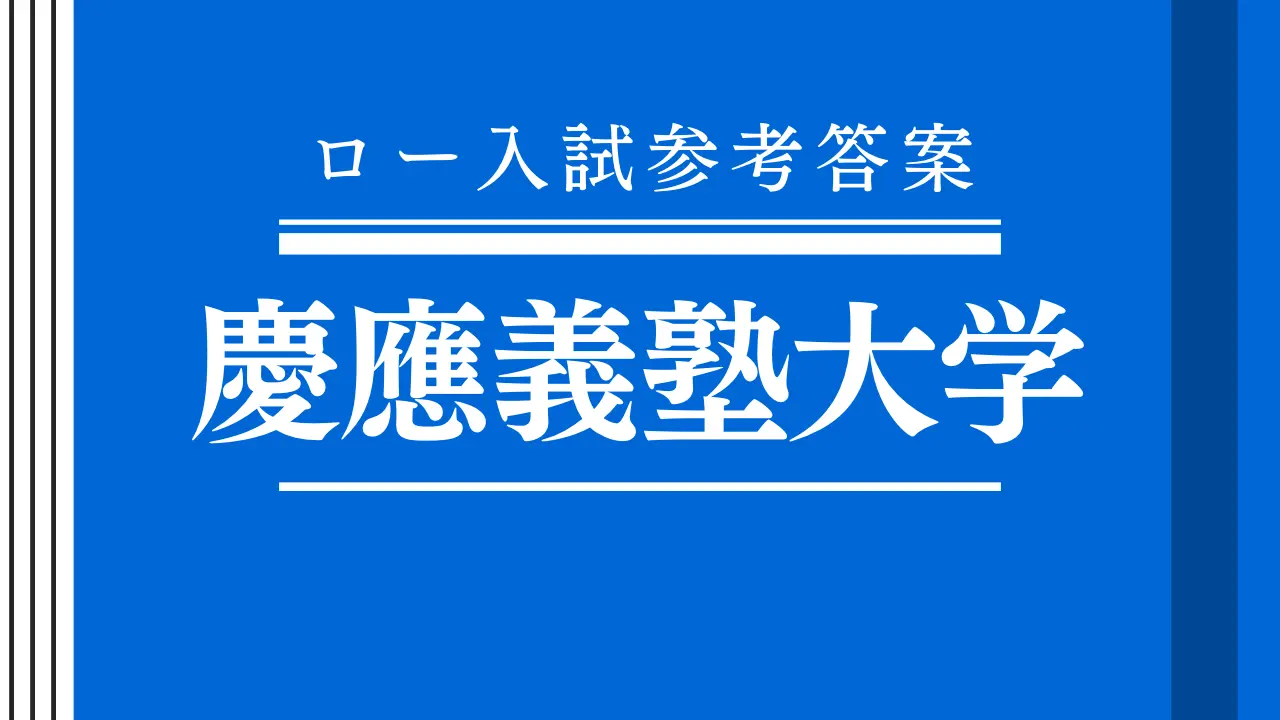
2023年 民事訴訟法 慶應義塾大学法科大学院【ロー入試参考答案
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
慶應義塾大学法科大学院2023年 民事訴訟法
第1 問1
1. 裁判所は、Xの請求を認容する判決をすべきである。
⑴ 本件では、口頭弁論終結の段階でYによる弁済の事実について真偽不明のため、証明責任に従ってかかる事実の有無が判断されることになる。そして、証明責任とは、裁判所がある要件事実について真偽不明に陥った場合に、判決においてその事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生または不発生が認められないことになる一方当事者の不利益をいう。したがって、証明責任の分配は、当該当事者にとって当該法規が有利かどうかによって判断されると考える。
これをみるに、本件で問題となる弁済の主張は、Xの消費貸借契約に基づく貸金返還請求権を消滅させる効果を有する抗弁である。そのため、弁済の主張が認められる場合にはYに有利な法律効果が発生することになるから、弁済についてはYが証明責任を負う。
したがって、本件では、弁済について真偽不明に陥っているから、かかる点については、Yが不利益を負うこととなり、裁判所は弁済についてはなかったものとして判決をすべきである。
⑵ 以上より、本件で弁済の事実は認められないこととなる。そして、Yは、Xから1億円の融資を受けたことについては自白しており、裁判所はかかる事実を判決の基礎とする必要がある(弁論主義第2テーゼ)。また、Yは弁済の主張以外の主張は行っていない。
したがって、本件で、裁判所は、Xの請求を認容する判決をすべきである。
第2 問2
1. Yは控訴することができるか。Yに控訴の利益が認められるかが問題となる。
⑴ 控訴は第1審判決に対する不服申し立てであるから、控訴が認められるためには、控訴の利益が認められる必要がある。
この点、処分権主義の下、自らの責任で審判対象を設定し全部勝訴した者については、上訴による不服申し立てを認める必要はなく自己責任をといえる。また、基準として明確である必要がある。
したがって、申立ての内容と判決を比較し、質的、量的に後者が不利である場合に限り控訴の利益が認められると考える。もっとも、全部勝訴であっても、後訴で自己責任を問うことが不当であると認められる場合には、例外的に後訴の利益を認めるべきである。
⑵ これをみるに、第1審において、YはXの請求を棄却する判決を得ており、全部勝訴しているから控訴の利益が認められないとも思える。しかし、第1審によるYの勝訴は、Yによる相殺の抗弁を認められた結果であるところ、相殺の抗弁については、既判力が生じるから(114条2項)、Yは後訴で同一債権について請求をすることができなくなってしまう。しかし、これは自己の申し立てによるものでなく自己責任を問うことは不当である。したがって、かかる場合には、例外的に控訴の利益を認め、相殺の抗弁によらずに勝訴する機会を与えるべきである。
⑶ 以上より、本件では、Yに控訴の利益が認められるから、Yは控訴することができる。
以上





