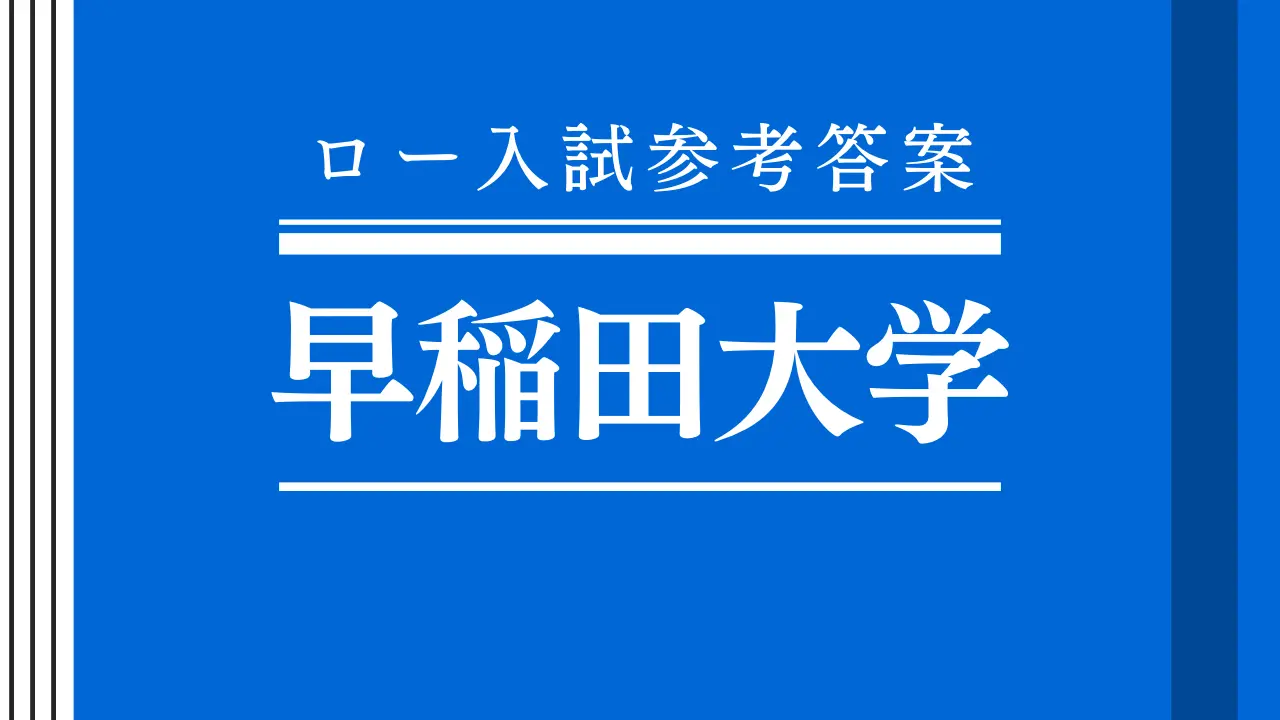
2022年 憲法 早稲田大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
早稲田大学法科大学院2022年 憲法
第1 違憲側の主張について
1. 特定秘密保護法(以下、「法」という)23条2項を本件のXに適用することは、以下に述べるように憲法(以下、省略)21条1項の自由を不当に制約するものとして、違憲である。
⑴ XはA県議会議員として、21条1項の表現の自由として、議員の発言の自由が保障される。そして、本件で問題となった県議会の委員会でのXのプログラムに関する発言(以下、「本件発言」という)も、議員の発言として、上記自由に服することは明らかである。そして、本件発言を行ったことを理由にXを刑事処罰することは、Xの上記の自由を制約することにほかならない。
⑵ 地方議員は、当該地域の住民に選挙で選ばれ、議会やその他の場所での発言を通して、これらの住民の生活等の向上のために活動する責務を有する。議員の発言は、表現活動としてのみならず、住民自治の原則を実現するためにも欠かせないものであるといえる。このことから、議員の発言の自由は、非常に重要な権利である。
⑶ また、上記制約は、当該プログラムに関する情報という表現の内容に着目した制約であり、特定の表現を市場から締め出すものであるからその合憲性は厳格に審査する必要がある。
⑷ これらのことから、憲法上の権利は「公共の福祉」(12条、13条)により制約されることはあるとはいえども、上記のように重要な権利に対する制約が正当化されるためには、当該表現を行うことで失われる公益が、当該発言を行うことで得られる利益を優越することが明らかであるといえなければならないと解される。
⑸ 本件発言は、A県内にある核燃料処理施設(以下、「本件施設」という)の安全性に関わるものであり、これを公開することでプログラムの内容が漏れると不正侵入など、重大なサイバー・テロを引き起こしかねない等の同施設のセキュリティ上の問題が発生しうる。しかしながら、本件発言は、本件施設を稼働させる上できわめて重要な制御用コンピュータ・プログラムに、深刻な事故を引き起こしかねない欠陥がありA県住民の生命・健康に重大な被害が生じる可能性があるという「確度の高い情報」をXが、本件施設と類似のプログラムの作成に関わったことのある専門家から聞いたためになされたものであり、A県議であるXが、生命身体という最も重要な法益を保護するために行ったものである。したがって、本件発言によって失われた公益は、これによって得られる利益に明らかに優越するとはいえない
2. 以上より、本件発言は社会通念に逸脱するものとはいえず、法23条2項における違法性を備えていないので、Xを処罰することは違憲である。
第2 合憲側の主張について
1. Xを法23条2項で処罰することは、以下に述べるように21条1項に反しない。
⑴ 本件におけるXの処罰は、Xの議員の発言の自由を制約することを目的としたものではなく、法10条に基づき秘密会を条件とした委員会で提供された情報が公開されることを条件として提供されたプログラムに関する情報を秘密会のないA県議会で公表したことを処罰するものであるので、Xの議員の発言の自由が結果的に制約されたとしても、それは上記目的に付随するものであるにすぎないといえる。このことからすれば、本件処罰は、Xの表現の自由に対する付随的な制約にとどまり、この制約を正当化するには利益衡量の際に、違憲側の主張するような公益の明らかな優越までは求められないと解される。
⑵ 本件発言は、本件施設のプログラムという安全保障上の重大な事項に関わるものの仕様を示すものであり、特定秘密として指定されて提供されたにもかかわらず、Xがこれを公開したのである。そして、核燃料施設という性質上、不正侵入などのサイバー・テロが行われると周辺住民の生命・健康にも重大な危険をもたらすおそれがあるから、本件施設のプログラムに関する情報の漏洩を防ぐことには、かなりの合理性があるといえる。他方、これによって制約されるXの議員の発言の自由は、その態様が付随的なものであるし、プログラムの仕様自体を示すことなく安全保障に配慮しながらプログラムの危険性を訴えることも十分可能でありXの本件施設のプログラムに関する発言すべてが制約されるわけではない。したがって、失われる利益は、上記の公益を上回るとは言えない。
3. 以上より、本件処罰は21条1項に反しないため、合憲である。
第3 私見について
1. 本件処罰は、21条1項に反するか。
⑴ これまでに述べたように、Xの議員の発言の自由が保障及び本件処罰がこれを制約するものであることは明らかである。また、Xの県議会議員としての発言は、同じく21条1項で保障されるA県の住民の知る自由にも資するものである。間接民主制を敷く地方議会においては、議員の発言をもって、当該地域の住民が単独では取得することが困難な情報を摂取し、自らの政治的思想の形成、生活の安全等に役立てるものである。したがって、違憲側の主張のようにXの議員の発言の自由そのものも重要な権利であるが、それだけでなく、上記住民の知る自由もその重要性は肯定される。
他方、合憲側の主張するように、上記の2つの自由に対する制約は、安全保障の貫徹という国家しか行いえないことを目的とするもので、憲法上の自由に対する制約は付随的なものにすぎない。21条1項は、国家による表現の弾圧が行われた戦前の反省をもって、表現の自由を広く保障するものである。とはいえ、付随的制約については主要な目的が表現の弾圧ではない以上、その合憲性の審査は比較的緩やかになされるべきである。
これらのことから、本件発言を処罰することによって得られる公益と上記のような権利の重要性を勘案したこれによって失われる利益を比較して、前者が後者に上回るといえる場合に限り、本件処罰は21条1項に反しないというべきである。
⑵ 本件発言はA県住民の生命・健康に重大な危険を及ぼし得る事項に関するものであり、Xの県議という地位や同住民の安全性という観点から、当該発言をすることでこの危険を回避するという利益は十分に合理的なものである。また、地方議員については51条のような議員の免責特権を明文で認める規定は存在しないものの、民主主義政治実現のために議員としての裁量に基づく発言の自由が確保されるべきことは、国会議員の場合と地方議会議員の場合とで本質的に異なるものとすべき根拠はないから、地方議員の発言もできる限りその自由を確保すべきである。もっとも、上記のとおり、本件発言の処罰によって制約されるXの利益は、行為に伴う弊害を防止する目的で当該行為を禁止することに伴い表現行為が規制されることとなるという付随的な制約にすぎない。また、Xはプログラムの仕様自体を示すことなく安全保障に配慮しながらプログラムの危険性を訴えることも十分可能であり、本件発言の処罰によってXの本件施設のプログラムに関する発言すべてが制約されるわけではない。一方で、本件発言の対象になったプログラムに関する情報は、我が国の安全保障、すなわち、日本国民全体の安全を確保するという観点から重要な事項であり、安全保障の観点から情報の公開を防ぐことは国家の責務であるといえる。また、現に上記情報は法10条1項の指定を受けた特定秘密であり、秘密会を条件に提供されたものである。そうであるにもかかわらず、Xが秘密会のないA県議会でこれについての発言を行えば、上記のような安全保障上重要な事項に不特定人がアクセスすることが可能となる。つまり、上記の国家としての責務を果たすことが現実的に不可能になるというべきである。このことから、国家としての責務を果たすために特定秘密であるプログラムに関する情報を公開したXを処罰して、のちの情報流出を防ぐことは公益として非常に大きなものであるといえる。加えて、上記の国民の安全確保という重要な国家の責務を果たす観点からは、サイバー攻撃の急増がXの発言が原因であるという確証がなかったとしてもその可能性が十分にある以上、発言をしたXを処罰することにも十分合理性がある。
これらのことから、本件発言を処罰することによって得られる公益はこれによって失われる利益を上回ると解するべきである。
2. 以上より、本件処罰は、21条1項に反しないので、合憲である。
以上





