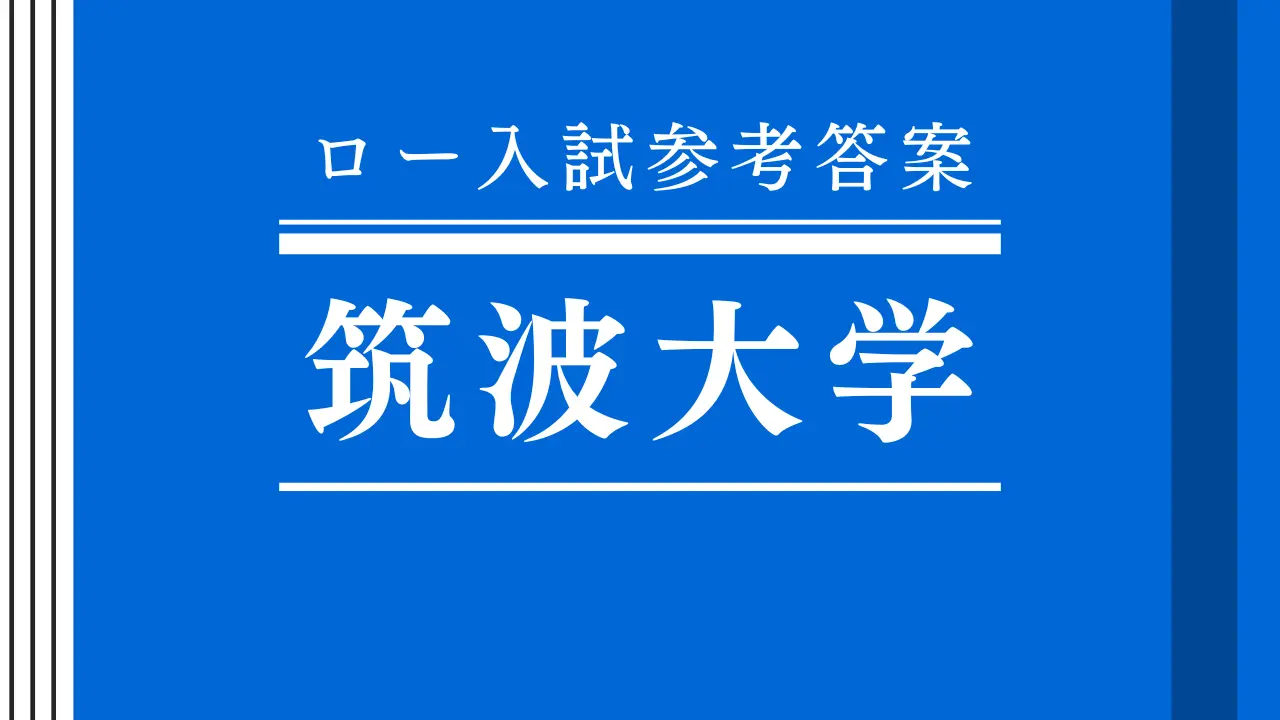
2022年 刑事法 筑波大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/30/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
日本大学法科大学院2022年 刑事法
刑法
第1 甲の罪責
1. 甲が、校地Aに抵当権を設定して、その旨の登記を完了した行為(以下、本件行為1とする。)に業務上横領罪(刑法(以下、略)253条)が成立するか検討する。
⑴ 「自己の占有する他人の物」とは、委託信任関係に基づき、事実上又は法律上支配力を及ぼしている他人所有の物をいう[1]。
本件で、甲は、X学園の理事長たる地位に基づき、X学園所有の校地Aを占有管理していた。そこで、校地Aは、甲が委託信任関係に基づき、法律上支配力を及ぼしている他人所有の物といえる。
したがって、校地Aは「自己の占有する他人の物」にあたる。
⑵ 甲のX学園の理事長という事務は、社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務であって、X学園から委託を受けて同学園の財物を占有・保管することを内容とするから、「業務」にあたる。⑶ 「横領」とは、不法領得の意思を発現する行為をいう[2]。そして、横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう[3]。
甲は、校地Aを占有管理する権限を学園Xから与えられていたに止まり、これを処分する権限までも有していたとの事情はない。それにもかかわらず、甲は、校地Aに抵当権を設定して、その旨の登記を完了しているから、甲は学園Xからの委託の任務に背いて、権限がないにも拘らず行った、所有者でなければできないような処分をする意思を発現する行為をしたとして、本件行為は「横領」にあたる。
⑶ あえて本件行為に及んでいる以上、甲には業務上横領罪の故意(38条1項本文)及び横領罪の不法領得の意思が認められる。
⑷ よって、本件行為1に業務上横領罪が成立する。
2. 甲が、乙を代理人として校地Aを丙に売却した行為(以下、本件行為2とする。)に業務上横領罪が成立するか検討する。
⑴ 上記の通り、甲による抵当権設定及び登記完了行為に業務上横領罪が成立する。そのため、甲と学園X間の委託信任関係はもはや破壊され、校地Aは「自己の占有する他人の物」にあたらないのではないか。
ア 一度横領行為が為されたとしても、委託信任を基礎付ける関係及び財物の管理状態に変動がない場合には、未だ委託信任関係が存続していると評価できるから、委託信任関係が認められる。
イ 甲による抵当権設定及び登記完了行為後も、甲は学園Xの理事長たる地位に就いており、従前のように校地Aを占有管理している。そのため、委託信任を基礎付ける関係及び財産の管理状態に変動が生じていないと評価できる。
ウ したがって、甲と学園Xとの間には未だ委託信任関係が認められ、校地Aは「自己の占有する他人の物」にあたる。
⑵ 甲のX学園の理事長という事務は、「業務」にあたる。
上記の通り、甲は、校地Aを占有管理する権限を学園Xから与えられたにとどまる。そして、校地Aを売却する行為は、当該土地の処分権限を有する者でなければ行い得ない。それにもかかわらず、甲は、校地Aに抵当権を設定して、その旨の登記を完了しているから、甲が学園Xからの委託の任務に背いて、権限がないにも拘らず行った、所有者でなければできないような処分をする意思を発現する行為をしたとして、本件行為2は「横領」にあたる。
⑶ あえて本件行為2に及んでいる以上、甲には業務上横領の故意及び横領罪の不法領得の意思が認められる。
⑷ 本件行為2は、先行する横領行為と同一客体に対して行われているところ、本件行為の違法性は先行行為の違法評価に包含され、不可罰的事後行為にあたらないか。
ア 「横領」とは、所有権の機能を危殆化する行為であれば足りる。そして、先行する横領行為と同一客体に対して行われた横領行為も、所有権の機能を危殆化するものといえる。そこで、後行する横領行為の違法性が先行行為の違法評価に包含されたとはいえず、不可罰的事後行為として扱われる余地はないものと解する[4]。
イ したがって、本件行為が不可罰的事後行為として扱われる余地はない。
⑸ よって、本件行為2に業務上横領罪が成立し、後述の通り、単純横領罪の限度で乙と共同正犯(60条)になる。
3. 以上より、業務上横領罪の単独正犯及び同罪の共同正犯(60条、253条)が成立し、両者は包括一罪となり[5]、甲はかかる罪責を負う。
第2 乙の罪責
1. 本件行為1に、乙との関係で横領罪の共同正犯(60条、252条1項)が成立するか検討する。非業務者かつ非身分者である乙に、業務上横領罪の共同正犯が成立し得るか。
⑴ 業務上横領に加工した非業務者かつ非占有者について、加工者に業務上横領罪が成立し、その刑を単純横領罪によるとする見解もある[6]。もっとも、65条1項、2項の文言から、同条1項は真正身分犯、同条2項は不真正身分犯の規定であると解する。また、非身分者も身分者を通じて身分犯の法益を侵害し得るから、「共犯」(同条1項)には共同正犯も含まれる。
そして、業務上横領罪は、「業務」がなければ横領罪が成立するという点で、不真正身分犯、「自己の占有」がなければ犯罪が成立しないという点で、真正身分犯といえる。
したがって、非業務者かつ非占有者には、真正身分である占有者の限度で65条1項が適用されて単純横領罪(252条1項)の共同正犯が成立し、不真正身分である業務者の限度で同条2項が適用されて結局単純横領罪が成立することになる。
以上により、非業務者かつ非身分者には単純横領罪の限度で共同正犯が成立し得る。
よって、乙には単純横領罪の共同正犯が成立し得る。
⑵ 一部実行全部責任の原則を定めた趣旨は、他の共犯が引き起こした結果に因果性を及ぼす点にあるから、①共謀、②共謀に基づく実行行為が認められる場合に、共同正犯が成立する。
甲は、乙の「土地を売り払っても、大丈夫でしょう。」と提案に対して、「お前に任せるよ」と返答しているから、両者には、横領罪の意思の連絡があったといえる。そして、乙は、甲に横領行為を提案した上、校地Aの売却先を探しており、甲を代理してこれを売却するという犯罪行為を遂行するために必要不可欠な行為を担っている。したがって、乙は、本件行為を自己の犯罪行為として遂行する意思を有していたといえ、同罪の正犯意思が認められる。そこで、両者間には同罪の共謀が認められる(①充足)。加えて、同共謀に基づき、乙は甲を代理して校地Aを丙に売り払ったのであるから、共謀に基づく実行行為が認められる(②充足)。
⑶ よって、本件行為に乙との関係で横領罪の共同正犯が成立する。
2. 乙が新聞紙を丸めたものにライターで火をつけ、これをエレベーターのかごに投げ込んだ行為(以下、本件行為3とする。)に、現在建造物放火罪(108条)が成立するか検討する。
⑴ 上記エレベーターはX大学西棟から容易に取り外すことができる物ではないため、「建造物」にあたる。もっとも、本件行為時にX大学西棟は無人である一方で、同棟と廊下で接続された本棟には宿直室に警備員が常駐しており、加えて理事長室には甲が残業をしていた。そこで、同エレベーターを、本棟と一体とみることによって「現に人がいる建造物」にあたるといえないか。
ア 同条の罪の重罰根拠は、建造物内部の人の生命・身体に対する高度な危険にあるから、建造物の一体性は、延焼可能性を考慮した物理的一体性、及び補完的に機能的一体性を考慮した上で、社会通念に従って判断すべきである[7]。
イ 本件では、エレベーターが取り付けられたX大学西棟と本棟は長さ約10メートルの渡り廊下で接続されており、両者は構造的に一体である。また、上記廊下には、防火扉等が設置されていなかったことに加え、両建物自体が高い不燃性を有しているとの事情はなく、上記エレベーターでの火災が西棟に延焼し、同廊下を伝って本館へ延焼する可能性がある。さらに、上記廊下は、大学棟同士を接続するものであって、頻繁に往来するから、両建物の機能的一体性は非常に強いと評価できる。よって、両建物は社会通念上、一体のものとして評価すべきである。
ウ したがって、上記エレベーターは「現に人がいる建造物」にあたる。
⑵ 本件行為3は、可燃性の高い新聞紙にライターをつけて、これを投げ込む行為であるから、焼損結果発生の危険性を惹起する「放火」行為にあたる。 「焼損」(同条)とは、火が媒介物を離れて独立に燃焼を継続し得る状態に達したことをいう[8]。
本件行為3によって、上記エレベーターの側壁に火を燃え移らせ、これに張られていた化粧鋼板表面の化粧シートの一部が、約5センチメートル四方にかけて焼失している。そこで、火が媒介物たる新聞紙を離れて独立に燃焼を継続し得る状態に達したといえるから、 「焼損」結果が生じたといえる。
⑶ 仮に、乙が本部棟に人が存在しないと誤認した上で、本件行為3に及んだ場合(以下、本件場合とする。)には、本件行為3に故意犯が成立しない(38条2項)のではないか。
ア 故意責任の本質は、反規範的人格態度に対する道義的非難である。そして、主観と客観に齟齬が存する場合であっても、両者に係る犯罪の客観的構成要件が同質的に重なり合う場合には、その限度で規範に直面したといえるから、当該限度で故意が認められる[9]。
イ 現在建造物放火罪と非現在建造物放火罪は、保護法益を不特定又は多数人の生命、身体及び財産とする点で共通する。また、両犯罪に係る行為はいずれも「放火」である点でも共通する。そこで、両犯罪は軽い非現在建造物放火罪の限度で重なり合うといえる。
ウ したがって、本件場合には非現在建造物罪の限度で故意が認められ、そうでない場合には現在建造物の故意が認められる。
⑷ よって、本件場合には現在建造物放火罪が成立し、そうでない場合には非現在建造物放火罪が成立する。
3. 以上より、本件場合には乙に単純横領罪の共同正犯及び非現在建造物放火罪が成立し、両罪は併合罪(45条前段)となる。他方で、そうでない場合には単純横領罪の共同正犯と現在建造物放火罪が成立し、両罪は併合罪となる。
第3 丙の罪責
1. 校地Aを甲から買い受けた行為(以下、本件行為4とする。)に、盗品等有償譲受罪(256条2項)が成立するか検討する。
⑴ 上記第1の通り、校地Aは横領罪の客体となっているから、校地Aは、「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(同項、同条1項)にあたる。
⑵ 本件行為は、代金5000万円で校地Aを買受ける行為であるから、「有償で譲り受け」(同条2項)る行為にあたる[10]。
⑶ 丙は、Aが甲の所有する土地ではなく、甲乙が勝手に売却しようとしていることを知っていた。そこで、盗品等有償譲受罪の客観的構成要件該当事実の認識・認容があるといえ、同罪の故意が認められる。
2. したがって、本件行為4に盗品等有償譲受罪が成立する。
刑事訴訟法
第1問
1. 職務質問とは、犯罪の予防、鎮圧等を目的とする行政警察上の作用であり[11](警察官職務執行法1条1項参照)、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」(同法2条1項)を対象として行われる。他方で、任意捜査とは、特定の犯罪についての犯人訴追の準備活動たる司法警察上の作用[12]である。
2. したがって、両者には、行政警察上の作用か司法警察上の作用かという異同があり、前者は特定の犯罪に限らず何らかの犯罪を犯していると疑われる者を対象としている一方、後者は特定の犯罪を犯したと疑われる者を対象として行われる違いがある。
第2問
訴因の特定とは、「罪となるべき事実を特定」(刑事訴訟法(以下、略)256条3項)することをいうところ、「罪となるべき事実」とは、特定の構成要件に該当する事実を意味する。そして、訴因の特定が要求される趣旨は、審判対象画定機能と防御権告知機能にあるところ、第一次的機能は前者にあり、後者の機能は前者の機能の裏返しに過ぎないから、訴因は、他の犯罪事実との識別が可能な程度に特定されていれば足りる (識別説)。
そこで、「罪となるべき事実を特定」したといえるには、①被告人の行為が当該犯罪の構成要件に該当するか否かを判定するに足りる程度の具体的事実が明らかにされており、②他の犯罪事実との区別が可能な程度に特定されていることが必要である。①については、(a)罪となるべき事実がどの構成要件に該当するかが明らかであり、(b)特定の構成要件を充足する事実をもれなく示していることが要求される。
第3問
1. 主要事実を推認する余地のない証拠を採用することは、真実発見との関係で何ら意味を有しない。そこで、証拠能力が認められるためには、最低限度の証明力(自然的関連性)を要するものと解する。
Yの供述を記した供述調書(以下、本件調書とする。)は、Xが「令和3年7月18日、東京都内のX方において、覚醒剤若干量を注射して使用した」旨を内容とするものである。当該調書から、その記載内容通りの事実があったことを認定でき、当該事実からXが「覚醒剤を使用」(覚醒剤取締法19条柱書)したという主要事実を推認することができる。
したがって、本件調書の内容通りの事実を要証事実とした場合には、本件調書に自然的関連性が認められる。
2. 本件調書が「公判期日における供述に代えて書面を証拠」(320条1項)とするものとして伝聞証拠にあたれば、原則として証拠能力が否定される。
⑴ 伝聞法則の根拠は、供述がなされる知覚・記憶・表現・叙述の過程において誤りが混入していないかを反対尋問(憲法37条2項)、裁判所による証人の態度等の観察、真実を述べる旨の宣誓(154条)、偽証罪(刑法169条)の告知によって吟味する点にある。とすると、かかる吟味が必要ない場合には、伝聞証拠に当たると考える必要はない。
そこで、伝聞証拠とは、①公判期日外の供述を内容とする証拠であって、②当該供述内容の真実性を立証するために使用されるものをいうと解する。そして、内容の真実性は、要証事実との関係で決せられるものと解する。
⑵ まず、本件調書は、公判期日外たる捜査段階で作成されたものである。そのため、本件調書の内容たる供述は、公判期日外の供述にあたる(①充足)。
次に、本件調書の要証事実は当該調書通りの事実の存在であること及び、主要事実への推認過程は上記1の通りである。そして、当該推認過程を経るためには、調書記載の供述内容が真実でなければならない。そこで、本件調書はその内容となっている供述の真実性を立証するために使用されるものといえる(②充足)。
⑶ したがって、本件調書は伝聞証拠にあたり、原則として証拠能力が否定される。
3. 本件調書を証拠として採用するにつき「同意」(326条1項)が存在する場合を除き、伝聞例外(321条1項3号)にあたらなければ、証拠能力が否定される。
⑴ 本件において、Yは公判廷において証言をしていることから、「供述をすることができ」(同号)ない事情はない。
⑵ したがって、本件調書は伝聞例外にあたらない。
4. よって、「同意」がない限り、本件調書に証拠能力は認められない。
以上
[1] 大塚裕史ほか『基本刑法Ⅱ〔第2版〕』279頁
[2] 大判昭和8年7月5日(刑集12巻1101頁)
[3] 最判昭和24年3月8日(刑集3巻3号276頁)
[4] 最判平成15年4月23日(刑集57巻4号467頁)
[5] 大阪地判平成20年3月14日
[6] 最判昭和32年11月19日(刑集11巻12号3073頁)
[7] 最判平成元年7月14日(刑集43巻7号641頁)
[8] 最判昭和25年5月25日(刑集4巻5号854頁)
[9] 最判昭和61年6月9日(刑集40巻4号269頁)
[10] 前掲・大塚346頁
[11] 最判昭和53年6月20日(刑集32巻4号670頁)
[12] 前掲・宇藤ほか30頁





