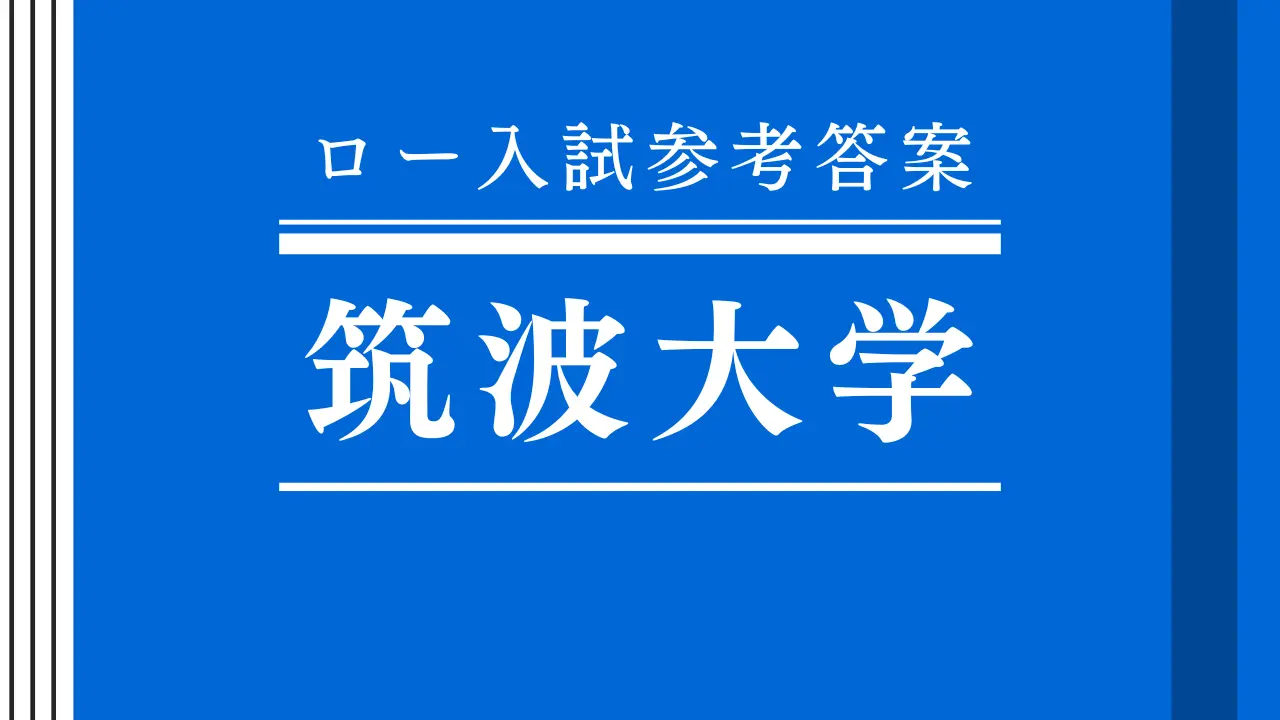
2025年 民事訴訟法 筑波大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/30/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
筑波大学法科大学院2025年 民事訴訟法
第1問
1. 結論
前訴確定判決は、後訴におけるXのYに対する請求に対して、既判力の消極的作用により、前訴の判決内容と異なる判断を裁判所が下すことが許されなくなる結果として、請求が棄却されるとの影響を及ぼす。
2. 上記結論に至る理由
⑴既判力(114条1項)とは、前訴確定判決における後訴に対する通用力・拘束力をいう。既判力は「主文に包含されるもの」、すなわち訴訟物について及ぶ。本件で、前訴及び後訴におけるXのYに対する訴訟物は売買契約に基づく代金支払請求権であり、両者は同一であるから、既判力が作用する場面にあたる。
⑵そうすると、既判力の消極的作用により、裁判所は前訴の判決内容と異なる判断を下すことが許されないこととなる。本件においては、裁判所において、Yが主張する弁済の事実を認め、Xの請求をすべて棄却する判決を下したという前訴の判決内容に拘束される結果、後訴において、かかる弁済の事実について異なる判断を下すことは許されなくなる。
⑶このような理由で、上記結論に至るものである。
第2問
1. 前訴確定判決は、後訴におけるXのZに対する請求に影響を及ぼすか。
2. ここで、反射効という概念により、実体法上の依存関係にある第三者に対して、当事者間の既判力について拡張を認める見解がある。かかる見解による場合、主債務の存在が認められなければ保証債務についても付従性により消滅するという実体法上の依存関係から、前訴における当事者であるX・Y間の既判力が第三者である保証人Zに対して及び、後訴におけるXのZに対する請求が棄却されるとの影響が及ぶこととなる。
3. しかし、処分権主義・弁論主義の下では、類型的に既判力と同様の機能を認めることができるのは、明文のある場合に限るべきである。そのような効力を明文の規定なく認めることは、手続保障の観点からも問題がある。したがって、反射効という概念は認められないと解する。
4. 以上より、反射効は認められず、Zは前訴確定判決の当事者ではなく、115条1項各号のいずれにもあたらないため、前訴確定判決の既判力は及ばない。よって、前訴確定判決は後訴におけるXのZに対する請求に影響を及ぼさない。
以上





