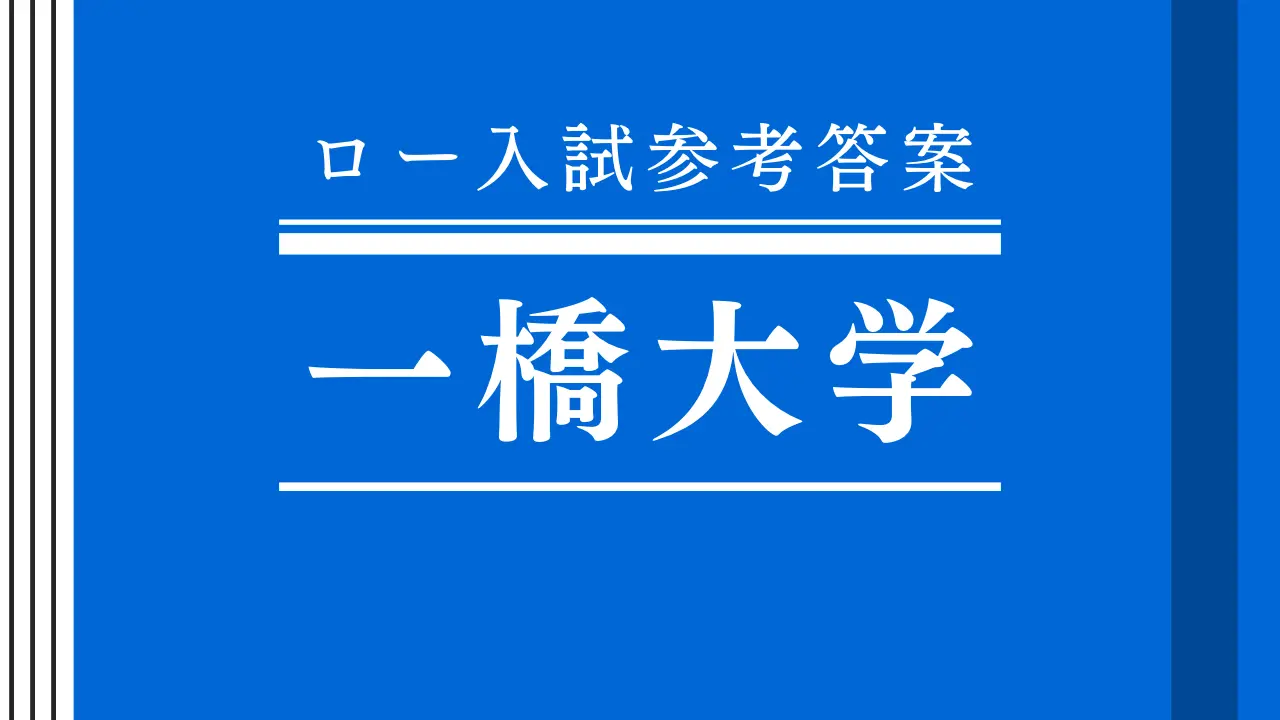
2021年 刑事系/刑事訴訟法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2021年 刑事系/刑事訴訟法
小問1
1. 携帯品・別送品申告書は、伝聞証拠(刑事訴訟法(以下略)320条1項)にあたり、証拠能力が認められず、証拠として採用できないのではないか。
⑴ 320条1項の趣旨は、供述証拠は知覚・記憶・表現・叙述という過程を経るところ、各過程に誤りや虚偽のおそれがあるため、公判での証人尋問による吟味が必要という点にある。そして、かかる吟味は、供述がその内容の真実性の証明に用いられる場合にのみ必要である。
そこで、伝聞証拠とは、公判外の供述を内容とする供述・書面で、要証事実との関係で当該公判外供述の内容たる事実の真実性の証明に用いられるものをいうと解する。
⑵ 本件では、携帯品・別送品申告書には、「いいえ」欄にチェックが有り、Xの署名もあるところ、それはXが同申告書に「私は他人から預かったものを持っていません」と書いたものと同様といえる。よって、公判外の供述を内容とする書面といえる。
また、立証趣旨は「彼告人が税関において預かり品はないと申告したこと」であり、被告人は、チョコレート缶はYから預かったもので、覚醒剤が入っていることは全く知らなかったと供述して故意を否認している。とすれば、検察官は、「いいえ」の欄にチェックが入っており、かつ年月日とXの署名がある携帯品・別送品申告書の存在から、Xが税関において預かり品はないと申告したことを証明し、もってXが他人から預かったものがあるにも関わらず、携帯品・別送品申告書に、他人から預かったものはない旨の虚偽の申告をしたことを推認し、それによってXがチョコレート缶に覚せい剤が入っていると認識していたことを証明する場合と言える。
よって、要証事実は、「いいえ」欄にチェックがなされXの署名がある携帯品・別送品申告書の存在と内容であり、同申告書は、要証事実との関係でその内容たる事実の真実性の証明に用いられるものではない。
したがって、伝聞証拠に当たらない。
2. 以上より、非伝聞証拠として、証拠能力が認められ、証拠として採用できる。
小問2
Xは、Yから預かったものがあるにも関わらず、携帯品・別送品申告書に、他人から預かったものはない旨の虚偽の申告をしている。
Xとしては、他人から預かったものがある旨の申告することにより、税関審査官からその内容物の詳細を尋ねられたり、X線検査などを経たりして覚醒剤であることが特定されてしまうことをおそれたと考えられる。
ここから、検察官の推論過程は、以下のとおりである。Xが虚偽の申告をしたとの事実を証明する。そこから、Xが税関審査官からその内容物の詳細を尋ねられたり、X線検査などを経るとまずい何か、すなわち、なにか違法な物を国内に持ち込もうとしていたという事実を推認する。さらに、持ち込み物の中に入っている違法な物が覚醒剤のみであれば、Xは覚醒剤という違法な物を輸入する故意があったこと推認するというものであると考えられる。
以上のような推論を用いて、Xの覚せい剤取締法違反(輸入)を証明できる。
小問3
まず、XはYから預かったものがあることを認識していたとしても、携帯品・別送品申告書に、他人から預かった物はない旨の虚偽の申告をすることはありうるから、虚偽の申告書の存在を持って、覚醒剤輸入の故意を証明できないと反論する。
すなわち、税関検査には相当の時間がかかるところ、他人から預かった物がある旨を申告すれば更に厳密な検査が行われ、その後の旅程に支障を来すおそれがあることから、とりあえず「いいえ」欄にチェックを入れて署名しただけであると反論しうる。また、同申告書は他人から預かった物の有無を問う質問以外にも複数の質問事項があったと推測され、Xは質問事項をよく読まずに「いいえ」欄にチェックを入れただけで、虚偽の申告をするべくして他人から預かった物の有無の質問につき「いいえ」と記載したわけではないと反論しうる。
以上





