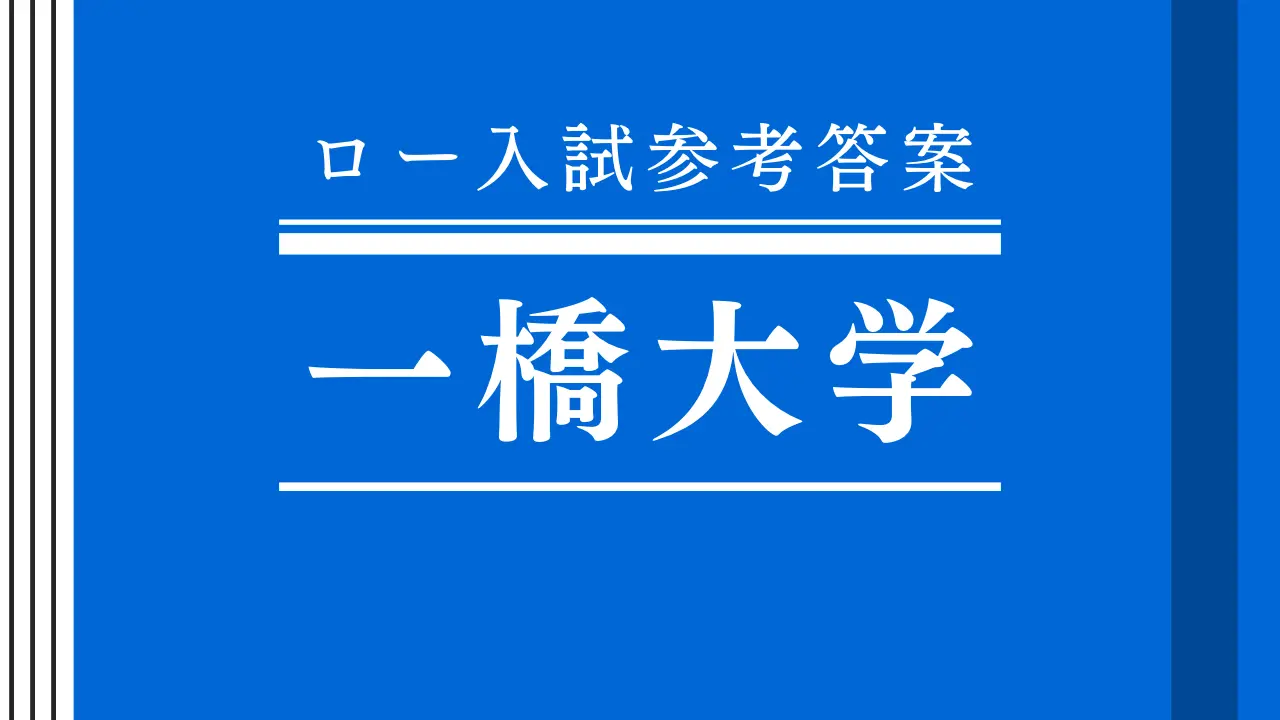
2024年 民事訴訟法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2024年 民事訴訟法
1. 裁判所が2022年9月までの賃料相当額の支払いを認める判決を出すことにつき、弁論主義第1テーゼに反しないか。
2. 弁論主義とは、事実の認定に必要な訴訟資料の収集・提出については当事者の責任ないし権能とする建前、をいう。
⑴ここで、「事実」とは主要事実を指すものと解する。間接事実及び補助事実については、主要事実を推認させる点で証拠と同様の機能を有するものであり、弁論主義を適用することは自由心証主義(247条)に抵触するおそれがあるためである。
⑵そして、一般条項等の不特定概念については、それを基礎づける具体的事実が主要事実にあたると解する。当事者はかかる具体的事実について攻撃防御を尽くすものであり、当事者の意思尊重及び被告の不意打ち防止という弁論主義の機能に鑑みれば、評価根拠事実こそが主要事実と考えるべきであるためである。
⑶本件においては、一般条項である信義則(民法1条2項)上の義務を基礎づける具体的事実が主要事実にあたると考えられる。したがって、当事者であるX・Yにおいて、Yは理事長の許可があれば70歳まで働くことを認めるなど、事実上70歳を定年とする運用をしてきたことや、教員はこれを前提として人生設計をしてきたこと、という信義則上の義務を基礎づける具体的事実を主張していたのであれば、裁判所が上記判決を出すことについて弁論主義第1テーゼには反しないこととなる。
3. 仮に弁論主義第1テーゼに反しないとしても、裁判所が上記判決を出すことは、法的観点指摘義務に反しないか。
⑴法の適用は裁判所の専権に委ねられるのが原則である。しかし、裁判所の想定する法的構成と当事者の主張する法的構成が異なる場合、何らの釈明なく判断を下すことは、当事者に対する不意打ちとなり、十分な攻撃防御が尽くされないおそれがある。そこで、当事者に対する不意打ちとなる場合は裁判所は釈明義務(149条1項)の一環として、法的観点指摘義務を負うものと解する。
⑵本件においては、弁論準備手続において主たる争点は本件合意の存否であることが確認されており、当事者たるX・Yにおいては、信義則上の支払い義務の点については法的構成として想定していなかったものであり、当事者に対する不意打ちとなる。そうすると、裁判所としてはかかる法的構成について釈明する義務を負っていたと解するべきである。
⑶それにもかかわらず、裁判所はX・Yに対して釈明を行っていない。したがって、裁判所が上記判決を出すことは法的観点指摘義務に反する。
以上





