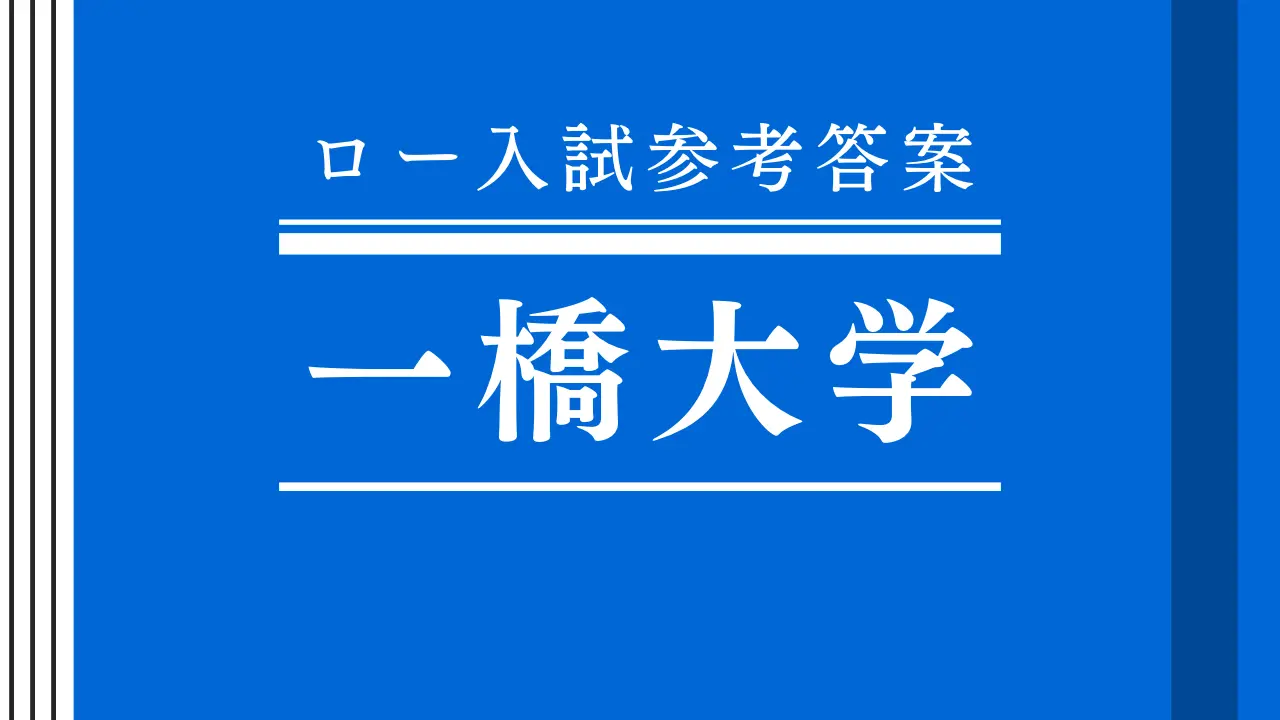
2024年 憲法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2024年 憲法
小問1
1. 処分①
⑴処分①は、、Xの政治活動の自由を制約し、憲法(以下略)21条1項に反し違憲である。
⑵ア 「表現の自由」(21条1項)は、思想・意見を表明する自由である。政治活動の自由は、政治的な思想・意見の表明を伴うものであるから、「表現の自由」として憲法21条1項により保障される。
イ Xが「処理水海洋放出反対!」と題した文書を18歳以上の生徒に対して許可なく配布することは、政治活動の自由として保障される。
⑶上記行為を理由に懲戒処分としての訓告(処分①)がなされており、上記自由の制約があるといえる。
⑷ア 政治活動は、民主主義的自己統治にとって不可欠なものである。とりわけ、上記のビラ配布行為は、Xの、「気候変動のような環境問題は資本主義による経済成長に起因しており、行きすぎた資本主義を見直す必要がある」という信条に密接に結びつくのであり、Xは、政府が福島第一原発からの 処理水の海洋放出を決定したことに反発していることからすれば、自己統治の価値が端的に現れる行為といえる。
また、Xは、A県B公立高校に通う18歳の日本国民であって、選挙権の享有主体であること、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、学校ごとに区々別々な政治的行為にかかる制限を設けることが望ましくないことからすれば、政治活動の規制に関してについて広範な裁量を認めることは到底できず、処分には特に慎重な配慮を要するというべきである。
イ そこで、形式的に、A県教育委員会の定めた県内の全公立高校に「政治的活動等に対する生徒指導に関する校則等の見直しについて」(以下、指針という)のに該当する場合でも、新通知の趣旨・目的に反しない場合には、校長は生徒を処分できないと解する。
新通知は、②において、放課後の学校構内で行う政治活動について、「学校教育上の支障が生じないよう、制限又は禁止の必要がある。」としている。そのため、学校教育上の支障が生じないような場合に指針を適用して処分をすることは、21条1項に反し許されないと解する。
ウ Xが上記のビラ配布を行ったところ、校長は、学校教育上の支障が生じるかを検討することなく処分①をしている。
⑸よって、処分①は、21条1項に反し違憲である。
2. 処分②
⑴処分②は、Xの政治活動の自由を侵害し、21条1項に反し違憲である。
⑵Xが、処理水放出に反対する野党が主催するデモに参加することは、政治活動の自由として21条1項により保障される。
⑶処分②は、Xの上記行為を理由になされているから、Xの政治活動の自由を制約するものといえる。
⑷指針⑵は、校外での政治的活動という、学校の管理権の及ばない範囲での行為について規制するものであり、事前規制的性格を有する。そして、政治的活動という上述の通り高価値な人権について、許可性という事前規制を設けるものである。そこで、指針⑵イ及びウにいう「支障がある」とは、政治活動の自由を保障することの重要性よりも指針⑵イないしウにいう「支障」が優越する場合をいうものと限定して解すべきである。その支障の程度としては、学業や生活ないし学校教育の実施に、支障が生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った支障が生じることが、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合でなければならない。
そうすると、指針⑵違反を理由に処分をすることができるのは、「支障」と政治活動との関連性が客観的事実に照らして明白であるときに限られるというべきである。
⑸本件では、担任から、最近のXは政治的活動に没頭する余り授業でも居眠りが続いているとの回答を得ているに過ぎず、これは、担任のした観念上の想定にすぎない。また、家に帰ってからも同高校の18歳以上の友人に対して頻繁に自己の政治的主張についてメールなどをしている事実は明らかになっておらず、担任がそのようであると考えているに過ぎない。居眠り等とデモ行進との関連性は明白でないから、これをもって、「支障がある」ということはできない。
⑹Xは届出義務には反しているものの、届出は本来受理されるべきものである。そのことを看過してなされた処分②は、Xの政治活動の自由を侵害し、21条1項に反し違憲である。
小問2
1. 処分①
⑴学校は法律について格別の規定がない場合であっても、その設置目的を達成するために必要な事項を学則等により一方的に制定し、これによって在学する生徒を規律する包括的権能を有するのであって、学校長には広範な裁量が認められるとの反論が想定されるも、失当である。
確かに、昭和女子大事件判決は、大学に包括的権能を認めている。もっとも、それは、学生が、大学に進学するか、また、どの大学に進学するかということを実質的にも自律的に判断できているのを前提とした判断と解される。一方、生徒は、学費や通学可能な範囲等の条件から限定的な範囲から高等学校を選択せざるを得ないのであって、高校に、大学と同様の広範な裁量を認めることはできない。エホバの証人剣道受講拒否事件が、校則を認識して入学したことを根拠に校則に同意した旨の主張を退けたことからもそう言える。校長には、学内の事情に通暁し直接教育の衝に当たるものであることから、合理的な裁量が認められるに過ぎないと解する。
⑵全国一律の基準によるべきなのであれば、文部科学省の公表する「新通知に関する Q&A」に従うべきであり、同Q&Aで、学校教育の目的の達成の観点から政治的活動等を「構内では禁止する」と校則で定めることも不当ではないとされていることからすれば、指針の適用になんらの問題もないとの反論が想定される。
確かに、学校は、同Q&Aに従うべきとは言える。学校が、本来的に教育等を目的とし、社会的・政治的活動のための施設でないことからすれば、構内の政治的活動への利用を原則禁止することには一定の合理性がある。しかしながら、その校則の適用にあたっては、Xの主張する通りの政治活動の自由の高価値性に鑑み、X主張の適用をすることが必要であると考える。
⑶処分①は、21条1項に反し違憲である。
2. 処分②
⑴学外での行為を理由としているとはいえ、停学という学校内にとどまる処分であるから、学長の裁量を広く認めるべきであり、原告の採用するような合憲限定解釈は認められないとの反論が想定されるも失当である。
校内での行為を理由とする処分であっても、学校長には、上述の根拠に基づき合理的な裁量が認められるに過ぎない。今日における高等学校等への進学率に鑑みると、処分の効果が構内にとどまることを根拠に裁量を広く認めれば、生徒の人権を、校長の裁量を根拠に無限定に侵害することとなりかねず妥当でない。政治的な主義主張は繰り返されるものであって、反復継続して処分がなされることで、累積加重的に重い処分がなされる可能性が高いことも考えると、少なくとも要件裁量は認めるべきではない。Xが主張する合憲限定解釈をするのが妥当である。
⑵次に、上記のQ&Aでは、休日等に学校の構外で行われる政治的活動について、届出をした者の個人的な政治的信条の是非を問うようなものでない限り、届出制とすることも許されるとされていることからすると、政治信念に着目せず、弊害に注目して、内容中立的に不許可事由を定める場合には、広く不許可事由を定めることが許されるべきであって、Xのいう合憲限定解釈は不当であるとの反論が想定されるが失当である。
あくまで、Q&Aが内容に着目した許可要件でない限り、届出制とすることを認めているからといって、内容中立的な不許可事由であれば無限定に認められることにはならない。Xの主張する通りの政治的活動の自由の高価値性に加えて、事前の届出制の場合予測に基づいて広範に規制がされやすいことを踏まえると、X主張の合憲限定解釈を採るべきである。
3. 以上より、反論はいずれも失当であり、処分②は21条1項に反し違憲である。
※出題趣旨には、処分②について思想・良心の自由を問題とすべきと読める記述がある。もっとも、現実的な受験生の人権選択のレベルからして、デモ行進という外部的行為の規制について、思想・良心の自由の制約として適切に論じ切ることは現実的でない。そこで、一橋ローに上位で合格できる最も書きやすい答案という観点から、政治活動の自由の問題として論じている。





