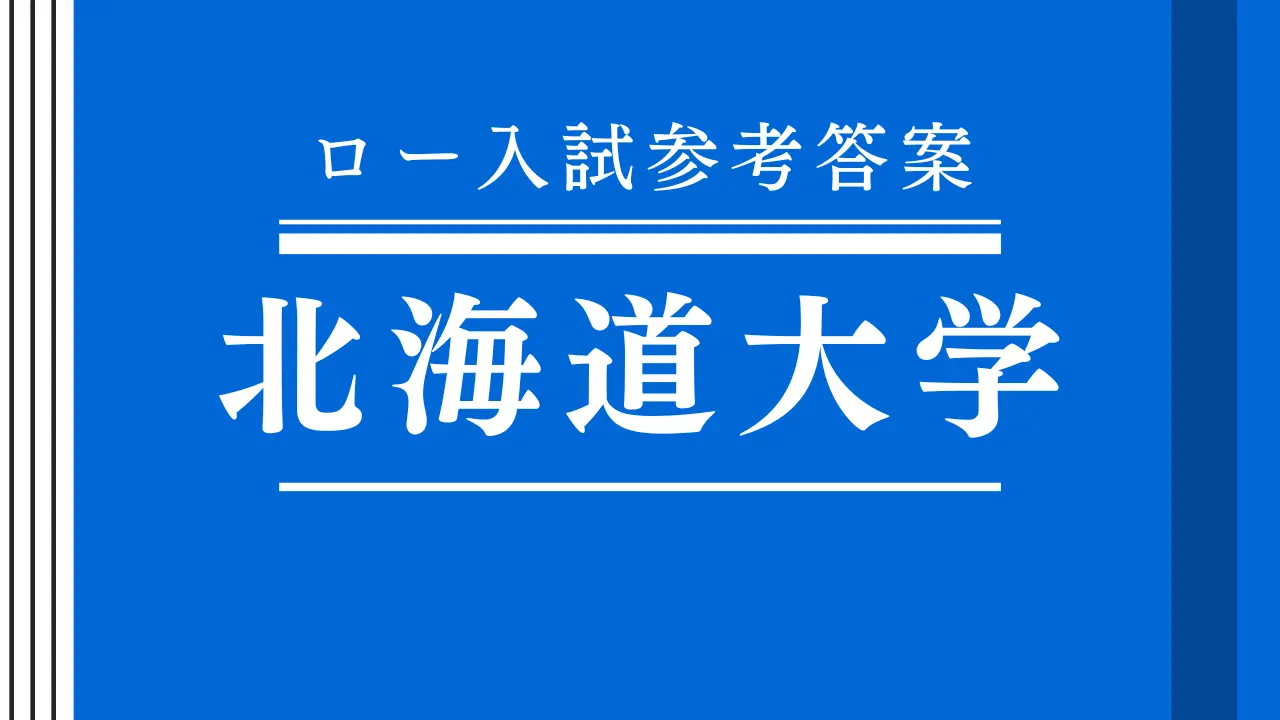
2023年 民事訴訟法 北海道大学法科大学院【ロー入試参考答案】
2/29/2024
The Law School Times【ロー入試参考答案】
北海道大学法科大学院2023年 民事訴訟法
問1
1. 弁論準備手続(168条)とは、口頭弁論期日以外の期日において、受訴裁判所又は受命裁判官が主催して行う争点整理手続をいい、準備的口頭弁論と異なり、口頭弁論ではないから、公開主義や双方審尋主義などの口頭弁論の諸原則が緩和されている。これにより、公開法廷ではない準備室などにおいて、裁判官と両当事者とがインフォーマルな雰囲気の中で討論や話合いをすることができ、当事者の主張を突き合わせて争いのある事実と争いのない事実とを振り分けることが可能となる。
2. 上記のような弁論準備手続の意義・機能からすると、弁論準備手続の終了に当たり確認するものとされる「その後の証拠調べにより証明すべき事実」(170条5項、165条1項)とは、主要事実のみならず、争点ないしこれに関係する当事者の主張、あるいは争いのある重要な事実をいい、主要事実の認定のために重要な間接事実や補助事実に争いがある場合には当該事実も含まれると解すべきである。
3. したがって、「その後の証拠調べにより証明すべき事実」(170条5項、165条1項)とは、主要事実のみならず、争点ないしこれに関係する当事者の主張、あるいは争いのある重要な事実をいい、主要事実の認定のために重要な間接事実や補助事実に争いがある場合には当該事実も含まれる。
問2
1. Zは、47条1項後段に基づいて独立当事者参加をすることができないか。
2. 権利主張参加(47条1項後段)の趣旨は、訴訟の目的についての権利に関する三者間の法律関係を矛盾なく解決することにある。そこで、「訴訟の目的の全部又は一部が自己の権利であることを主張する第三者」(47条1項後段)とは、本訴請求と参加人の請求とが請求の趣旨の次元で論理的に両立し得ない関係にある場合に認められると解すべきである。また、論理的に両立し得ない関係にあるかどうかは、参加人の請求の趣旨の次元で判断されるから、本案審理の結果、判決において本訴請求と参加人との請求とが両立することになっても差し支えない。
3. 本件では、XのYに対する所有権移転登記請求と、ZのXに対する所有権確認請求及びZのYに対する所有権移転登記請求とは、訴訟物の次元では両立する。Yは、X及びZとの関係では「第三者」(民法177条)に当たらないため、X及びZからの請求に対して、所有権移転登記を備えるまでは所有者とは認めない旨の対抗要件の抗弁(民法177条)を主張することができないからである。
したがって、XのYに対する所有権移転登記請求と、ZのXに対する所有権確認請求及びZのYに対する所有権移転登記請求とは、裁判において双方認容される可能性がある。しかし、X及びZの勝訴判決が下された後、Yが一方について所有権移転登記を具備させた場合、他方が所有権を取得していなかったことが確定するから、双方の勝訴判決の内容が実現されることはあり得ない。
4. よって、請求の趣旨の次元ではXの請求とZの請求とは両立せず、Zによる権利主張参加は認められる。
以上





