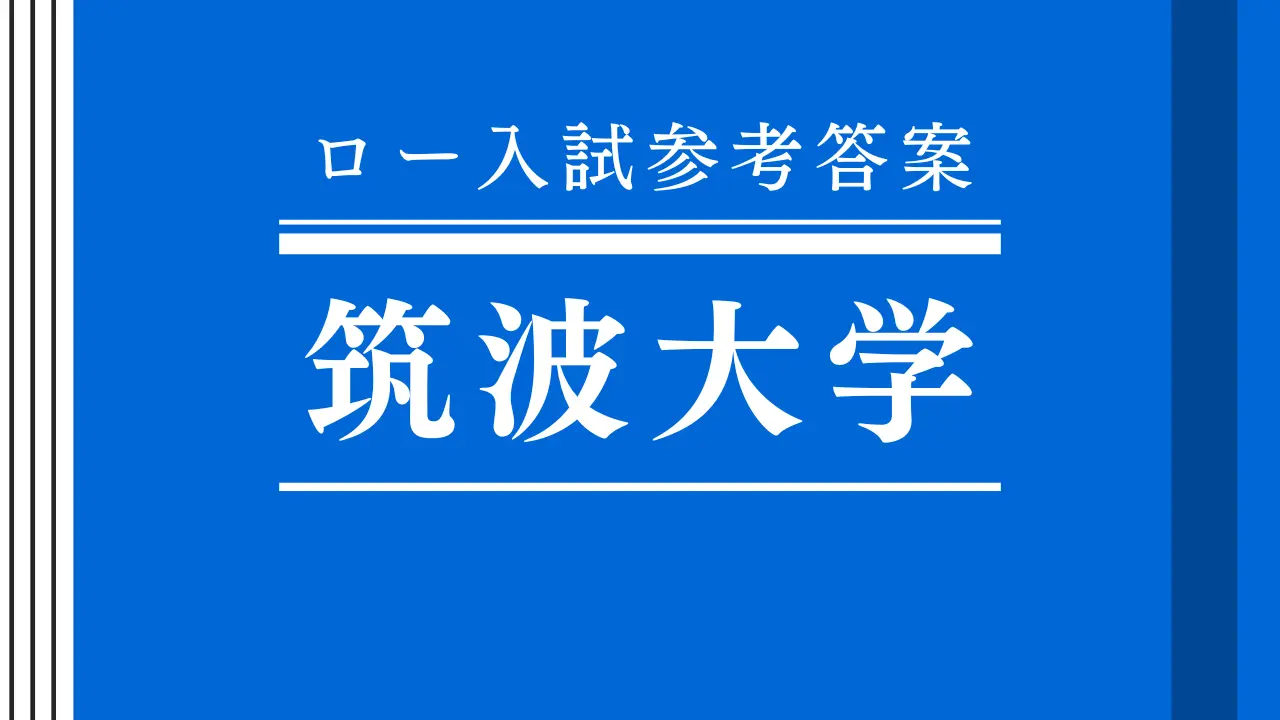
2024年 民法 筑波大学法科大学院【ロー入試参考答案】
7/11/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
筑波大学法科大学院2024年 民法
第1問⑴
1. BはDに対すして甲土地の所有権(206条)に基づく妨害排除請求として、移転登記の抹消手続き請求をしている。
2. AはBに対し、甲土地を3000万円またはそれを超える価格で売却すること、および、売却した際に買主に登記名義を移転することを内容とする代理権を授与(99条1項)している。そして、BはAの代理人としてD会社と甲土地を3000万円でDに売却する契約を締結している(555条、99条)。
3. もっとも、Bは甲土地の売却代金をAには渡さずにC会社の運用資金に流用しており、そのことをCは知りつつ甲土地を購入しているから、「代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をし」、「相手方がその目的を知」っていたといえ、本件行為はは無権代理とみなされ本人が追認しない限り、本人に効果帰属しない(113条1項)。
Aは本件行為について、しばらく静観することとしていたが、その後死亡しているから、「本人の追認」がなくBの行為の効果はAに帰属しない。
4.⑴そこで、Bとしては、Aの地位をもって追認を拒絶すると主張する。
ここで、地位の融合を認めれば相続という事情で偶然に相手方を利することになり妥当ではないから、法的地位は併存すると解する。
もっとも、自らした無権代理行為を、後になって相続によって得た本人の地位に基づいて追認を拒絶するのは禁反言の法理に抵触する。よって、無権代理人は信義則(1条2項)上追認を強制させられる。また、追認拒絶権は、その性質上共同相続人全員に不可分に帰属しているから(264条、251条参照)追認拒絶権は分割行使できないが、他の共同相続人が追認する場合には、無権代理人は、自己の相続分についても追認を拒絶できない。
⑵BはGとAを共同相続(898条)しているものの、Gは、Aの相続財産にあまり関心がなかったことから、Dへの甲土地の売却を追認している。よって、Bは追認を拒絶することはできず、追認が擬制される。
4. したがって、BのDに対する請求は認められない。
第1問⑵
1. Dは、原料乙をCに売却していることから、「動産の売買」による先取特権(311条5号、321条)に基づき、競売の申立てをする。
2. これに対し、Hは丙倉庫内のすべての製品ならびに原料につき譲渡担保権の設定を受けている。
丙倉庫と集合物の場所的範囲が特定され、そこに在所するすべての製品ならびに原料と、種類及び量的範囲を指定して目的物のはにが特定されているから、それら全体につき1つの譲渡担保権が有効に成立しているといえる。
3. では、Dの動産売買先取特権とHの譲渡担保権はどちらが優先するか。
譲渡担保の法的性質は行為の外形を重視して所有権の移転と解するから、「第三取得者」(333条)には譲渡担保権者も含む。また、占有改定も完全な引渡しの方法なので、「引き渡し」(同条)には占有改定の方法も含まれる。よって、譲渡担保権者が優先すると解する。
よって、Hが優先する。
4. したがって、Dの申立ては認められない。
第2問
1. XはYに対して、債務不履行に基づく損害賠償請求(415条1項)をする。
2.⑴本問では、XとYは交渉段階であるから、契約が成立しておらず、債務不履行責任を追及することができず、不法行為(709条)での責任追及しかできないのが原則である。
もっとも、契約準備段階にある当事者は、信義則(1条2項)の支配する緊密な関係に入る。そのため、相互に相手方の人格・財産を害しない信義則上の義務を負い、これに違反すれば、債務不履行責任が発生する。具体的には、①当事者間の交渉等が契約締結に向けての機縁的準備にとどまらず、社会通念上契約締結のための準備的段階に成熟し、②契約の一方当事者が締約へ向けた確固たる意思表明をし、③それに起因して、他方が「締約は確実である」と信頼して準備行為を始めており、かつ、④そうすることが相当ならば、他方当事者は、かかる準備行為を防止する注意義務を負い、これに違反すれば債務不履行責任を負うと解する。
⑵本問において、Yはクリニックを開設するための物件を探しており、Xが建設中のマンション一区画を購入しようとし、Xとの交渉に入っている。Yは交渉中に、クリニックとするためのスペースについて注文を出したり、レイアウト図を交付するなどしている。また、YはXに対し電気容量の不足を指摘し、Xが容量増加のための設計変更および施工をすることを容認している。Yはこれらの要望を出し、Xも容認しているから、契約の基本事項に関する了解があったといえる(①)。
そして、それらのYの行動からは、契約の締結に向けた確固たる意思表明だと評価できる(②)。
また、これに起因して、Xが実際に設計変更および施工を開始したと考えられるから、③も認められ、上記のYの行動からは購入の意思が確実であると思われるから、準備行為を始めることが相当であるといえ、YはXの設計変更および施工を防止する義務を負い、かかる義務に違反したといえるから、債務不履行責任を負う(④)。
3. 以上より、XはYの信義則上の注意義務違反を理由として、Yに対して損害賠償請求をすることができる。
4. では、いかなる範囲の賠償を請求することができるか。
⑴損害賠償の範囲を類型化することは困難だから、信頼利益の範囲に限らず、原則通り、上記注意義務の違反と相当因果関係にある損害につき賠償責任を負うと解する。
⑵本問において、YはXに契約が締結されるという過大な期待を抱かせていることからすれば、Xが得るべき利益は通常損害であるといえる。したがって、416条1項に基づき、信頼利益である設計変更及び施工費用を請求することができる。
以上





