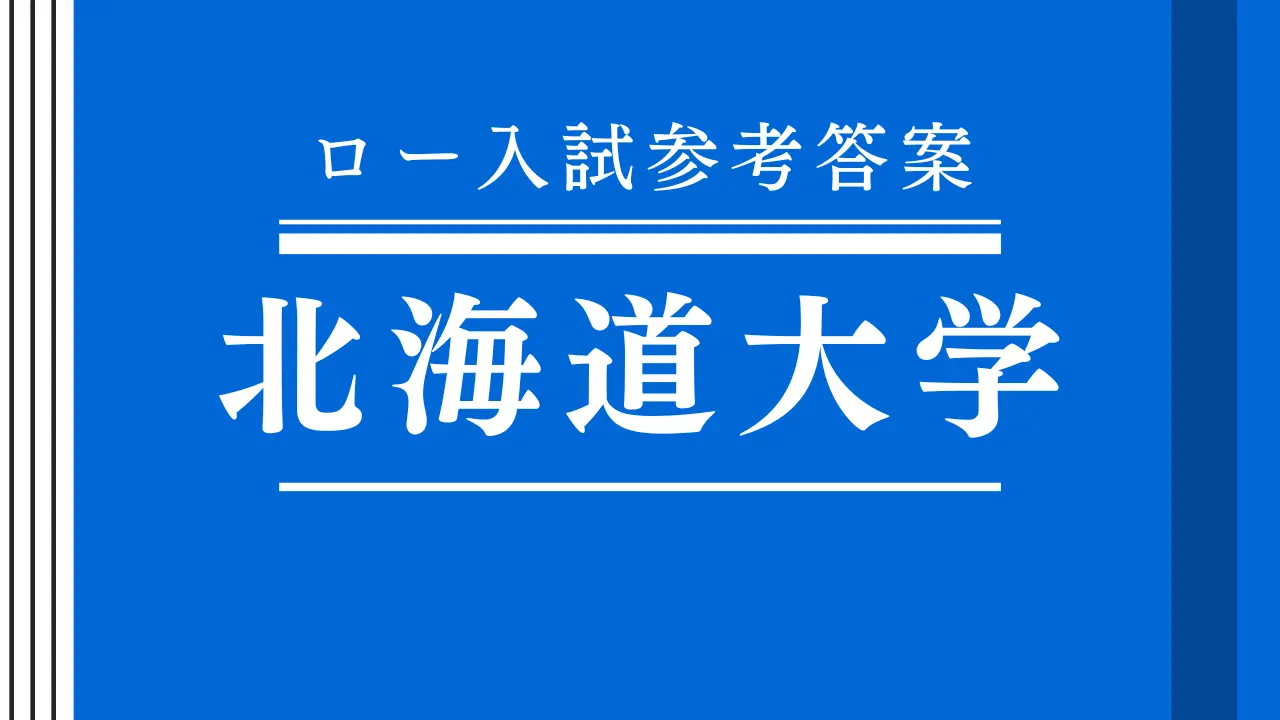
2022年 民法 北海道大学法科大学院【ロー入試参考答案】
10/26/2023
The Law School Times【ロー入試参考答案】
北海道大学法科大学院2022年 民法
第1問
1. 小問(1)
⑴ Bに対する請求
Dは、Bに対し、不法行為に基づく損害賠償請求(民法(以下略)709条・710条)をする。
ア Bは、甲車を運転していたところ、甲車をDに衝突させてDに大ケガを負わせており、Dの身体という「他人の権利」を「侵害」している。
イ Dは、治療費などの「損害」を被っている。そして、かかるBの行為と上記損害の間には因果関係が認められるため、かかるBの行為「によって」、「損害」を被ったといえる。
ウ 上記BがDをケガさせた行為は、Bが脇見をしたことが原因で生じたのであるから、Bに「過失」がある。
エ 以上より、DはBに対し、上記請求をすることができる。
⑵ Aに対する請求
Dは、Bの勤務先であるA株式会社に対し、使用者責任としての損害賠償請求(715条1項)をする。
ア 前述の通り、行為者であるBは709条の要件を満たしており、またBはAの従業員であるから、実質的指揮命令関係にあるといえ「使用」関係がある。
イ では、Bの運転行為が、Aの「事業の執行について」なされた行為といえるか。
(ア)判例は、使用者責任の趣旨を利益のあるところに損失も帰するという報償責任の原理にあると解した上で、かかる趣旨に照らせば被害者の信頼を保護し、被害者を広く救済することが妥当であるとして、「事業の執行について」と言えるか否かを行為の外形から客観的に判断している。
しかし、いわゆる取引的不法行為の場合と異なり、本件のような事実的不法行為の場合には、その行為が「事業の執行について」の行為であるとの被害者の信頼はありえない。そこで、事実的不法行為の場合には、加害行為が使用者の支配領域内の危険に由来するか否かにより判断すべきであると解する。
(イ)本件では、甲車はAが所有し管理している営業車であり、BはAから甲車を業務のために使用する権限を与えられていた。とすれば、甲車を運転する行為は、Aの支配領域内の危険に由来するといえる。
よって、「事業の執行について」の行為といえる。
ウ また、上記行為によって、「第三者」たるDに大ケガによる治療費等の「損害」が生じている。
エ そして、相当な注意をした場合又は相当な注意をしても損害が生ずべき場合には免責される(715条1項ただし書)が、AがBに対して営業以外で使用しないように注意を促したり、運転に際しての交通指導を行ったりしていたなどの事情はない。
よって、免責事由は認められない。
オ 以上より、DはAに対し、上記請求をすることができる。
2. 小問(2)
Fに対する賠償金の全額を支払ったBは、Aに対して求償権を行使して(715条3項類推適用)、BがFに支払った賠償金の支払いを請求する。そこで、いわゆる逆求償が認められるかが問題となる。
⑴ 確かに、715条3項は、使用者責任が認められ、使用者が損害を賠償した場合における費用者に対する求償権を認めた規定であり、被用者から使用者に対する求償権の存在を直接規定していない。しかし、同項の趣旨は、損害の公平な分担にあると解するところ、同項は使用者側からの求償権に限定した規定ではなく、被用者側からの求償権を排除するものではないと解する。
そこで、使用者と被用者の双方が不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合には、715条3項を類推適用して、被用者側からの求償権が認められると解する。
⑵ 本件では、小問⑴と同様に、BにはFに対する709条の損害賠償責任が、AにはFに対する715条1項の損害賠償責任が成立する。
以上より、715条3項を類推適用して、BのAに対する上記請求が認められる。
第2問
1. 小問(1)
⑴ 庭石と石灯籠は、B家に代々受け継がれ本件根抵当権設定登記具備前に本件土地建物に従たる物として付属した従物(87条1項)である。抵当権の効力は、付加一体物(370条本文)に及ぶが、抵当不動産の従物も付加一体物として抵当権の効力が及び、Aの訴えが認められるか。
ア 判例は、付加一体物とは、物理的一体性を有する物と解している。また、抵当権の設定を「処分」(87条2項)ととらえ、抵当権設定当時に存在した従物について同項の適用により、抵当権の効力が及ぶとする見解がある。しかし、抵当権の本質は、目的物の占有を設定者のもとにとどめつつ交換価値を把握する点にある以上、付加一体物とは、抵当不動産の経済的価値を高める物をいうと解するべきである。
そして従物は、主物の経済的価値を高める物である(87条1項参照)。
よって、従物も付加一体物として、抵当権の効力が及ぶ。
イ 本件でも、庭石と石灯籠は、付加一体物として本件根抵当権の効力が及ぶ。
⑵ 以上より、Aの請求は認められる。
2 小問⑵
⑴ 小問⑴では、抵当権設定当時に存在した従物に抵当権の効力が及ぶかが問題となった。これに対して小問(2)では、従物たる庭石と石灯籠は、本件抵当権設定後に存在するに至ったが、かかる場合にも抵当権の効力が及び、Aの請求は認められるか。
ア 抵当権の実行を「処分」(87条2項)ととらえ、抵当権設定時に存在していた従物のみならず、抵当権設定時に存在しなかった従物でも、抵当権実行時に存在していた限り、同項の適用により抵当権の効力が及ぶとする見解がある。しかし、前述の通り、抵当権の本質に鑑みれば、抵当権の効力は付加一体物すなわち抵当不動産の経済的効用を高める物に及ぶと解するべきである。
イ 本件でも、庭石と石灯籠は、抵当権の設定時・実行時に関わらず、本件土地建物の経済的効用を高める物といえ、付加一体物として抵当権の効力が及ぶ。
⑵ 以上より、Aの請求は認められる。
以上





