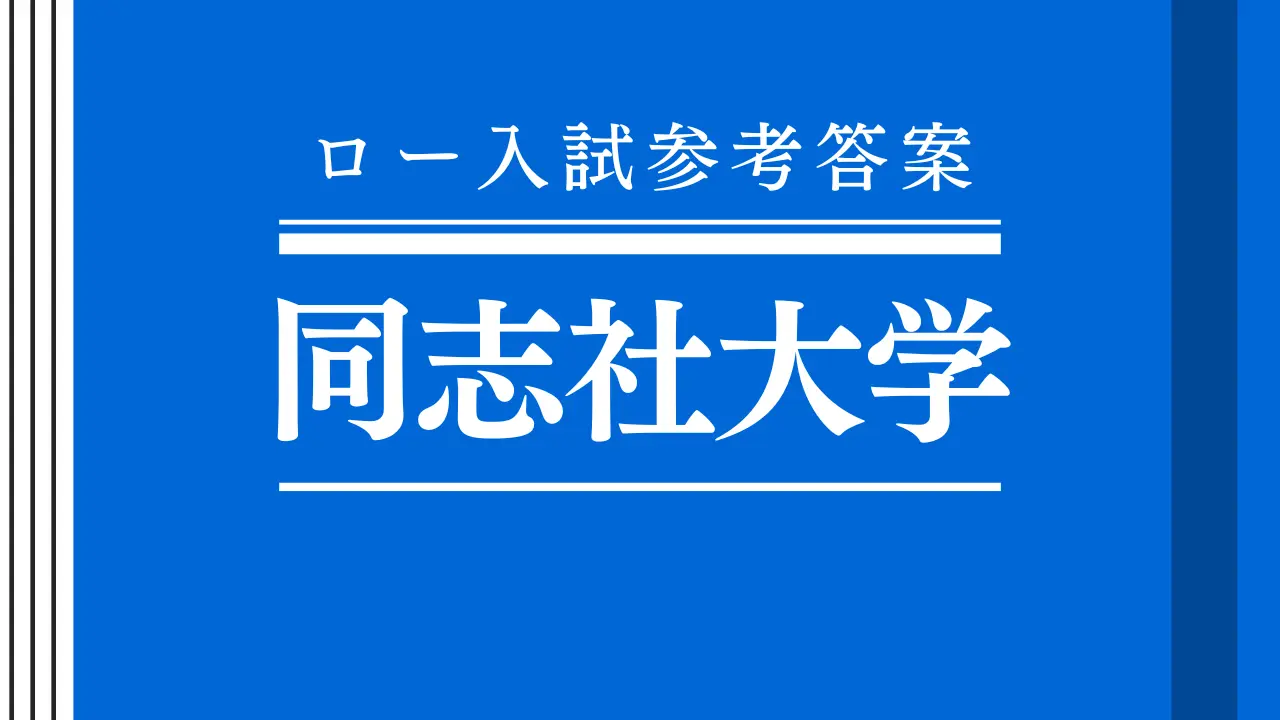
2025年 民法 同志社大学法科大学院【ロー入試参考答案】
5/11/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
同志社大学法科大学院2025年 民法
問(1)
1. DはBから甲を買ったのであって、Aとの間に契約関係はない。DのAに対する請求の根拠は、194 条である。
もっとも、本件においてDは代価弁償の提供を受ける前に甲をAに任意に返還している。このような場合でも、なお代価弁償を求めることができるか、条文上明らかでなく問題となる。
194条の趣旨は占有者と被害者等との保護の均衡を図る点にあるから、同条は、被害者等に代価を支払って物を回復するか、物の回復を諦めるかの二択を与えていると解される。また、単に目的物の引渡しを拒みうる抗弁権のみを認めたと解すると、被害者に任意に返還した者が代価の弁償を受けられず、かえっていつまでも返還を拒んだ者が弁償を受け得るという不均衡が生じる。そこで、194条は抗弁権のみならず、独立の請求権としての代価弁償を定めたものと解する。そのため、即時取得者は、一度任意に目的物を被害者に交付した後でも、代価の弁償を請求できる。
2. では、即時取得(192条)は成立するか。
⑴Dは甲を購入した際に、引き続き乙倉庫で保管してほしい旨述べており、BはDの依頼を了承して、Cに対して本日以降、甲をDのために保管するよう依頼している。Dは現実の占有を得ているわけではなく、指図による占有移転(184条)を受けているにすぎない。では、指図による占有移転も「占有を始めた」に含まれるのか。
即時取得制度は、占有という動産に関する権利の外形を信頼し、所有者の支配領域を離れて流通するに至った動産に対して、支配を確立した者を特に保護するものである。指図による占有移転を行った時点で、占有改定と異なり現実に動産を所持しているわけではない譲渡人は、一切の占有を失う。そうすると、譲渡人を介して間接的に占有していた所有者も占有を失うので、所有者の支配領域を離れて流通したといえる。この段階に至れば、第三者の信頼をより保護すべきであり、即時取得を成立させても所有者に酷とはいえない。よって、指図による占有移転は「占有を始めた」に含まれるものと解する。
本問において、甲をCが直接占有しており、BはCを通じて間接占有をしていた。そして、BのDへの譲渡によってBが間接占有を失うことになるから、Dの信頼を保護すべきである。 よって、Dは、「占有を始めた」と言える。
⑵また、かかる占有の開始は、「取引行為」に基づく。そして、「平穏」「公然」「善意」は186条1項から推定される。「無過失」は、188条より適法に処分権を有すると推定されるものとの取引行為があったことから推定される。それそれ、推定を覆す事情はないから、各要件を満たす。
⑶よって、甲の即時取得が認められる。
3. そして、Dが甲をAに返還したのは、Aが甲が「遺失物」であるとして、193条に基づき回復請求をしてたのに対し、その履行として甲を返還したものと整理できる。
4. Bは工事用計測機器の新品・中古販売を営むBから善意で甲を買い受けているから、「占有者」が「遺失物」を「同種の物を販売する商人から、善意で買い受けた」といえる。よって、194条の要件を満たし、Dの請求は認められそうである。
5. これに対して、Aは使用利益の控除を求めている。
たしかに、「回復」という法現象を観念するため、回復請求をなし得る2年間の動産の所有権は原所有者にとどまると解する。しかし、194条の趣旨は、占有者と被害者等との保護の均衡を図る点にあるところ、被害者等が対価を弁償して盗品を回復することを諦めた場合には、占有者は使用利益の返還義務を負うことはないにもかかわらず、回復請求がなされた場合には使用利益の返還義務を負うとするのは、不均衡であり趣旨に反する。
また、194条に基づき弁償される対価には利息が含まれないので、占有者の使用収益権を認めることが被害者と占有者の公平に適う。そこで、194条の趣旨から、特別な権能として、占有者に使用収益権が認められると解する。
よって、Dに使用収益権が認められるから、使用利益の控除を求めるAの主張は認められない。
5. 以上から、DのAに対する120万円の支払い請求が認められる。
問(2)
1. FのAに対する所有権(206条)に基づく丙土地の引渡し請求は認められるか。
2. FはEと丙土地について売買契約を締結しているものの、前主たるEは丙土地につき無権利者であるから、Fは原則として丙土地の所有権を取得できない。また、AE間に通謀虚偽表示がないから、94条2項の適用もない。
3. もっとも、94条2項と110条の類推により、丙土地の所有権を取得しうる。
⑴94条2項は、虚偽表示をした本人と虚偽の外観を信頼した第三者の利益衡量のための規定である。そこで、①虚偽の外観の存在、②真の権利者の帰責性、③外観に対する保護すべき第三者の信頼がある場合がある場合には、94条2項と110条の類推により、第三者が保護されると解する。
⑵登記上は、AからEへと所有権が移転したことになっているが、真実は、その様な権利移転はない。そのため、かかる登記は実態に反しており、虚偽の外観があるといえる(①)。
②については、94条2項と110条の類推により第三者を保護する場合、積極的に虚偽の外観を作出し、又は承認した場合の他、これらと同視し得る重い帰責性がある場合にも認められる。広範かつ継続的に委ねられた不動産取引や登記事務の処理の範囲を超えて不実の登記が作成されたとき、それを容易になせる状況を作出した権利者の帰責性は110条の本人の帰責性と類似するからである。
AはEから必要な書類を交付するように要求された際に、売却先が決まってからでも遅くないのではないかと質問したが、Eは不動産取引に関する豊富な知識を使って、どうしてもこれらの書類が必要であると説明し、根負けしたAは変更が完了したら必ずその登記事項証明書を見せてほしいと述べて、要求された書類をEに交付している。AはEに書類を交付することによって、不実登記のもとになるものを与えてしまっているから、Aの帰責性が認められる(②)。
③については、真の権利者との利益衡量により過失の要否を判断すべきであり、94条2項と110条の類推により第三者を保護する場合、第三者は善意に加えて、無過失である必要がある。
本問では、FはEが無権利者であることにつき善意であった。また、EはAが丙土地で電気工事店を営んでいたことを知っており、それがどうなったのかをEに質問しているから、無過失といえそうである。もっとも、Aに登記がある可能性があるなかで、土地は高価なものであるから、登記名義が誰なのかという事項については慎重に確認する必要があった。それなのに、EがAから登記名義を取得し、売買契約をすることになったというEの供述を信用したFには過失があるといえる。よって、外観に対する保護すべき第三者の信頼があるとは言えない(③)。
⑶したがって、Fは所有権を取得していない。
4. 以上より、Fの請求は認められない。
以上





