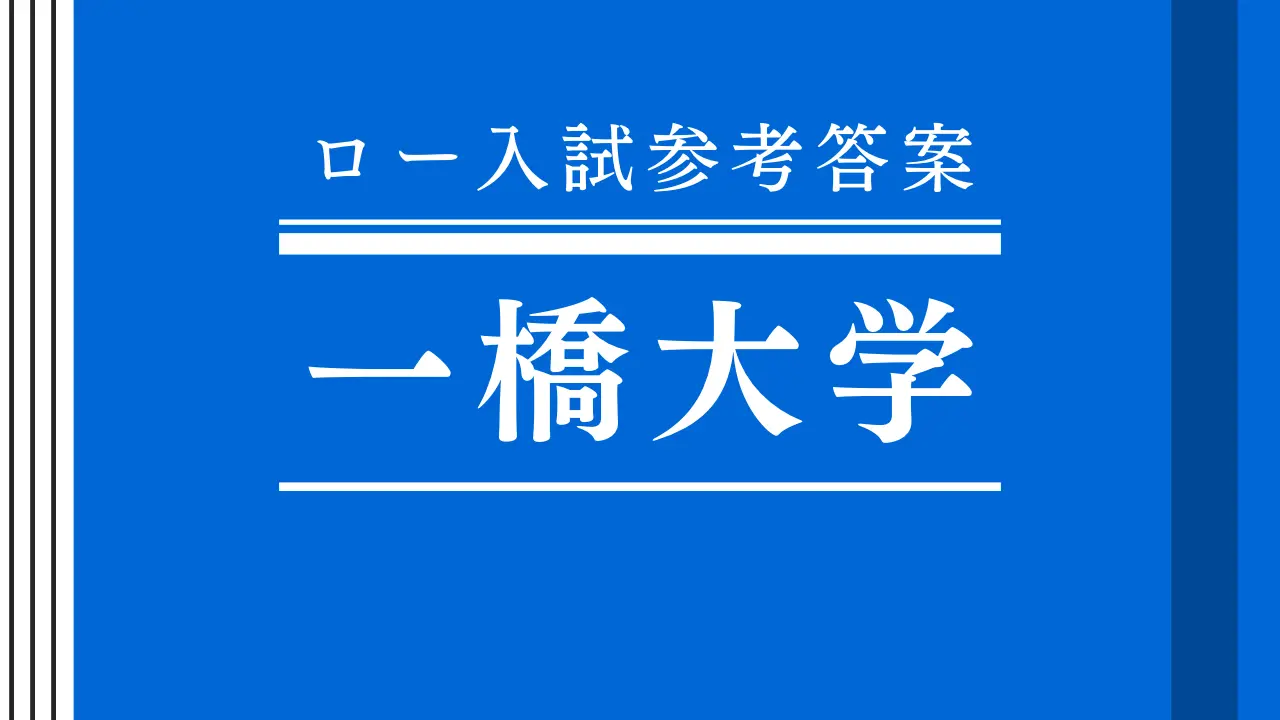
2022年 民事系/民法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2022年 民事系/民法
第1問
(1)について
Aは、Cに対し、所有権に基づく返還請求権としての乙建物収去甲土地明渡請求をする。まず、Aは甲を取得し、所有権(民法(以下略)206条)を有している。また、甲上に乙が存在し、乙を所有していたBが死亡してC(「配偶者」)がBを単独相続した(882条・890条)ことでCが乙所有権を承継取得した(896条本文)。もっとも、その後Cは、乙をDに売却(555条)したことでDが乙所有権を有している。そのため、Cを相手方として上記請求ができるかが問題になる。
1. 原則として、土地所有権に基づく建物収去、土地明渡請求の相手方は、知情建物の所有者である。しかし、土地所有者と、建物収去土地明渡請求の相手方との関係は、あたかも当該建物についての物権変動における対抗関係にも似た関係にあるといえる。そこで、他人の土地上の建物の所有権を取得し、自らの意思に基づいて登記を経由した者は、その建物の登記名義を保有する限り、土地所有者に対し、建物所有権の喪失を主張できないと解する。このように解さなければ、請求の相手方の事情によって、請求の可否が変わることになり、請求権者に酷である。
2. 本件では、CはBの配偶者として乙を相続し、自らの意思で登記を経由している。そして、Dに売却後も所有権移転登記を行わず、Cが登記名義を有している。
3. 以上より、AはCに対して乙建物収去甲土地明渡請求を行うことができる。
(2)について
Eは、抵当権(369条1項)に基づく妨害排除請求権として、Fに対して、丙を甲に戻すように請求する。
1. 丙は「付加して一体となっている物」(370条本文、以下、付加一体物)としてEの抵当権(以下、本件抵当権)の効力が及ぶか。
⑴ 抵当権が抵当不動産の交換価値を支配する価値権であることにかんがみ、「付加一体物」とは、担保評価の際に抵当不動産と経済的に一体をなしていると評価される物をいう。そして「従物」(87条1項)は主物に従属してその経済的効用を高めるから、抵当不動産と経済的に一体をなしていると評価されるものとして、「付加一体物」にあたる。
⑵ 本件で、甲土地の「所有者」であるAが丙(「物」)を甲土地に設置(「附属」)させているから、丙は甲の従物に当たる。(87条1項参照)。
⑶ よって、丙は付加一体物として抵当権の効力が及ぶ。
2. もっとも、丙はFに売却され、甲から分離してFの自宅へ搬出されているところ、かかる場合にも本件抵当権の効力が及ぶか。
⑴ 抵当権が抵当不動産の交換価値を支配する価値権であることからすれば、いったん付加一体物としてその交換価値を抵当権により支配された以上、分離・搬出されても、当該物に抵当権の効力は及んでいると解する。もっとも、取引安全の要請もあるから、第三者が当該物を即時取得(192条)した場合には、第三者に対し抵当権の効力を対抗できなくなると解するべきである。
⑵ 本件で、丙は甲から分離して搬出されている。そして、たしかにFは丙を甲土地から持ち帰る際に、Aとの会話を通して甲土地に本件抵当権が設定されていることを知っていた。しかし、即時取得の「善意」の基準時は「取引行為」時点である。そのため、AF間の売買時にFが本件抵当権の存在を過失なく知らなかった場合には、「善意」である。そして、平穏公然は186条1項により推定されかかる推定を覆滅する事実もない。
⑶ よって、AF間の売買時にFが本件抵当権の存在を過失なく知らなかった場合には、丙に本件抵当権の効力は及ばない。
3. 以上より、AF間の売買時にFが本件抵当権の存在を過失なく知らなかった場合には、Eの請求は認められない。
第2問
1. 解除の可否
⑴ Bとしては、Aからブレーキに不具合のない甲であることを内容として買い受けた(民法(以下略)555条)にも関わらず、引渡し前から不具合があった。そして、甲は滅失しているため、不具合のない甲を引き渡すことができないので履行不能となっている(412条の2第1項)。そのため、債務不履行に基づき売買契約を解除(542条1項1号)すると主張する。
ア まず、548条により解除権をBは失っているとの反論が考えられる。
しかし、甲が滅失した原因は、甲のブレーキの不具合である。そのため、B(「解除権を有する者」)が「故意もしくは過失」によって目的物を「返還することができなくなった」とは言えない。そのため、548条により解除は制限されない。
イ 次に、対してAは、引渡し後にBが甲を乗り回したことで事故を起こし、滅失しているから、かかる債務不履行が「債権者」たるBの「責めに帰すべき事由によるものである」場合であるとして、543条により解除は認められないと反論する。
しかし、かかる事故の原因は甲のブレーキの不具合である。そのため、Bの「責めに帰すべき事由」によって甲が滅失したとは言えない。
よって、上記反論は認められない。
⑵ またAは、引渡し後に「双方の責めによらない事由によって滅失」したため、解除は認められないと反論する(567条1項前段)。
しかし、Aは、売主として甲に不具合がないかどうかを確認する義務がある。にもかかわらず、ブレーキの不具合に気づかずに、あるいは気づいていながら引き渡したといえる。そして、Bは甲のブレーキの不具合が原因で事故を起こし、甲が滅失している。とすれば、Aに甲の状態を確認していなかった、ないし気づいているにもかかわらずこれを告げずに引き渡したという点で、Aの帰責性が認められる。
よって、双方の責めによらないとはいえず、上記反論は認められない。
⑶ 以上より、Bの解除の主張は認められる。
2. 契約の清算について
⑴ まず、解除に基づく原状回復請求として、Bは、Aに対して代金の返還を請求できる(545条1項本文)。
他方Aもまた、Bに対して甲の返還を請求することが考えられるが、甲は滅失しており、原状回復が不能であるから、かかる請求はできない。もっとも、原状回復義務は現存利益に限定されていない(121条の2第1項参照)ため、滅失した物の価額相当額の支払いは請求できると解するべきである。そのため、不具合のあった甲の価額相当額を請求できる。
⑵ さらにBは、事故によって損害を被った場合には、Aに対して債務不履行を理由に損害賠償請求できる(415条1項)。
他方Bもまた、Aに対して甲が滅失して原状回復できないことを損害として、損害賠償請求することが考えられるが、前述同様、甲が滅失したのはAの責めによるから、Bに免責事由があり、かかる請求は認められない(415条1項但書)。
以上





