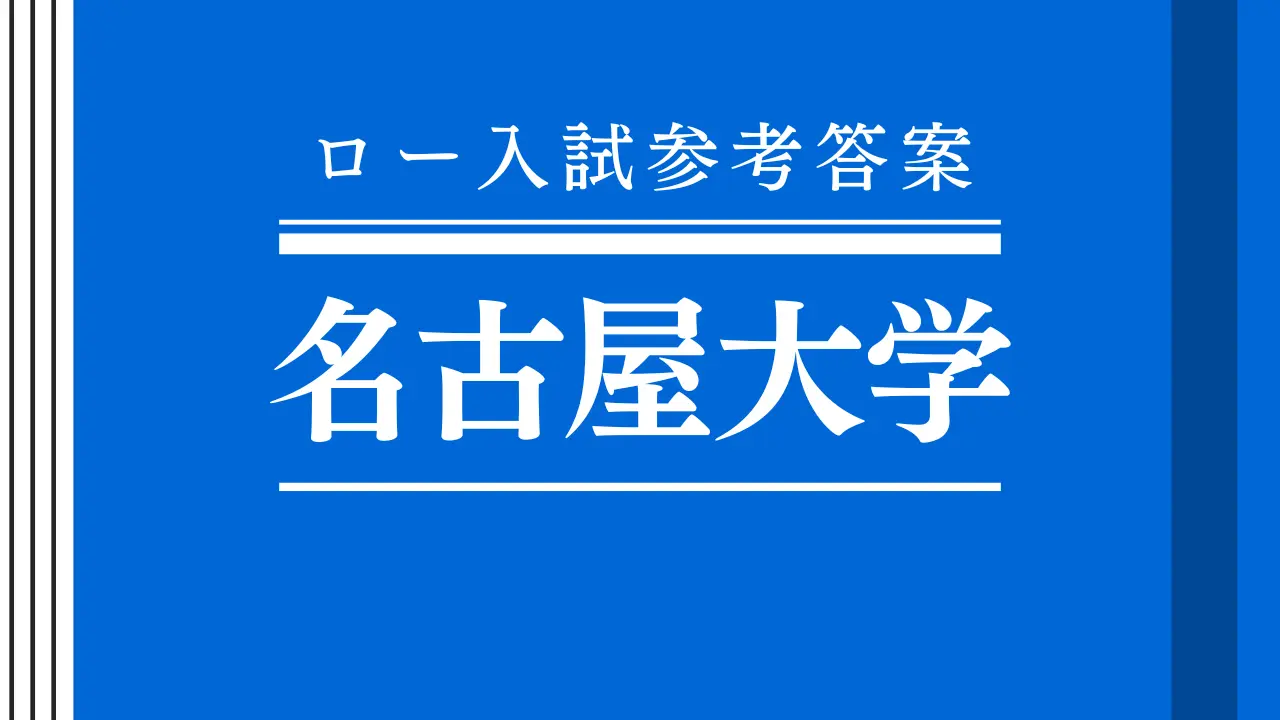
2021年 公法系 名古屋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/18/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
名古屋大学法科大学院2021年 公法系
Ⅰ (1)
1. 衆議院の解散とは、衆議院議員の任期満了前に衆議院議員全員の資格を失わせる行為である(憲法(以下略)69 条参照)。
2. 衆議院の解散には、自由主義的意義、すなわち、内閣による議会への抑制手段という意義及び、民主主義的意義、すなわち、解散に続く総選挙によって国民の審判を求めるという意義がある。
3. そして、衆議院解散の形式的根拠は天皇にある(7条3号)と解する。そして、衆議院の解散は、本来的に政治的行為なものであるところ、天皇は国政に関する権能を有しないのであるから(4条)、天皇の解散権は形式的な表示行為に限られ、実質的解散権は、天皇の解散に対して「助言と承認」を与える内閣に帰属する。
(2)
1. 行政行為とは、行訴法3条2項にいう「処分」と同義であり、公権力の主体たる国または公共団体の行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を画定することが法律上認められているものをいう。
2. 一方、行政指導(行手法2条6号)は、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
3. あくまで任意の協力要請である行政指導には、法的根拠を要さず、不利益な内容であっても意見陳述等の機会が設けられておらず、抗告訴訟によっては原則として争えないのに対して、国民の権利義務を直接に画定する行政行為については、法的根拠を要し、不利益処分いついては弁解ないし聴聞の機会が与えられ、抗告訴訟において争える点で異なる。
Ⅱ
Xの主張
1. 本件検定は「検閲」(21条2項前段)に該当し、国賠法上違法である。
⑴「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、表現物の一部または全部の発表を禁止する目的で、対象とされる表現物を一般的・網羅的に、発表前に審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することをいい、絶対に禁止される。
⑵本件検定は、文部科学大臣という行政権が主体となっている。また、『新しい公共』は、Xは自らの研究成果に基づき、集団的自衛権の行使を一部容認するような閣議決定は、日本国憲法9条に反する旨の思想内容等の表現物である。また、本件検定は、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解又は最高裁判所の判例が存在する場合には、それらに基づいた記述がされているかを審査するものであるから、思想内容等を対象とされる表現物を一般的・網羅的に、発表前に審査するものである。そして、教科書として刊行されることに特に意味をみいだしている本件においては、本件検定は発表の禁止に等しいものと評価できる。
⑶ 以上から、本件検定は、検閲に該当し、21条2項前段に反し違憲である。
2. 仮に検閲に該当しないとしても、文部科学大臣の判断は裁量を逸脱したものであり、「表現の自由」を侵害して21条1項に反し違憲である。
事前抑制である本件検定は、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されると解すべきであり、裁量判断には慎重な検討を要する。そこで、「閣議決定…に基づいた記述がされている」に基づいていないと判断できるのは、閣議決定と異なる内容をさも閣議決定の内容として記載さているような場合に限られると解する。集団的自衛権の行使を一部容認するような閣議決定は、日本国憲法9条に反する旨の記述は、閣議決定の内容を正確に伝えた上で、それを批判しているに過ぎない。にもかかわらず、検定基準に反するとの判断は裁量を逸脱したものであり、表現の自由を侵害し違憲である。
私見
1. 一般図書としての発行を何ら妨げるものでないから、発表の禁止を目的とするものとは言えないし、発表を禁止するものとも言えない。そのため、検閲には当たらない。
2. また、本件検定の判断は、内容の学問的正確性、中立・公正性等の様々な観点から多角的に行われるもので、学術的、教育的な専門技術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣の合理的な裁量に委ねられるものであって、X主張の解釈は取れない。看過し難い過誤の認められない基準に従ってなされた処分として合憲である。
Ⅲ
1. Yによる本件支給決定の取消しは行政庁が職権により、当初から瑕疵のある行政行為について遡及的にその効力を消滅させるものであるから、行政行為の職権取消しに該当する。
2. まず、明文の根拠なくしてがこれを行えるかが問題となるも、行政行為に違法の瑕疵がある場合、法律による行政の原理に違反しているから、それを解消する取消しに、法律の根拠は不要であると解する。
3. ⑴もっとも、本件支給決定は受益的行政行為である。
⑵ここで、授益的行政行為については、相手方・利害関係人の信頼や法的利益に配慮すべきである。そこで、その取り消しは、相手方に帰責性があるときを除いては、相手方・第三者の既得権益を失わせることの不利益より公益上の必要性が高いことを要すると解する。
⑶「被災地の速やかな復興」という法の目的からすれば、支援金とした金額については、被災した家屋の復建やその他飲食物等に直ちに使用されることが予定されているのであって、被支給者は受け取った金額を既に有していない蓋然性が極めて高い。そうであるにもかかわらず、B市の職員が本件マンションの被害の状況について一方的に再調査した結果が従前と異なることを理由に、Xに上記金銭の返還を申し出る行為は、被災直後の混乱時期に消費した金銭の調達を義務付け、Xの生活の安定を著しく害する。
このような場合に、取消しをするのは、むしろ法の趣旨を害するのであって、相手方・第三者の既得権益を失わせることの不利益より公益上の必要性が高いとは言えない。
4. 以上より、本件支給決定の取り消しは認められない。
以上





