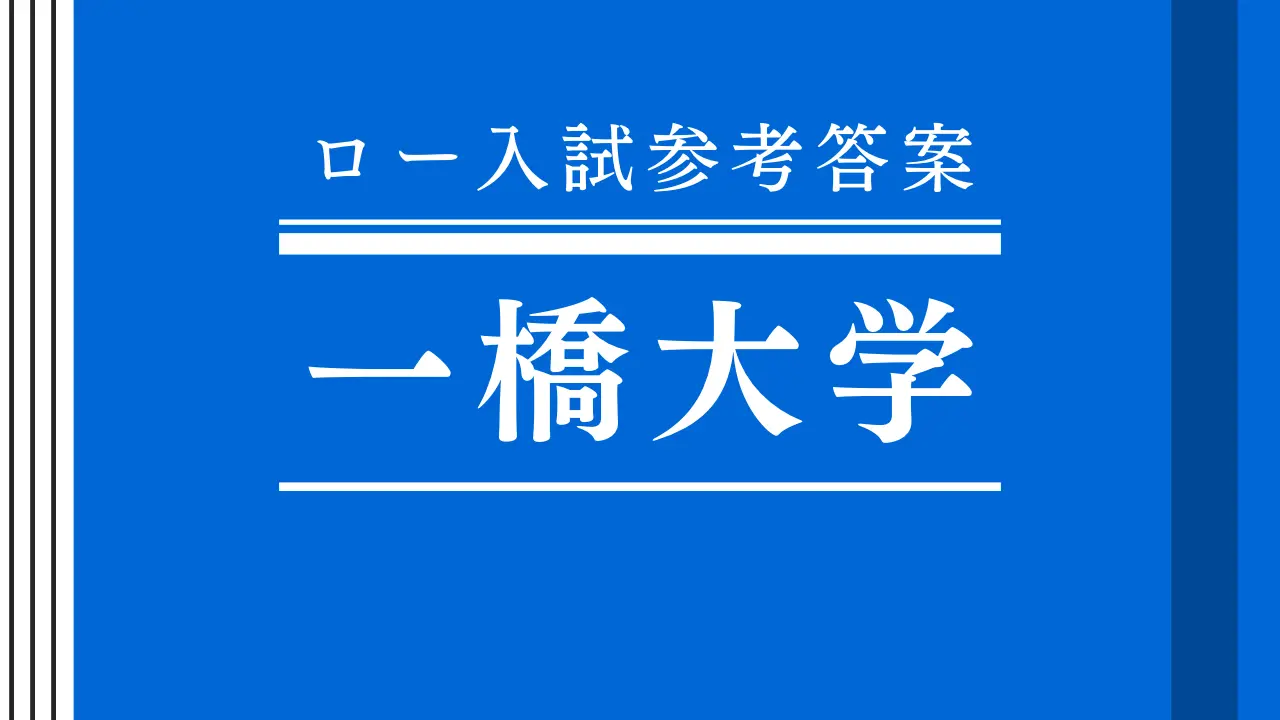
2021年 民事系/民事訴訟法 一橋大学法科大学院【ロー入試参考答案】
6/29/2025
The Law School Times【ロー入試参考答案】
一橋大学法科大学院2021年 民事系/民事訴訟法
設問(1)
1. 本件において、控訴審裁判所はどのような処理を行うべきか。
2. まず、法人の訴訟行為はその代表者が追行するものである(民事訴訟法(以下、略)37条)。本件では、法人Yの代表権を有するのはBであるところ、理事長ではなくなり代表権のないAのところに訴状が送達されている。そのため、Aへの送達は無効であり、本件では適切な送達がなされていないから、訴訟要件を欠いている。したがって、訴えが不適法となるのが原則である。そして、本件では、かかる事実が看過されて本案判決がなされているため、第一審判決は上訴の対象となる確定判決に該当する。
3. もっとも、本件ではXがY法人の登記簿を確認し代表者がAであると認識しているという事情が存在する。会社の代表者を確定するには登記簿を確認するしかなく、登記上の代表者への送達を無効とすることは登記を信頼した者に酷である。また、審理が進んでいる以上、訴訟経済にも反する。そこで、実体法上の表見法理の規定(民法109条、会社法354条、908条2項)を類推適用し、法人の代表者でない者への送達を有効とすることができないか。
⑴ この点について、表見法理の規定は取引の安全を保護するために設けられており、取引行為ではない訴訟行為への類推適用の基礎を欠く。また、表見支配人を規定する商法24条が訴訟行為を適用範囲から除外しており、訴訟行為については相手方の保護を否定するのが法の趣旨であると考えられる。加えて、類推適用を肯定した場合には、法人の真の代表者により裁判を受ける機会が奪われることになるし、相手方の善意・悪意により結果が左右されることになり手続きの画一性が害される。以上より、表見法理の類推適用は否定されると解される。
⑵ したがって、表見法理の類推適用によりAへの送達を有効とすることはできない。
4. よって、裁判所はXに真の代表者であるBを代表者とする補正(137条1項)を明示、Xがこれに応じた場合には、裁判所はBへの訴状の送達をした上で本案審理を最初からやり直すべきである。一方で、Xが補正に応じない場合には、訴えが不適法であるとして、訴え却下判決を下すべきである(140条)。
設問(2)
1. まず、本件では、裁判所はXY間の売買契約の締結がなされ、XはYから300万円の支払いを受けたがそのうち100万円はノートパソコンの売買契約の代金として支払われたとの心証を抱いている。もっとも、ノートパソコンの売買により100万円を支払ったとの事実はXYのどちらも主張していない。そのため、かかる事実を認定することは弁論主義に反するのではないか。
⑴ 弁論主義とは、私的自治の訴訟法反映を根拠とする訴訟資料の収集提供を当事者の権限・権能に任せる建前をいう。弁論主義が適用されると裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできない(第一テーゼ)。
この点、弁論主義の適用範囲を重要な間接事実にまで適用する見解がある。しかし、間接事実と補助事実は主要事実の存在を推認させる点で証拠と共通の働きをすることから、これらの事実に自白拘束力を認めると裁判官に不自然な事実認定を強制し自由心証主義(247条)に反するおそれがある。加えて、弁論主義の趣旨・機能から訴訟の勝敗を決する主要事実にのみ弁論主義を及ぼせば足りる。そのため弁論主義の適用は主要事実にのみ限られると考える。
⑵ そして、主要事実とは訴訟物たる権利の発生・障害・消滅・阻止を定める規範の要件に直接該当する具体的事実を意味する。一方で、間接事実とは主要事実の存否を経験則によって推認させる具体的な事実を指す。
⑶ 本件をみるに、本件訴訟の訴訟物は、売買契約に基づく代金支払請求権である。そして、本件の100万円が別の職務用ノートパソコンの売買代金として支払われたものであるという事実は、Yが支払った代金のうち100万円はタブレットの売買契約についてなされたものではないとの認定に用いられる。そのため、かかる事実はYがタブレットの代金を支払ったとの主張と両立せず、Yが証明責任を負う事実と両立しない事実を積極的に述べるものであるから、Xの積極否認に当たる。すなわち、かかる事実は抗弁事実にあたらず主要事実ではない。
⑷ したがって、裁判所が上記事実を認定することは弁論主義に反しない。
2. 以上より、タブレットの300万円の売買契約とそのうち200万円が弁済により消滅したことが認定できる。つまり、Xの請求のうち100万円の存在が認められる。加えて、100万円の一部認容はXの意思に反さず、Yの防御権を害するものではないため処分権主義(246条)にも反しない。
3. よって、裁判所は100万円の存在を認める一部認容判決をすべきである。
以上





